REIT投資を始めてから数年が経ち、「保有銘柄の分配金は安定しているものの、利回りをもっと高められないか」と感じる投資家は多いはずです。実は、同じ市場環境でも視点を少し変えるだけでリスクを抑えつつ収益力を上げる余地があります。本記事では、2025年10月時点の最新データをもとに、経験者が押さえるべき利回りの分析手法と実践的な改善策を解説します。読み終えるころには、数字の裏側を読み解き、次の一手を具体的に描けるようになるでしょう。
REITの利回りを正しく理解する
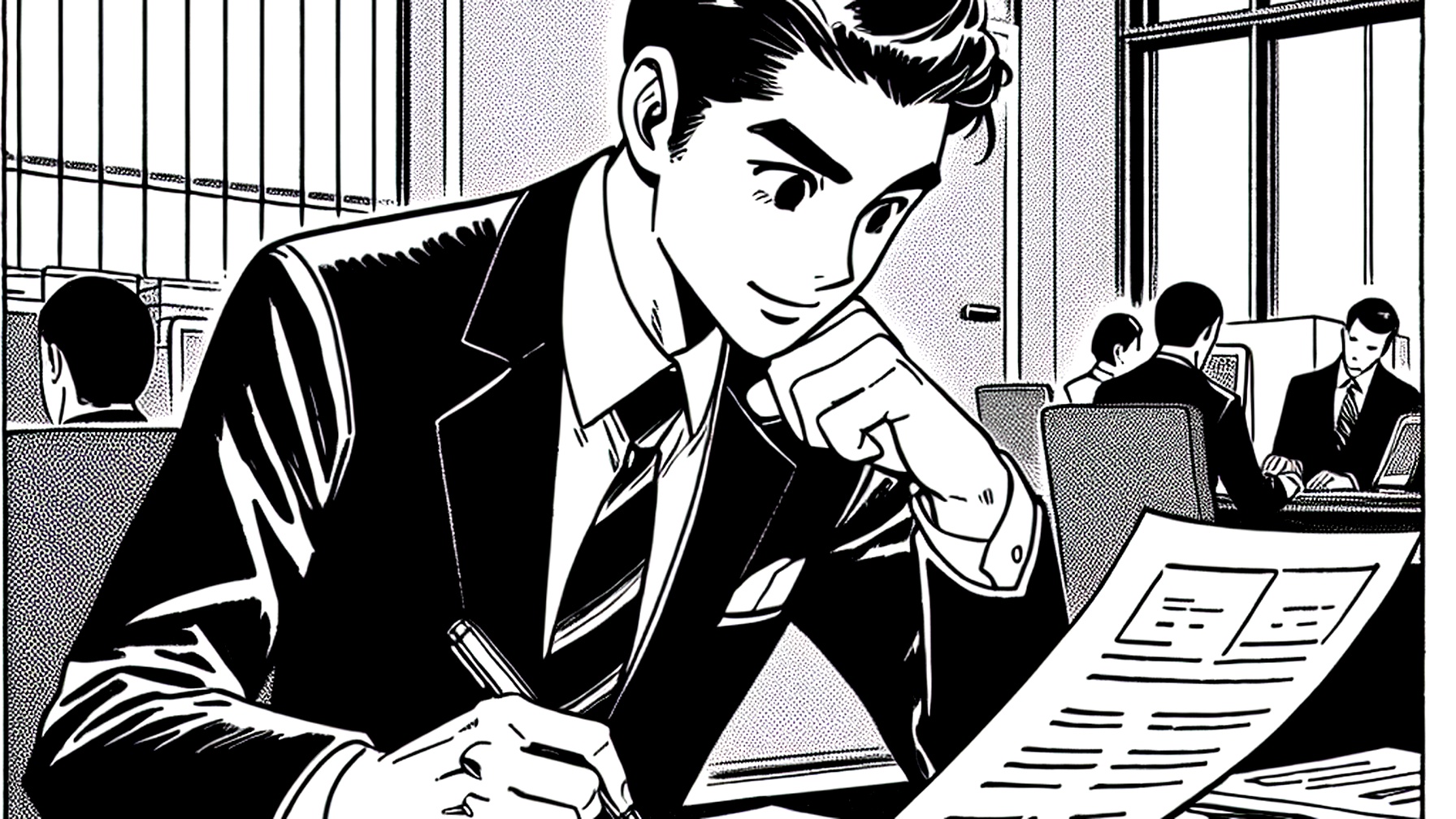
まず押さえておきたいのは、利回りという言葉が複数の意味で使われている点です。分配金利回りだけで判断すると、リスク調整後のリターンを見誤る恐れがあります。経験者ほど言葉の定義を再確認することが成果を左右します。
最もよく目にする分配金利回りは、株価に対する年間分配金の割合です。株価が下がれば数字は上がりますが、物件の収益力が向上したとは限りません。一方、NOI利回り(Net Operating Income)は、賃料収入から運営費用を引いた純収益を物件価格で割ったものです。こちらは内部のキャッシュフローを示すため、物件の稼ぐ力を測る指標として有効です。
さらに、キャップレートという概念も重要です。キャップレートは将来のキャッシュフローを現在価値に割り戻す際の割引率として使われ、物件売買価格の妥当性を測る際に欠かせません。分配金利回りが高くてもキャップレートが低すぎる場合、追加投資余力は限定的です。つまり、複数指標を並べて初めて利回りの質を判断できるのです。
市場環境から読み解く最新利回り動向
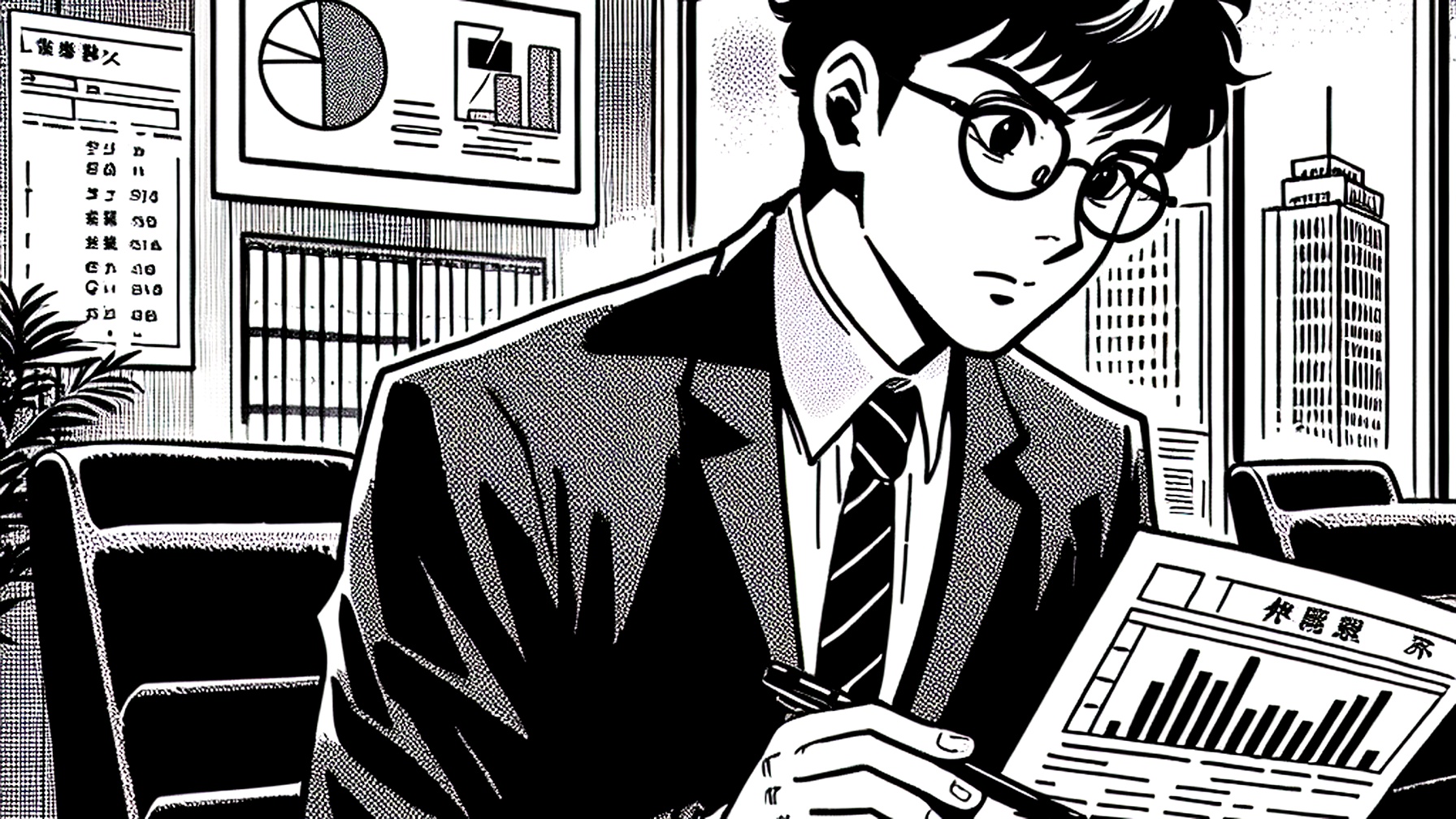
ポイントは、マクロ環境とREIT固有要因の両面から数字を読むことです。2025年時点で日銀はマイナス金利を解除し、長期金利は1%台前半で推移しています。金利上昇はREITの調達コストを押し上げるため、表面利回りの確保が一段と重視されます。
日本不動産研究所の調査によると、東京23区オフィスのキャップレートは平均3.6%で前年より0.2ポイント上昇しました。金利が上がる局面でも賃料の上昇期待が利回りの下支えになっていると言えます。一方で物流施設はテナント競争が激化し、キャップレートは4.2%へ0.3ポイント拡大しました。用途によって利回りの動きが異なるため、分散投資の意義が高まっています。
海外REITとの比較も見逃せません。米国総合型REITの平均分配金利回りは2025年10月時点で4.8%ですが、ドル金利が5%近い水準にあるためスプレッドは縮小傾向です。国内REITの平均分配金利回りは3.9%でスプレッドは依然としてプラスですが、クレジットスプレッドの縮小が示す通り安全域は薄くなりつつあります。この局面では、銘柄選択とタイミングの妙が利回り差を生む鍵になります。
個別銘柄で差が出るポイント
重要なのは、物件ポートフォリオの質と運用会社の戦略です。同じ用途でも立地と築年数の組み合わせで賃料成長率は大きく変わります。たとえば、東京23区の築浅オフィスは平均賃料が前年比4%伸びていますが、築25年以上のビルは横ばいです。
運用会社のリサイクル戦略も利回りを左右します。含み益の出た物件を売却し、利回りの高い新規物件へ組み替えると、分配金を押し上げながら内部留保も確保できます。東証REIT指数に採用される大型銘柄は資金調達が容易なため、この戦略を積極的に行える点が強みです。一方、中型REITは資金調達コストが高く、物件取得競争で不利になりやすいものの、地域特化による情報優位を生かせば高いキャップレートを獲得できる余地があります。
ガバナンスも見逃せない要素です。2024年度に金融庁が導入した外部委員の選任ガイドラインに基づき、運用会社の独立性が強化されつつあります。情報開示が進むことで投資家はリスク要因を早期に把握でき、結果として適正利回りの判断精度が上がるでしょう。
利回り向上に役立つ投資戦略
実は、利回りを高める方法は銘柄選びだけではありません。保有期間中の運用テクニックが総合リターンを大きく引き上げます。代表的なものが信用取引の活用と配当再投資です。
信用取引でレバレッジを効かせる場合、金利コストが分配金利回りを上回らない水準に抑えることが前提です。2025年10月の主要証券会社の信用金利は1.8〜2.2%で、分配金利回りとの差額がスプレッド益になります。ただし、株価変動リスクが増幅されるため、ボラティリティが低い物流系や住宅系REITに限定して活用するのがセオリーです。
配当再投資は複利効果を生みます。東証REIT指数の過去15年トータルリターンを見ると、分配金を再投資した場合の年率リターンは6.5%で、配当を受け取るだけの場合より1.7ポイント高くなります。長期で見れば小さな差が大きな資産形成につながるとわかります。
加えて、海外ETFとの組み合わせも検討に値します。日本市場が調整局面に入った際、為替ヘッジ付きの米国REIT ETFを組み込むことでキャッシュフローを維持しながらポートフォリオ全体のボラティリティを下げる効果が期待できます。つまり、戦略的分散と再投資が経験者の利回り向上を後押しします。
税制と手数料を踏まえた実質利回り計算
ポイントは、税引き後のキャッシュフローで利回りを評価することです。上場REITの分配金は20.315%の源泉徴収がかかります。NISA口座で購入すれば非課税ですが、2024年開始の新制度では年間投資枠360万円までという制限があります。経験者ほど枠はすぐ埋まるため、課税口座とのバランスが重要です。
さらに、投資信託型REITと比較すると、信託報酬が実質利回りを押し下げます。平均的なREIT ETFの信託報酬は年0.15%前後ですが、オープン型投信では0.7%を超えるケースも珍しくありません。手数料が0.5ポイント違うだけで、10年後の総リターンは約5%差になる計算です。
住民税の配当控除適用外である点も留意しましょう。REIT分配金は株式配当と違い総合課税での控除が使えません。そのため、高所得者ほど実質利回りは目減りします。一方、法人名義で保有すれば所得分散が可能となり、節税メリットを享受できる場合があります。結論として、税制を踏まえた投資形態の選択が最終的な利回りを左右するのです。
まとめ
ここまで、REIT 経験者向け 利回りを高めるための視点と具体策を整理しました。利回りは分配金だけでなくNOIやキャップレートを合わせて評価し、市場環境と銘柄特性を多面的に捉える必要があります。さらに、レバレッジや再投資、税制最適化といった運用手法を組み合わせることで、安定収益と成長双方のバランスを取れます。今日紹介したフレームを使い、自身のポートフォリオを再点検すれば、次の購入タイミングや売却判断がより明確になるはずです。まずは保有銘柄の実質利回りを計算し、改善余地を洗い出してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 投資信託協会「REITデータブック2025」 – https://www.toushin.or.jp
- 日本銀行「金融システムレポート 2025年4月」 – https://www.boj.or.jp
- 金融庁「投資信託に関する制度改正の概要」 – https://www.fsa.go.jp
- 東証リート指数データ(株式会社JPX) – https://www.jpx.co.jp

