年収が700万円前後になると、貯蓄も増え、将来の資産形成を真剣に考え始める方が多いものです。しかし、都心のマンション価格は高騰が続き、「自分の年収で不動産投資など無理では」と感じる読者も少なくありません。本記事では、年収700万の会社員でも手が届きやすい価格帯で、かつ高利回りを狙える収益物件の選び方を解説します。資金調達のポイントから物件タイプの比較、2025年度時点で使える税制メリットまで、基礎から丁寧に説明しますので、最後まで読めば投資への第一歩を踏み出す具体的なイメージがつかめるはずです。
年収700万の融資枠を最大化する考え方
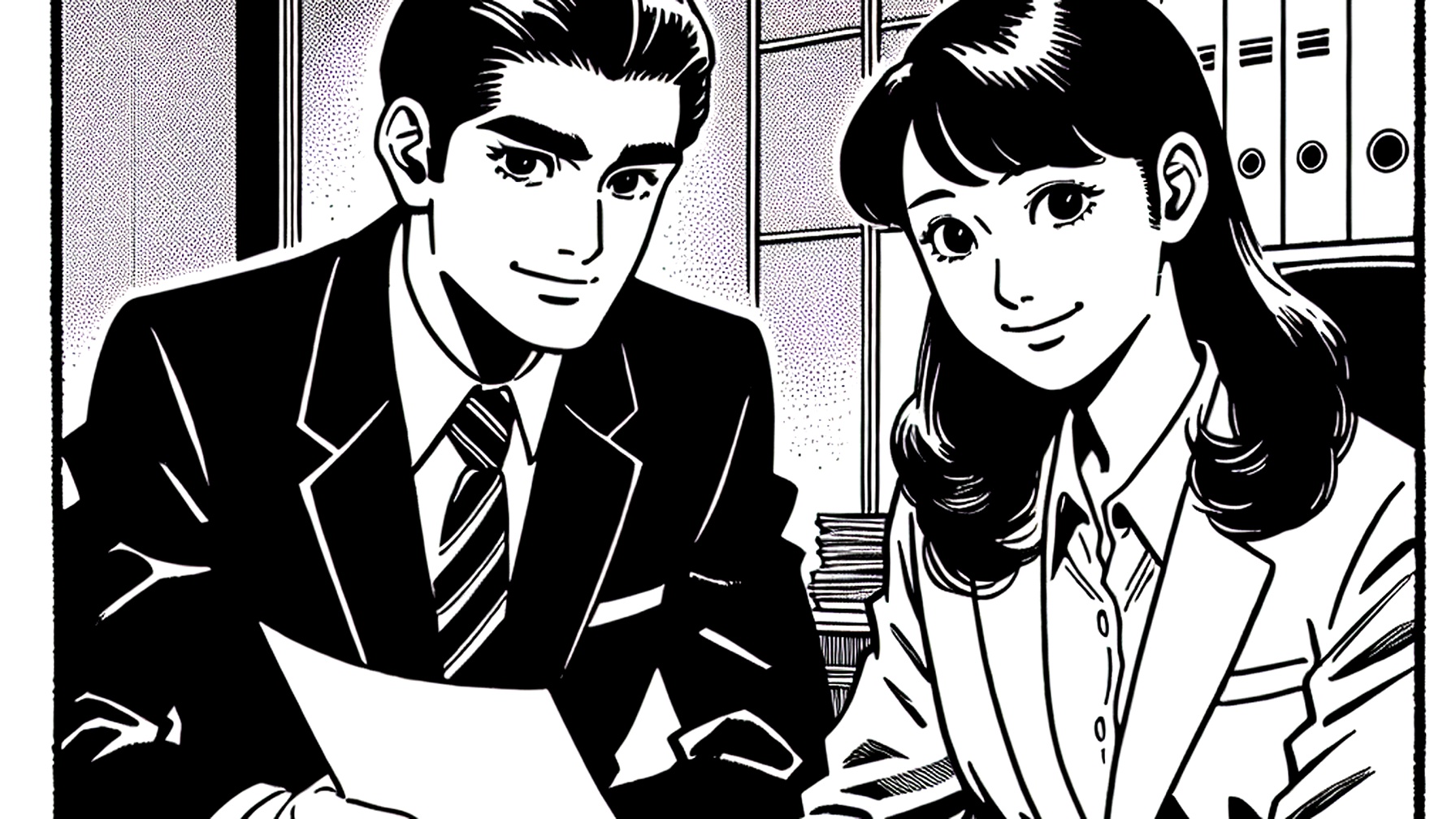
まず押さえておきたいのは、金融機関が年収700万円の投資家にどれほどの融資枠を提示するかです。一般に、返済負担率は年収の35%以内が目安とされ、金利2.0%、返済期間25年で試算すると、借入可能額はおおむね7,000万〜8,000万円に達します。ただし、既存の住宅ローンやカードローンがある場合は、その分が差し引かれる点に注意が必要です。
次に重要なのは自己資金の割合です。自己資金を1割以上用意できれば、金融機関の印象が良くなり、金利面で優遇を受けられる可能性が高まります。特に2025年10月現在は、都市銀行が投資用ローンの審査を厳格化している一方で、地方銀行や信用金庫がエリア限定で70〜80%融資を行うケースも増えています。
さらに、借入先を1行に集中させず、生活口座とは別の金融機関を使うと総与信枠を広げやすいというテクニックがあります。つまり、属性が同じでも「使う銀行」と「見せる自己資金」によって融資枠は大きく変わるわけです。融資交渉を行う際は、家計簿や確定申告書を用意し、返済余力を数値で示すと説得力が増します。
高利回りを生む立地選定のコツ
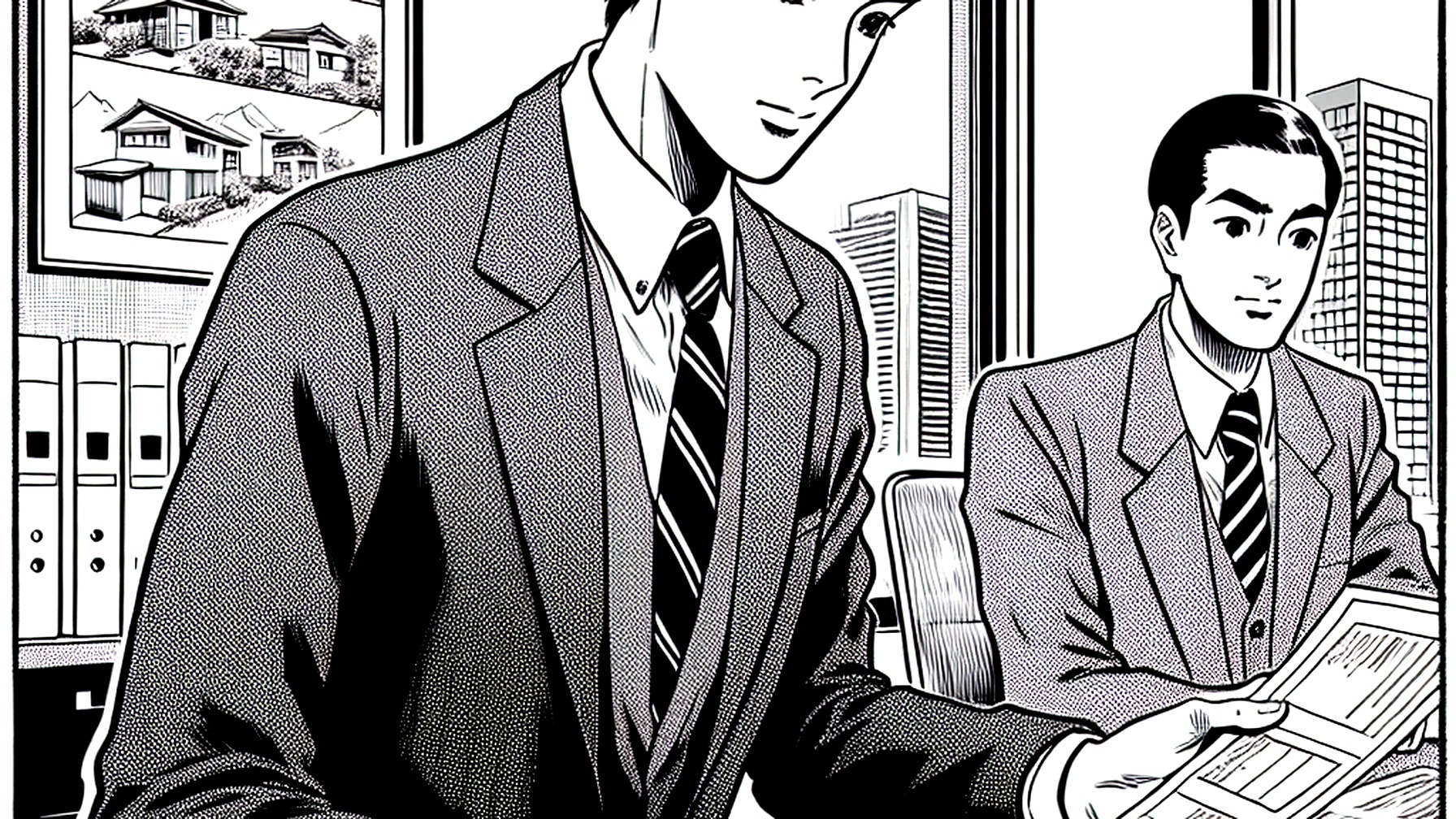
ポイントは、家賃水準が高く、かつ物件価格が抑えられるエリアを選ぶことです。具体的には、都心まで30分圏内の準急停車駅や、再開発が進む地方中核都市の駅徒歩10分圏が狙い目です。日本不動産研究所の2025年調査によると、東京23区のワンルーム平均表面利回りは4.2%ですが、同調査で多摩地域や埼玉南部の一部駅では6〜7%台のデータも確認できます。
一方で、高利回りエリアには空室リスクがつきものです。人口動向を市区町村単位で調べ、単身世帯の増減と大学や工業団地の立地状況を合わせて判断しましょう。また、隣駅に競合する大型マンションが建設予定かどうか、自治体の開発計画をチェックすると長期的な需要の見通しが立てやすくなります。
実は、賃貸需要は「駅近」だけで決まるわけではありません。バス便が充実し、スーパーや総合病院が徒歩圏にある郊外エリアでも、駐車場付きのファミリー向け物件なら8%超の利回りが見込める例があります。重要なのは、家賃設定を周辺相場より5%程度低く抑え、長期入居を狙うことで実質利回りを安定させる戦略です。
物件タイプ別に見る収益性の違い
まずワンルームマンションは、流動性が高く管理も容易ですが、表面利回りは4〜6%程度にとどまります。その代わり空室期間が短く、サラリーマン投資家が初めて手掛けるには扱いやすい点がメリットです。また、築15年以内で修繕積立金が適正に積み立てられている物件を選ぶと、予期せぬ出費を抑えられます。
アパート一棟投資は、建物と土地を同時に所有するため資産価値が残りやすく、減価償却費を多く計上できる点が魅力です。木造2階建ての築浅アパートなら表面利回り7〜9%も珍しくありません。特に年収700万円の投資家の場合、土地値が低い郊外で総額5,000万〜7,000万円の案件を狙うと融資枠に収まりやすくなります。
一方、RC造(鉄筋コンクリート)のファミリーマンション一室を区分で購入する手法もあります。RC造は法定耐用年数が47年と長いため、長期融資を引きやすく、税金面での繰延効果が期待できます。表面利回りは3.8〜5.0%と控えめながら、修繕費が計画的に積み上がる管理組合の物件を選べば長期間の安定収入が見込めます。
つまり、利回りだけでなく、修繕リスク・流動性・税務メリットを総合的に比較し、自分の資金計画とリスク許容度に合った物件タイプを選ぶことが成功の鍵になります。
資金計画とリスク管理のリアル
重要なのは、想定外の支出をあらかじめシミュレーションに組み込むことです。例えば、空室率20%、家賃下落年1%、金利上昇1.5%という厳しめの条件でもキャッシュフローが赤字にならないか確認しましょう。年間家賃収入800万円、経費率20%としても、手元に残るのは約640万円です。そこから元利返済を差し引いた後に、少なくとも年間50万円程度の純益が確保できる計画が望ましいといえます。
さらに、突発的な修繕費に備えて家賃収入の10%を毎月積み立てると安心です。2025年現在、物価上昇の影響で屋上防水や外壁塗装の単価が3年前より1〜2割上昇しているため、長期修繕計画は余裕を持たせる必要があります。また、火災保険料が2024年秋に改定され、築古物件の保険料率が上がった点にも注意してください。
レバレッジをかける際は、返済比率が家賃収入の50%を超えないように設定すると、空室や家賃下落局面でも耐えやすくなります。加えて、固定金利型の商品を3割ほど入れておくと金利上昇リスクを平準化できるでしょう。こうした保守的な資金管理が、長期にわたる不動産経営を安定させる土台になります。
2025年度に活用できる税制・公的サポート
まず、2025年度も継続している固定資産税の新築住宅軽減措置は見逃せません。賃貸用共同住宅であっても、居住用割合が2分の1以上であれば、3年間は税額が2分の1に減額されます。新築アパートを建築する場合、このメリットを試算に織り込むと実質利回りが0.3〜0.5ポイント向上するケースがあります。
次に、減価償却は所得税対策として有効です。木造アパートなら法定耐用年数22年のうち、築12年の物件を購入すれば残存耐用年数は10年、加速度的に経費を計上できます。年収700万円層の場合、課税所得を圧縮することで住民税も含め年間30万〜50万円の節税効果が見込める例もあります。
また、国土交通省の「賃貸住宅管理業登録制度」が2021年から義務化されたことで、登録事業者による管理を受けると融資審査の評価が上がる傾向が続いています。登録番号を取得した管理会社を選べば、金融機関が想定する運営リスクが下がり、金利優遇や融資期間延長につながる場合があります。
最後に、設備の省エネ改修に対する地方自治体の補助金が拡充されています。東京都の例では、賃貸住宅に高効率給湯器を導入すると1台あたり5万円の補助が受けられ、2026年3月末まで予算枠が確保されています。こうした小規模な補助金でも、累積すれば表面利回りを押し上げる効果がありますので、自治体サイトをこまめに確認しましょう。
まとめ
本記事では、年収700万円の会社員が高利回り収益物件を手に入れるための戦略を、融資枠の拡大、立地選定、物件タイプ別比較、資金管理、そして2025年度の税制メリットという流れで解説しました。あらためて強調したいのは、利回りだけを追うのではなく、空室率や金利変動といったリスクを数字で管理し、長期的なキャッシュフローを意識する姿勢です。まずは生活費の半年分を別に確保したうえで、自己資金を1割以上用意し、信頼できる管理会社とタッグを組むところから始めてみてください。行動を起こせば、5年後には家賃収入が家計を大きく支える柱となり、経済的な選択肢が格段に広がるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 国税庁「令和6年度税制改正の解説」 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省統計局「人口推計」 – https://www.stat.go.jp/
- 金融庁「金融機関の融資姿勢に関する調査」 – https://www.fsa.go.jp/
- 東京都環境局「賃貸住宅向け省エネ設備補助金」 – https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/

