家賃収入で資産を築きたいけれど、「1億円もの借り入れをして本当に大丈夫だろうか」と不安に感じる方は少なくありません。実は同じ金額を投じても、立地によって将来のキャッシュフローは大きく変わります。本記事では、1億円規模のアパート経営を検討する初心者向けに、失敗しない立地選定の考え方と2025年時点の最新データを交えた判断基準を解説します。読み終えるころには、物件探しの焦点が「価格」から「立地と需要」へと自然にシフトし、自信を持って次の一歩を踏み出せるはずです。
なぜ1億円規模のアパート投資では立地がカギになるのか
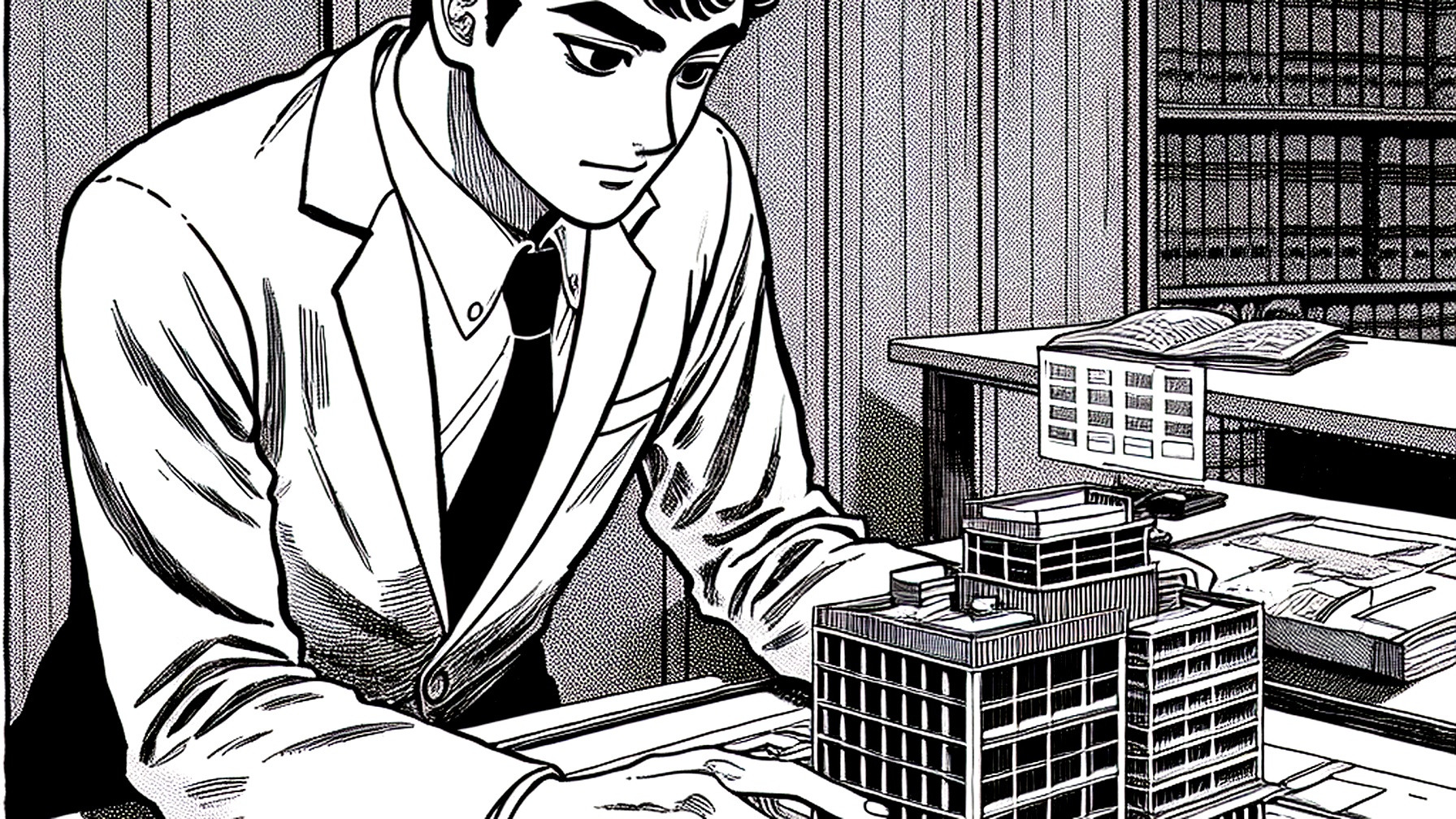
重要なのは、金額の大きさゆえに出口戦略まで視野に入れた立地判断が不可欠という点です。1億円クラスの物件はローン期間も長く、空室率の影響が顕著に表れます。国土交通省の2025年8月調査によると、全国平均のアパート空室率は21.2%ですが、東京23区内の駅徒歩10分圏では13%前後にとどまります。 人口動態を見ても、総務省が公表する2025年国勢調査の推計値では、県庁所在地を除く地方都市の20代人口は前年より1.4%減少しました。一方、東京都心3区はほぼ横ばいで推移しています。つまり、長期保有を前提とするなら、需要が減りにくいエリアほどキャッシュフローが安定しやすいのです。 さらに、売却時の評価額にも立地は直結します。都心の利回りは低めでも、出口が見えやすい点で金融機関の評価が高く、結果として借入金利や融資枠が優遇される傾向があります。初心者が1億円という大きなレバレッジを安全に活用するうえで、立地選定はリスクコントロールの第一歩となります。
投資目的別に見るエリア分析の基本手順
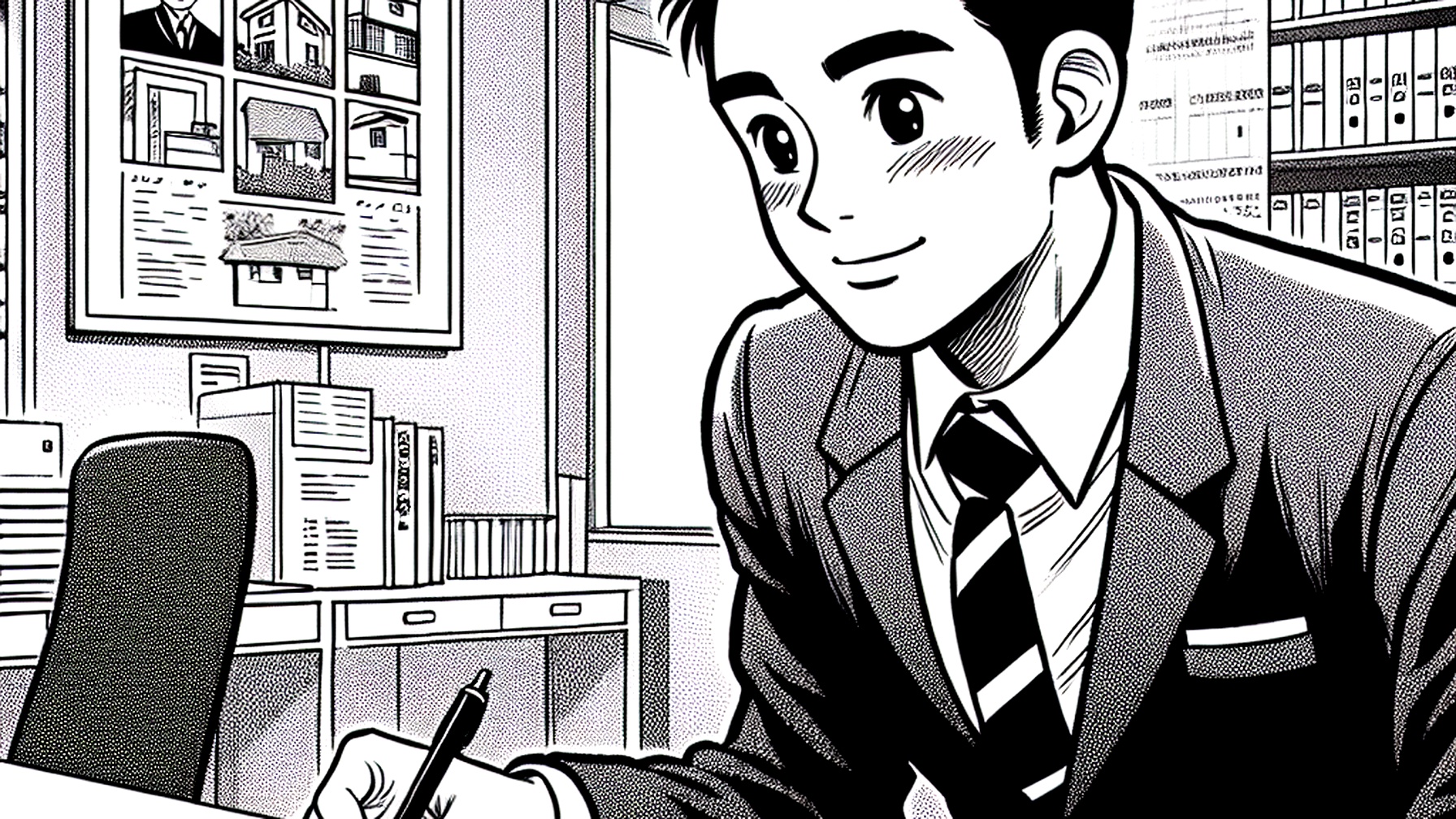
まず押さえておきたいのは、「キャッシュフローメイン」か「資産価値重視」かで適する立地が変わることです。前者は地方中核都市の築浅アパートでも高利回りを狙えますが、後者は都心部での資産保全を重視します。どちらを選ぶかで、同じ1億円でも期待収益とリスクのバランスがまったく異なります。 次に、需給を数字で確認する手順を見ていきましょう。①最寄り駅の乗降客数推移、②エリアの世帯数増減、③賃料相場と新築供給戸数のバランスを三つの柱にします。たとえば札幌市中央区では、2024年から2025年にかけ新築ワンルーム供給戸数が前年比15%増えましたが、単身世帯数は6%増にとどまっており、将来的な賃料調整の余地が大きいと判断できます。 最後に、自治体の都市計画を確認します。再開発が決定している駅前は短期的には工事騒音のリスクがありますが、完成後の賃料上昇や売却益を期待できます。一方、用途地域が第一種低層住居専用に限定されるエリアでは、将来的な建替えや増改築の自由度が低く、長期的な土地活用に制約が生じる点に注意が必要です。
データで読み解く立地評価の具体的ポイント
実は、立地の良し悪しは感覚ではなく客観指標で測れます。ここでは実務でよく使う三つのデータを紹介します。 一つ目は「空室率の時系列比較」です。国交省統計は都道府県単位ですが、民間の賃貸情報サイトAPIを利用すると駅単位まで取得可能です。過去5年で空室率が5ポイント以上上昇しているエリアは、将来も需要が減少する傾向が強いため慎重に検討します。 二つ目は「賃料下落率」です。同じ空室率でも賃料が維持されていれば需要は底堅いと判断できます。日本不動産研究所の2025年レポートでは、仙台市青葉区の賃料下落率は年間0.2%と安定していますが、築地町周辺は1.6%とやや高めでした。 三つ目は「人口流入超過数」です。総務省の住民基本台帳移動報告によると、2024年度から2025年度にかけて福岡市は約7,800人の転入超過でした。プラスの移動が続くエリアは空室リスクが低く、新築アパートでも早期満室になりやすいといえます。 これらの指標をエクセルにまとめてスコアリングすれば、複数物件を比較する際に主観を排除できます。点数化の基準は、空室率15%以下で+3点、賃料下落率0.5%以下で+2点、人口流入超過で+2点といった具合にシンプルでも構いません。
資金計画と金融機関が見る立地の目
ポイントは、立地が良ければ融資条件も好転しやすいという事実です。日本政策金融公庫の担当者にヒアリングすると、都心駅近のRC造アパートでは自己資金1割でも融資が通るケースがある一方、郊外木造の場合は2〜3割を求められる傾向が続いています。つまり、立地は「返済可能性」を裏づける最重要資料なのです。 借入金利についても同様です。2025年9月時点で、地銀のアパートローン固定金利は平均1.85%ですが、借地権付き物件や人口減少エリアの案件では2.4%を提示される例が見られます。金利差0.55%は1億円の借入を25年返済すると総支払額で約750万円の違いになります。 また、金融機関は出口戦略を重視します。都心駅近物件なら、将来の再開発や区分化販売で残債を上回る価格で売却できる可能性が高いため、期間30年の長期融資も検討の対象になります。立地選定を誤ると「担保余力が足りない」と判断され、借入額が減額されるか、そもそも審査落ちになるリスクがあるので注意しましょう。
2025年度制度を活用したリスクヘッジ
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続する「住宅ローン減税」の賃貸併用適用条件です。自宅部分が床面積の2分の1以上ならローン残高の最大0.7%を所得控除できます。1億円のうち3,000万円を自宅区画として組み込めば、年21万円の税控除が10年間受けられる計算です。 一方で、アパート全体が賃貸用の場合は「賃貸住宅省エネ改修補助金(2025年度)」を検討しましょう。外壁断熱や高効率設備の導入に対し、1戸あたり最大65万円(予算上限あり)の補助が受けられます。断熱性能が向上すれば、入居者募集で光熱費の低さをアピールでき、賃料維持にもつながります。 さらに、地方で投資を考えるなら「地域活性化賃貸住宅リノベ支援事業(2025年度)」も有効です。過去に商業施設だった建物を賃貸住宅に用途変更する場合、設計・工事費の3分の1(上限2,000万円)が補助されます。立地面で若干劣る郊外でも、共用部にコワーキングスペースなどを設けることで入居需要を創出できる点が魅力です。
まとめ
立地選定は「空室率」「賃料下落率」「人口流入」といった客観データで可視化できます。1億円規模のアパート経営では、良質な立地ほど融資条件が改善し、長期的なキャッシュフローと出口戦略の両面で有利になります。さらに、2025年度の住宅ローン減税や省エネ改修補助金を組み合わせれば、実質利回りを高める余地も広がります。まずは気になるエリアのデータを収集し、スコアリング表を作成して物件を比較してみましょう。数字に基づく判断が、将来の不安を自信へと変えてくれるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 日本政策金融公庫 – https://www.jfc.go.jp
- 住宅金融支援機構 – https://www.flat35.com

