都市部のマンション価格が高止まりし、「現物不動産は手が届かない」と感じる人が増えています。一方で、少額から始められるREIT(リート)に注目が集まり、「実際のところ評判はどうなのか」「買っても大丈夫なのか」といった声をよく聞きます。本記事では、2025年10月時点の最新データを基に、REITの仕組みからメリット・デメリット、制度面の変化までをやさしく解説します。読み終えたときには、自分に合ったREITを見極める判断軸が手に入るはずです。
REITとは何か──仕組みと基本概念
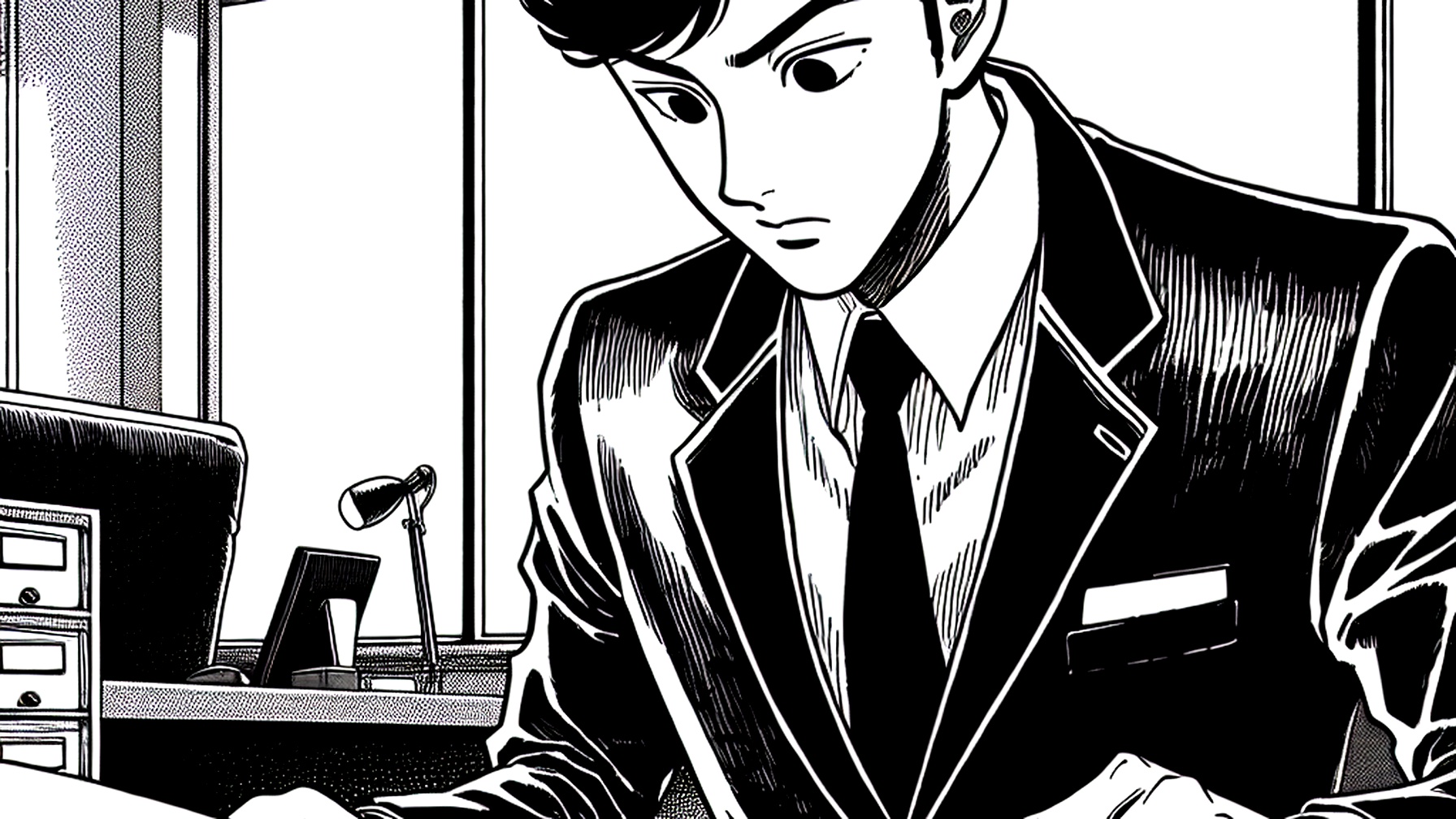
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を小口化した金融商品だという点です。投資法人がビルや物流施設などを保有し、賃料収入を投資家に分配します。言い換えると、投資家は証券取引所でREITを買うことで、不動産の「家賃」を間接的に受け取れるわけです。
日本のREITはJ-REITと呼ばれ、2001年に市場が開設されました。東京証券取引所のデータによれば、2025年9月末時点で70銘柄以上が上場し、時価総額は約20兆円に達しています。これは東証プライム全体の約2%に相当し、着実に資産クラスとして確立したと言えます。
重要なのは、REITが法律上「投資法人」であり、利益の90%以上を分配することで法人税が実質免税になる点です。そのため、収益の大部分が分配金として投資家に還元されます。ただし、賃料が減少すれば分配金も減るため、物件の管理やテナントの質が直接リスク要因になる点を忘れてはなりません。
日本のREIT市場の現状と評価

ポイントは、2024年から続く金利上昇局面でも、J-REITの平均配当利回りが約4%と上場株式平均を上回っていることです。日本銀行の長期金利統計を見ると、10年国債利回りが1%台半ばまで上昇した一方、REITの分配利回りは相対的に魅力を維持しています。
また、物件用途の多様化もポジティブに評価されています。オフィス主体の時代は終わり、物流施設・データセンター特化型が増えました。国交省の「不動産市場動向調査」によれば、2025年上期の物流施設空室率は2%台と依然低水準で、安定収益への期待が高まっています。
しかし、地方オフィスに特化した一部銘柄では空室率上昇が続き、SNS上では「分配金が減った」「REIT 評判が悪化した」との声も散見されます。つまり、銘柄間の実力差が広がっているのが現状です。平均値だけでなく個別のポートフォリオを精査する必要があります。
投資家が感じるメリット・デメリットと評判の真実
実は、REITが高い評価を受ける理由の一つは「手間の少なさ」です。現物不動産と異なり、物件探しや入居者対応をプロに任せられます。さらに、最低投資金額は数万円程度からと参入障壁が低く、分配金も年2〜4回と現金化しやすい点が好評です。2025年版NISA口座でもREITは上場株式と同様に非課税枠の対象となり、若年層の利用が増えています。
一方で、デメリットに関する評判も根強くあります。市場価格が株式同様に日々変動するため、相場下落時には元本割れリスクを抱えます。また、金利上昇に弱いとの指摘があります。これは、借入比率(LTV)が高い銘柄ほど金利負担が増え、分配金が圧迫される可能性があるためです。投資家のコミュニティでは「LTV50%超の銘柄は要注意」といった議論が目立ちます。
つまり、REITは「不動産の安定性」と「株式の値動き」を併せ持つハイブリッド商品です。評判をうのみにせず、どちらの性質が自分の投資方針に合うかを見極める姿勢が不可欠です。
REIT選びで押さえておきたい指標とチェックポイント
重要なのは、配当利回りだけに目を奪われないことです。たとえばLTV(Loan To Value=総資産に対する借入比率)、NAV倍率(純資産価値に対する市場価格)、そして稼働率の推移を総合的に確認しましょう。これらは投資法人の決算説明資料で公開されています。
例えば、LTVが40%台前半で、稼働率が95%を超えている物流特化型REITは、金利上昇耐性と安定収益の両立が期待できます。一方、LTV60%超で地方オフィス比率が高い銘柄は、利回りが高く見えてもリスク要因が多いと判断できます。
加えて、「増資履歴」にも注目してください。頻繁な公募増資は物件取得による成長を示すものの、既存投資家の1口当たり利益を希薄化する側面があります。日本取引所グループの統計では、2023〜2025年度の増資回数が10回を超える銘柄は全体の15%程度にとどまりますが、そのパフォーマンスは二極化しています。
最後に、運用会社のスポンサー力も見逃せません。大手不動産デベロッパーや金融機関がスポンサーの場合、資金調達や物件パイプラインで優位性があります。REIT 評判の裏には、こうしたスポンサーの信用力が大きく影響しているのです。
2025年度の制度変更と今後の見通し
ポイントは、2025年度から適用されている「不動産特定共同事業法」の改正です。オンライン完結型の小口不動産ファンドとREITの競合が進み、投資家の選択肢が拡大しました。しかし、金融庁によるとREITは上場規制が厳格な分、情報開示が透明である点がむしろ評価されています。
また、2025年度税制改正では、REITに対する法人課税の優遇措置が維持されました。期間の明確な延長は示されていませんが、現行制度は当面継続見込みとされています。したがって短期的に税制リスクは小さいと考えられます。
一方で、日銀の金融政策は依然として不確実性を伴います。市場では「2026年までに政策金利がさらに0.25%上がる」との観測もあり、REIT価格のボラティリティが高まる局面が想定されます。分配利回りが魅力的に見えても、金利感応度が高い銘柄への集中投資は避け、セクター分散を図ることが安全策となるでしょう。
まとめ
本記事では、REITの仕組みから日本市場の現状、投資家の評判、指標の読み方、そして2025年度の制度動向までを解説しました。結論として、REITは少額で不動産収益を得られる魅力的な選択肢ですが、銘柄ごとのリスク差が広がる時代に入っています。配当利回りだけでなくLTVや稼働率、スポンサー力を確認し、自分のリスク許容度に合った銘柄を選ぶことが成功の近道です。まずは各REITのIR資料に目を通し、分散投資で長期的な資産形成を目指してみてください。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 東京証券取引所「J-REIT市場データ」 – https://www.jpx.co.jp/
- 国土交通省「不動産市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行「長期金利統計」 – https://www.boj.or.jp/
- 一般社団法人不動産証券化協会 – https://www.ares.or.jp/

