投資を始めたいけれど、いきなり1,000万円以上の物件は怖い――そんな悩みを抱える方は少なくありません。実は地方の区分マンションや築古アパートの一室なら、500万円前後でも収益物件を取得できます。ただし低価格だからこそ、綿密な収支計算を怠ると「家賃は入るのに手残りゼロ」という事態に陥りがちです。本記事では「収益物件 500万円 収支計算」をテーマに、投資初心者でも再現できる算式とシミュレーション手順を解説します。読み終えたときには、購入判断に必要な数字の読み方と2025年度時点で活用できる制度上の注意点まで理解できるようになります。
500万円前後の物件が狙えるエリアと種類
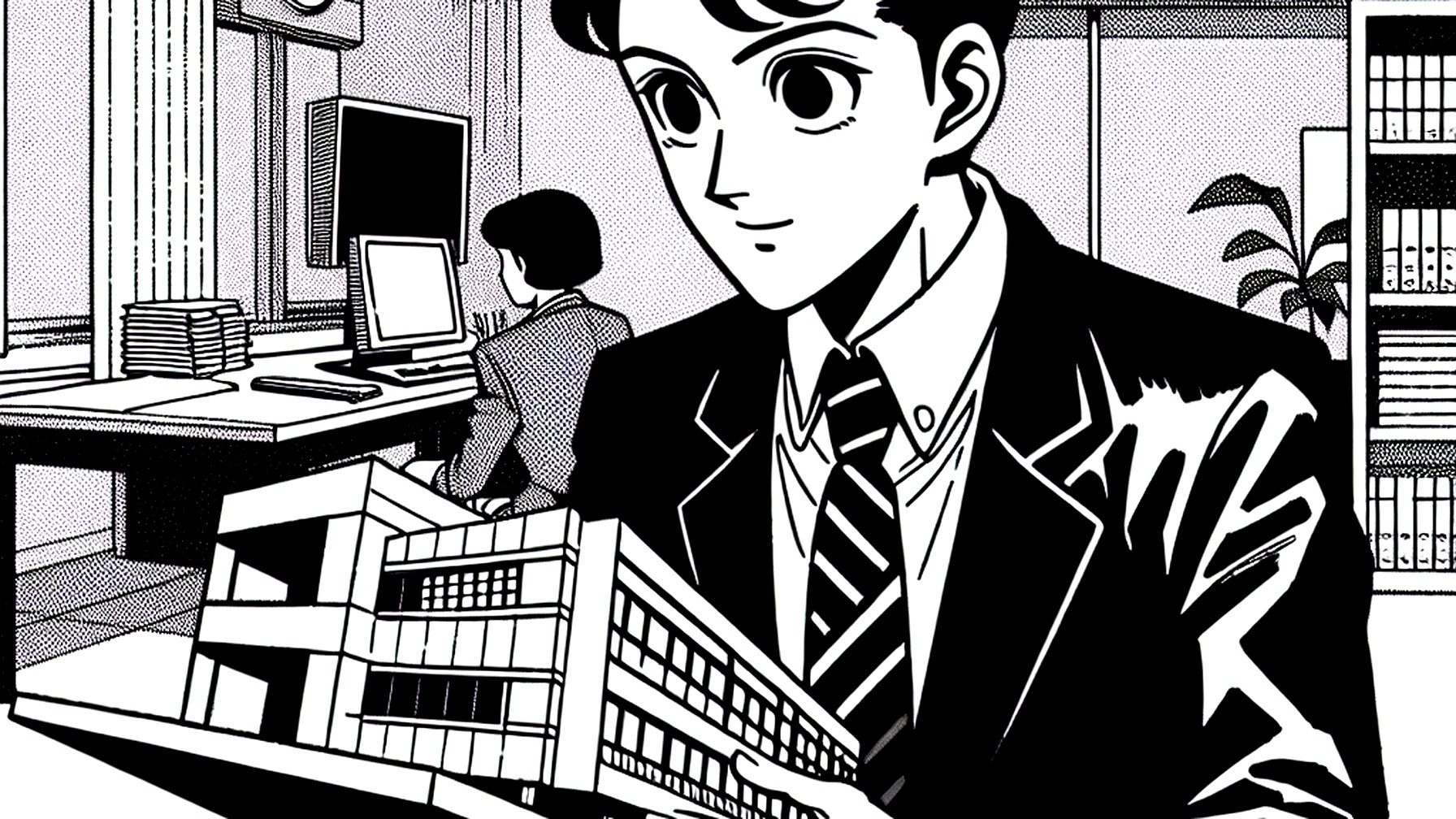
まず押さえておきたいのは、500万円クラスの物件が成立する市場背景です。国土交通省「不動産価格指数(2025年6月速報)」によると、地方中核都市でも築25年以上のワンルーム区分価格は平均380万〜620万円のレンジに収まっています。人口15万〜30万人規模の地方都市であれば、賃貸需要が底堅く、500万円台の物件も供給されています。
一方、同価格帯の木造アパート一棟ものは、築30年以上・最寄り駅徒歩20分以上といった条件が一般的です。利回りは表面12〜15%と高めでも、修繕負担が大きくキャッシュフローが圧迫されやすい点に注意しましょう。つまり「区分で安定・一棟で高利回り」の違いを理解し、戦略とリスク許容度を合わせることが肝心です。
重要なのは、賃料相場と空室率を客観視することです。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会のデータでは、地方中核都市の平均空室率は14.1%(2024年度)ですが、駅徒歩10分圏内の築古区分は約9%に下がります。エリアと物件種別の組み合わせによって収益構造が大きく変わるため、購入前にデータで裏付ける姿勢が成功を左右します。
収支計算の基本フローを押さえる
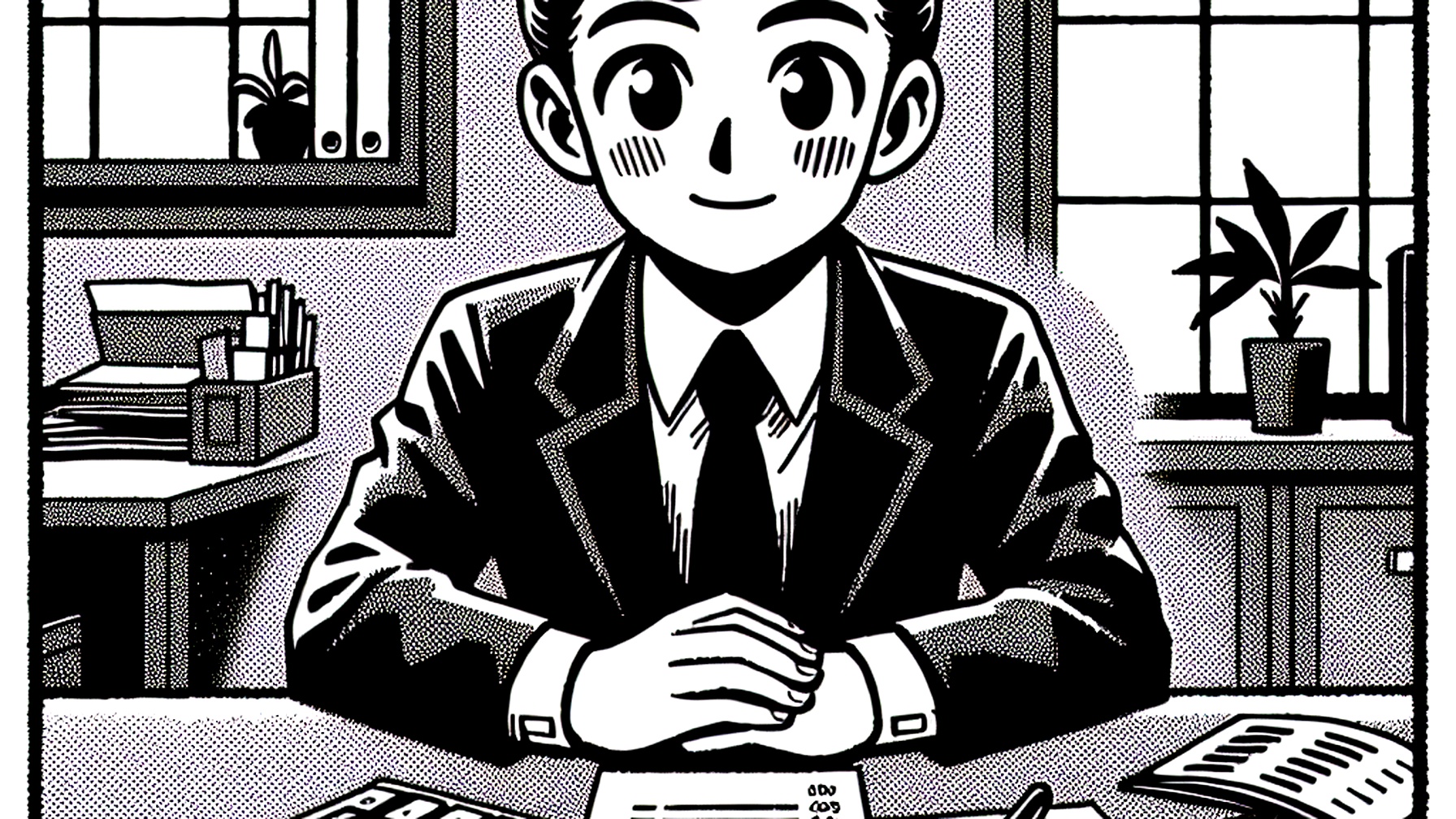
ポイントは、家賃から経費と返済を差し引き、最終的な手残り(キャッシュフロー)を確認する流れを守ることです。計算手順を文章で整理すると、次のようになります。
- 想定年間家賃収入を求め、空室リスクを反映して調整後家賃収入を算出
- 管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険料など毎年かかる運営経費を差し引く
- 借入を利用する場合は年間返済額を計算し、運営経費差引後の純収益から控除
まず家賃設定は、周辺成約事例の下位20%水準を基準にすると保守的な数字になります。次に経費率ですが、区分マンションなら年間家賃の25〜30%、木造アパートなら30〜35%を見込むと、突発的な修繕にも対応しやすいです。
運営経費を差し引いた後に残る「NOI(ネットオペレーティングインカム)」を把握したら、借入返済を控除してキャッシュフローを確定します。ここまで計算して初めて利回りが自分の投資基準を満たすかどうか判断できます。返済比率(返済額÷NOI)が50%を超えると資金繰りがタイトになるため、慎重に検討しましょう。
実例で学ぶキャッシュフローシミュレーション
実は具体的な数字を当てはめると、収支のイメージが一段と鮮明になります。以下は、地方中核都市の築28年RC造ワンルーム(購入価格500万円、専有面積20㎡)を想定したケースです。
まず家賃は月4万5,000円、年間54万円とします。平均空室率10%を見込み、調整後家賃収入は48万6,000円です。管理費・修繕積立金は月6,000円で年間7万2,000円、その他の経費(火災保険・固定資産税など)は年間4万円とします。経費合計は11万2,000円、したがってNOIは37万4,000円です。
次に融資条件を年利2.2%、期間15年、自己資金100万円、借入400万円と仮定します。年間返済額は約32万4,000円(元利均等)です。NOIから返済を引くとキャッシュフローは5万円、表面利回りは10.8%、実質利回り(NOI ÷ 購入価格)は7.5%、自己資金利回り(キャッシュフロー ÷ 自己資金)は5%。一見、数字は悪くありませんが、空室率が15%に上がれば手残りはほぼゼロになる点が課題です。
つまり、500万円物件では少額とはいえ利益幅も限られているため、入居付けを安定させる管理体制が何より重要になります。また、毎月5,000円の修繕費が追加で発生すると赤字転落するため、購入時に給排水管や屋根防水の状態を必ず確認しておきましょう。
運用コストとリスク評価を忘れない
基本的に収支計算で見落としがちな費目は、将来の大規模修繕と退去時リフォームです。国土交通省「マンション総合調査(2024年度)」では、築30年超物件の平均修繕積立水準は月300円/㎡ですが、実際の工事費はその1.4倍に達するケースが多いと報告されています。差額は所有者が一時金で負担する可能性が高いため、事前に積立不足を確認してください。
また、賃貸借契約更新料や広告料もキャッシュフローに影響します。更新料1万円、広告料家賃の1か月分といった費用は、運営経費に含めておけば収支ブレが抑えられます。さらに、2025年10月時点で導入が進むインボイス制度は、課税事業者オーナーにとって消費税納税額を増やすリスクがあります。免税事業者なら影響は限定的ですが、売上1,000万円超を視野に入れる場合は税理士と相談したほうが安全です。
空室リスクに対しては、物件設備のアップデートが有効です。例えばネット無料化やスマートロック導入は、初期費用10万円程度で入居付けのスピードが向上したという管理会社の事例もあります。リスクを数字で管理しつつ、収益改善策を組み合わせる姿勢が、少額投資を成功に導く鍵となります。
2025年度の融資と税制でチェックしたい項目
ポイントは、低金利環境が続く一方で、金融機関の融資姿勢が物件規模によって明確に分かれていることです。地銀や信用金庫は500万円前後の小口案件に積極的とはいえず、ノンバンクや信販系ローンを活用するケースが増えています。金利は2.0〜3.5%程度が中心ですが、返済期間が最長15年に制限されることが多いため、返済負担率の計算を怠らないでください。
税制面では、2025年度の所得税法で定める減価償却期間に変更はなく、築28年のRC造区分なら残存法定耐用年数は22年−28年=0年となります。0年の場合、短期償却(4年)を用いる特例により大きく経費計上できるメリットがありますが、赤字が続くと融資審査に影響するためバランスが必要です。
さらに、2025年度の「住宅セーフティネット制度」では、登録住宅への改修補助が継続しています。ただし対象は高齢者・子育て世帯向けのバリアフリー改修を行う貸主であり、上限は改修費の1/3・最大50万円です。500万円物件の利回り改善には有効ですが、地方自治体ごとに募集枠が異なるため、申請前に最寄りの都道府県窓口で詳細を確認しましょう。
最後に、譲渡所得税の軽減措置(長期譲渡20.315%)は2025年も有効です。売却益を視野に入れるなら、5年以上保有して税率を下げる計画を立てると、手残りを最大化できます。融資・税制の最新動向を踏まえ、買う前に出口戦略まで描いておくことが、堅実な投資には欠かせません。
まとめ
500万円の収益物件は、少額で始められる一方、利益幅が小さい分だけ収支計算の精度が問われます。家賃、経費、返済を保守的に見積もり、NOIとキャッシュフローを必ず確認してください。さらに、修繕積立不足や空室リスクといったコストを織り込み、インボイス制度や減価償却など2025年度の最新ルールにも注意を払いましょう。行動を起こす際は、数値で裏付けた計画と信頼できる管理体制をセットで準備することが、安定した不動産投資への近道です。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数(2025年6月速報) – https://www.mlit.go.jp
- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場データ(2024年度版) – https://www.jpm.jp
- 国土交通省 マンション総合調査(2024年度) – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 税制改正資料(2025年度) – https://www.mof.go.jp
- 環境省 住宅セーフティネット制度ガイドライン(2025年度版) – https://www.env.go.jp

