不動産投資に興味はあるけれど「高額な物件を直接買うのは怖い」と感じる読者は多いはずです。そこで注目されるのが少額で始められるREIT(リート)ですが、「REITは本当に安全なのか」という疑問も残ります。本記事では安全性を左右する仕組みやリスク管理のポイントを、2025年10月時点の最新制度を交えて丁寧に解説します。読み終えたころには、REITを安心して活用するための具体的な判断軸が手に入るでしょう。
REITの基本構造と安全性を測る視点
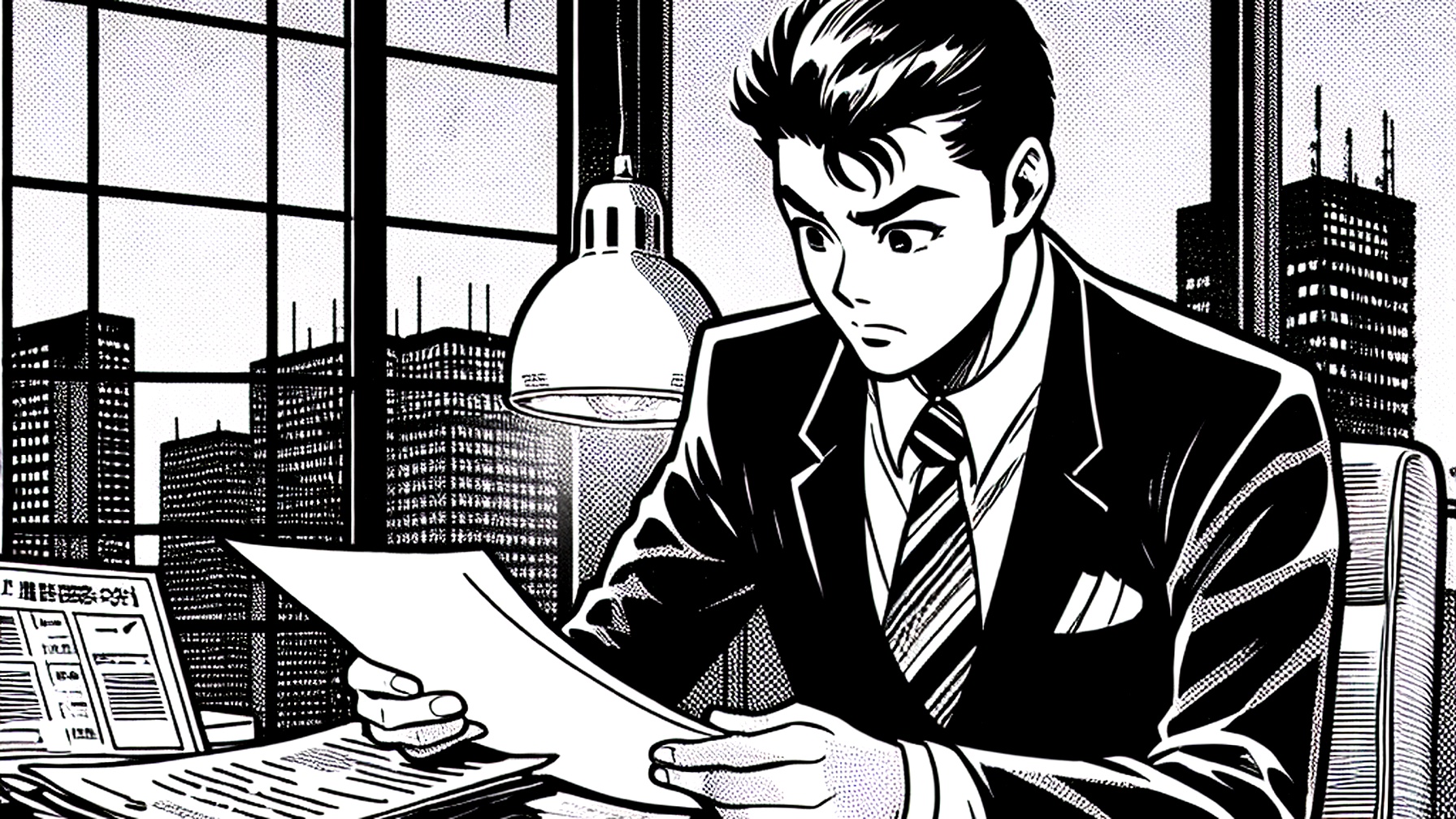
まず押さえておきたいのは、REITが投資家から集めた資金で複数の不動産を保有し、その賃料収入や売却益を分配する仕組みだという点です。この構造により、一つの物件で起こるトラブルが全体の収益に直結しにくく、リスクを薄める効果が期待できます。
国土交通省の2025年版「不動産市場動向調査」によると、東京証券取引所に上場するJ-REITの平均利回りは3.8%前後で推移しています。これは長期国債利回りを上回る水準でありながら、年間の価格変動幅は主要株価指数より低い傾向にあります。つまり価格のブレを抑えつつ、一定のキャッシュフローを得やすい点が安全性の源泉と言えます。
一方で、REITは株式と同じく市場で取引されるため、景気悪化や金利上昇の影響を無視できません。安全性を語る上では、物件ポートフォリオの分散度合い、財務レバレッジ(借入比率)、運用会社の実績を複合的に確認することが重要になります。
資産分散とプロ運用がもたらす防御力
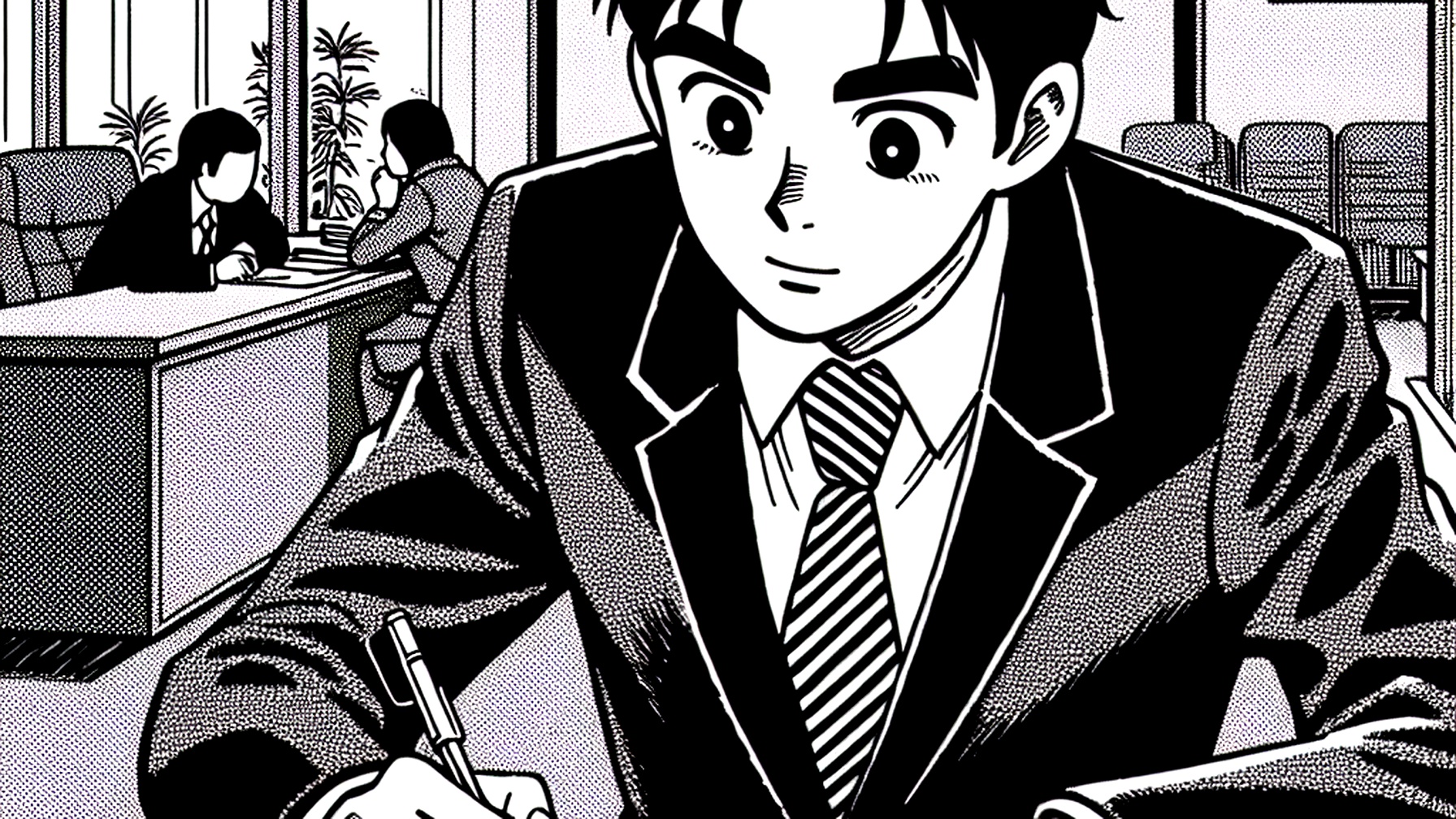
重要なのは、REITが「複数物件への分散投資」と「専門家による運用」を両立している点です。個人がワンルームマンションを一棟買う場合、空室が出れば即座に収益が途切れますが、REITならオフィスビルや商業施設、物流倉庫などさまざまな用途の不動産から賃料が入ります。
投資信託協会の2025年レポートによれば、上場REITの平均運用物件数はおよそ100棟に及びます。用途別の比率もバランスよく調整されており、例えば商業系40%、オフィス系30%、住居系20%、その他10%といった形です。この比率は景気循環による影響を互いに打ち消す効果が期待でき、安全性向上に寄与します。
さらに、プロの運用会社がテナント管理や資金調達を一括して行うため、個人で発生しがちな管理の手間や交渉リスクを省けます。REIT 安全という観点では、この専門性こそが最大のメリットです。ただし運用会社の手腕によって成績が分かれるため、過去の分配金推移や格付機関の評価を確認する姿勢が欠かせません。
市況変動時にREITが受ける影響とその備え
ポイントは、REITの価格が「不動産市況」と「金融市場」の両方の影響を受ける点にあります。景気後退局面ではテナント退去による賃料減少リスクが高まり、同時に株式市場の下落がREIT価格を押し下げることがあるのです。
例えば2023〜2024年の金利引き上げ局面では、一部のJ-REIT銘柄が年間で15%程度調整しました。しかし東京証券取引所のTOPIXが同期間に約20%下落したのと比べると、REITの価格弾力性は相対的に低かったことが分かります。これは賃料収入が比較的安定していたためで、市場全体が動揺しても配当利回りが下支えになる構造が働きました。
実は、REIT 安全を確保する上で注目すべき指標があります。それがLTV(Loan to Value:総資産に対する借入金比率)です。LTVが50%を超える銘柄は金利上昇時に返済負担が増しやすく、分配金減少のリスクが高まります。一方で40%前後に抑えられたREITは資金余力があり、逆風下でも安定した運営が見込めます。
個人投資家が実践できる安全策
まず個人が取るべき基本行動は、複数銘柄への投資でさらなる分散を図ることです。REIT自体が分散投資商品とはいえ、一つの銘柄に偏れば建物用途や地域が集中し、想定外のリスクに晒されます。毎月積立で複数銘柄を購入すれば、時間と銘柄の二つの分散が働きます。
次に重視したいのが保有コストです。証券口座によってはJ-REIT取引の売買手数料が無料化されている場合があります。コストを抑えれば、分配金の実質利回りが高まり、長期保有の安全域が広がります。また、分配金をそのまま再投資する「DRIP」機能を使えば、価格変動の影響を平準化しながら資産を拡大できます。
そして、情報を継続的に追う姿勢も欠かせません。運用報告書や決算説明資料には、テナントの入退去状況、借入金利、物件取得方針など安全性を判断する材料が豊富に含まれています。半年に一度でも目を通す習慣を持つだけで、突発的なリスクを早期に察知できます。
2025年の制度を活用して安全性を高める
基本的に、税制優遇を上手に使えば投資効率が高まり、同じリスクでも手取りリターンが増えるため安全域が広がります。2025年度の新しい「成長投資枠付きNISA」は年間360万円まで非課税で再投資が可能で、上場REITも対象です。非課税期間が無期限化されたことで、長期保有するほど税効果が大きくなります。
さらに、確定拠出年金制度の一つであるiDeCo(個人型確定拠出年金)でも、REITを組み込める運用商品が増えています。掛金は全額所得控除、運用益も非課税という2重の優遇が受けられるため、リスク許容度の範囲内でREITを組み込むと実質的な手取り利回りが向上します。
ただし、制度には拠出上限や引き出し制限など独自のルールがあります。NISAは年間投資額、iDeCoは60歳まで原則引き出せない点をふまえ、流動性リスクと安全性を天秤にかける必要があります。制度を活用する際は、金融庁の公式ガイドを参照し、最新の上限額と手続き方法を確認しましょう。
まとめ
REIT 安全のカギは「分散」「プロ運用」「適切な指標確認」の三点に集約されます。物件分散と専門家の運用体制がリスクを抑え、LTVや利回りといった指標が安全度を測る物差しになります。さらに2025年度のNISAやiDeCoを利用すれば、税負担を減らしながら長期保有による恩恵を最大化できます。まずは複数のREITを少額ずつ積立し、運用報告を定期的にチェックするところから始めてみてください。堅実な一歩が、安定収益への近道になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 東京証券取引所 J-REIT市場統計 – https://www.jpx.co.jp
- 投資信託協会 REITレポート2025 – https://www.toushin.or.jp
- 金融庁 NISA・iDeCo公式ガイド – https://www.fsa.go.jp
- 総務省 統計局 経済指標データ – https://www.stat.go.jp

