60代になり、退職金や年金だけで老後を乗り切れるか不安を抱く方は少なくありません。また、預貯金の金利は低迷し続け、資産を眠らせておくだけでは目減りする一方です。こうした状況で注目されているのが、毎月の家賃収入を得ながら資産を守れるマンション投資です。特にファミリー向け物件は長期入居が期待でき、安定を重視する60代に適した選択肢と言えます。本記事では最新データを交えつつ、物件選びから資金調達、リスク管理、相続までを体系的に解説します。読み終えたころには、老後の安心と家族への資産承継を両立させる具体的な行動イメージが得られるでしょう。
60代からのマンション投資が注目される背景
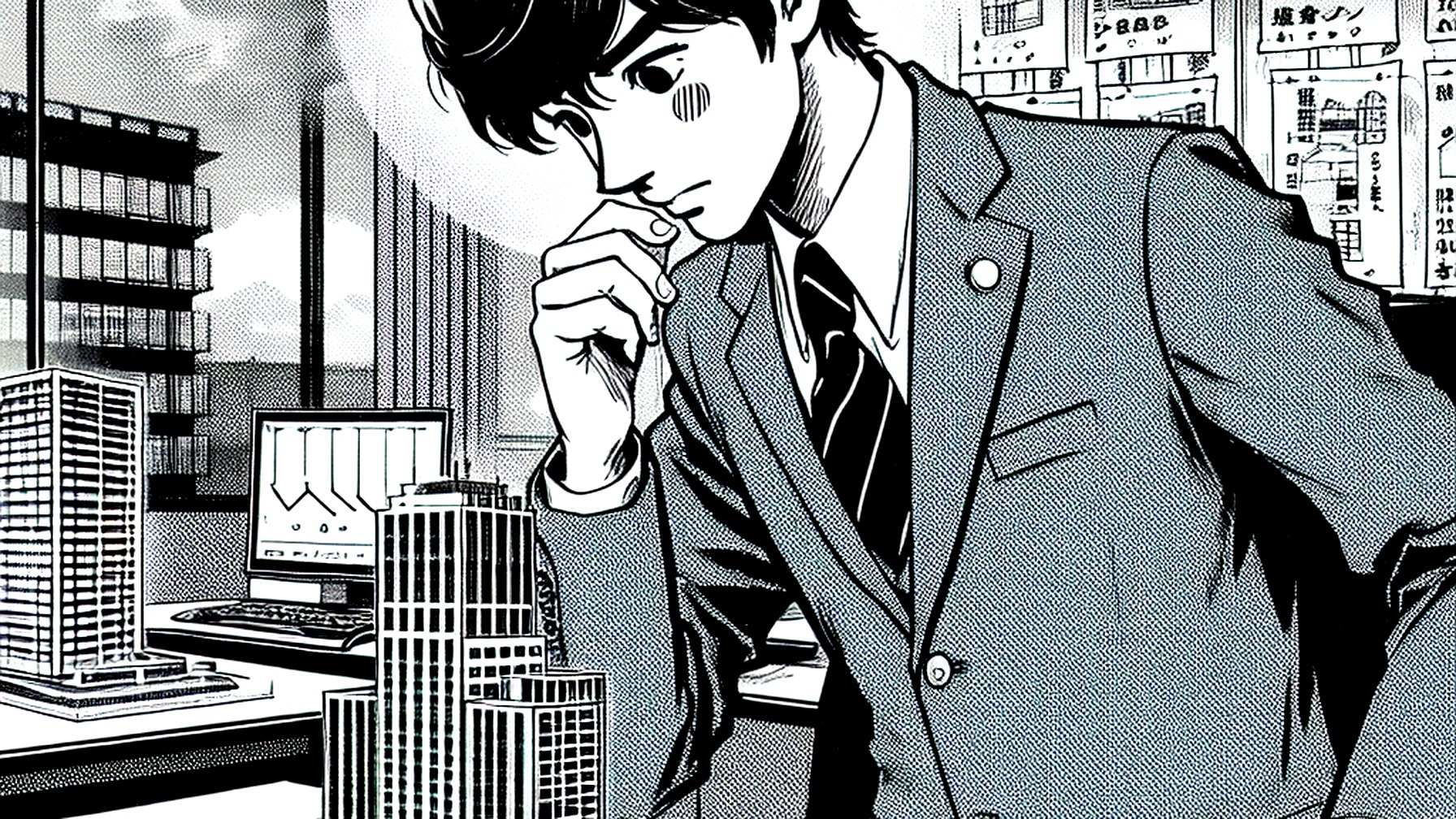
重要なのは、年金収入だけに頼らない複線的なキャッシュフローを確保することです。総務省「家計調査」によると、65歳以上の無職世帯の平均純貯蓄は1,800万円ですが、医療費や介護費の増加で20年後には不足するという試算が示されています。そこで家賃収入を得る不動産投資が選択肢に上がるのです。
まず、マンション投資のなかでもファミリータイプは入居期間が平均7年程度とされ、単身向けワンルームの約4年と比べて長い傾向があります。長期入居は空室損失の低減につながり、将来の収支予測を立てやすくします。また、2025年10月時点の東京23区新築マンション平均価格は7,580万円ですが、築15〜20年の70㎡台ファミリー物件なら4,000万円台も珍しくありません。価格ゾーンが多様で選択肢が広がることも魅力です。
一方で、60代は金融機関の融資条件が厳しくなるという現実があります。しかし、自己資金を多めに入れる、返済期間を短く設定するなど工夫すれば、依然として融資を受けられる余地はあります。つまり、年齢を理由に投資機会を諦める必要はないのです。
ファミリー向け物件ならではのメリットと注意点
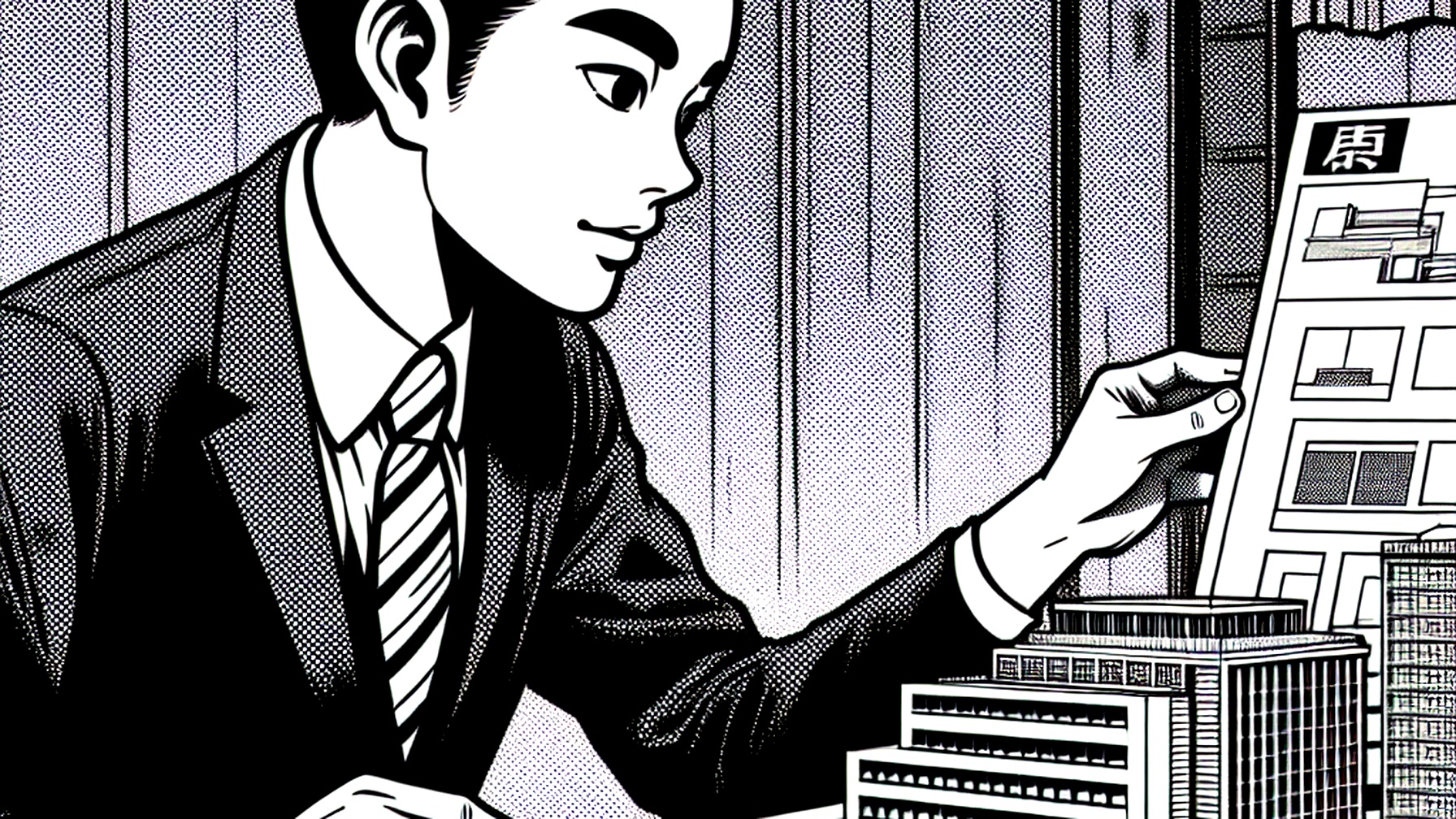
ポイントは、生活利便性と教育環境が両立する立地を選ぶことです。ファミリー世帯は子育てを重視するため、小学校まで徒歩10分圏内、スーパーや公園が近いエリアを好む傾向があります。国土交通省の住宅市場調査でも、この条件を満たす物件は空室率が半分以下に抑えられるとのデータがあります。
具体的には、駅徒歩10分以内で70㎡前後の3LDKが最も成約スピードが速いと言われます。家賃設定も単身向けより高く、同じ面積単価でも収益額は上がりやすいのが強みです。ただし広さがあるぶん、修繕費や固定資産税も大きくなるため、長期的なランニングコストを必ず試算しておく必要があります。
さらに、ファミリー向け物件は設備の故障リスクが高い点に注意が必要です。人数が多いほど水回りや給湯器の使用頻度が増えるからです。実際、日本マンション管理士会の統計では、築20年超の3LDK物件では給湯器交換が10年に1回以上発生する確率が72%とされています。費用は20万円前後かかるため、年間キャッシュフローに織り込んでおくと安心です。
資金計画と融資の現実:60代でも可能な調達方法
実は、60代であっても融資を受けることは十分可能です。日本政策金融公庫や一部地方銀行は、完済時年齢80歳までを上限とする商品を提供しています。例えば70歳完済なら10年ローンが組める計算です。自己資金を50%程度入れると、返済比率が下がり審査通過率が大幅に上がります。
また、退職金を頭金として活用し、残りをローンで賄うのが王道です。退職金1,500万円を頭金にし、利回り5%・借入金利2%・10年返済でシミュレーションすると、年間キャッシュフローは約90万円前後が見込めます。退職金を銀行預金のまま0.001%で置いておくのと比べ、資産効率が格段に上がるわけです。
ただし、変動金利に依存し過ぎると金利上昇リスクに晒されます。住宅金融支援機構の「フラット投資35」は利用できませんが、地方銀行が提供する固定期間選択型ローンを組み合わせるなど、金利タイプを分散すると安定度が増します。
空室・修繕リスクと管理体制:長期安定運用のポイント
まず押さえておきたいのは、入居者ターゲットを明確にし、募集条件を柔軟に調整することです。ファミリー層はペット可や宅配ボックスなど生活利便設備を重視する傾向が強いため、競合物件との差別化が欠かせません。管理会社と月1回程度の進捗確認を行い、賃料や広告料の見直しを機動的に行う体制を整えましょう。
次に、長期修繕計画の把握が必須です。分譲マンションでは管理組合が修繕積立金を決定しますが、築20年を超えた物件の平均積立金は月額300円/㎡前後に上昇すると言われます。70㎡なら月2万円以上が目安です。購入前に過去の総会議事録を確認し、将来の負担増を見極めてください。
さらに、地震や水害リスクへの備えも怠れません。国土交通省のハザードマップポータルサイトで所在地を確認し、リスクが高い場合は地震保険・水災補償を付帯します。保険料は年間数万円ですが、万一の損害を補償できれば家賃収入の途切れを防げます。
相続と出口戦略:次世代に資産をつなぐコツ
ポイントは、「生前贈与」と「相続時精算課税」を組み合わせて負担を軽減することです。2025年度も贈与税の特例は存続しており、年間110万円までの非課税枠が活用できます。さらに、相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円まで非課税でまとめて贈与でき、相続開始時にまとめて精算する仕組みです。マンションを将来渡したい子どもがいる場合、賃料収入を贈与する形で早めに持分を移転しておくと、相続税評価額を抑えながら家族に収益を分配できます。
出口戦略としては、将来の市場動向を踏まえ、築25年を超えた時点で売却かリノベーションかを検討するのが現実的です。国土交通省のデータでは、築30年を超えると家賃が平均15%下落する一方、売却価格は築20年を過ぎても緩やかな下落に止まっています。つまり、キャッシュフローが目減りしてきた段階で売却し、次の資産運用に乗り換えるのも賢明な選択です。
「結論として」、60代のマンション投資はキャッシュフローと資産承継を同時に実現できる有力な手段です。しかし、融資条件や修繕費、相続まで視野に入れた長期計画が不可欠です。専門家と連携しながら、出口戦略まで描いた投資を進めましょう。
まとめ
ここまで、60代の方がファミリー向けマンション投資に取り組む際の要点を確認してきました。安定した賃料を得るためには、長期入居が期待できる立地と広さに焦点を当て、修繕や金利の変動を視野に入れた保守的なシミュレーションを行うことが大切です。また、退職金を頭金にして融資期間を短縮すれば、年齢による審査ハードルを下げられます。最後に、早めの相続対策と出口戦略を検討することで、家族に負担をかけずに資産を継承できます。本記事を参考に、まずは物件情報の収集と資金計画の作成から着手してみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 総務省統計局「家計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 住宅局「住宅市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫「生活衛生貸付」 – https://www.jfc.go.jp
- 住宅金融支援機構「民間住宅ローンの実態」 – https://www.jhf.go.jp

