不動産投資に興味はあっても「数字が苦手だから」と一歩を踏み出せない人は多いものです。特に収益物件を購入した後に経営者として収支計算を誤ると、思わぬ赤字に転落しかねません。本記事では、初心者がつまずきやすい収入と支出の考え方を丁寧に解説し、2025年10月現在の制度や税制を踏まえた現実的なシミュレーション方法まで紹介します。読み終えたときには、自分で収支表を作り、将来のキャッシュフローを描けるようになるはずです。
収益物件の収支計算を押さえる理由

まず押さえておきたいのは、収益物件の成功要因は「購入時」ではなく「保有期間」にあるという事実です。物件を選ぶ段階では利回りばかりに目が向きがちですが、経営者としては長期にわたる収支計算を精緻に行うことでリスクを可視化できます。国土交通省の不動産投資市場調査(2024年版)でも、購入後に実質利回りが想定を下回った投資家の約六割が「支出項目の過小予測」を要因に挙げました。このデータは、計算一つで結果が大きく変わる現実を示しています。
次に、収支計算とは「年間総収入―年間総支出」を基本としますが、ここには減価償却費のような現金の出ない費用も含める必要があります。なぜなら税金計算の基礎となり、手残りに直結するからです。言い換えると、税引き後キャッシュフローまで把握しなければ、本当の収益力は見えません。また、金融機関は融資継続の判断材料として長期収支計画を要求することが多く、計算精度が低いと資金調達に苦戦する点も見逃せません。
さらに、2025年度も存続する新築住宅に対する固定資産税の3年間軽減措置など、公的優遇は収支改善に貢献します。ただし適用条件を満たすのは建物用途や規模によって異なるため、制度概要を理解したうえで物件選定に反映させる視点が必要です。
家賃収入を見積もる際の空室率設定
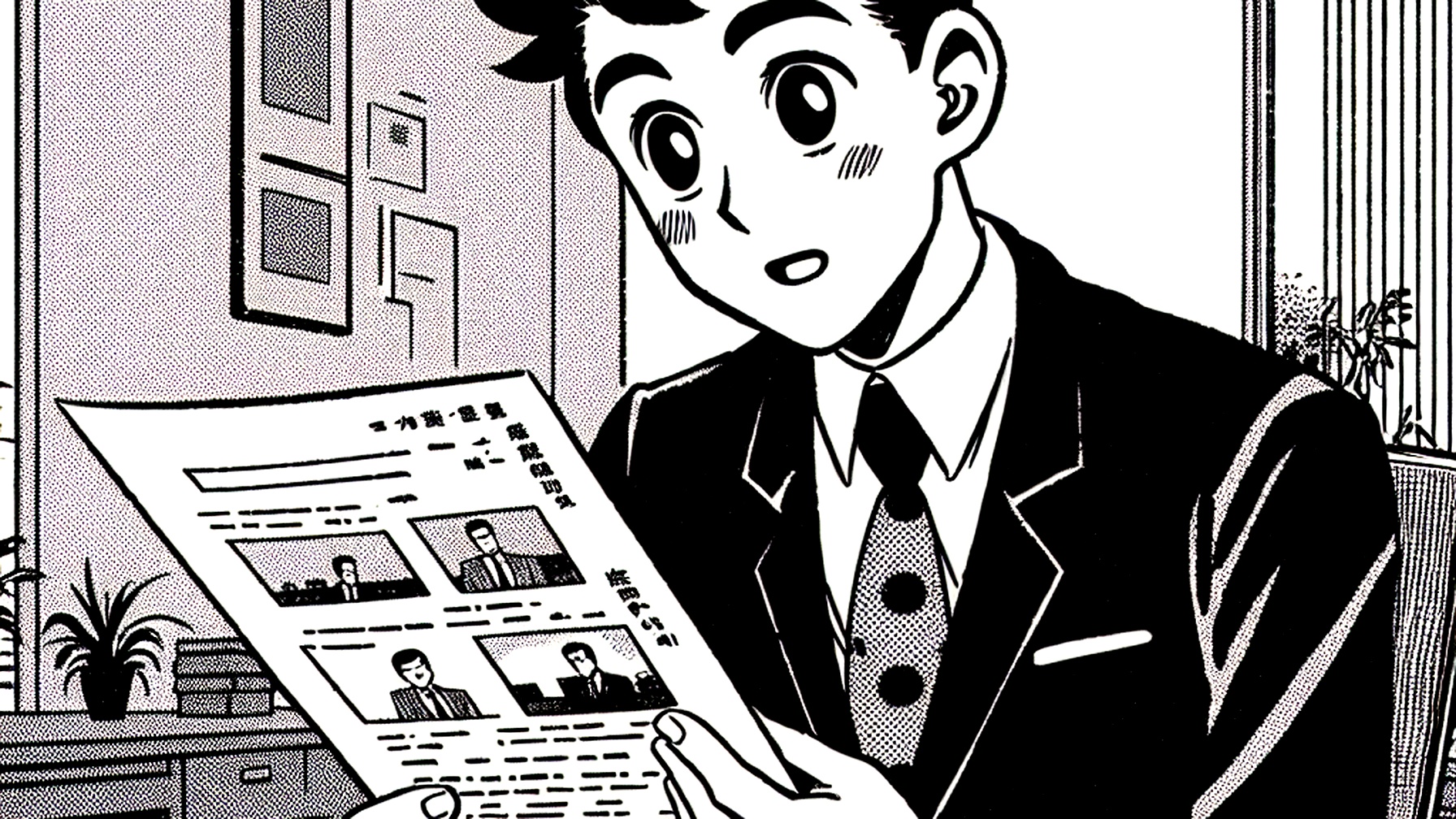
ポイントは、家賃収入を「満室想定」で終わらせないことです。総務省「住宅・土地統計調査」(2023年確定値)によると、全国平均の空室率は13.8%ですが、地方都市では20%を超えるエリアも珍しくありません。つまり立地や物件タイプによって適切な空室率を設定しなければ、収入予測が甘くなります。
最初のステップとして、近隣の成約家賃を複数サンプル取得し、中央値を基準に設定すると過度な楽観を避けられます。次に、購入予定物件が築浅か築古かによって賃料下落率を別々に置くと精度が増します。例えば築10年未満なら年間1%下落、築20年以上なら2%下落を想定するなど、国土交通省「賃貸住宅市場の概況」(2024年)に基づく平均値を参考にする方法が有効です。
一方で学生向けや単身者向けのワンルームは入退去が多く、ファミリータイプよりも空室期間が延びやすいとされています。経営者の立場で考えるなら、募集開始から成約までの広告コストやフリーレント期間も家賃収入を圧縮する要因として加味すべきです。こうした細かい調整が「期待利回りと実質利回りの差」を縮め、安心して長期保有できる土台を築きます。
経営者視点で見るコスト構造
実は支出項目は「見えるコスト」と「見えにくいコスト」に大別できます。見えるコストは管理委託手数料、固定資産税、火災保険料など毎年請求が来るものです。これらは比較的予測しやすいため、過去実績や自治体税率を確認すれば大きく外れることはありません。また2025年度の火災保険料は、損害保険料率算出機構の統計によると築年数が30年を超える木造物件で平均15%上昇しており、築古物件を選ぶ場合はここを高めに見ておくと安心です。
一方で見えにくいコストの代表格が修繕費です。国立研究開発法人建築研究所の「長期修繕費実態調査」(2024年)では、RC造マンションの平均修繕積立額は㎡あたり月240円、築30年以降は同420円に増加します。つまり築古RCを購入するなら、将来の大規模修繕を想定し、月の家賃収入の10%前後を修繕積立に振り向けるとキャッシュフローが急変しません。
さらに、ローン金利上昇リスクもコスト構造に含まれます。日本銀行が2025年4月に長期金利の上限を1.5%へ引き上げたことで、変動金利型アパートローンでもじわりと金利が上昇しています。金融機関が示すストレスシナリオ(+1.0%)を自分自身の収支計算でも反映し、返済比率が家賃収入の40%を超えないかチェックする姿勢が求められます。
キャッシュフローと税金の基礎
基本的にキャッシュフローは「税引き後」で評価するのが実務的です。家賃収入から経費を差し引いた不動産所得に対して、所得税と住民税が課税されるため、税効果を無視すると資金繰りを読み誤ります。国税庁「令和6年分所得税の税率表」によれば、課税所得が195万円以下なら5%、330万円以下なら10%と段階的に上がるため、物件が増えるにつれ手取り率が下がる点に注意してください。
減価償却費は税金を抑える主要手段です。例えば築25年の木造アパートを購入すると、法定耐用年数22年の1.5倍ルールにより残存耐用年数は3年になります。短期償却で経費を一気に計上できる半面、4年目以降は償却費がなくなり税負担が急増するため、追加投資や修繕で経費バランスを調整することが重要です。
また、2025年度も適用される「特定中古住宅の取得に伴う登録免許税軽減」は、個人投資家でも要件を満たせば税率が本則の2.0%から1.0%へ下がります。取得初年度のキャッシュアウトを抑えられるため、購入タイミングで忘れずに申請しましょう。ただし適用期限は2026年3月末までと告示されているため、長期計画に組み込む場合はスケジュール管理が欠かせません。
収支計算の実践シミュレーション
重要なのは、数字を「動かして」初めてリスクの大きさが見える点です。ここでは首都圏郊外の築15年RCマンション(総戸数12戸・表面利回り7.5%)を例に、年間収支を試算します。家賃収入は満室想定で年間960万円とし、空室率10%を適用して864万円に修正します。管理費・修繕積立・固定資産税・保険料などを合計すると年間250万円、ローン返済は金利1.5%、期間25年、元利均等で年間360万円になります。
この時点で税引き前キャッシュフローは254万円です。さらに減価償却費200万円を計上すると課税所得は54万円となり、所得税住民税合計は約11万円(税率20%想定)に抑えられます。結果として税引き後キャッシュフローは243万円、月額約20万円が手残りとなります。
しかし金利が+1.0%上昇すると返済額は年間40万円増え、キャッシュフローは203万円に縮小します。空室率が15%へ拡大すると家賃収入は816万円に下がり、さらに48万円減少します。このように主要パラメータを同時に動かすことで、最悪シナリオでも資金繰りがプラスかどうかチェックできます。言い換えると、キャッシュフローがゼロ付近になるラインを把握しておけば、追加資金や販促策を前倒しで打てるため、赤字転落を回避できるわけです。
結論として、収支計算は一度作って終わりではなく、毎年アップデートしながら金融情勢や物件状態の変化を数字で管理する習慣が、収益物件を経営者目線で守り育てる鍵となります。
まとめ
ここまで、収益物件を購入した後に経営者として押さえるべき収支計算の手順と注意点を解説しました。家賃収入の見積もりでは空室率と賃料下落率を現実的に設定し、支出面では修繕費や金利上昇といった見えにくいコストを忘れずに組み込みます。さらに税引き後キャッシュフローで評価することで、実際の手取りを把握できます。これらを踏まえてシミュレーションを継続的に更新すれば、環境変化に柔軟に対応できる堅実な投資運営が可能です。まずは自分の物件に当てはめて数字を動かし、安定したキャッシュフロー体質を築いていきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場調査2024 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp/
- 損害保険料率算出機構 火災保険参考純率 2025 – https://www.giroj.or.jp/
- 建築研究所 長期修繕費実態調査2024 – https://www.kenken.go.jp/
- 国税庁 所得税法令解説 令和6年版 – https://www.nta.go.jp/

