マンション一棟投資に興味を持ちつつも、「危険 マンション投資 一棟買い」という検索ワードに戸惑う人は少なくありません。自己資金の何倍もの借入を背負い、長期にわたり運用する以上、一つの判断ミスが家計を揺るがすからです。本記事では、初心者がつまずきやすい五つのリスクを取り上げ、数字の読み方から管理のコツまで具体的に解説します。読み終えるころには、物件選びと資金計画を自分でチェックできる力が身につくでしょう。
キャッシュフローを可視化する第一歩
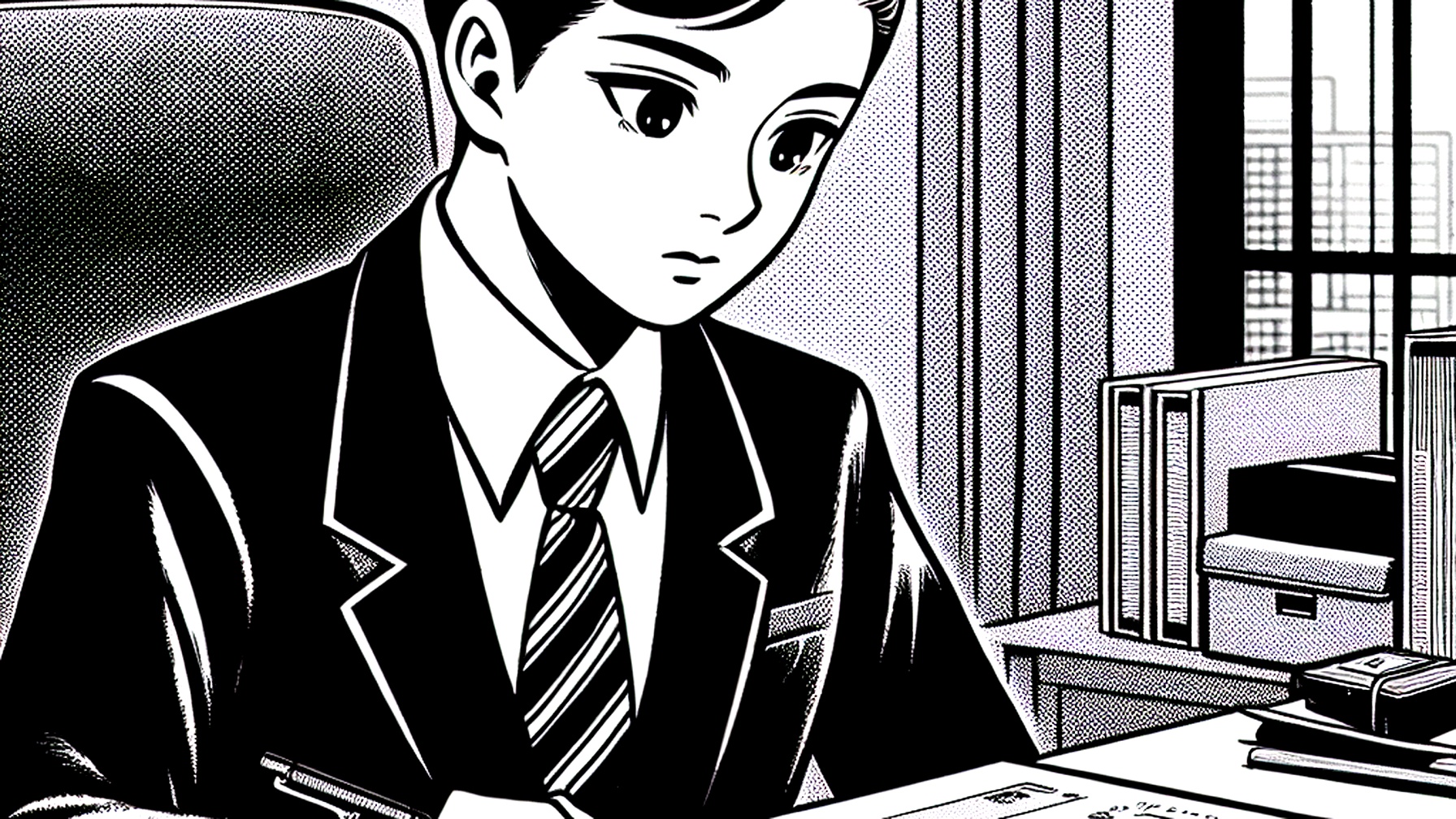
重要なのは、毎月の実質収支を事前に数字で確認することです。表面利回りだけを追うと、思わぬ赤字に転落するリスクがあります。
キャッシュフローとは、家賃収入からローン返済や管理費を差し引いて手元に残る現金の流れを指します。銀行は返済比率が基準を満たせば融資を出しますが、投資家はさらに固定資産税や火災保険まで織り込み、税引き後の数値をチェックしなければなりません。数字を見える化することで、購入前に危ない物件をふるい落とせます。裏を返せば、この段階での甘い見積もりは後から取り返しがつきにくいのです。
実は、表面利回りが10%でも、管理費と修繕積立を合わせて収入の15%が出て行けば、実質利回りはすぐに7%台へ下落します。さらに空室3カ月を想定すると、手残りはゼロに近づく場合もあります。東京都23区の新築マンション平均価格は2025年10月時点で7,580万円(不動産経済研究所)まで上昇しており、ローン返済額も膨らみがちです。だからこそ、購入前に最悪シナリオまで組み込んだ収支表を作る姿勢が欠かせません。
ポイントは、減価償却や青色申告特別控除など税務上のメリットも併せて算入し、一年単位だけでなく十年スパンで比較することです。長期的にプラスに転じるかどうかを冷静に見極めることで、資金ショートの不安を大幅に減らせます。
想定外を呼ぶ空室率と家賃下落
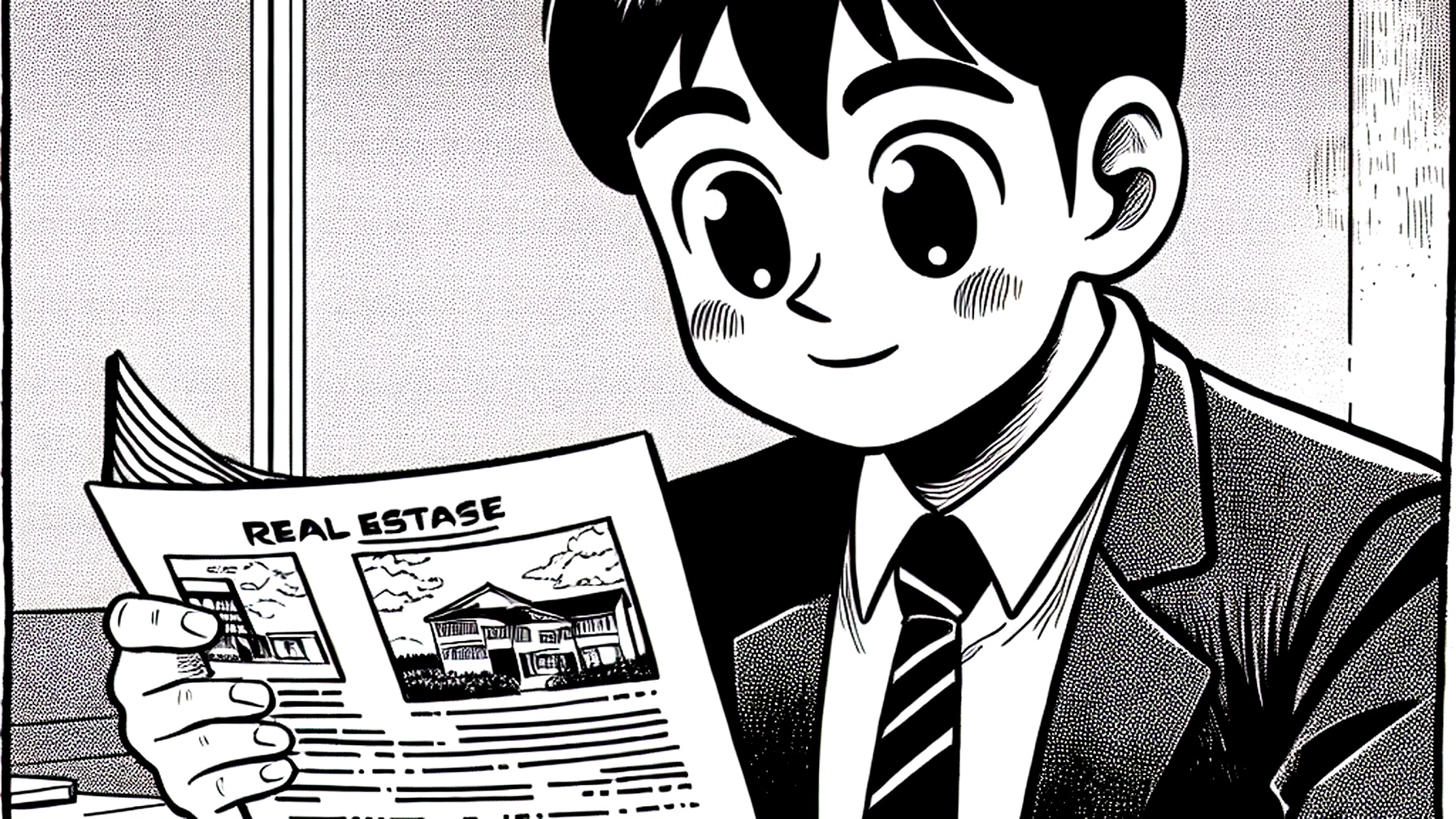
まず押さえておきたいのは、空室と家賃水準が収益構造を大きく左右する事実です。人口動態や地域需要を読む力が不足すると、期待利回りが絵に描いた餅になります。
国立社会保障・人口問題研究所の推計では、東京圏でも2040年以降に単身世帯数が頭打ちになると示されています。需要が伸び悩むエリアでは、わずか2%の空室率上昇でも家賃が下がりやすく、キャッシュフローのマイナス幅が拡大します。例えば家賃8万円の部屋が1万円下がると、年間家賃は12万円減り、利回りは約1.5ポイント低下します。
郊外や築古物件を安く仕入れる戦略は一見魅力的ですが、建物の競争力が低い場合は値下げ合戦に巻き込まれやすい点に注意が必要です。実際、筆者の顧客で築25年・駅徒歩15分の一棟物件を購入したケースでは、入居付けのために家賃を10%下げざるを得ず、初年度から赤字に転落しました。
空室リスクを抑えるには、ターゲットとなる入居者像を明確にし、周辺の競合物件と差別化できる設備を導入することが有効です。インターネット無料やスマートロックなど低コストで導入できる付加価値は、退去抑止にもつながります。
修繕積立と大規模修繕の資金計画
実は、一棟投資で見落とされがちなのが修繕費の積立不足です。外壁補修や屋上防水などの大規模修繕は避けて通れません。
国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」によると、延べ床面積2,000㎡規模の物件では、15〜18年ごとに数千万円規模の工事費が必要と示されています。分譲マンションなら区分所有者から集めますが、一棟オーナーの場合は全額を自分で負担する点が大きく異なります。初期のキャッシュフローがプラスでも、15年目に一度に出て行く現金が足りなければ破綻しかねません。
さらに、築年数が30年を超えるとエレベーターや給排水管の更新も重なりやすく、長期修繕計画の精度が収益安定の鍵を握ります。筆者は毎月の家賃収入の10%を目安に積立口座へ自動振替する仕組みを推奨しています。こうして工事時期を迎えても借入を増やさずに済む体制を整えれば、資産価値の維持と家賃水準のキープが期待できます。
ポイントは、工事の発注先を複数社で比較し、長期保証やアフターサービスの内容まで含めて総コストを評価することです。相見積もりを取ることで、費用を平均15%程度削減できた事例も珍しくありません。
2025年度の融資環境と金利上昇リスク
基本的に、融資条件は投資家の返済能力と物件評価で決まりますが、金利情勢も重要な変数です。2025年度の国内主要銀行の不動産投資ローン固定金利は年1.8〜2.5%のレンジで推移しています。
日本銀行は2024年にマイナス金利を解除し、緩やかな利上げ局面へ入りました。金融庁統計によると、2025年7月時点で長期金利は1.1%に達し、今後もインフレ率次第で上方向へ動く可能性があります。金利が1%上昇すると、1億円を30年返済で借りた場合の総返済額は約1,700万円増える試算です。数字を具体的に把握すると、低金利前提で組んだシミュレーションがいかに脆いかが分かります。
そこで、返済比率は家賃収入の50%以内に抑え、金利上昇2%まで耐えられる計画を設定することが安全圏といえます。さらに、期間短縮型の繰上返済や、固定と変動を組み合わせるミックスローンを活用し、金利リスクを分散させる手法も検討価値があります。
金融機関によって融資方針は異なるため、同じ属性でも金利が0.3%前後変わるケースは珍しくありません。複数行へ事前相談し、条件を比較することで総返済額を数百万円単位で圧縮できる余地があります。
管理体制で差がつく収益安定策
ポイントは、自主管理か管理会社委託かを含め、入居者対応の質を高めることです。管理が行き届かない物件は、早期退去と家賃下落の温床になります。
管理会社へ丸投げすると、日常清掃の頻度やクレーム対応の速度が把握しにくくなります。オーナーとして月一度は物件を訪れ、清掃状態や掲示物の更新状況を確認するだけでも、管理品質は向上します。住環境の改善は口コミサイトの評価にも反映され、結果として空室期間の短縮につながります。
一方で、入居者対応をすべて自分で行うと、夜間トラブルや法的手続きに追われ、時間的コストが増大します。専門知識を要する退去精算や訴訟リスクを考えると、管理手数料3〜5%は保険料と割り切る考え方も合理的です。
結論として、管理体制は「費用対効果」と「時間対効果」のバランスで選ぶのが現実的です。定期的な業務報告書の提出を義務付け、KPIとして入居率と家賃回収率を共有する仕組みを作れば、委託でも質をコントロールできます。
まとめ
一棟買いのマンション投資は、高利回りが期待できる一方で、キャッシュフロー計算、空室リスク、修繕積立、金利変動、管理品質という五つの壁を乗り越える必要があります。数字を厳しく検証し、最悪シナリオでも資金が尽きない体制を整えることが、長期で資産を守る唯一の近道です。今日紹介したチェックポイントを物件購入前に一つずつ確認し、自分の許容範囲を超えない計画を立ててください。慎重な準備こそが、危険をチャンスへ変える最大の武器になります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 – https://www.ipss.go.jp
- 国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行統計データ – https://www.boj.or.jp
- 金融庁「金融レポート2025」 – https://www.fsa.go.jp

