不動産投資に興味はあるものの、物件を直接買うのはハードルが高い。そんな悩みを持つ人がたどり着くのがREITです。しかし「評判は良さそうだけれど、本当のデメリットは何だろう」と不安を抱く方も多いでしょう。この記事では、REITの基礎からリスク管理までを丁寧に説明し、2025年時点で有効な制度を踏まえて賢い選択のコツをお伝えします。読み終えたとき、あなたはメリットとデメリットを正しく比較し、自分に合った投資判断を下せるようになるはずです。
REITのしくみと基本メリット
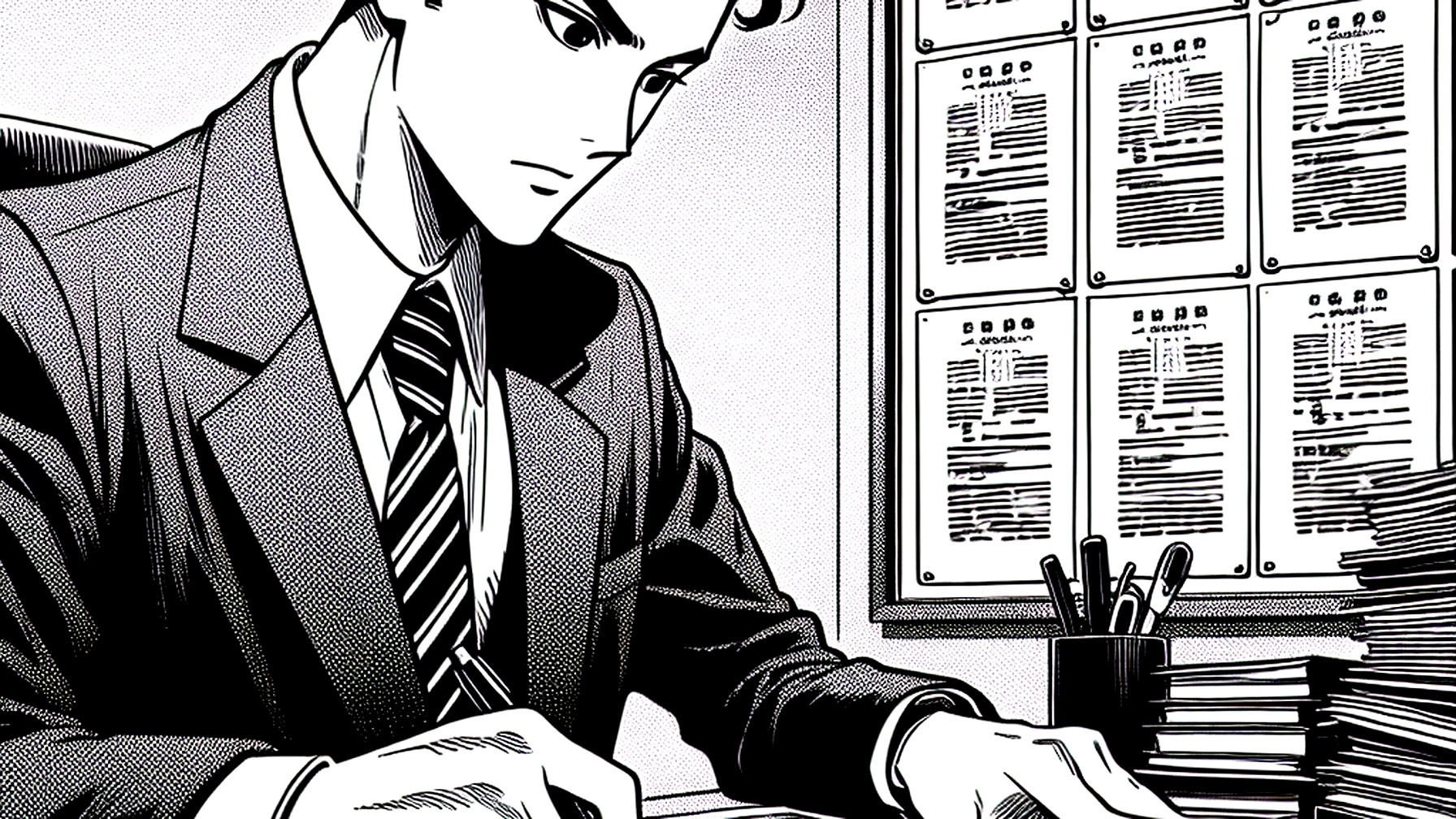
まず押さえておきたいのは、REITが不動産投資信託という金融商品であり、多くの投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設を保有し、その賃料収入を分配する仕組みだという点です。少額から分散投資できるため、初心者でもスタートしやすいのが大きな特徴になります。
REITは不動産投資のハードルを下げる役割を担います。国土交通省のデータによると、東京証券取引所に上場するJ-REITの最低投資金額は2025年10月時点で平均十万円台です。現物物件の頭金と比べれば圧倒的に低コストであり、複数銘柄を組み合わせた分散も可能です。また、運用や管理を専門家に委ねられるため、テナント対応や修繕計画を自分で行う必要がありません。
さらに、J-REITは法律上、利益の九〇%以上を分配することで法人税が免除されます。そのため配当利回りが比較的高く、東証全体の平均配当利回り二%前後に対し、J-REITは四%程度で推移しています。インカムゲインを重視する投資家にとって、安定した収益源となる点は魅力です。
流動性の高さも無視できません。株式と同じく市場で売買できるため、現金化までの時間が短いのが特徴です。急な資金需要が発生した場合でも、一般的には数日で売却代金を受け取れます。これは売却に数カ月かかる現物不動産と比較して大きなメリットと言えます。
見逃しがちな手数料とコスト
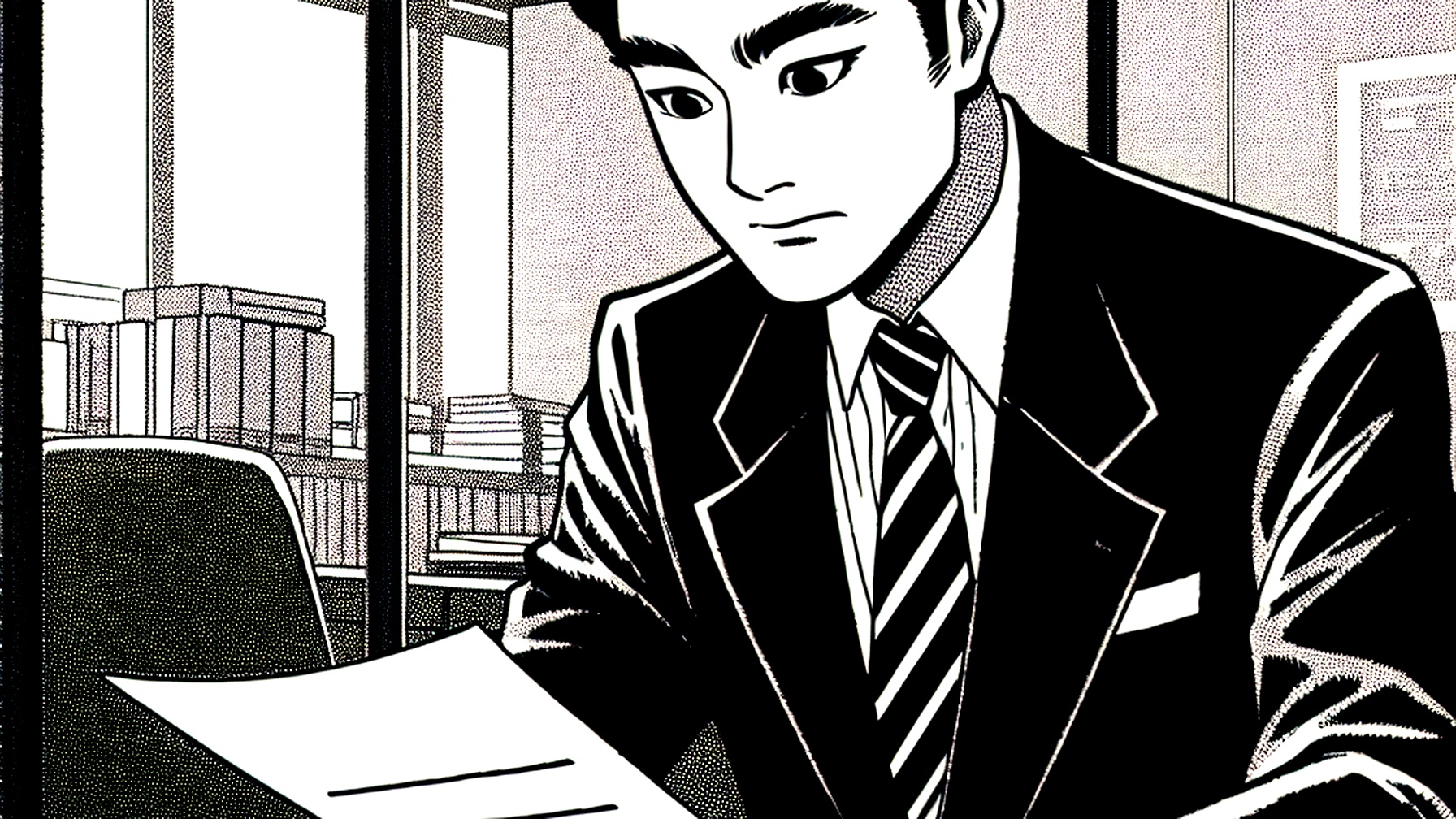
実は、手数料の存在こそが「評判 REIT デメリット」として語られる最初のポイントです。購入時と保有中に複数のコストが発生し、トータル利回りを目減りさせる可能性があります。
購入時には証券会社に売買手数料を支払います。ネット証券では無料プランも増えていますが、対面型では約定金額の一%前後かかる例もあります。また、REITそのものが保有する不動産の取得費や修繕積立金などは、運用報告書上で「運用費用」として控除されるため、投資家の手取り分配金に直接影響します。
信託報酬にも注意が必要です。これは資産残高に対して年率〇・三〜一・〇%程度発生し、毎営業日少しずつ差し引かれます。数字だけ見ると小さく感じますが、長期で保有すると複利的に効いてきます。たとえば年率〇・七%の信託報酬を十年間負担すると、単純計算で七%相当の利回りが失われる計算です。
さらに、広告費や物件入替え時の売買仲介手数料も分配金を押し下げる要因になります。公表資料を読んでも把握しづらい部分なので、投資前には運用報告書の「費用明細」欄を必ず確認しましょう。手間を惜しまず比較することが、純粋な投資成果を守るカギとなります。
市場価格の変動リスク
重要なのは、REITが株式市場で売買される以上、基準価額が日々変動するという事実です。物件から得られる賃料は比較的安定していても、投資口価格は金利動向や景気の先行きで大きく上下します。
具体的には、長期金利が上昇するとREIT価格は下落しやすくなります。これは、分配金利回りと国債利回りが競合関係にあるためです。日本銀行の統計によれば、二〇二三年から二〇二四年にかけて長期金利が一%付近まで上昇した局面で、東証REIT指数は一二%下落しました。金利が上がるほどREITの魅力が相対的に薄れる点は覚えておきたいところです。
また、地震や感染症拡大などの外的ショックも価格を揺らします。二〇二一年の緊急事態宣言下では、ホテル系REITが四〇%以上下落した例がありました。分配金が維持されても、市場心理で売られれば含み損が発生します。短期売買を前提にすると、大きな値動きに翻弄されるリスクが高まるので注意が必要です。
値動きを抑える手段として、セクター分散とドルコスト平均法が有効です。オフィス、住宅、物流など複数の用途に分散し、定期的に同額を積み立てることで平均取得単価を平準化できます。価格変動は避けられませんが、長期視点でリスクを管理することが大切です。
物件ポートフォリオと情報の非対称性
ポイントは、REITがどのような物件に投資しているかを投資家自身が十分に把握しづらい点です。運用会社から提供される情報は詳細ながら、専門用語が多く読み解きに時間がかかります。
たとえば、築年数や空室率が数字で示されても、エリア特性や賃料水準との関連を理解しなければ物件の競争力は判断できません。2025年度の国土交通白書では、築二〇年以上のオフィスビルの平均空室率が築十年未満に比べて約二倍高いと示されています。このような定量データを踏まえて分析しないと、老朽化リスクを見逃す恐れがあります。
REITは通常、複数の物件を束ねて投資効率を高めます。しかし、ポートフォリオの中でも収益力の高い物件と低い物件が混在しているのが実情です。投資家は運用会社が公表する「物件別収益貢献度」を確認し、特定物件への過度な依存がないかをチェックする必要があります。依存度が高い場合、テナント退去や修繕コスト増加が即時に分配金へ影響するリスクが高まります。
情報の非対称性を減らす方法として、運用会社の決算説明動画やIRセミナーに参加し、質疑応答で疑問点をクリアにする手があります。手間はかかりますが、他の投資家が見落としがちな情報を得ることで思わぬ損失を回避できることがあります。
税制と2025年度の優遇措置を活かす方法
まず押さえておきたいのは、REITの分配金が「配当所得」に区分され、株式の配当と同じく一律二〇・三%の源泉分離課税が適用される点です。節税を図るには、2024年に刷新された「新NISA」を活用するのがもっともシンプルな方法になります。年間三六〇万円までの成長投資枠を使えば、分配金と譲渡益が非課税です。2025年も制度は継続しており、非課税保有限度額一八〇〇万円まで積み立てることが可能です。
一方で、新NISA口座は損益通算ができないため、課税口座で損失が出ても相殺できないというデメリットがあります。価格変動リスクの高いREITの場合、非課税メリットと損益通算不可のデメリットを天秤にかける必要があります。
2025年度も適用される配当控除は、総合課税を選択した場合のみ利用できます。課税所得が九〇〇万円以下の人なら、配当控除を活用して実質税率を引き下げる選択肢も検討価値があります。ただし、所得税率が高い層では逆に税負担が増えるケースもあるため、確定申告前にシミュレーションを行うことが欠かせません。
法人でREITを保有する場合、不動産所得と経費計上の柔軟性を得られる反面、個人と比べて税率が高くなりがちです。法人化は規模拡大や相続対策とセットで考えるテーマなので、税理士に相談しながら慎重に判断しましょう。
まとめ
この記事では、REITのメリットと並んで「評判 REIT デメリット」と呼ばれるポイントを丁寧に解説してきました。少額で分散投資でき、流動性も高い一方、手数料や市場変動、情報の非対称性がリスクとして存在します。さらに、税制優遇を最大限活かすには新NISAや配当控除など制度の特性を正しく理解することが欠かせません。自分の投資目的とリスク許容度を明確にし、運用報告書やIR資料を細部まで確認する姿勢が、後悔しないREIT投資への近道です。まずは少額から始め、経験を積みながらポートフォリオを最適化していきましょう。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 国土交通省 – https://www.mlit.go.jp
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 – https://www.boj.or.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp

