不動産価格が上がり続けるなか、「預金だけではお金が増えにくい」と感じていませんか。特にマンション投資は少額から始められる一方で、リスクや手間が気になり踏み出せない人が多いものです。この記事では、15年以上の実務経験を持つ筆者が、マンション投資の代表的なメリットを最新データとともに整理します。読了すれば、投資判断の軸がはっきりし、次の行動を具体的に描けるはずです。
安定収入を生む家賃収入の強み
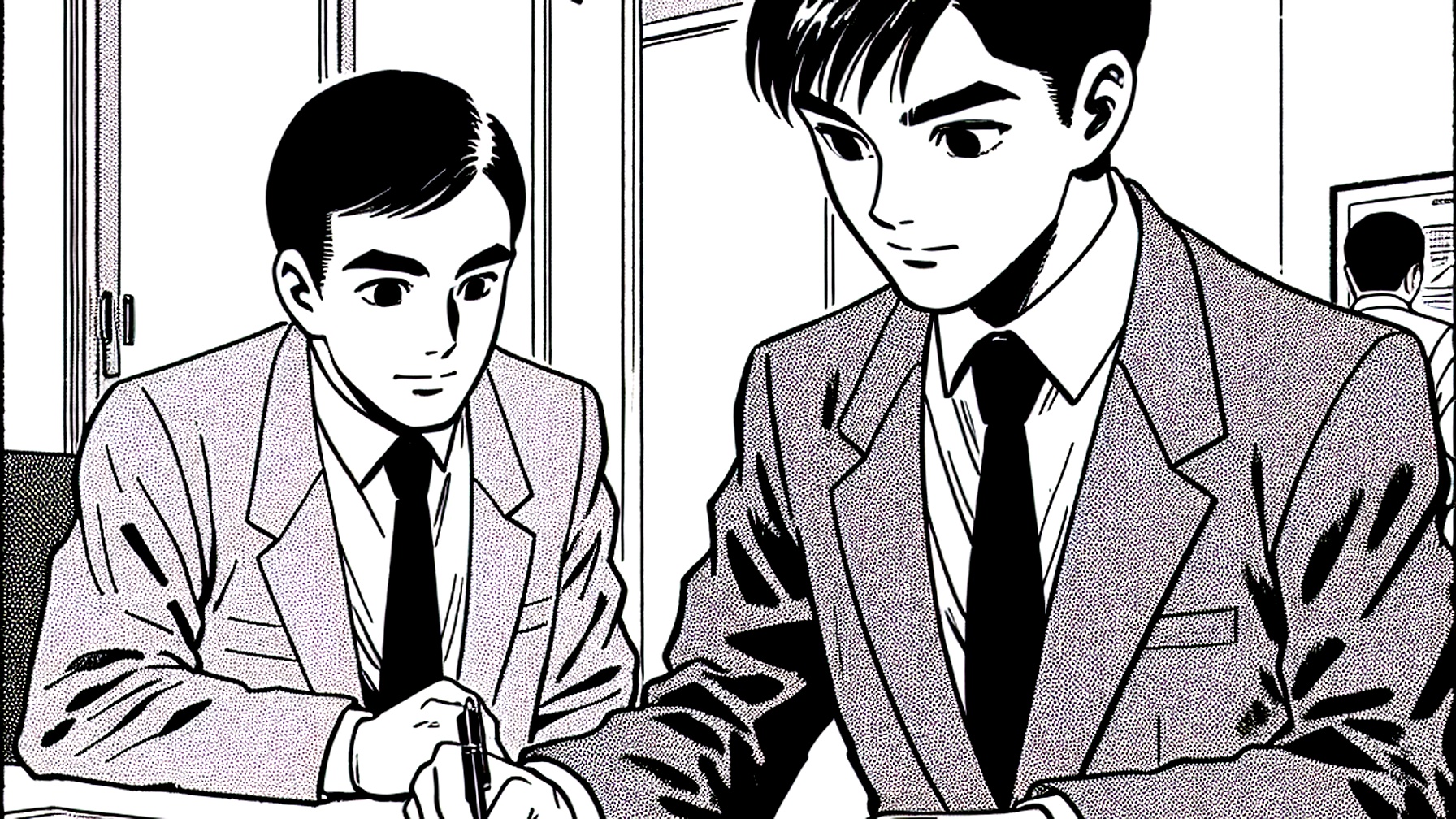
重要なのは、マンション投資が毎月のキャッシュフローを生み出す点です。株式配当は年2回が一般的ですが、賃料は月々入るため生活設計に組み込みやすくなります。
まず、新築でも中古でも賃料の契約期間は2年が主流です。長期のローン返済と並行して、空室がなければ一定額が口座に積み上がります。住宅金融支援機構の2025年度調査によると、首都圏のワンルーム平均空室率は4.2%にとどまり、想定家賃を90%で計画しても現実的です。
また、家賃が物価スライドしやすい点も見逃せません。総務省の消費者物価指数が上昇すると、更新時の家賃改定に反映されるケースが増えます。つまりインフレ局面では実質収入が維持されやすく、手取りが目減りしにくい構造です。
最後に、管理会社へ業務を委託すれば日常対応はほぼ任せられます。手数料は家賃の3%〜5%が相場ですが、オーナー自身が本業に集中しながら副収入を得られる点が大きな魅力です。
インフレ・円安への効果的なヘッジ
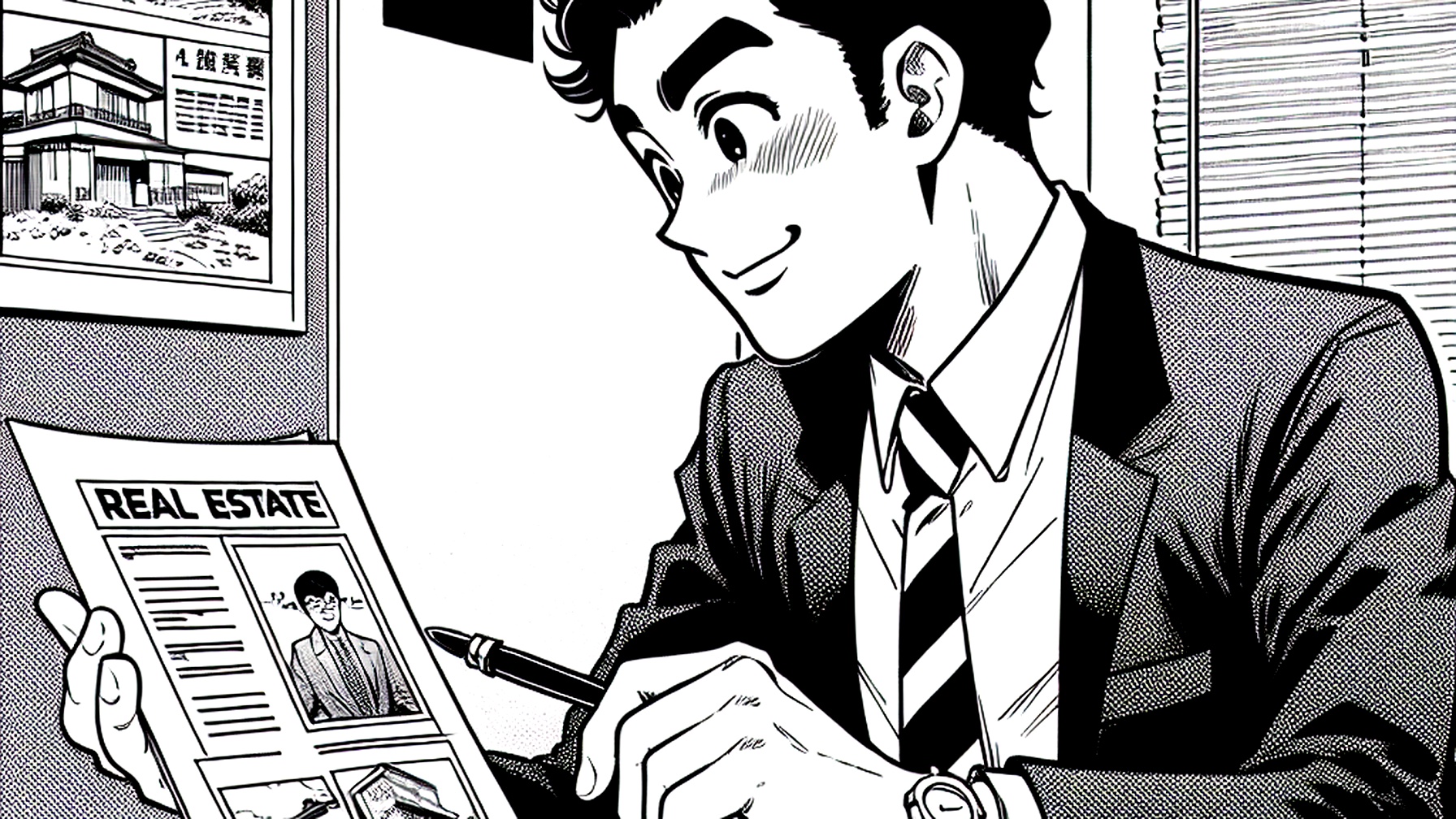
ポイントは、不動産が実物資産であることです。紙幣価値が下がる局面でも、土地と建物自体の価値は相対的に維持されやすい特徴があります。
たとえば2021年から続く円安で輸入品価格が高騰しましたが、東京23区の新築マンション平均価格は2025年10月時点で7,580万円と前年比3.2%上昇しました(不動産経済研究所)。通貨価値が揺らいでも、マンション価格が堅調だった事実はインフレヘッジ効果を示しています。
さらに、金利との関係も押さえておきましょう。一般に物価と金利は連動しますが、固定金利でローンを組めば返済額は変わりません。家賃が少しずつ上がる一方で返済額が据え置かれるため、実質利回りが高まる可能性があります。
一方で、変動金利を選ぶ場合は金利上昇リスクを織り込む必要があります。金利が1%上がると月々の返済が数千円増えるケースも珍しくありません。自己資金を2割以上入れておくと、返済比率を抑えつつインフレメリットを享受しやすくなります。
節税につながる諸経費計上と減価償却
実は、マンション投資では現金支出を伴わない経費計上が可能です。それが減価償却費という会計上の費用で、木造より長い47年の耐用年数で按分します。
最初に知っておきたいのは、所得税・住民税で損益通算できる点です。ローン利息、管理費、修繕積立金、火災保険料などを合算し、給与所得と合算して赤字になれば還付を受けられます。国税庁の2025年度統計では、給与所得者の平均還付額は約9.6万円ですが、マンション投資による還付はそれを上回るケースも珍しくありません。
一方で、赤字が拡大しすぎると金融機関の追加融資審査でマイナス評価となります。年間の帳簿上赤字は家賃収入の2割程度に抑え、長期でプラス収支へ転じる計画を組むことが重要です。
さらに、将来売却時の譲渡所得にも注意が必要です。減価償却を進めるほど簿価が下がり、売却益が大きく計上されます。節税効果と出口戦略のバランスを常に確認しておくと安心です。
区分所有ならではのリスク分散と流動性
まず押さえておきたいのは、区分所有なら小口化された資産として扱える点です。1棟所有と違い、複数戸をエリア分散で保有しやすいため、空室リスクを薄められます。
具体的には、都心1戸・郊外1戸といった組み合わせが有効です。都心は賃料単価が高く、郊外は利回りが高い傾向があるため、収益カーブを平均化できます。ちなみに2025年10月の東京都市部空室率は3%台ですが、千葉県郊外は5%台にとどまります。この差を逆手に取り、平均利回りを底上げする戦略が実践的です。
加えて、流動性の高さも見逃せません。レインズ(不動産流通標準情報システム)によると、首都圏区分マンションの成約までの平均日数は2025年上期で54.6日でした。価格さえ適正なら、約2カ月で現金化できるデータは心強い材料と言えます。
それでも価格変動は避けられません。周辺再開発や金利動向を定期的に調べ、売り時を見誤らないようにすることが、リスクコントロールの鍵になります。
2025年市場データで見る投資タイミング
ポイントは、需給バランスが投資成果を左右する事実です。人口減少が進む日本でも、都心への転入超過は止まっていません。東京都総務局の2025年1月速報で、23区への転入超過は約4.7万人と4年連続のプラスでした。
需要が底堅い一方で、建築コスト高から供給は伸び悩んでいます。国土交通省の着工統計では、2025年度上期の分譲マンション着工戸数は前年同期比8.1%減となりました。供給減は中古価格の下支え要因となり、保有期間中の資産価値を押し上げます。
さらに、2025年度の住宅ローン税制は自宅用のみ対象で投資用は含まれませんが、金融機関の投資向け融資姿勢は緩和傾向です。都市銀行の平均金利は1.9%前後と低位で推移し、インフレ率を差し引けば実質金利はほぼゼロに近い水準と言えます。
つまり、低金利と供給減が重なる今は、長期的に見て入りやすいタイミングです。ただし、金利が上昇する兆しが出た段階で借換えや一部繰上げ返済を検討し、利払い負担を固定化しておくとリスクを抑えられます。
まとめ
マンション投資 メリットを整理すると、家賃収入による安定キャッシュフロー、インフレヘッジ効果、節税余地、リスク分散と流動性、そして需給バランスを背景にした価格の下支えが挙げられます。これらは単独ではなく相互に作用し、長期保有で威力を発揮します。まずは自己資金比率と金利タイプを決め、具体的な物件を3件ほど比較する行動から始めてみてください。行動を積み重ねることで、将来の資産形成が現実のものとなります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 住宅金融支援機構「賃貸住宅市場データ」 – https://www.jhf.go.jp
- 総務省統計局「消費者物価指数」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「建築着工統計」 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都総務局統計部「人口移動報告」 – https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp

