マンション投資に興味はあるものの、「本当に安全なのか」「損はしないのか」と不安を抱く方は多いはずです。表面的には家賃収入が得られる魅力的な資産運用に見えますが、実際にはリスクも存在します。本記事では、経験者が語るリアルなデメリットを最新データとともに丁寧に解説し、対処策まで紹介します。読了後には、投資判断をより慎重に行うための視点が身につくでしょう。
失敗しやすい資金計画の落とし穴
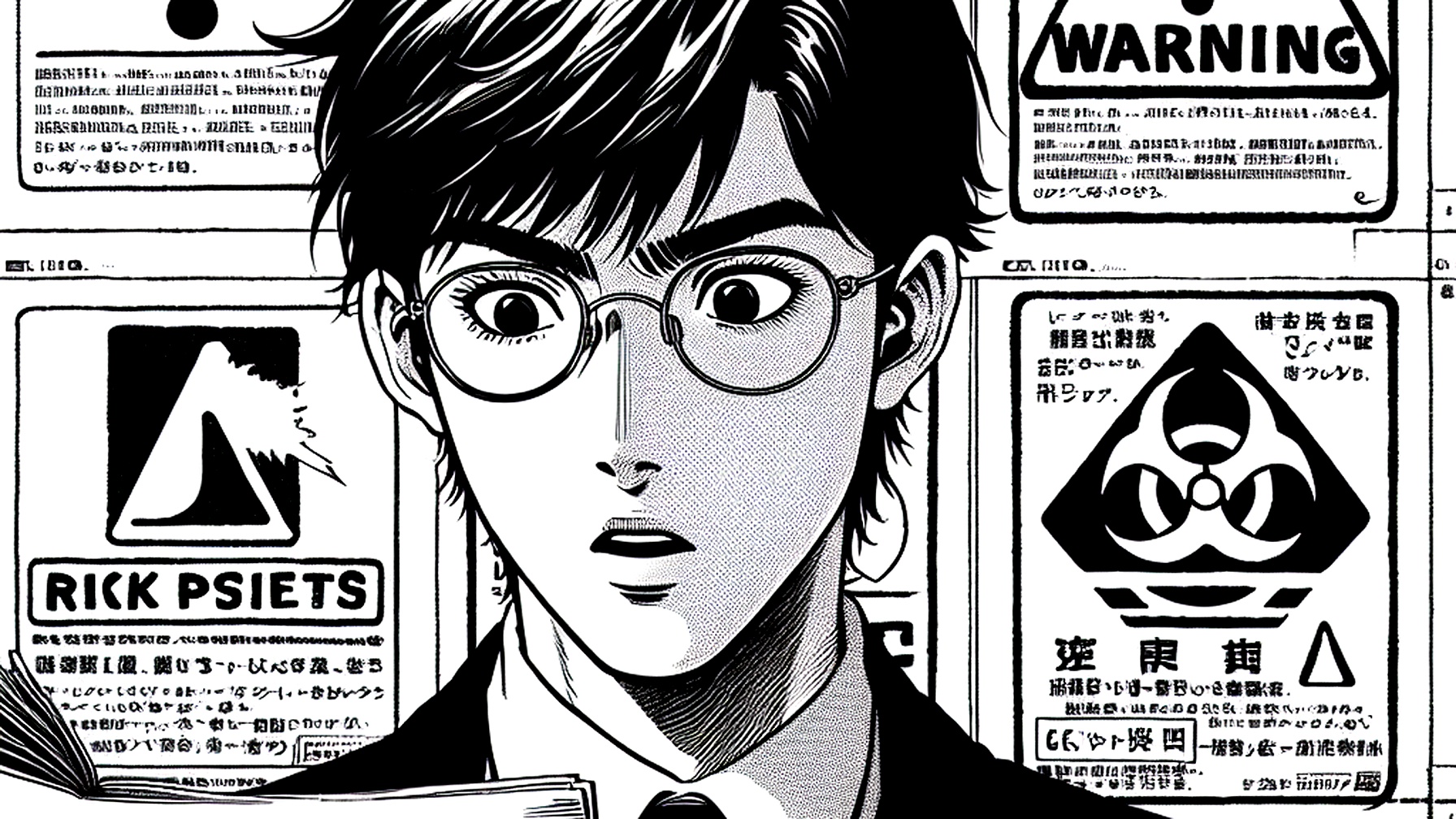
重要なのは、購入時点だけでなく長期的な返済計画を描けるかどうかです。表面利回りが高くても、キャッシュフローが赤字では意味がありません。
まず、フルローンを組んでしまうと毎月の返済比率が高くなりがちです。金融庁の「家計調査」では、住宅ローンを含む債務返済負担率が年収の30%を超えると延滞リスクが急上昇すると示されています。つまり自己資金を2〜3割入れることで、返済比率を抑えやすくなります。
次に、諸費用を軽視しないことが大切です。登記費用やローン手数料、火災保険などで物件価格の7〜10%は追加で必要になります。これらを含めずにシミュレーションすると、実際の利回りは簡単に1%近く下がるため、収支が狂います。
さらに、金利変動にも目を向けましょう。日本銀行によると長期金利は2025年夏に1.1%まで上昇しました。変動金利型ローンを選択した場合、金利が1%上がると返済総額は数百万円単位で増える恐れがあります。ゆえに固定金利の検討や、余裕を持った返済計画が欠かせません。
空室リスクと家賃下落の現実
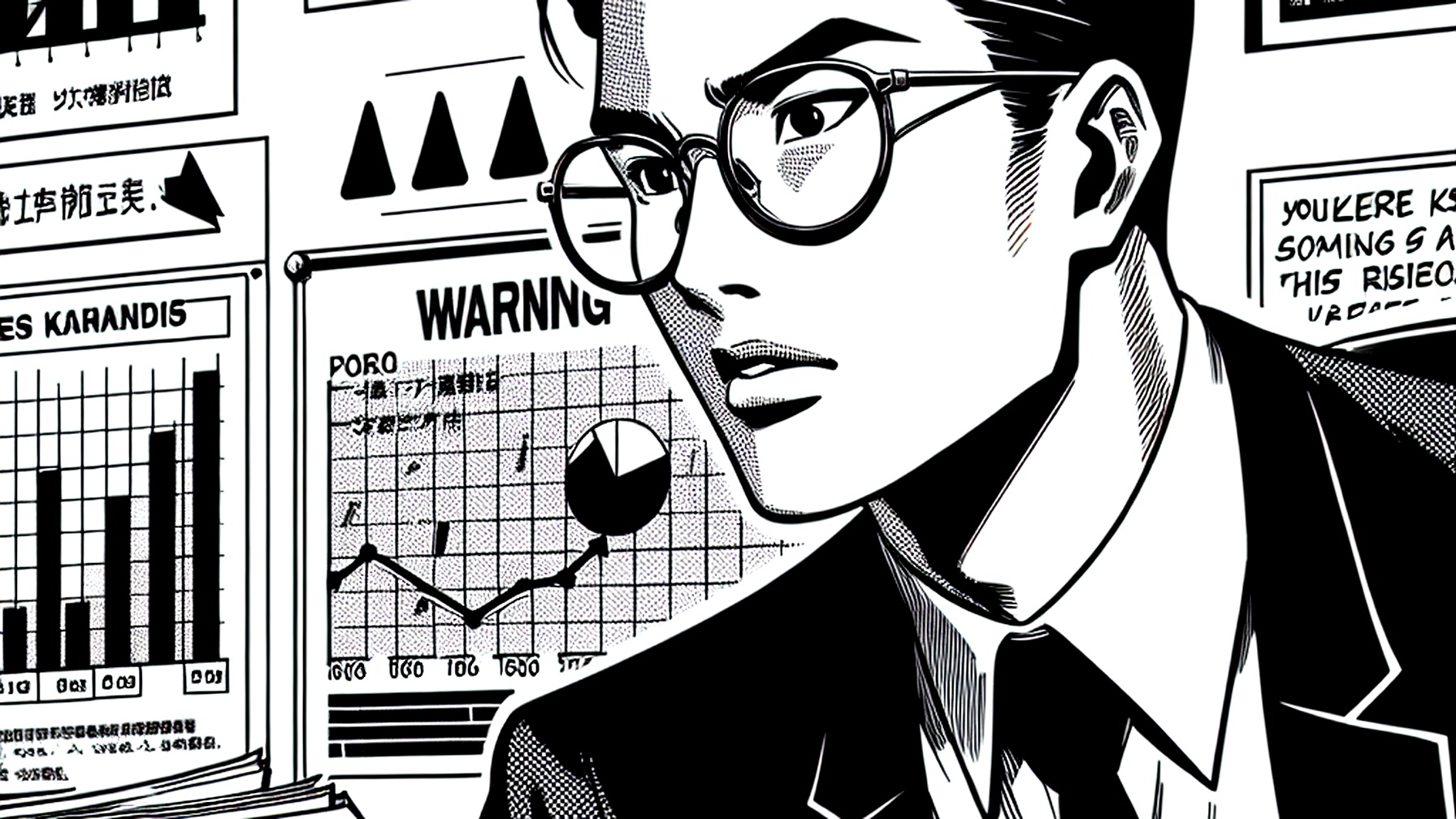
まず押さえておきたいのは、空室率と家賃は地域により大きく異なるという事実です。全国平均の住宅空室率は総務省の2023年調査で13.8%ですが、地方都市の一部では20%を超えています。
実は、都心でも安心はできません。東京23区の平均空室率は7%前後と低水準ですが、築20年を過ぎると新築に比べ家賃が15〜20%下がる傾向があります。不動産経済研究所によると2025年の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しましたが、賃料はそこまで伸びていません。このギャップが利回りを圧迫します。
また、学生や単身者向け物件は入退去が頻繁です。2月から4月の繁忙期を逃すと次の入居まで半年以上空く例も珍しくありません。家賃が入らない期間でもローン返済と管理費は発生するため、6か月分の運転資金を別に確保しておくと安心です。
最後に、賃貸ニーズの変化にも注意が必要です。テレワーク普及で広めの間取りが好まれるようになり、ワンルーム人気は相対的に下がっています。購入前に周辺の賃貸募集サイトを定点観測し、家賃推移や成約スピードを確認する習慣を身につけましょう。
修繕積立金・管理費が膨らむ仕組み
ポイントは、年数とともにランニングコストが必ず増える点にあります。購入時の区分所有契約書を読むと、修繕積立金は5年ごとに段階的に引き上げる計画が組まれているケースがほとんどです。
国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」では、大規模修繕費用の目安として延床面積1㎡あたり月250円程度を推奨しています。しかし築30年を超えると実際の平均額は月350円を超える物件も多く、想定との差額が家賃収入を圧迫します。
加えて、エレベーターや給排水管など高額設備の交換時期が重なると、一時金として数十万円を請求される場合があります。管理組合の積立金が不足していればなおさらです。過去の総会議事録と修繕履歴を確認し、直近で高額工事が予定されていないか必ずチェックしましょう。
管理費も油断できません。管理会社の委託費が上がると、区分所有者全員で負担するため自動的に支出が増えます。管理会社を変更するには総会での合意が必要で、個人の意向だけでは動かせない点が区分所有のデメリットです。
売却時に直面する出口戦略の難しさ
まず、マンション投資の最終利益は売却価格で大きく左右されます。資産価値が下がると、それまでの家賃収入で黒字でもトータルでは赤字になることがあります。
中古マンションの取引事例をみると、築25年を超えると価格下落が加速し、東京都心でも新築時の45〜55%まで値下がりするケースが一般的です。この水準でローン残債が多いと「オーバーローン」となり、売却損を現金で埋める必要があります。
一方で、好立地かつ管理状態の良い物件は築20年でも高値で取引されることがあります。つまり保有期間中にどれだけ修繕や管理を適切に行ったかが、出口戦略の成否を分けるのです。購入前に将来の再開発計画や交通インフラの更新予定を調べ、長期的な需要を見極めることが重要になります。
流通性も考慮しましょう。ワンルーム専有面積20㎡未満の物件は住宅ローンが組みにくく、購入者が投資家に限られます。その結果、市況が冷え込むと買い手が付きにくいという構造的な弱点があります。出口を意識した物件選びが欠かせません。
2025年の制度と税制で注意すべき点
実は、税金や補助制度は毎年見直されており、最新情報を把握しないと思わぬ負担増につながります。2025年度は大きな優遇措置こそありませんが、既存の減価償却ルールと不動産取得税に関する改正が行われました。
まず、減価償却の耐用年数見直しにより、築古マンションを購入した場合でも最短4年での一括償却はできなくなりました。これにより初年度の経費計上額が減るため、節税効果は限定的です。税務署の確認も厳格化されているため、実態とかけ離れた償却は避けるべきです。
次に、2025年度の住宅ローン控除は自己居住用が対象で、投資用マンションには適用されません。投資家が利用できるのは「損益通算」による所得税軽減ですが、家賃収入が安定すれば赤字額も縮小し控除メリットは減る点に注意してください。
最後に、エネルギー性能向上リフォームに対する国の補助金「既存住宅省エネ改修促進事業」が継続しています。ただし対象はオーナー自ら工事費の3分の1を負担し、賃貸併用でも入居者保護の措置が求められます。期限や上限額は毎年度変わるため、実施前に必ず公式サイトで確認しましょう。
まとめ
結論として、マンション投資 デメリットの本質は「コストの不確実性」と「需要変動の影響」をいかにコントロールするかにあります。資金計画を保守的に立て、空室と家賃下落を見越したシミュレーションを行い、修繕積立金や制度改正の情報を常に更新することでリスクは大幅に減らせます。まずは気になる物件の管理状況と地域の賃料動向を細かく調べることから始めてみてください。知識武装が、長期的に安定した投資への第一歩になります。
参考文献・出典
- 国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」 https://www.mlit.go.jp
- 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」 https://www.stat.go.jp
- 不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向2025」 https://www.fudousankeizai.co.jp
- 金融庁「家計の金融行動に関する世論調査2024」 https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行「長期金利の推移(2025年レポート)」 https://www.boj.or.jp

