家賃相場の伸び悩みや金利の上昇を背景に、「もう収益物件は持たなくていいのでは」と考える人が増えています。実際、手間やリスクを避けて現金や投資信託に資金を移す動きも目立ちます。しかし、2025年10月時点の市場環境を冷静に見渡すと、単純に「収益物件 いらない」と判断する前に検討すべき要素が多いことに気づきます。本記事では、収益物件を手放す心理やメリット・デメリットを整理しつつ、所有以外の収益方法や最新の税制を踏まえた戦略を解説します。読了後には、自分にとって最適な資産形成の選択肢が見えてくるでしょう。
収益物件が「いらない」と感じる背景
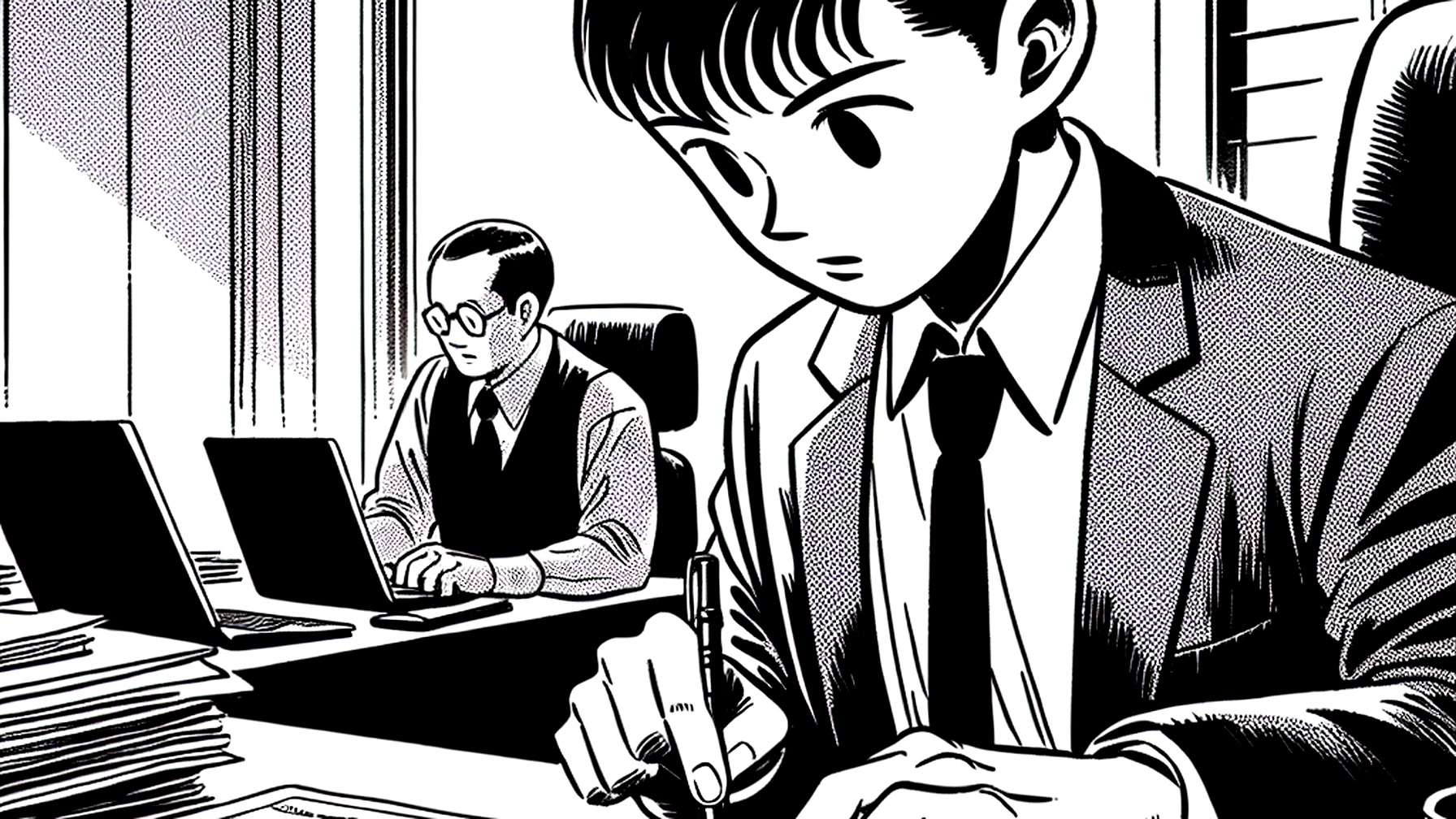
まず押さえておきたいのは、多くの投資家が収益物件に魅力を感じなくなった主な理由です。その背景には、金利上昇によるキャッシュフローの悪化と、管理コストの増加があります。一方で、日本全体では人口減少が続くものの、都市部への集中は強まっており、エリアによる二極化が鮮明です。つまり、「収益物件 いらない」と感じるのは、市場全体を一括りに見ていることが一因と言えます。
次に金利の動向です。日本銀行は2024年から段階的に金融緩和を縮小し、2025年10月時点で住宅ローン変動金利は1.2%前後に達しました。過去の0.5%台と比べると返済負担は確実に増えます。特に短期固定で借りていたオーナーは、更新時の利率上昇で手残りが減り、「だったら手放したい」と考えがちです。ただ、金利の上昇は物件価格の調整も促すため、買い手市場が広がる局面でもあります。
さらに修繕費の増加も見逃せません。国土交通省の調査では築20年を超える賃貸マンションの大規模修繕費は、延床1㎡あたり平均1万8千円とされています。材料費の高騰で今後さらに上がる見通しです。こうしたランニングコストの負担感が、「いらない」との声を後押ししています。しかし、逆にいえば築浅や省エネ性能の高い物件は相対的に競争力が高まり、賃料を維持しやすくなるチャンスもあるのです。
保有しない選択のメリットと落とし穴
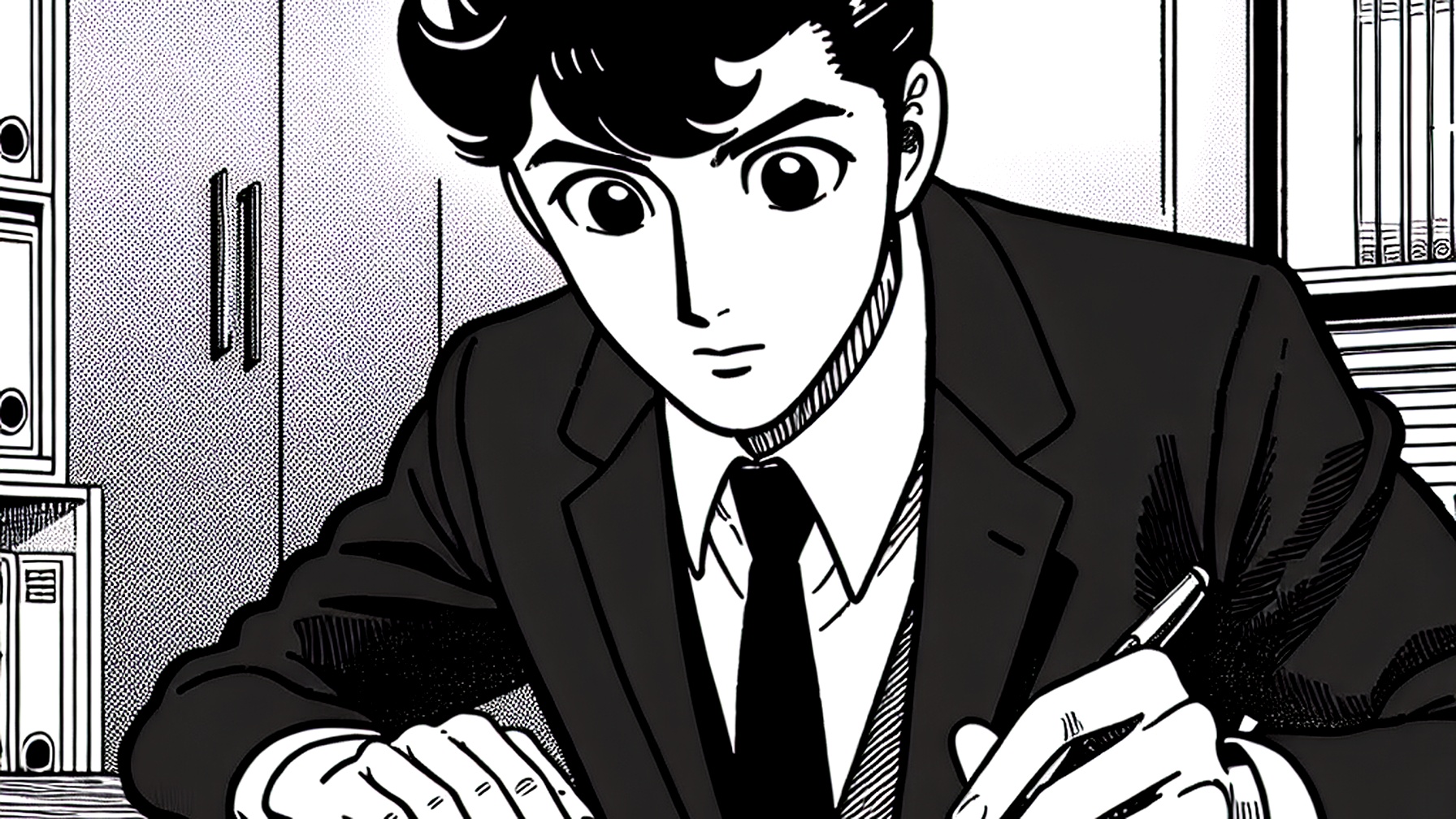
重要なのは、収益物件をあえて持たないことで得られるメリットを正しく理解することです。最もわかりやすい利点は、空室や家賃滞納のストレスから解放される点でしょう。さらに、流動性の高い金融商品に置き換えれば、急な資金需要にも柔軟に対応できます。しかし、その裏にはインフレ耐性の弱さや節税機会の喪失といった落とし穴も潜んでいます。
たとえば、現金比率を高めれば確かに安心感はありますが、消費者物価指数が年2%で上昇した場合、10年で実質価値は約18%目減りします。一方、賃料は契約更新時にインフレ連動で上げやすく、物件価格も長期的には再調達原価に引っ張られて上昇する傾向があります。言い換えると、不動産はインフレヘッジの役割を果たすため、完全に手放すとリスク分散が崩れるかもしれません。
節税面でも違いが出ます。収益物件の減価償却費は、所得税や住民税の課税所得を圧縮する有効な手段です。特に高所得者層にとっては、年間数十万円のキャッシュメリットが維持コストを上回るケースもあります。対照的に、預貯金や公社債の利子は源泉徴収で一定税率が差し引かれ、節税余地が限定的です。この点を無視して「いらない」と判断すると、手元資金が増えても手取りが減る paradox に陥ります。
実は所有以外にもある不動産収益の手段
ポイントは、収益物件を直接保有しなくても不動産のキャッシュフローにアクセスできる点です。具体的には不動産投資信託(J-REIT)、クラウドファンディング型ファンド、さらには不動産特定共同事業法に基づく電子取引型ファンドなどが挙げられます。これらは少額から参加でき、資産分散もしやすいのが魅力です。
J-REITの平均分配利回りは2025年9月末時点で年4.1%と、公募債より高く、上場株式と比較して値動きも安定しています。クラウドファンディング型の場合、運用期間1~3年で利回り5%前後の案件が多く、資金拘束期間が短い点が特徴です。一方で元本保証はなく、劣後出資のある案件でも損失リスクがゼロになるわけではありません。つまり、直接保有しない代替策を選んでも、リスク評価は欠かせないということです。
また、不動産管理の煩わしさを軽減する手段として、サブリース(家賃保証)契約や管理委託の活用もあります。手取りは減るものの、実務をプロに任せられるため、時間を他の投資や本業に振り向けやすくなります。結局のところ、「いらない」と切り捨てずに、自分の手間とリターンのバランスをどう設計するかがカギとなります。
2025年度の税制・補助と戦略的な活用法
基本的に、2025年度の税制は大幅な変更がなく、減価償却や損益通算の仕組みも継続しています。ただし、所得税の累進税率は最高45%が維持される見込みで、高所得者ほど節税効果が大きい状況です。また、耐震・省エネ性能を高めた賃貸住宅には、固定資産税の減額措置(適用後5年間、最大1/2)が引き続き利用できます。これらは国交省の「賃貸住宅の質向上促進施策」として2025年度予算に組み込まれています。
国の補助金を受ける場合、2025年度の「住宅省エネ2025支援事業」が賃貸住宅の高断熱改修を対象としています。補助率は工事費の1/3、上限120万円で、申請期限は2026年3月末です。つまり、築古物件を保有しつつエネルギー性能を高めれば、空室リスクを抑えながら税メリットと補助金を同時に享受できます。手放そうか迷う場面でも、改修という選択肢を入れるだけで採算が好転する例は少なくありません。
金融面では、地方銀行や信用金庫が「省エネ改修ローン」を提供しており、金利は通常融資より0.3%ほど低く設定されています。金利上昇局面でも優遇幅があるため、融資条件を見直すだけでキャッシュフローが改善する可能性があります。つまり、制度と金融商品の両輪を活用すれば、「いらない」と感じた物件でも利益体質に変える余地は十分あるのです。
長期視点で考えるべき資産形成のバランス
実は、資産運用における最大のリスクは短期的な感情で資産配分を変えることです。株式、債券、不動産を組み合わせることで、景気循環や金利変動に対するクッションが生まれます。そのなかで不動産は、安定収入とインフレヘッジを提供する独自の役割を担います。
たとえば、総資産1億円のうち不動産が5000万円、金融資産が5000万円というポートフォリオを、家賃低迷期だからといって全額金融商品へ移すと、利回りが下がる可能性があります。国土交通省「不動産価格指数」によると、リーマンショック後でも住宅系指数は10年で15%程度の上昇を示しました。長期で見れば、短期の値動きを気にしすぎるより分散効果を保つ方が合理的なのです。
また、ライフプランの観点も欠かせません。賃料収入は年金の上乗せとして機能し、老後の収入源を複線化します。医療費や介護費がかさむ70代以降に、家賃が生活費を支える構図は心強いものです。つまり、「収益物件 いらない」という判断は、将来の生活設計まで踏まえて行う必要があります。
まとめ
ここまで見てきたように、金利や修繕費の上昇で収益物件を敬遠する動きは理解できます。しかし、インフレ耐性や節税効果、補助金の活用余地を総合すると、単純に手放すだけが得策とは限りません。まずは自分のリスク許容度と時間的リソースを整理し、直接保有・ファンド型・改修によるバリューアップなど複数の選択肢を比較しましょう。そのうえで、長期的な資産形成のバランスを意識すれば、「いらない」と感じた物件も再び価値ある資産へ変えられるはずです。行動を先延ばしにせず、今こそ具体的なシミュレーションを始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 令和7年度(2025年度)住宅省エネ支援事業概要 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 総務省 消費者物価指数データベース – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨 – https://www.boj.or.jp
- 一般社団法人 不動産証券化協会 J-REITマーケットレポート – https://www.ares.or.jp

