不動産投資に興味はあるものの、「表面利回りが高ければ本当に収益が出るのか」「マンション投資と他の投資手法では何が違うのか」と悩む方は多いはずです。特に最近はSNSで“利回り10%超”といった数字が独り歩きし、初心者ほど混乱しやすい状況になっています。本記事では、表面利回りの正しい意味や実質利回りとの違いを丁寧に解説し、2025年10月時点の最新データを交えながら、マンション投資で失敗しないためのポイントを紹介します。読み終えたとき、数字の裏側を読み解く力が身につき、より堅実な投資判断ができるようになるでしょう。
表面利回りとは何か
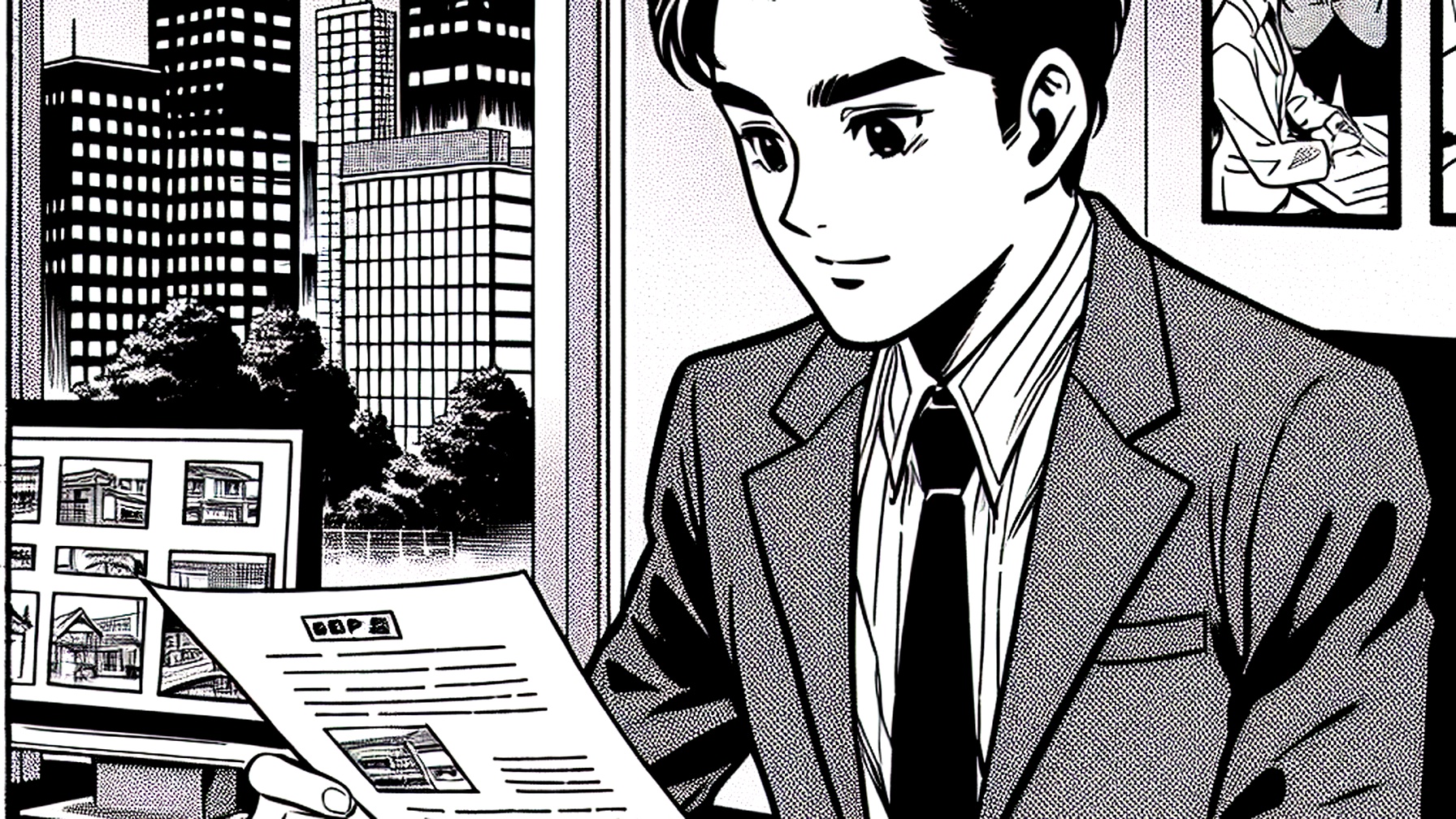
まず押さえておきたいのは、表面利回りが「年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100」で計算される非常にシンプルな指標だという点です。広告や物件資料で最初に目にする数字は大半がこの表面利回りです。取引の共通言語として便利な一方、必要経費や空室リスクを考慮していないため、実際の手残り額とは大きく乖離します。
例えば、年間家賃120万円、販売価格3,000万円の東京都心ワンルームは、表面利回り4%と算出できます。しかし、管理費や修繕積立金などを差し引いた後の手取りは、後述する実質利回りで見ると2%台に落ち込むケースも珍しくありません。つまり、表面利回りは“物件の粗利”を示す記号にすぎず、投資判断の最終結論には使えないわけです。
日本不動産研究所の調査によると、2025年10月時点の東京23区平均表面利回りはワンルーム4.2%、ファミリータイプ3.8%です。数字だけを見ると大差ないようにも感じますが、維持費や想定入居期間が異なるため、同じ利回りでも実際のキャッシュフローは大きく変わります。この段階で「高ければ良い」と短絡的に判断しないことが、賢い投資家への第一歩です。
実質利回りとの違いを押さえる
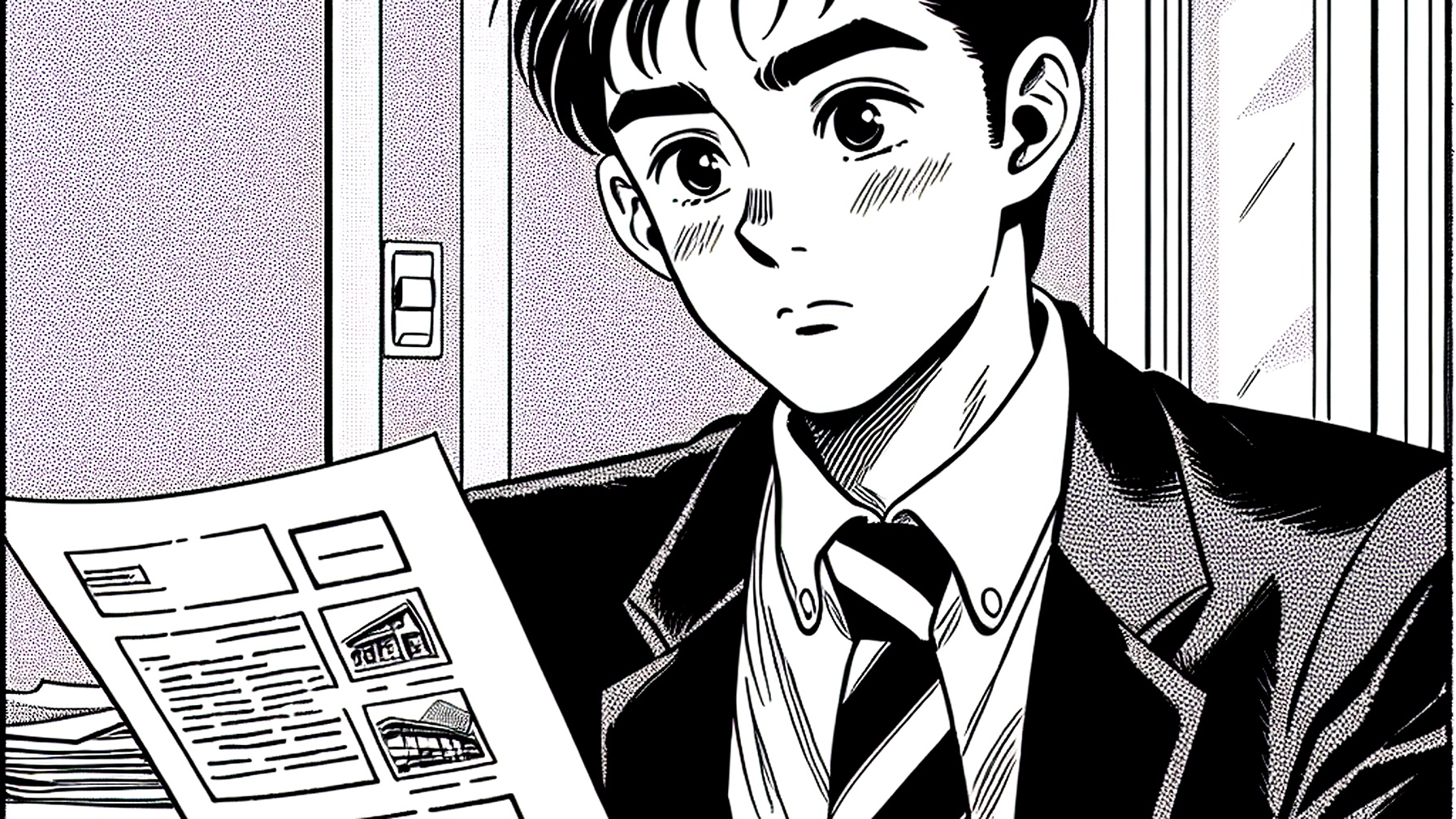
重要なのは、実質利回りが「年間家賃収入 − 年間経費 ÷ 物件価格 × 100」で求められる点です。この“経費”には管理委託費、修繕積立金、固定資産税、火災保険料、さらには空室期間も織り込む必要があります。つまり、実質利回りこそがキャッシュフローを把握するための核心指標なのです。
実は、表面利回り6%の中古区分マンションよりも、表面利回り4%でも管理費・修繕積立金の安い新築マンションの方が、実質利回りで上回る事例があります。具体的には、月額家賃10万円の物件で管理費などが2万円なら経費比率は20%ですが、1.2万円なら12%に抑えられます。この差が年間では9.6万円、10年で96万円に達し、見かけの利回り差を逆転することもあるのです。
さらに、融資を利用する場合は金利負担も加わります。例えば、金利1.5%・融資割合90%で購入すると、年間返済比率は約3.5%前後になります。この負担を含めた“レバレッジ後利回り”を試算しないと、手元に残るキャッシュが赤字になるリスクを見逃してしまいます。
結論として、表面利回りと実質利回りの差を自ら試算できるかが、マンション投資で成功するかどうかの分岐点になります。
マンション投資で利回りを高めるポイント
ポイントは、経費を抑えつつ家賃水準を維持できる物件を選ぶことです。そのためには「立地」「管理体制」「間取り」の三要素をバランス良く評価する必要があります。
まず立地ですが、都心部は空室リスクが低い反面、物件価格が高いため表面利回りが下がりがちです。一方、郊外は価格が抑えられるものの、人口減少による空室リスクが高まります。総務省の住民基本台帳によれば、東京都23区は2024年から2025年にかけて人口が1.2%増加したのに対し、郊外市部は0.4%減少しました。つまり、利回りだけでなく将来の需要変動を視野に入れることが欠かせません。
次に管理体制です。新築時は管理費が低く設定されるケースが多いものの、築10年を過ぎると修繕積立金が段階的に上がることが一般的です。国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」では段階増額方式が推奨されており、将来の負担増を想定しないシミュレーションは危険です。
最後に間取りですが、ワンルームは単身者向け需要が底堅い一方、退去率が高い傾向があります。ファミリータイプは入居期間が長く、空室期間が短いものの、リフォーム費用が大きくなる可能性があります。つまり、投資家のキャッシュフロー戦略によって適切な間取りは変わるのです。
物件タイプ別利回り比較と注意点
実は、同じマンションでも築年数と規模によって利回りの傾向が大きく異なります。2025年10月時点の平均表面利回りを改めて整理すると、ワンルーム4.2%、ファミリータイプ3.8%、そして一棟アパートは5.1%です。
ワンルームは立地が良ければ短期間で売却しやすい流動性の高さが魅力です。反面、管理費比率が家賃の15〜25%とやや高めに設定されることが多く、実質利回りで見れば計算以上に目減りしやすい点に注意しましょう。
ファミリータイプは表面利回りこそ低めですが、家族世帯の平均入居期間は約4年とされ、退去時の原状回復費用を抑えやすいメリットがあります。ただし、占有面積が広いぶん、水回りの修繕が高額になりやすいので、長期修繕計画の確認が必須です。
一棟アパートは利回りが高いものの、土地と建物をまとめて購入するため多額の自己資金が求められ、空室リスクも棟単位で負うことになります。また、2025年度税制では木造アパートの法定耐用年数22年が変わっておらず、築古物件では原価償却の加速度的減価こそ魅力ですが、金融機関の融資年数が短くなり、返済比率が上がる点に注意が必要です。
2025年度税制・補助制度が与える影響
まず押さえておきたいのは、2025年度の住宅ローン控除が新築住宅に対して最大13年間、年末残高の0.7%を控除する制度として継続している点です。区分マンション投資でも自己居住用であれば適用対象ですが、賃貸用としては対象外ですので混同しないようにしましょう。
一方で、賃貸住宅向けの直接的な補助金は現時点では存在しません。しかし、エネルギー性能向上リフォームに対する「賃貸住宅高効率給湯器導入促進事業(2025年度)」は活用できます。高効率給湯器に交換すると、1戸あたり最大5万円の補助が受けられるため、修繕費の圧縮と入居者満足度向上の両方に寄与します。
また、所得税の損益通算ルールは2021年度改正以降、赤字幅が家賃収入を超える部分について制限が設けられています。2025年度もこの取り扱いは継続しており、過度な節税目的での赤字計上は難しくなっています。つまり、キャッシュフローが黒字化する投資戦略を前提にシミュレーションする姿勢が求められます。
最後に、固定資産税の軽減措置として、築年数が浅い耐火構造住宅に対しては新築後5年間、固定資産税が半額になる制度が2025年度も続いています。この期間をどう活用するかで、実質利回りの立ち上がりが変わるため、購入時期と築年数の兼ね合いを意識すると良いでしょう。
まとめ
ここまで、表面利回りと実質利回りの違いを中心に、マンション投資で見るべき指標や注意点を解説しました。表面利回りは物件比較の入り口として有用ですが、経費や空室リスクを織り込んだ実質利回りこそが収益の現実を映し出します。さらに、立地・管理体制・間取りの三要素を踏まえ、最新の税制や補助制度まで視野に入れれば、数字の裏に隠れたリスクを最小限に抑えられます。まずは気になる物件で実質利回りを自計算し、将来の家賃下落や修繕費増も織り込んだキャッシュフロー表を作成してみてください。数字を味方につけることで、安定したマンション投資への一歩を踏み出せるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 国税庁 所得税法関連資料(2025年度) – https://www.nta.go.jp

