不動産投資に興味はあるものの、「現物は高くて手が出ない」と感じていませんか。実は、上場不動産投資信託(REIT)は証券口座さえあれば数万円から購入でき、物件管理の手間もかかりません。本記事では「REIT いくら」で検索した読者が知りたい最低投資額の目安、コスト構造、そして2025年度の制度活用までを網羅します。読み終えるころには、ご自身の資金計画に合わせた投資シミュレーションが描けるはずです。
REITの基礎と少額投資の魅力
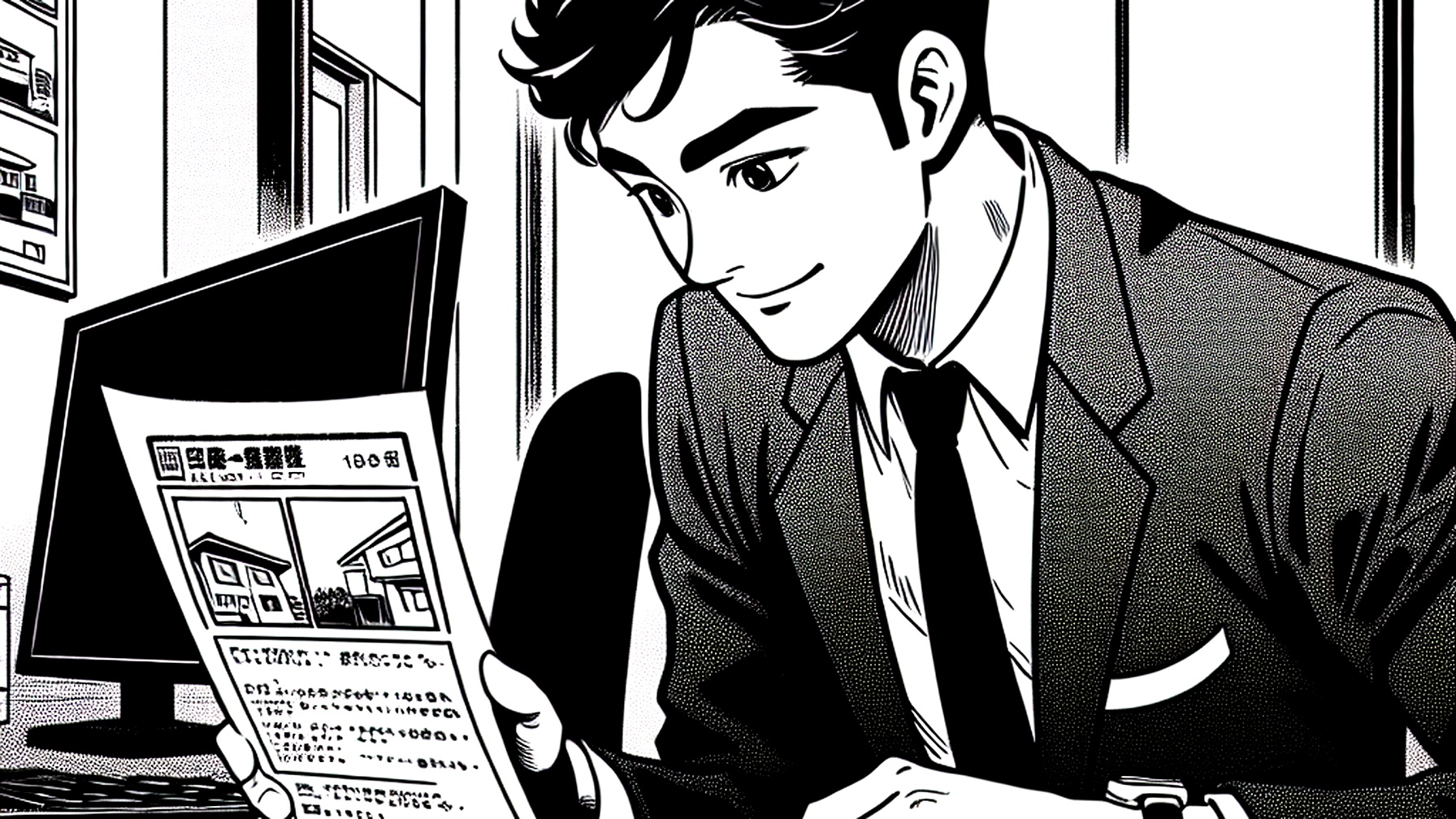
まず押さえておきたいのは、REITが「投資家から集めた資金で複数の不動産を保有し、賃料収入などを分配するしくみ」を持つ金融商品だという点です。東京証券取引所によると、2025年10月時点で上場REITの銘柄数は66本に増え、オフィス、住宅、物流施設など投資対象も多様化しています。現物不動産と違い、管理業務や入居者対応をプロに任せられるため、時間の制約がある会社員でも取り組みやすいのが特徴です。
さらに、少額で分散投資ができる点も魅力です。REITは株式と同様に1口単位で売買でき、最低購入価格(株価×1口)さえ用意すれば参入できます。物件を丸ごと買うのに比べ、リスクを限定しながら賃料収入を得られるので、投資経験が浅い人のステップアップとして適しています。つまり、REITは「現物よりハードルが低い不動産投資」として位置づけられています。
いくらから買える?市場価格と取引単位のしくみ
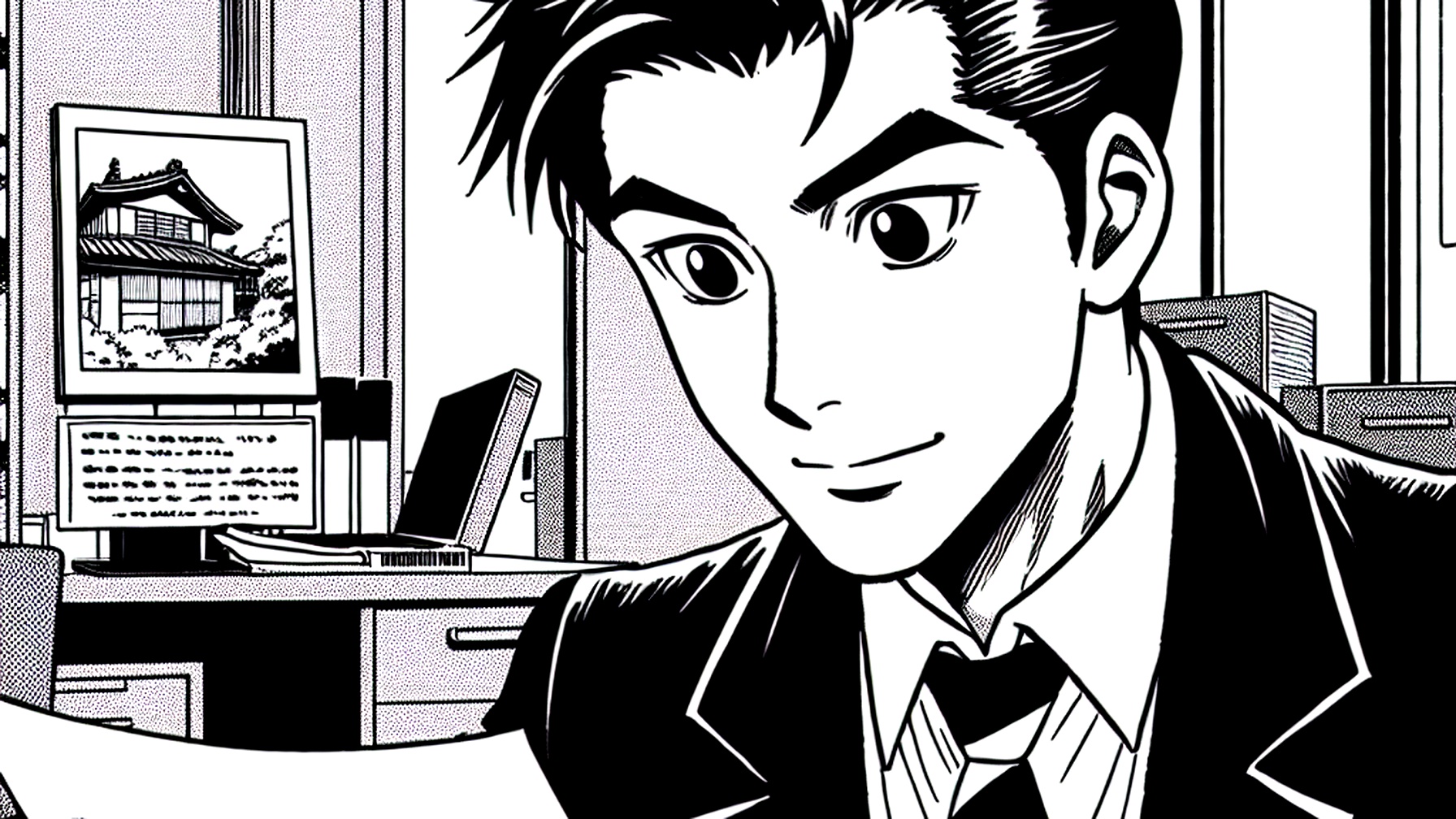
ポイントは、REITの投資額が「株価×口数」で決まる点です。東証の統計によれば、2025年10月の平均価格は1口11万5,000円前後ですが、最も安い銘柄は5万円台、高い銘柄は20万円超と幅があります。つまり、「REIT いくら」で調べたとき、多くの入門者は5万円〜12万円を目安に考えると現実的です。
取引単位は原則1口なので、株式のように100株単位でまとまった資金を用意する必要はありません。証券会社によっては「単元未満取引」を提供しており、1口未満の小口化も可能です。ただし、流動性が低い銘柄では希望価格で約定しにくい点に注意しましょう。また、ネット証券の売買手数料は無料化が進んでいる一方、管理報酬(運用会社への費用)は年間0.2〜0.7%程度が基準です。目に見えにくいコストなので、目論見書で必ず確認してください。
予算別シミュレーション:1万円・10万円・100万円
重要なのは、自分の資金規模に合わせたポートフォリオを描くことです。ここでは仮想例として、分配金利回り4.1%の銘柄A、3.8%の銘柄B、3.6%の銘柄Cを使用します。
まず1万円から始めたい場合、単元未満取引を利用して銘柄Aの0.1口(約1万1,500円)を購入すると、年間分配金はおよそ470円です。金額は小さいものの、値動きと配当サイクルを体験できるため、勉強代としては十分なリターンと言えます。
次に、10万円を投じるケースでは銘柄Bを1口、残りは銘柄Cの0.8口を組み合わせる方法があります。年間分配金の合計は約3,920円となり、複数銘柄に分散することで価格変動リスクを抑えられます。また、分配金再投資を続ければ、複利効果で保有口数が徐々に増える点もメリットです。
最後に、100万円を用意できる場合は、オフィス系、物流系、住宅系を各3〜4口ずつ購入し、残額を投資法人債やREIT ETFに振り向ける戦略が考えられます。このポートフォリオでは年間4万円前後の分配金を期待でき、市場環境に応じて資産配分を調整する「リバランス」も実践できます。つまり、同じ「REIT いくら」でも予算次第で運用戦略は大きく変わるのです。
コストとリスクを抑える三つの視点
一方で、リスク管理を怠ると少額投資でも損失は避けられません。まず価格変動リスクについては、J-REIT指数とTOPIXの相関係数が過去10年平均で0.6前後というデータが示すように、株式市場の影響を完全に逃れることはできません。そのため、値上がり益だけを狙うのではなく、分配金利回りを評価軸に加える視点が欠かせません。
次に、金利上昇リスクがあります。REITは物件取得資金として借入を行うため、長期金利が上がると財務コストが増えて分配金が圧迫されるおそれがあります。投資法人の有利子負債比率(LTV)が50%を超える銘柄は警戒が必要です。IR資料に目を通し、固定金利比率が高いほど金利変動の影響を受けにくい点を意識しましょう。
最後に、自然災害や人口動態の変化など特定セクター固有のリスクも存在します。物流施設はEC拡大で追い風を受けていますが、郊外住宅は空室率の上昇が懸念される地域もあります。セクターを分散させ、財務の健全性と物件ポートフォリオの地域バランスを両輪で確認することが、リスク低減への近道です。
2025年度の税制優遇と制度の活用ポイント
実は、2025年度もNISA(少額投資非課税制度)の恒久化により、年間360万円までの投資枠でREIT分配金と譲渡益が非課税になります。非課税保有限度額1,800万円の中でREITを組み込めば、税引き後利回りを実質0.2〜0.4ポイント押し上げられる計算です。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)ではREIT ETFを選択でき、掛金控除と運用益非課税の二重メリットが得られます。
さらに、環境性能の高い物件を多く保有する「グリーンREIT」は、2025年度も国土交通省のグリーンビル認証制度に基づく優遇融資を受けやすい状況が続いています。投資家への直接補助金はありませんが、運用コストが下がることで分配金の底上げが期待できます。制度の詳細は各運用会社の開示資料で最新情報を確認してください。
つまり、税制メリットと運用会社の資金調達環境をセットで把握することで、少ない元手でも手取りリターンを最大化できる余地が広がります。制度の公募要件や期限は毎年更新されるため、2025年10月の時点で有効な情報かを必ず確かめる姿勢が重要です。
まとめ
ここまで、REITを「いくらから」「どのように」始めるかを資金別に解説してきました。最低5万円台から購入できる一方で、価格変動や金利上昇のリスク管理も欠かせません。NISAなど2025年度に有効な非課税制度を活用しながら、分配利回りと財務指標を軸に銘柄選定を行うことで、少額でも堅実なキャッシュフローを構築できます。まずは証券口座を開き、気になる銘柄のIR資料を読むところから一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産市場動向 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 NISA制度概要(2025年度版) – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ J-REIT指数データ – https://www.jpx.co.jp/markets/indices/j-reit-index
- 一般社団法人投資信託協会 REITハンドブック – https://www.toushin.or.jp

