海外資金が流入し円安が続くいま、都心マンションの価格は高騰する一方で賃料は緩やかな上昇にとどまります。「高値づかみにならないか」「利回りが伸びないのでは」と不安を抱く人も多いでしょう。この記事では、表面利回りを軸に円安時代のマンション投資を読み解き、リスクを抑えて収益を確保する方法を解説します。初心者でも理解しやすいよう基礎から順に説明するので、読み終えるころには投資判断の指針が手に入るはずです。
表面利回りが示すものと限界
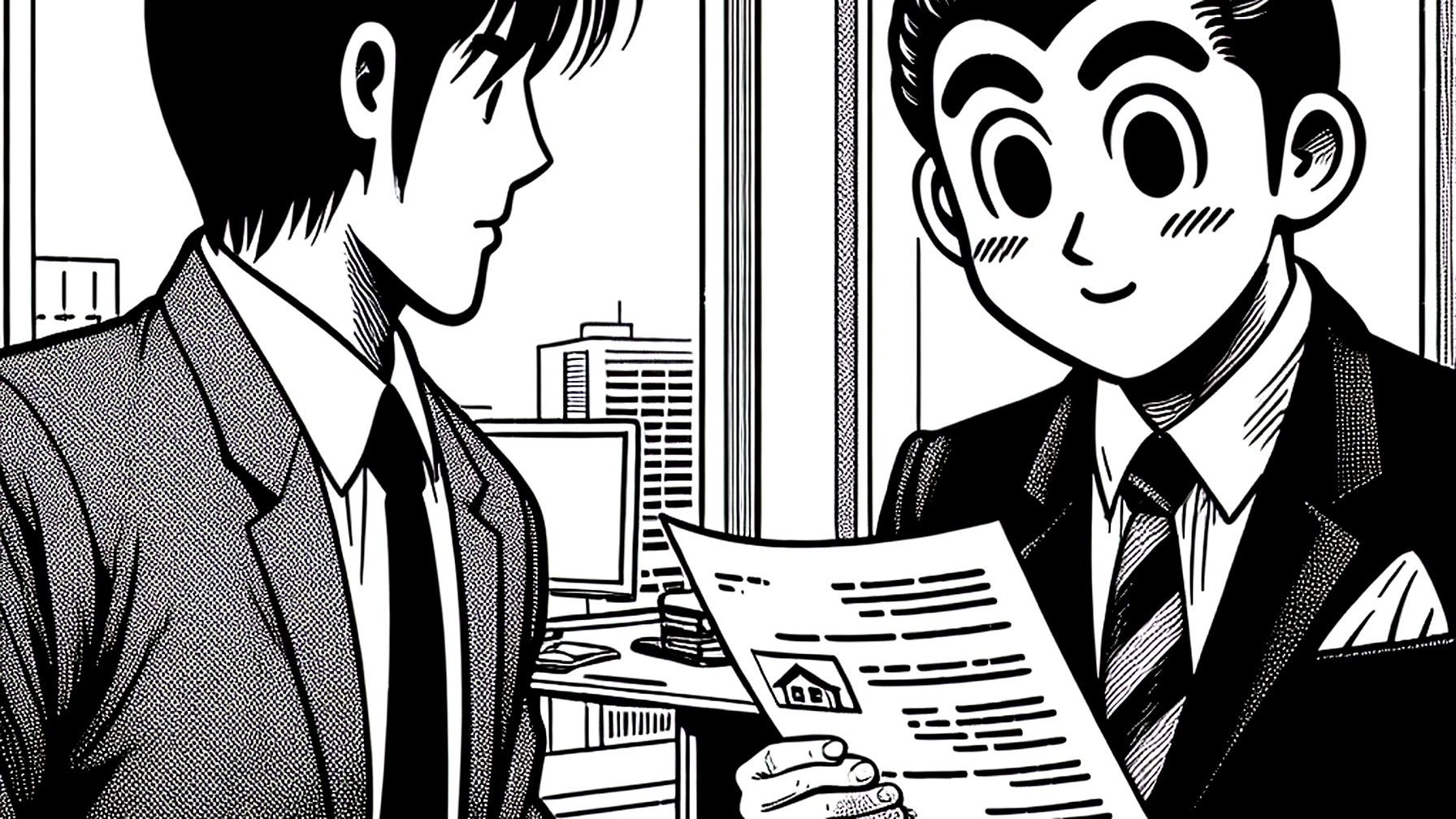
まず押さえておきたいのは、表面利回りが物件の収益力を測る最もシンプルな指標である点です。年間家賃収入を購入価格で割るだけで算出できるため比較が容易ですが、経費や空室の影響が反映されないという弱点も併せ持ちます。
日本不動産研究所によれば、2025年10月時点の東京23区平均表面利回りはワンルームで4.2%、ファミリータイプで3.8%です。数字だけを見ると魅力が薄いように見えますが、都心の空室率は2%前後と低く、安定性が高い点を評価すべきでしょう。一方で、地方都市では6%超の物件も散見されますが、人口減少に伴う空室リスクが高まります。つまり、表面利回りの数値だけで判断すると、後から修繕費や稼働率の低下に苦しむ可能性があります。
重要なのは、実質利回りを試算し直すことです。管理費や固定資産税、将来の大規模修繕費を盛り込み、空室率を5〜10%程度想定して再計算すると、都心と郊外の差は縮まるケースが多いと感じるはずです。このプロセスを経て初めて物件を比較できるようになります。
円安時代がもたらす価格と賃料のミスマッチ
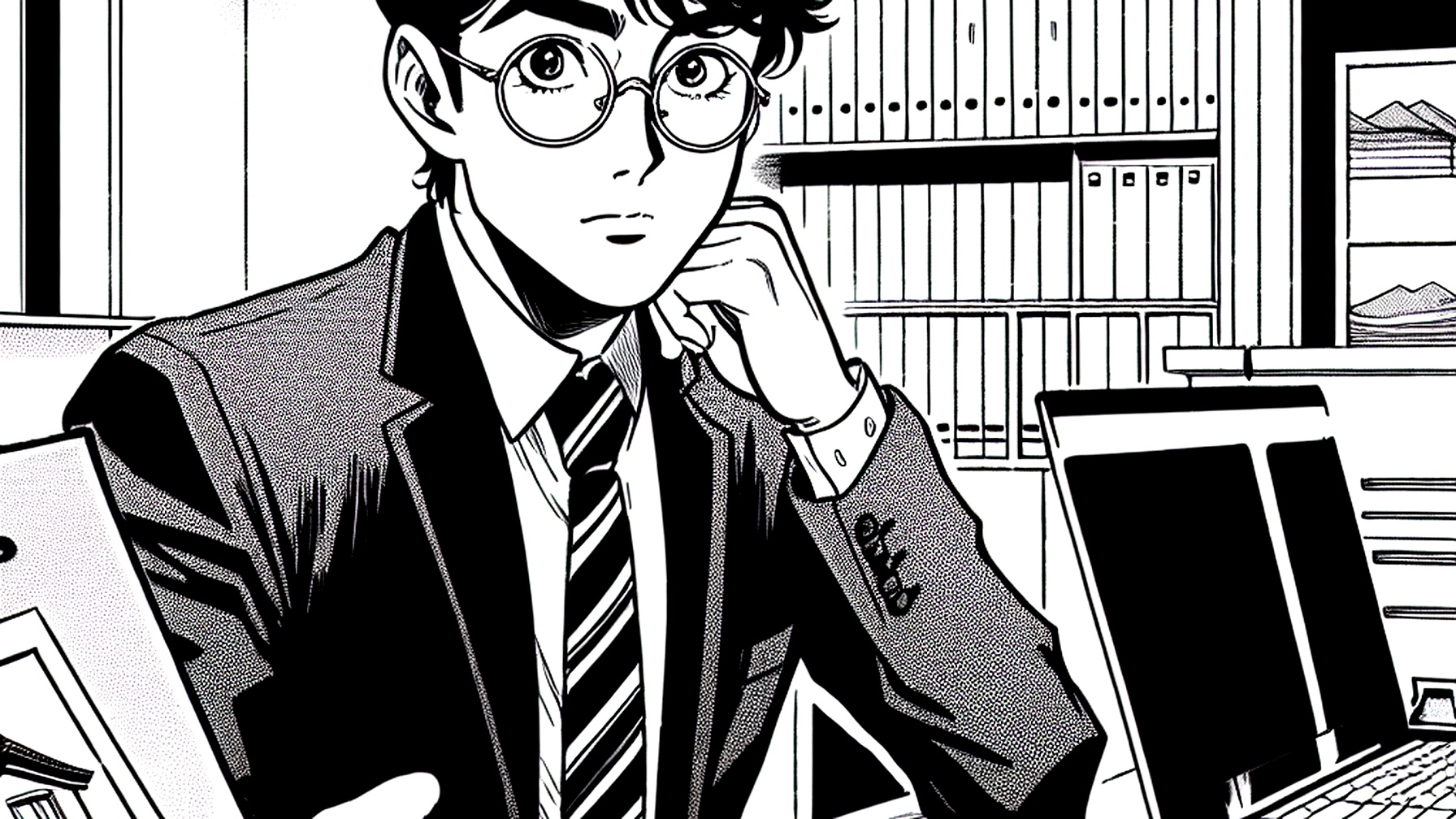
円安が長期化すると、海外投資家にとって日本の不動産は割安に映ります。その結果、特に東京23区の新築マンション価格は2025年10月時点で平均7,580万円と前年比3.2%上昇しました(不動産経済研究所)。しかし、賃料は同期間で1.5%程度の上昇にとどまっています。
実は、この価格と賃料の伸び率の乖離が表面利回りを押し下げる主因です。価格が速く上がれば分母が大きくなり、利回りは低下します。それでも円安が継続すれば、将来的な売却益を狙うキャピタルゲイン型の戦略が有効になる可能性があります。一方で、賃料収入を軸に考えるインカムゲイン型の投資家は、購入価格の抑制と高稼働の両立が欠かせません。
ポイントは、為替と金利を同時に見ることです。円安局面では輸入インフレが進み、国内金利もじわじわ上昇する傾向があります。金利が1%上がると35年ローン総返済額は約700万円増えるため、利回り低下とダブルパンチになりかねません。したがって、契約前に固定と変動のどちらが自分のリスク許容度に合うか、シミュレーションを繰り返す必要があります。
成功する物件選びと資金計画
重要なのは、購入前に「出口戦略」と「資金繰り」をセットで描くことです。都心の駅徒歩5分以内という王道立地は価格が高くても、賃料下落が小さいため長期保有に向きます。逆に、再開発が予定される準都心エリアは短期的に賃料が伸びることがあり、数年後の売却益を狙う選択肢も見えてきます。
資金計画では、自己資金を物件価格の20〜30%用意するのが目安です。頭金を厚くすることで月々の返済負担を抑え、金利上昇局面でもキャッシュフローを守りやすくなります。また、修繕積立金の不足が指摘される築浅マンションもあるため、購入前に管理組合の長期修繕計画を必ず確認しましょう。
さらに、賃貸管理会社の選定も利回りに直結します。管理料が月額家賃の5%から3%に下がれば、表面利回り4%の物件でも実質利回りが0.2ポイント改善する計算です。つまり、物件の良し悪しだけでなく、管理コストの最適化が収益改善の鍵を握ります。
リスク管理と長期戦略の立て方
まず、自然災害リスクを無視するのは危険です。ハザードマップで洪水や液状化の可能性を確認し、必要なら火災保険に水災特約を付けるなど備えましょう。保険料は経費計上できるため、実質的な税負担は軽減されます。
一方で、空室リスクを低減するには差別化が効果的です。インターネット無料やスマートロックの導入は月額数千円のコストで済み、退去抑制につながります。また、家具付き短期賃貸に転用できる間取りであれば、観光需要の回復期に家賃を上げられる可能性があります。
不動産は長期保有が原則ですが、ライフプランの変化に応じて売却や買い替えを検討する柔軟性も必要です。東京都心の実売データでは、築10年以内のワンルームは購入価格比105%前後で取引される例があります。こうした情報を常に収集し、出口の想定価格をアップデートすることで、償却年数やローン残高とのバランスを整えられます。
2025年度の税制と活用できる制度
ポイントは、制度を知って適切に使いこなすことです。2025年度も不動産所得に対する主要な税制は大きく変わらず、減価償却費を活用することで課税所得を圧縮できます。鉄筋コンクリート造(RC造)の法定耐用年数は47年であり、築20年の中古マンションなら残存耐用年数は27年です。長めに償却できるため、表面利回りが低くても税引き後キャッシュフローが改善するケースがあります。
また、住宅ローン減税は居住用が対象ですが、投資家でも併用住宅や将来の自己居住を視野に入れたスキームを取ることで恩恵を受ける事例があります。ただし、適用条件は厳密なので、税理士に相談して慎重に進めることが不可欠です。
さらに、2025年度も続く「既存住宅省エネ改修補助金」は自己居住用の改修が前提ですが、将来住む予定の区分所有マンションを先に購入する場合には活用余地があります。期限は2026年3月までと発表されているため、該当する人は早めに検討したいところです。賃貸用区分には直接使えませんが、自宅を補助で高性能化し、浮いた資金を投資用に回すという発想も有効です。
まとめ
表面利回りだけを追うと、円安時代のマンション投資は魅力が薄れて見えます。しかし、実質利回りを精査し、価格上昇と賃料の乖離を踏まえた資金計画を立てれば、都心物件でも安定したキャッシュフローを確保できます。円安に伴う海外マネーの流入や金利動向を注視しつつ、保険・税制・管理体制を最適化することが成功への近道です。この記事で紹介した視点を自分の投資戦略に当てはめ、まずは一件の物件を徹底検証してみてください。行動することでしか得られない経験が、次のチャンスを確実につかむ力になります。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 気象庁 ハザードマップポータル – https://disaportal.gsi.go.jp

