副業や事業拡大のために資産運用を始めたいものの、「物件を買うのはハードルが高い」と感じる個人事業主は多いでしょう。不動産クラウドファンディングであれば少額から分散投資ができ、事業用資金を圧迫せずに不動産収益を得られます。本記事では、2025年10月時点の最新情報を踏まえ、仕組みの基本から案件選び、税務のポイントまでを丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合ったサービスを見極め、次の一歩を踏み出す自信が得られるはずです。
不動産クラウドファンディングの仕組みを理解する
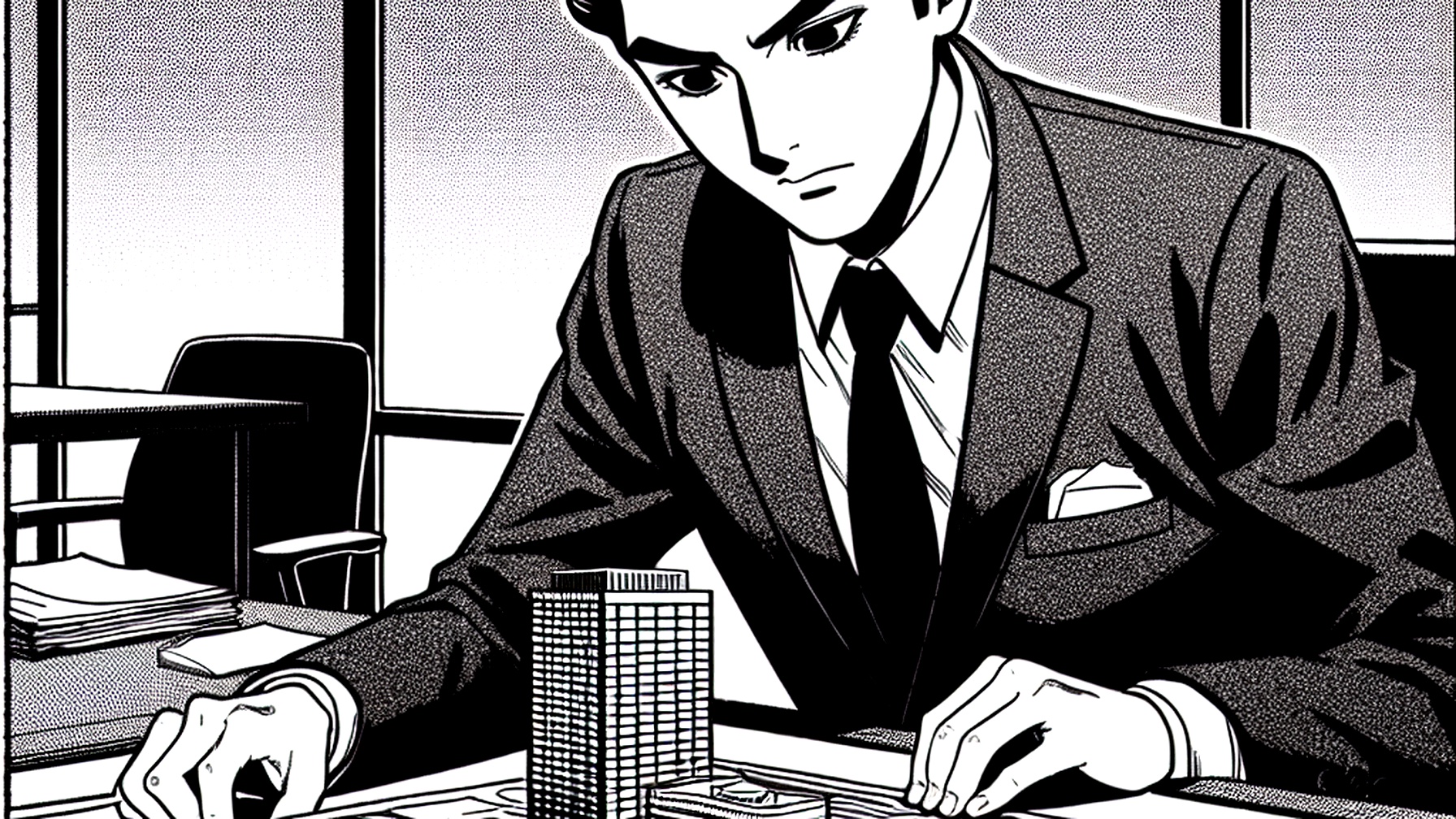
まず押さえておきたいのは、クラウドファンディングとREIT(不動産投資信託)の違いです。不動産クラウドファンディングは、インターネット上で投資家を募り、特定の物件や開発プロジェクトに限定して資金を集めます。運用期間が半年から三年程度と比較的短く、募集金額も数千万円から十数億円とスケールが幅広い点が特徴です。
金融庁の「ソーシャルレンディング・クラウドファンディング統計」(2025年6月時点)によると、市場規模は年間1,800億円を超え、前年同期比で約25%伸びています。つまり、この市場は成長中であり、個人事業主でも参加しやすい環境が整いつつあるのです。
また、投資家は「優先出資」と呼ばれる立場をとる場合が多く、一定割合までは事業者が劣後出資で損失を吸収します。これにより、元本割れリスクを抑えやすい設計になっています。ただし、元本保証ではないため、案件ごとのリスク開示を読み込み、利回りだけで判断しない姿勢が必要です。
個人事業主が享受できるメリットと注意点
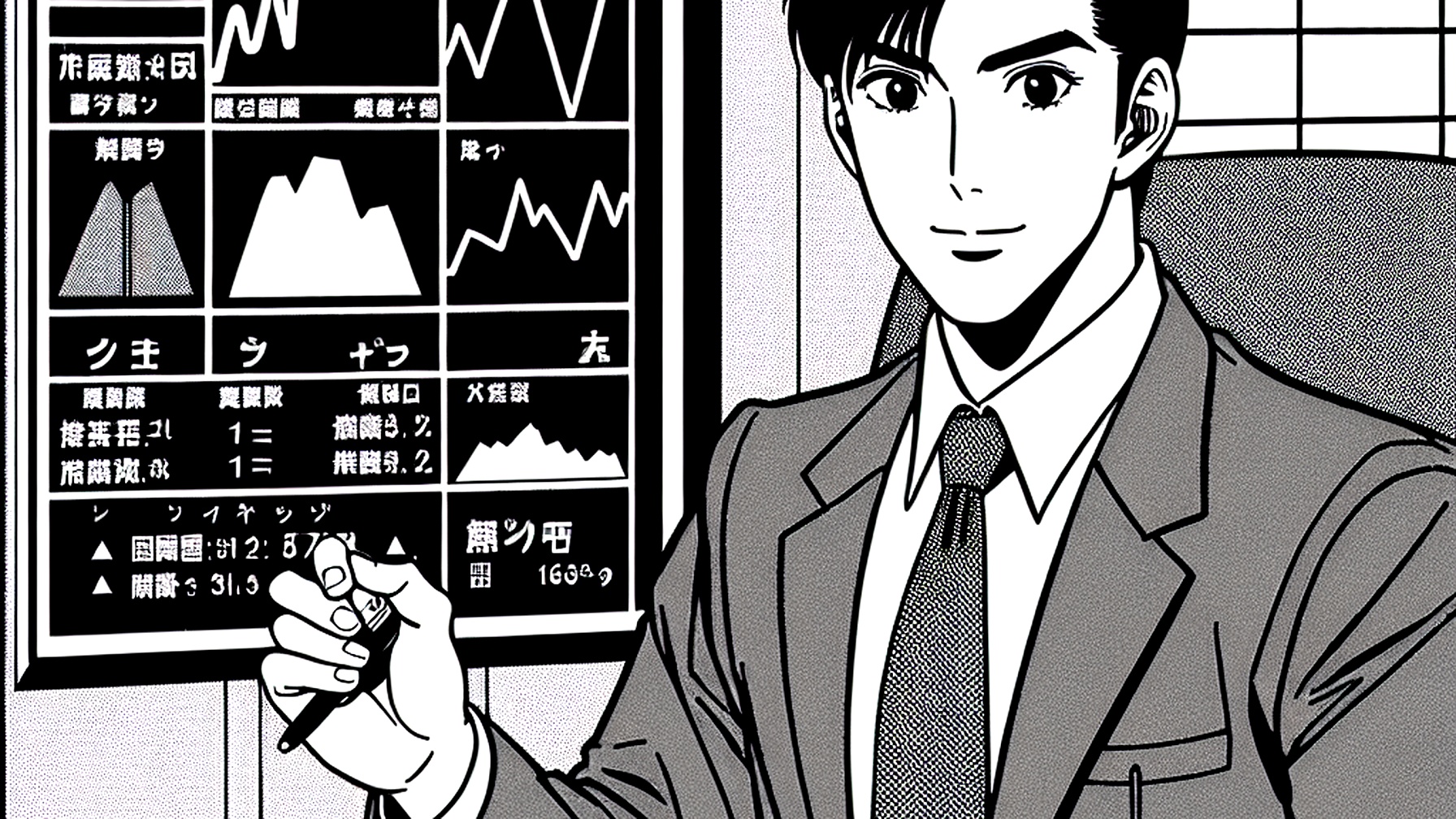
ポイントは、事業と資産運用を両立できる手軽さにあります。最低投資額は1万円前後が主流で、資金繰りの波が大きい個人事業主でも参加しやすいのが魅力です。投資口数を細かく調整できるため、繁忙期のキャッシュ不足を回避しながら長期的な資産形成を図れます。
一方で、案件によっては分配金が源泉徴収後に振り込まれるため、確定申告で損益通算ができない場合があります。白色申告のままでは経費計上の自由度も限定的です。2025年度税制では、青色申告者が65万円控除を受ける条件が従来どおり維持されているので、早めに青色に切り替えるほうが有利になります。
さらに、クラウドファンディングの配当は「雑所得」に区分されるのが一般的です。事業所得と合算すると税率が上がるケースもあるため、シミュレーション時は課税所得の階層を必ず確認しましょう。金融機関から事業融資を受ける予定がある場合は、投資の損失リスクが審査に影響する可能性があることも忘れないでください。
案件選びで重視すべき四つの視点
実は、高利回りよりも「情報の透明性」を最優先すべきだと言えます。第一に、運営者の実績が豊富かどうかを確認しましょう。日本クラウド不動産協会の2025年調査では、運用実績100件以上の事業者と10件未満の事業者では、予定利回りとの差異が平均1.2ポイント生じています。経験値は成果に直結するのです。
第二に、物件の立地と用途を読み解く力が必要です。住宅系は景気変動に強い一方、オフィス系は空室率が市況に左右されやすい傾向があります。国土交通省の「不動産市場動向レポート」(2025年8月)では、東京23区の住宅空室率が4.2%で横ばいなのに対し、同期間の地方主要都市オフィス空室率は7.5%へ上昇しています。数字が示す通り、物件タイプでリスクが変わる点を意識してください。
第三に、劣後出資割合は損失クッションの厚さを示す重要指標です。20%以上を事業者が負担している案件なら、軽微な価格下落で元本割れに至る可能性は低くなります。ただし、過度な割合は資金繰りを圧迫し運営不全を招く恐れもあります。目安として10〜30%の範囲でバランスを確認するといいでしょう。
最後に、運用期間と途中解約条件を読み込みましょう。個人事業主は急な資金需要が起きやすいため、半年ごとに分配と償還を行う短期案件や、二次流通市場で売却可能なサービスを選ぶと柔軟性が高まります。
2025年注目のプラットフォームを比較する
まず、有名どころとしてCREAL、OwnersBook、Rimpleの三社を取り上げます。CREALは一口1万円から投資可能で、優先劣後比率が30%と高めに設定される案件が多いのが特徴です。最長運用期間は36カ月程度に収まり、流動性リスクを抑えたい人に向いています。
OwnersBookは想定利回り4〜7%で、担保評価額を詳細に開示している点が強みです。地味ながら東京23区内オフィス中心の案件が多く、安定志向の投資家から支持されています。実際に2025年9月の運用報告によると、累計償還額は800億円を超え、一度も元本割れが発生していません。
一方、Rimpleは上場企業のプロパティエージェントが運営し、居住用区分マンションに特化しています。抽選制で競争率が高いものの、運用期間6〜12カ月と短めの案件が主体です。即時換金こそできませんが、短期的にキャッシュを回収したい個人事業主には相性がいいでしょう。
ここで「不動産クラウドファンディング おすすめ 個人事業主」という検索ニーズに答えるなら、自身の資金繰りサイクルに合わせて上記三社を組み合わせることが現実的です。具体的には、半年から一年で償還されるRimpleで流動性を確保しつつ、CREALで中期運用、OwnersBookで長期安定収入を狙う三本立てがバランスの良い戦略になります。
税務と資金計画を整えて長期戦に備える
重要なのは、投資から得られる利益を「事業の余剰資金」として位置づけ、青色申告決算書と合わせて一元管理することです。現金主義では入出金タイミングによる利益のブレが大きくなるため、2025年度税制で認められている「発生主義」に切り替えると経営判断がしやすくなります。
また、クラウドファンディングで得た配当は減価償却が伴わないため、他の不動産保有による減価償却費と組み合わせて節税を図る方法が有効です。例えば、自宅兼事務所のリフォームを行い、耐用年数が15年の設備を導入すれば、毎年均等に経費計上でき、課税所得を圧縮できます。
資金計画では、投資用と事業用の口座を分けるだけでなく、運用利益の20%を「突発的な事業経費予備費」としてプールするルールを設けると、景気後退期にも事業基盤を守れます。日本政策金融公庫の統計(2025年4月)では、突発費用を予め確保していた小規模事業者の黒字継続率は、確保していない事業者に比べて1.6倍高いというデータがあります。数字が示すとおり、キャッシュリザーブは長期的な成長を支える鍵なのです。
まとめ
不動産クラウドファンディングは、物件を直接保有せずに不動産収益を得られる手軽な手段です。個人事業主にとっては、少額から分散投資ができ、事業資金と切り離して資産形成を進めやすい点が大きな魅力と言えます。ただし、案件ごとのリスク構造や税務上の取り扱いを理解し、資金繰り計画と一体で運用する姿勢が不可欠です。今回紹介したサービス比較や税務の要点を踏まえ、自分の事業フェーズに合った投資戦略を組み立ててみてください。行動を先送りせず、小さく試して学んでいけば、安定したキャッシュフローが将来の挑戦を後押ししてくれるでしょう。
参考文献・出典
- 金融庁 ソーシャルレンディング・クラウドファンディング統計(2025年6月) – https://www.fsa.go.jp
- 国土交通省 不動産市場動向レポート(2025年8月) – https://www.mlit.go.jp
- 日本クラウド不動産協会 市場調査レポート(2025年) – https://www.jrea.or.jp
- 日本政策金融公庫 小規模事業者経営統計(2025年4月) – https://www.jfc.go.jp
- CREAL 運用実績データ(2025年9月公開) – https://creal.jp

