不動産投資信託(REIT)に興味はあるものの、「REIT 分配金 いくら受け取れるのだろう」と悩む方は少なくありません。株式と違い、物件賃料が原資になるため安定していると言われますが、実際の金額や計算方法が分からなければ一歩を踏み出しにくいものです。本記事では、分配金の仕組みから目安の算出、2025年度の税制までを体系的に解説します。読み終えるころには、自分にとって適切な投資額と期待利回りを具体的にイメージできるはずです。
REITの分配金はどうやって決まるのか
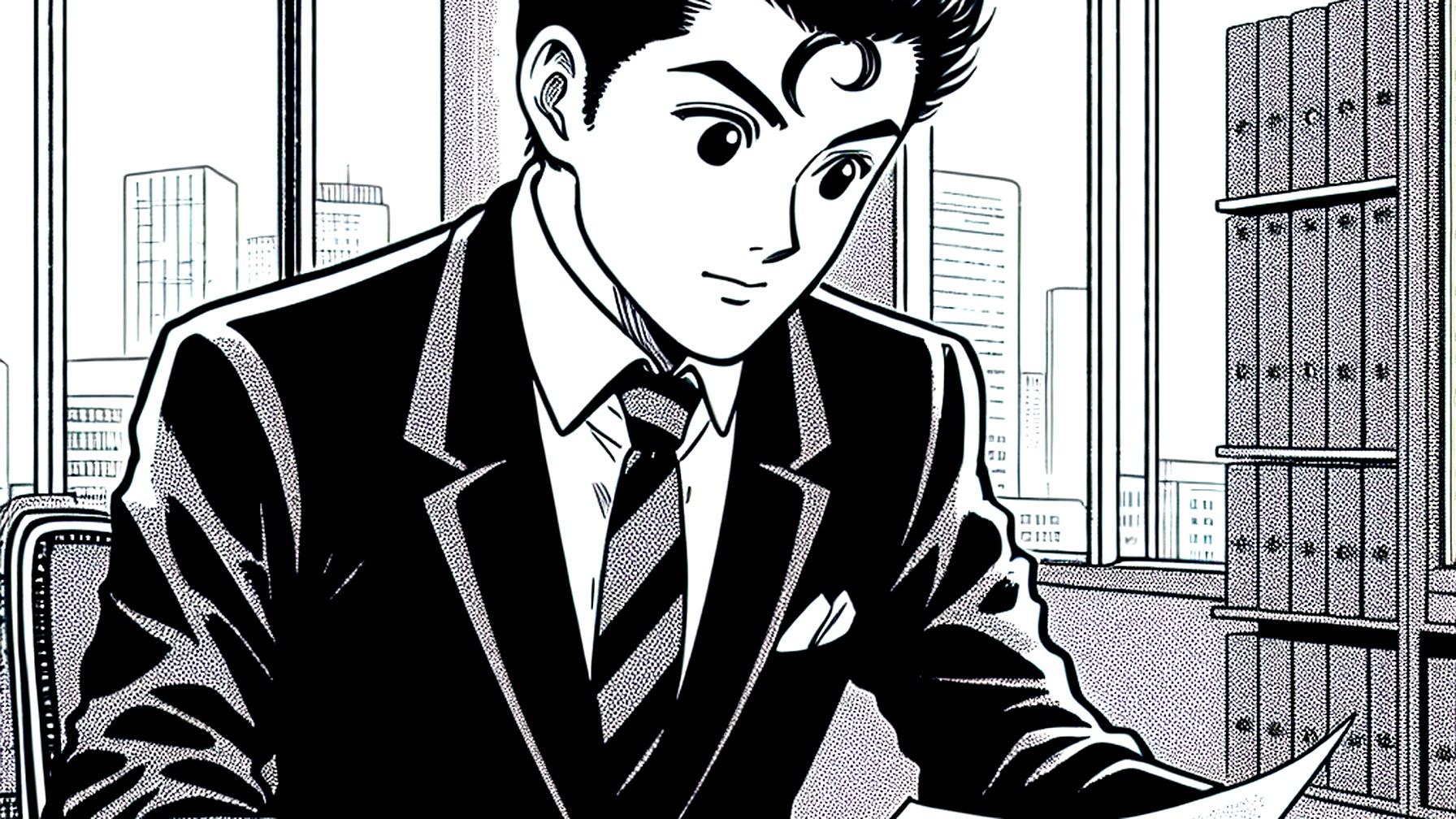
まず押さえておきたいのは、REITの分配金は賃料収入などの不動産収益をもとに計算される点です。法律上、投資法人は利益の90%以上を分配することで法人税が実質的に免除されるため、高い分配性向が維持されます。
実際には、物件から得た賃料や共益費、売却益などが運用収益になります。そこから修繕費や管理費、金利などの運営コストを差し引き、最終的な利益が確定します。利益の大半を分配するため、収益が安定していれば分配金も安定しやすい仕組みです。また、金融庁の開示規則により、投資法人は半期ごとに損益状況を開示しており、投資家は分配金の原資を透明に確認できます。
一方で、物件の入替えや増資による希薄化が起こると、一口当たりの利益が変動する点には注意が必要です。物件入れ替え時に売却益が計上されると、その期の分配金は一時的に増える場合がありますが、継続的に増えるとは限りません。つまり、単に「高い分配金=安定」と判断するのではなく、収益構造と運用方針を合わせて確認することが重要です。
分配金はいくらもらえる?目安を計算する方法
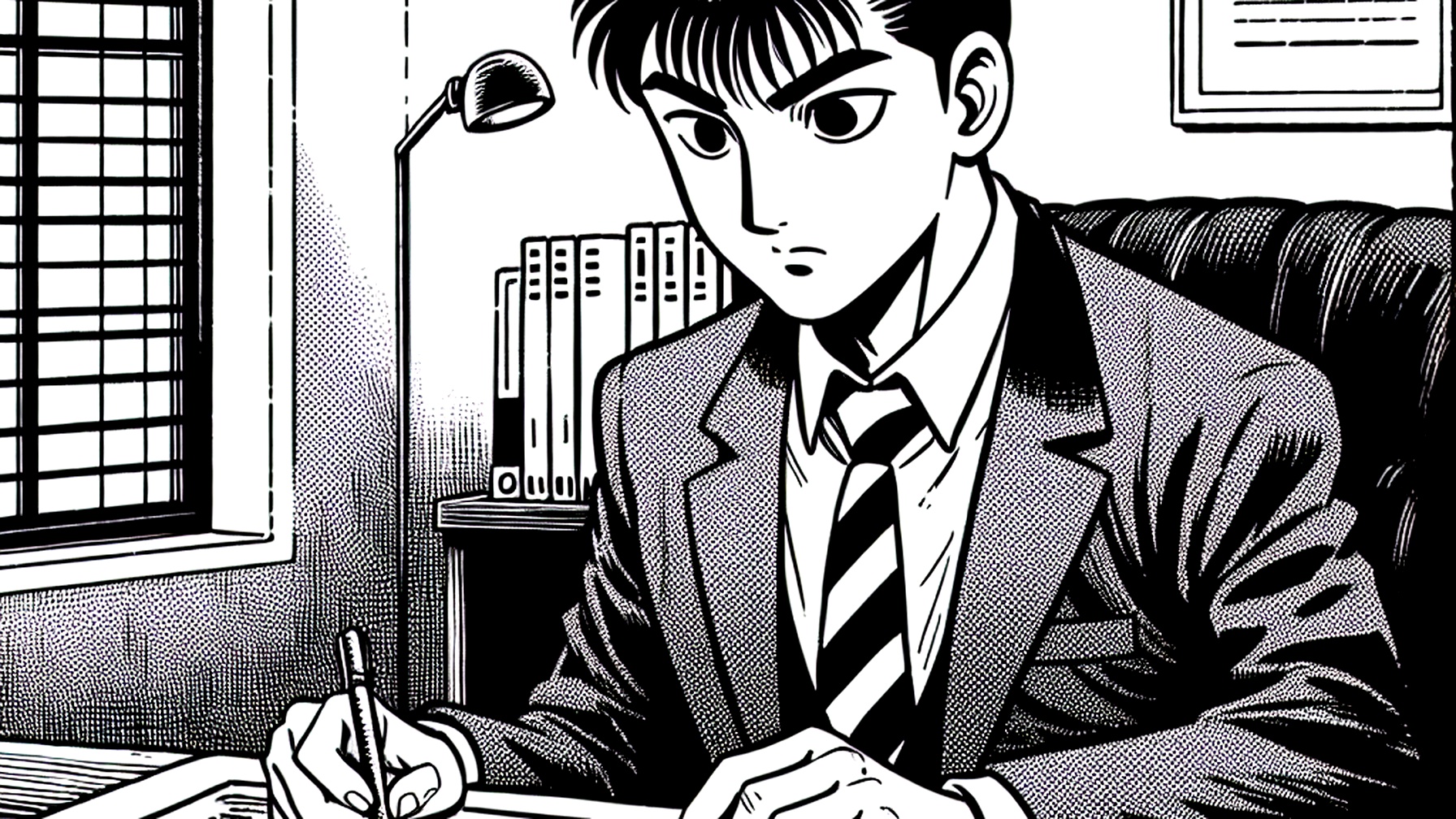
ポイントは、分配金利回りと投資口数を掛け合わせるだけで概算が得られることです。たとえば、東証REIT指数の平均利回りは2025年10月時点で年3.8%程度と報告されています。100万円を投資した場合、年間の分配金はおおむね3万8千円、半期配当なら1万9千円が目安です。
しかし、これはあくまで市場平均の目安であり、個別銘柄ごとの利回りは1.5%から7%台まで幅があります。利回りが高い銘柄はテナント入替えリスクや物件立地の偏りなど潜在的なリスクを抱えていることも多いため、単純比較は禁物です。また、上場REITは価格変動があるため、購入時の取得価格によって実質利回りが変わります。投資時点での株価(投資口価格)に対する利回りを「購入利回り」と呼び、これを基準に年間分配金額を試算するのが実務的です。
具体的な計算は簡単です。例えば「購入利回り5%・投資額200万円」の場合、年間分配金は10万円前後になります。半期分配なら5万円ずつ受け取るイメージです。資産形成のスピードを測るには、このキャッシュフローが家計にどれだけ寄与するかをシミュレーションするとよいでしょう。
分配金を左右する三つの要素
実は、分配金の大小を決める主要因は「物件収益」「負債コスト」「運営方針」の三つに集約できます。まず物件収益は立地やテナントの契約形態で決まるため、都心オフィスや都市型住宅を多く組み入れるREITほど安定傾向にあります。一方、ホテルや物流施設主体のREITは景気変動や需要サイクルの影響を受けやすく、分配金が期ごとに揺れやすい特徴があります。
次に負債コストです。REITは物件取得資金の30〜50%を借入金で賄うケースが一般的で、金利が上昇すると支払利息が増え、分配余力が縮小します。日本銀行は2024年にマイナス金利を解除しましたが、2025年10月時点でも政策金利は0.5%前後で推移し、借入金利も平均1%台に収まっています。ただし、長期的には金利上昇余地があるため、固定金利比率や返済スケジュールを開示しているREITほど安心感があります。
最後に運営方針です。増資で資金調達し物件規模を拡大する場合、長期的には分配金総額が増えるものの、短期的には「一口当たり分配金」が希薄化することがあります。投資法人の開示資料で「外部成長戦略」や「内部成長戦略」のバランスを読み解き、自分の投資期間と照らし合わせる視点が欠かせません。
分配金利回りとリスクのバランスを考える
重要なのは、高い利回りだけを追いかけず、リスクとセットで評価する姿勢です。金融庁の統計によれば、直近5年間で東証REIT指数の年間変動率は平均15%前後でした。つまり、価格変動による元本リスクを理解しないまま分配金だけを比較すると、想定外の評価損を抱えるおそれがあります。
具体的には、利回り6%台の物流REITを保有しながら、テナントの解約で賃料が10%下落すると、翌期の分配金が一気に減る可能性があります。また、オフィスREITでは2023年以降のリモートワーク定着で空室率が上昇し、一部銘柄の分配金は前年比5%程度減少しました。利回りが高い銘柄ほどこうした逆風での影響が大きくなるため、分散投資が効果的です。
一方で、財務レバレッジを抑えた住宅特化型REITなどは利回り3%台と控えめですが、賃料収入が比較的安定しており、分配金も緩やかに伸びています。言い換えると、リスク許容度が低い投資家は堅実型REITを中心にポートフォリオを組み、残りを高利回り銘柄で補完する形が現実的です。
2025年度の税制と手取り分配金の計算
まず、2025年度も上場株式等の配当と同様に、REITの分配金には20.315%の申告分離課税(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。NISAを利用しない場合、先ほどの年間分配金10万円の例では、税引き後手取りはおよそ8万円に減少します。NISA口座で保有すれば非課税になるため、利用枠に余裕があれば優先的に組み入れたいところです。
2024年に刷新された新NISAは2025年度も継続中で、つみたて投資枠と成長投資枠の合計年間投資上限が360万円、非課税保有限度額が1,800万円となっています。REITは成長投資枠で購入できますが、枠を使い切ると課税口座での保有となるため、分配金の手取りを最大化するには、毎年の投資計画を立ててから発注することが重要です。
また、給与所得者が課税口座でREITを保有すると、源泉徴収で完結するため確定申告は不要です。しかし、ほかの株式配当や譲渡損失と損益通算したい場合、確定申告により税金を取り戻せるケースもあります。つまり、分配金の「いくら」に加えて「いくら残るか」を考えることで、より正確な収支シミュレーションが可能になります。
まとめ
REIT 分配金 いくら受け取れるのかを知るには、購入利回りと投資額を掛け合わせるだけで概算が得られます。ただし、物件収益や負債コスト、運営方針といった要素が変動すれば利回りも変わるため、平均利回り3.8%という数値を鵜呑みにせず、個別銘柄を丁寧に分析する姿勢が欠かせません。税引き後の手取りも忘れず計算し、NISAなどの優遇制度を活用しながら、自分に合ったリスクとリターンのバランスを見つけてください。
参考文献・出典
- 金融庁 統計情報 – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 一般社団法人投資信託協会 – https://www.toushin.or.jp
- 総務省 統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp
- 財務省 税制改正資料 2025年度版 – https://www.mof.go.jp

