家賃収入で安定したキャッシュフローを狙いつつ、税負担も軽くしたい――そんな思いから不動産投資に興味を持つ人が増えています。しかし、節税策には所得税から相続税まで多岐にわたり、それぞれ適用条件や効果が大きく異なります。本記事では、2025年9月時点で有効な制度だけに絞り、初心者でも理解しやすい形で「不動産投資×節税」のポイントと違いを解説します。読み進めることで、自分に合った節税戦略を描けるようになるはずです。
不動産投資と節税の基本を整理する
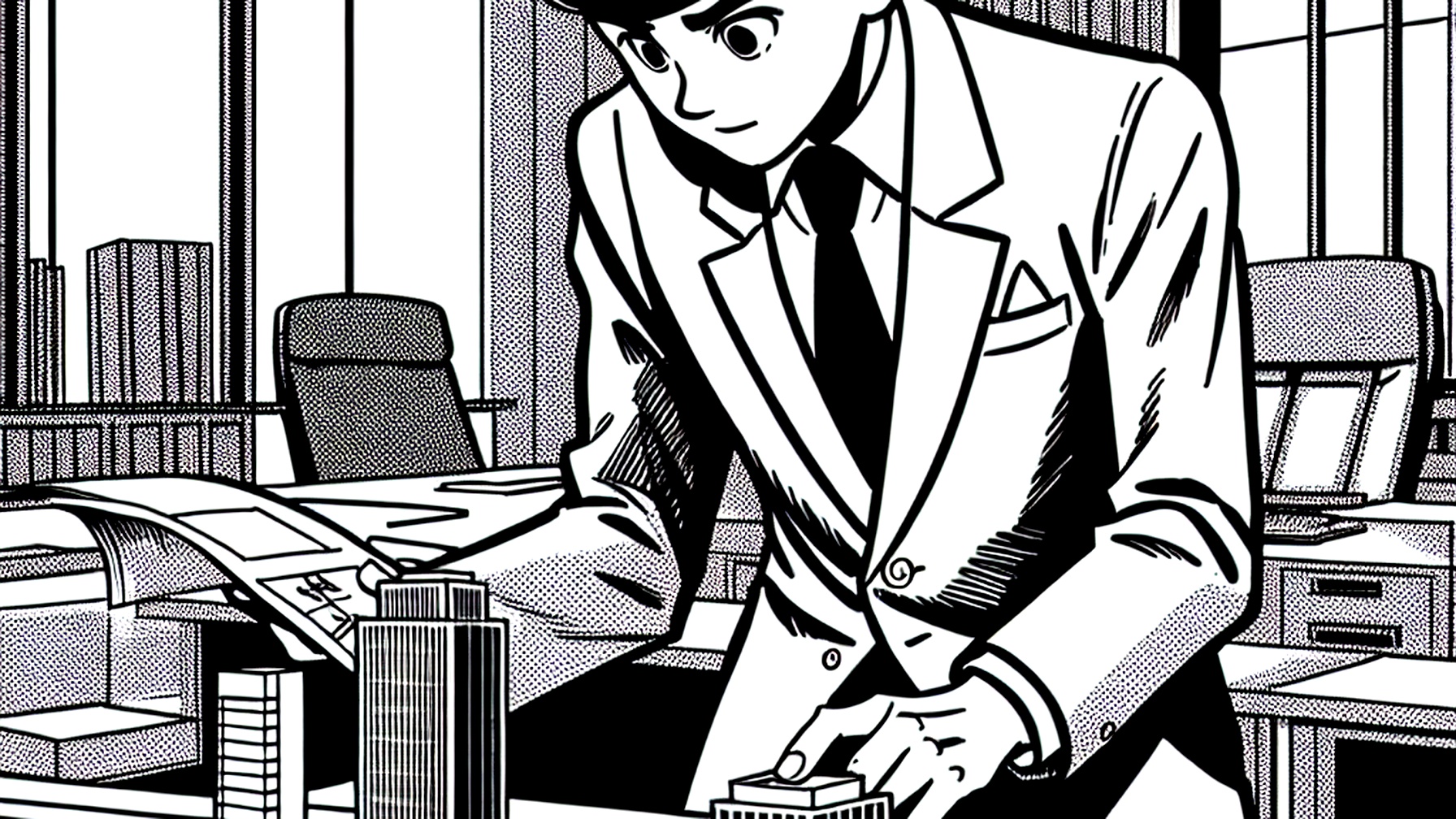
まず押さえておきたいのは、税金は“課税タイミング”によって種類が変わる点です。不動産購入時には不動産取得税、保有中は固定資産税・所得税、売却時には譲渡所得税が課されます。これらに加え、資産承継局面では相続税や贈与税も登場します。
国税庁の統計によれば、個人大家の9割超が所得税と住民税を合わせて年70万円以上支払っています。つまり、節税のインパクトが最も大きいのは保有期間中の所得課税です。実務では減価償却費の計上や青色申告特別控除を活用し、課税所得を圧縮する手法が王道といえます。
一方、相続税対策としては評価額を下げる効果を持つ賃貸用アパートの建築が代表的です。土地の相続税評価額は貸家建付地の補正によりおおむね2〜3割下がるため、現金で保有するより有利となります。ただし、将来の空室リスクや修繕費も増えるため、節税効果だけで判断しない姿勢が欠かせません。
所得税対策としての減価償却の威力
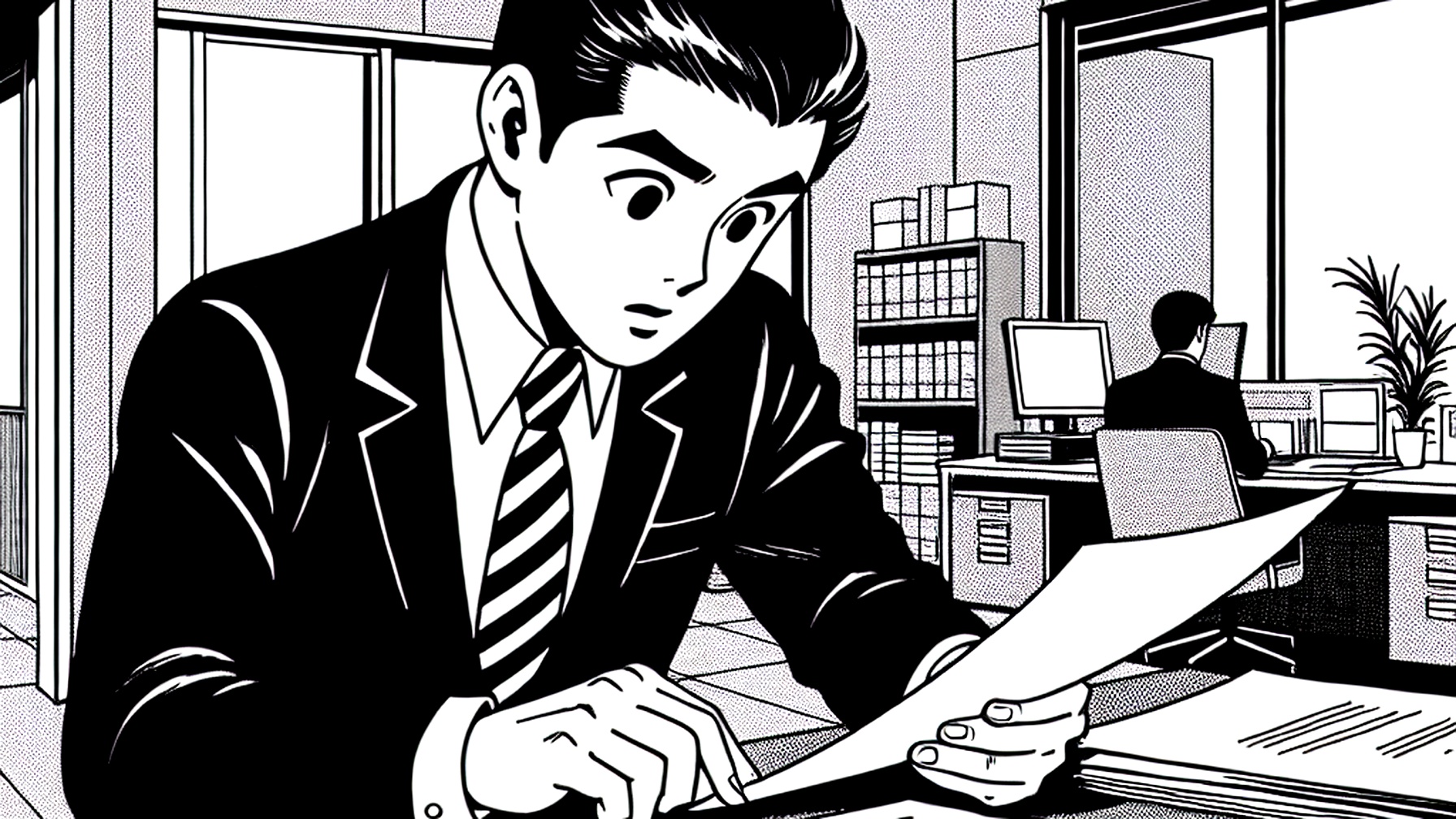
ポイントは、減価償却が“キャッシュを減らさずに経費を計上できる”仕組みだという点です。建物価格を法定耐用年数で均等配分して毎年費用化することで、課税所得を抑えられます。
たとえば鉄筋コンクリート造(RC)は耐用年数47年です。中古で築20年の物件を取得すると、残り耐用年数は27年ですが、国税庁通達により“短縮償却”が認められ、最短で9年まで圧縮可能です。実際、家賃収入500万円、経費100万円の物件でも、年間200万円程度の減価償却費を計上すれば所得税率20%の場合で40万円の税負担が削減できます。
ただし、償却が進んだ後は帳簿価額が下がり、将来売却時に譲渡所得が膨らむ可能性があります。いわゆる“出口税”を意識し、売却益を繰り延べるのか、計画的に繰り上げ返済して簿価を維持するのか判断が求められます。また、2025年度税制改正で創設された「高耐久リノベ特例」は、外壁・屋根に省エネ材を用いた場合に追加で10%の償却加速が認められますが、工事完了が2026年3月末までと期限付きです。適用を狙うなら早めの見積もりと着工が必須となります。
相続税・贈与税対策で見る保有形態の違い
実は、同じ物件でも所有形態によって相続税評価が大きく変わります。個人所有の場合、土地は「貸家建付地」、建物は「固定資産税評価額×70%」が基本です。一方、家族信託を活用すると、受益権分割により相続発生時点での遺産分割トラブルを回避しつつ、贈与税の基礎控除を年間110万円ずつ利用する“分割贈与”が可能です。
さらに、賃貸物件を持ち株会社に移す方法もあります。2025年度の「中小企業経営承継円滑化法」に基づき、事業承継税制を受ければ自社株評価額の最大80%が納税猶予となり、10年後の雇用要件を満たせば全額免除が視野に入ります。ただし、賃貸業は“みなし事業”と判定されるため、事前に税理士と適格性を確認しておく必要があります。
相続開始後は3年以内の物納や延納が検討できますが、賃貸物件は流動性が高くないため、まとまった納税資金を用意しておくのが現実的です。あくまで“生前対策が主戦場”と心得て、早くから土地活用や持ち株会社の設計を進めましょう。
法人化と個人投資の税務メリットを比較する
重要なのは、法人化が万能ではないという事実です。法人税率は所得800万円以下で15%、800万円超で23.2%(2025年度)と、累進課税の個人より低く見えます。しかし法人でも社会保険料の負担が重く、経理や決算報告のコストも加わります。
たとえば家賃収入1,200万円、経費と償却で600万円の利益を想定すると、個人の最高税率33%なら約200万円、法人の実効税率23.2%なら約139万円と差は61万円です。ただし、役員報酬を支給すると法人所得が下がり、個人に所得税が発生するため、シミュレーション次第で実効税率は逆転することもあります。
また、赤字の損失繰越期間は法人が10年、個人は3年です。新築RCの大型投資で初期赤字が大きい場合は法人化が有利ですが、中古の小規模物件をコツコツ買い進めるスタイルなら個人課税でも十分にコントロールできます。法人化は“規模拡大フェーズ”で検討するのが現実的でしょう。
2025年度制度を踏まえた実践ステップ
まずやるべきは、青色申告による65万円控除の確実な取得です。帳簿の電子化が要件となりますが、クラウド会計ソフトの普及で運用コストは大幅に下がりました。次に、建物と設備を分けて購入する“区分評価”を行い、短期で償却できる設備費用を増やすことで初年度からキャッシュフローを高めます。
さらに、2025年度から新設された「住宅用太陽光売電収入の課税特例」にも注目です。賃貸住宅の屋根に太陽光パネルを設置し、売電収入が家賃の10%を超えない場合は事業所得に合算できます。固定価格買取制度は2035年まで続く見込みで、長期的な収益源として検討価値が高いと言えます。
最後に、出口戦略としての“買い替え特例”も計画に組み込みましょう。不動産を譲渡し、1年以内に一定条件を満たす物件に買い替えた場合、譲渡所得税を繰り延べできます。物件の収益性が低下したタイミングで、耐用年数が長い新築へリレー投資することで、節税とポートフォリオ再構築を同時に実現できます。
まとめ
この記事では、不動産投資における節税策の違いを所得税、相続税、法人化という切り口で整理しました。減価償却や青色申告は今日からでも取り組める基本戦略であり、相続や法人化は長期計画が欠かせません。まずは自分の投資規模と将来のライフプランを見据え、税理士や金融機関と連携しながらシミュレーションを重ねましょう。賢く節税しつつ堅実なキャッシュフローを築くことで、不動産投資の魅力を最大限に引き出せるはずです。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 金融モニタリングレポート2025 – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025年4月 – https://www.boj.or.jp

