不動産投資に興味はあるものの、「本当に儲かるのか」「リスクが怖い」と迷っている方は多いはずです。確かに物件価格の高騰や空室リスクなど不安要素はありますが、正しい知識と準備があれば安定した収益を得ることは十分可能です。本記事ではデメリットを具体的に示しつつ、初心者でも実行できる儲け方を最新データとともに解説します。読み終えたとき、あなたは自分に合った投資判断ができるようになるでしょう。
不動産投資は本当に儲かるのか
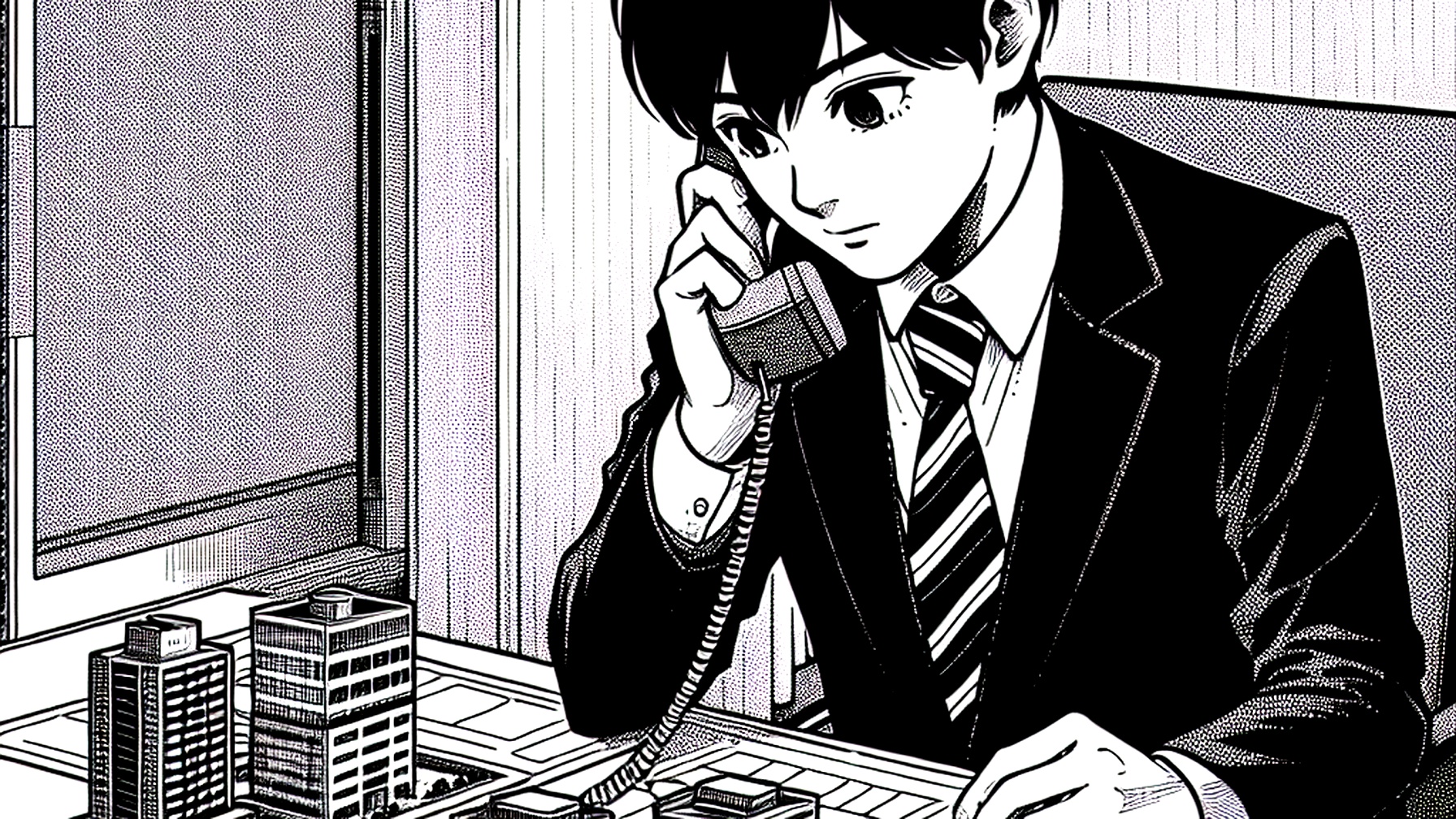
まず押さえておきたいのは、不動産投資の収益構造が家賃収入と売却益の二本柱で成り立つ点です。国土交通省の「不動産市場動向調査2025」によると、主要都市の住宅平均利回りは4〜5%で推移しており、低金利が続く中では相対的に魅力的といえます。さらに日本政策金融公庫の統計では、自己資金3割・固定金利1.5%で借入した場合、キャッシュフローは年間30〜50万円の黒字になるケースが多いと示されています。
一方で、利回りだけで「儲かるか否か」を判断すると落とし穴にはまります。購入時の諸費用、継続的な修繕費、そして空室期間の収入減を含めたシミュレーションを行わなければ、実際の手取りは期待を下回るからです。つまり収益を伸ばすには、運営コストをいかに抑えつつ入居率を高めるかが鍵になります。
実は物件価格が高い都市部でも、需要の底堅さから長期的に見ると家賃下落は緩やかです。反対に郊外はいま手頃に購入できますが、将来の人口減少が空室率に直結するおそれがあります。目的とリスク許容度を明確にし、表面利回りだけでなく10年後の賃貸需要を読み解くことが、最終的な「儲かる」に直結します。
見落としがちなデメリット
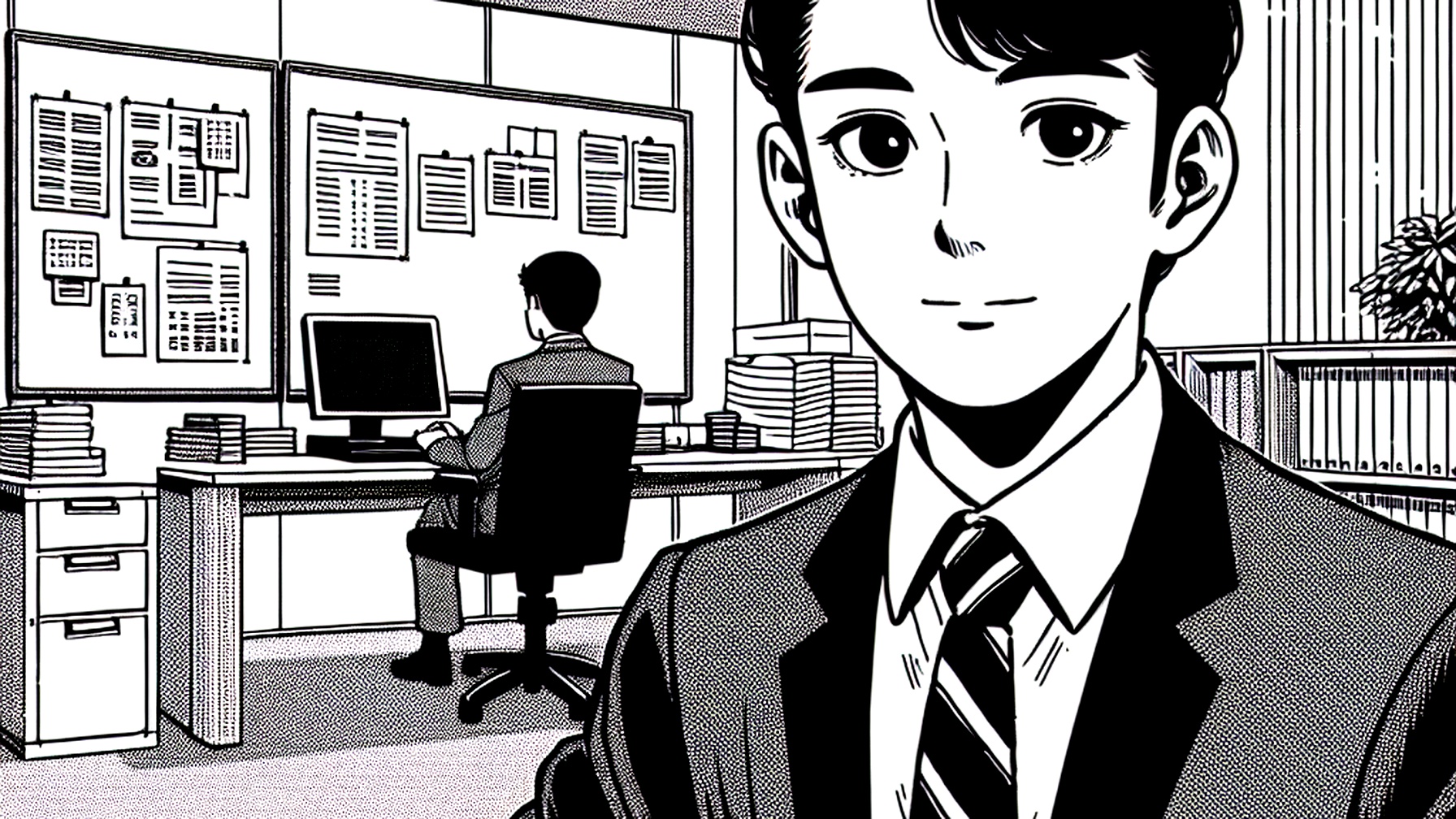
重要なのは、華やかな成功談の裏に潜むデメリットを正しく把握することです。代表的なのは空室リスク、金利上昇、修繕コストの三つですが、実務では退去時の原状回復や賃借人トラブルといった細かな費用も無視できません。家賃が一年間入らないだけで、想定利回りは簡単にマイナスへ転落します。
さらに2025年に入り、建築資材価格は2020年比で約20%上昇しました。国土交通省の資材統計が示す通り、今後も高止まりが続く見通しのため、大規模修繕のタイミングが重なるとキャッシュフローは大きく圧迫されます。また、金融庁「2025年金融レポート」は変動金利の底打ちを示唆しており、1%の金利上昇で返済額は月々数万円増える例も少なくありません。
加えて、税務上の注意点もあります。減価償却を過度に計上して赤字を作り、給与所得と損益通算する手法は今も認められていますが、国税庁は2025年度から不自然な高額修繕を重点的に調査すると公表しています。節税メリットに頼りすぎると、追徴課税のリスクを抱える点は覚えておきましょう。
最後に心理的な負担です。賃借人からの深夜連絡やクレーム対応を自主管理で行うと、時間と精神を奪われやすいのが現実です。管理会社を入れると手数料が発生しますが、負担とコストのバランスを見極めることが、長く投資を続けるうえで欠かせません。
デメリットを抑えつつ儲ける仕組み
ポイントは、リスクを価格に織り込みながら運営効率を高めることです。その第一歩として、有力エリアの築古物件をリノベーションし、家賃を維持しつつ表面利回りを底上げする戦略があります。総務省「住宅・土地統計調査」によれば、築30年以上のマンションでも駅徒歩10分以内なら入居率は90%を超えています。購入価格が割安な分、多少の修繕費をかけても投資回収期間を短くできるのが利点です。
また、サブリース契約の安易な利用は避けるべきですが、短期的にキャッシュフローを安定させたい場合は2〜3年の限定的な家賃保証を活用し、空室リスクを初期に集中させない方法も有効です。家賃相場を把握し、保証賃料が市場より大幅に低くないか確認することが前提となります。
資金調達では、地方銀行や信用金庫が提供する「投資用アパートローン」で固定金利を選択すると、金利上昇局面でも支出を読めます。日本銀行が2025年4月にマイナス金利を解除したあとも、地域金融機関では1.3〜1.8%台の固定型が残っています。借入期間を20年以内に抑え、元金返済を早めることで、将来売却時の残債を圧縮しやすくなる点も見逃せません。
さらに、IT活用で管理コストを削減する動きが広がっています。クラウド型の入居申込システムやスマートロックを導入すると、内見から契約まで非対面化でき、管理会社の手数料を年3〜5%削減した事例もあります。こうした小さな改善を積み重ねることで、デメリットを利益に変える循環が生まれます。
2025年度の制度と税制で押さえるポイント
実は制度を味方に付けるだけで、年間数十万円の手取り差が生じます。2025年度も継続する代表的な措置として、賃貸用の新築住宅に対する固定資産税の軽減があります。具体的には、床面積40〜280㎡の住居用部分について、建物分の税額が3年間1/2となる制度で、自治体へ6月30日までに申請すれば適用されます。新築RCマンションを検討している場合、この軽減分を実質利回りに上乗せして試算すると収益性が見えやすくなります。
また、不動産所得で青色申告を行うと65万円の特別控除が得られます。電子申告と電子帳簿保存を満たせば最大55万円の控除が2025年度も継続し、さらに10万円控除が上乗せされます。クラウド会計ソフトを使えば帳簿作成は難しくなく、結果として実効税率を数%下げる効果が期待できます。
減価償却については、木造アパートで耐用年数22年を超えた物件を取得した場合、4年間で一気に償却できる定額法の特例が引き続き利用可能です。高年収層がキャッシュフローより節税効果を狙う際、この特例は大きな魅力になりますが、その後の帳簿価額が小さくなるため売却益に課税しやすくなる点には注意が必要です。
国土交通省が推進する「賃貸住宅管理業法」も2025年度で4年目に入り、サブリース業者の業務適正化が進んでいます。登録業者であれば、契約前に将来家賃の下落リスクを説明する義務があるため、初心者が情報格差で不利になる場面は減りつつあります。制度を正しく理解し、公的なルールを逆手に取る発想が、デメリットを最小化しつつ儲かる道を開くのです。
成功に近づく情報収集と行動習慣
まず重要なのは、数字に強くなることです。利回りやキャッシュフローといった基本指標に、融資条件と税金を加えた「手取りベース」の収支表を自分で作れるようになると、物件選びのスピードと精度が格段に上がります。難しい関数は不要で、家賃、空室率、金利、修繕費を変数にしたシミュレーションをエクセルで組むだけでも大半の判断材料がそろいます。
さらに、月に一度は現地へ足を運びましょう。オンライン資料では分からない駅前の再開発や競合物件の内装レベルを、自分の目で確認する習慣が差別化につながります。日本不動産研究所の調査では、現地確認を必ず行う投資家は、行わない層に比べ平均入居率が5ポイント高い結果が出ています。
人脈づくりも欠かせません。信頼できる不動産仲介、管理会社、税理士の三者がそろうと、トラブル時の対応スピードが一気に向上します。2025年は全国各地で不動産投資家向けの交流会が活発化しており、SNSやオンラインサロンを通じて地方在住でも専門家とつながれる環境が整いました。つまり、知識とネットワークを同時に育てることで、デメリットは情報優位でカバーできるわけです。
最後に、出口戦略を最初に決める姿勢を持ちましょう。5年後に売却利益を狙うのか、20年以上家賃を積み上げるのかで、立地や融資期間は変わります。出口が決まれば、途中の意思決定にブレが少なくなり、物件ごとの「儲かるかどうか」を冷静に判断できます。行き当たりばったりの購入を避け、長期視点での数字と行動を一致させることが、成功への近道です。
まとめ
ここまで、不動産投資は「デメリット 不動産投資 儲かる」という三つのキーワードを軸に、リスクと利益のバランスを立体的に解説しました。空室や金利上昇といった弱点を理解し、制度やITで補えば、安定収益を目指すことは十分可能です。まずは手取りベースの収支を作成し、信頼できる専門家とのネットワークを築くことから始めてみてください。行動を積み重ねた先に、あなた自身の理想的なキャッシュフローが待っています。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向調査2025 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 所得税法 青色申告特別控除の手引き(2025年度) – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 2025年金融レポート – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 金融経済統計レビュー2025 – https://www.boj.or.jp
- 日本政策金融公庫 生活衛生関係調査 不動産賃貸業編 – https://www.jfc.go.jp

