不動産投資に興味はあるものの、「収益物件は本当に利益を生むのか」と疑問を抱く方は多いはずです。自己資金やローン返済、空室リスクなど不安要素は尽きません。しかし、仕組みを理解し、数字を正しく読めれば、安定したキャッシュフローを実現できます。本記事では2025年10月時点の最新データを踏まえ、収益物件の魅力と落とし穴を初心者でも分かるように解説します。最後まで読めば、物件選びから資金計画、税制優遇まで一通りの判断材料がそろい、行動に移す自信が得られるでしょう。
収益物件は本当に儲かるのか?
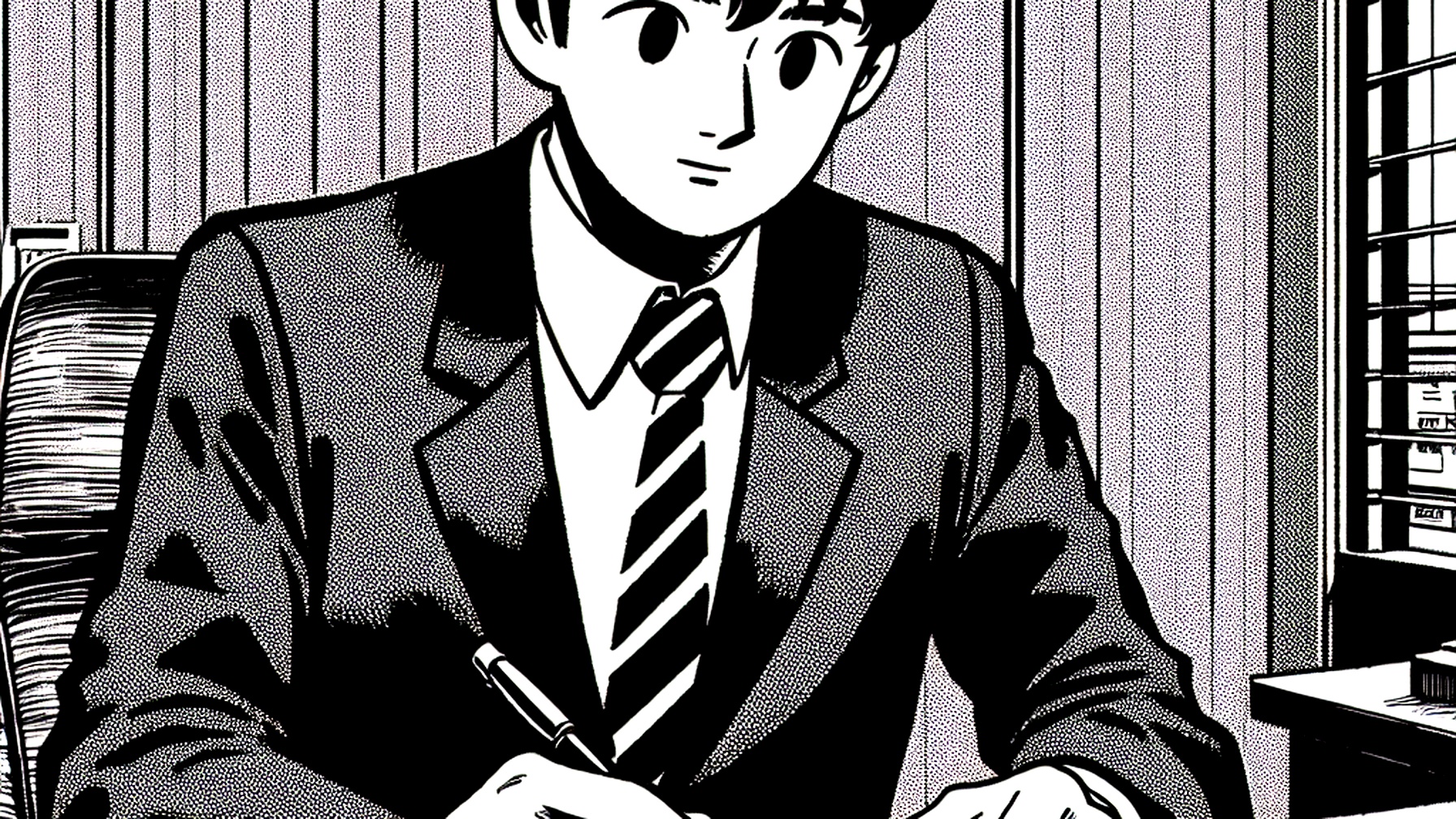
ポイントは、家賃収入がローン返済と経費を上回るかどうかという単純な構図を具体的な数字で把握することです。
まず、総務省の住宅・土地統計調査2023によると、全国の賃貸住宅平均空室率は13.1%でした。都心部は7%前後にとどまるものの、地方郊外では20%を超える地域も珍しくありません。この差が収益物件の成否を左右します。家賃10万円、空室率7%の物件なら実効家賃は月9万3千円です。一方で管理費、修繕積立、固定資産税などを合算すると年間家賃収入の15〜20%が経費に消えます。つまり利回りだけを見ても実態は分からず、現金の出入りを示すキャッシュフローで判断する必要があります。
実は、地方高利回り物件に飛びついて失敗する例が後を絶ちません。利回り12%と聞くと魅力的ですが、空室率が30%に達すれば実質利回りは一気に8%へ下落します。それでも表面利回りしか見ない投資家が多いのが現状です。結論として、収益物件が「儲かるかどうか」は数字の読み取り方しだいで大きく変わります。
キャッシュフローを見抜く計算のコツ
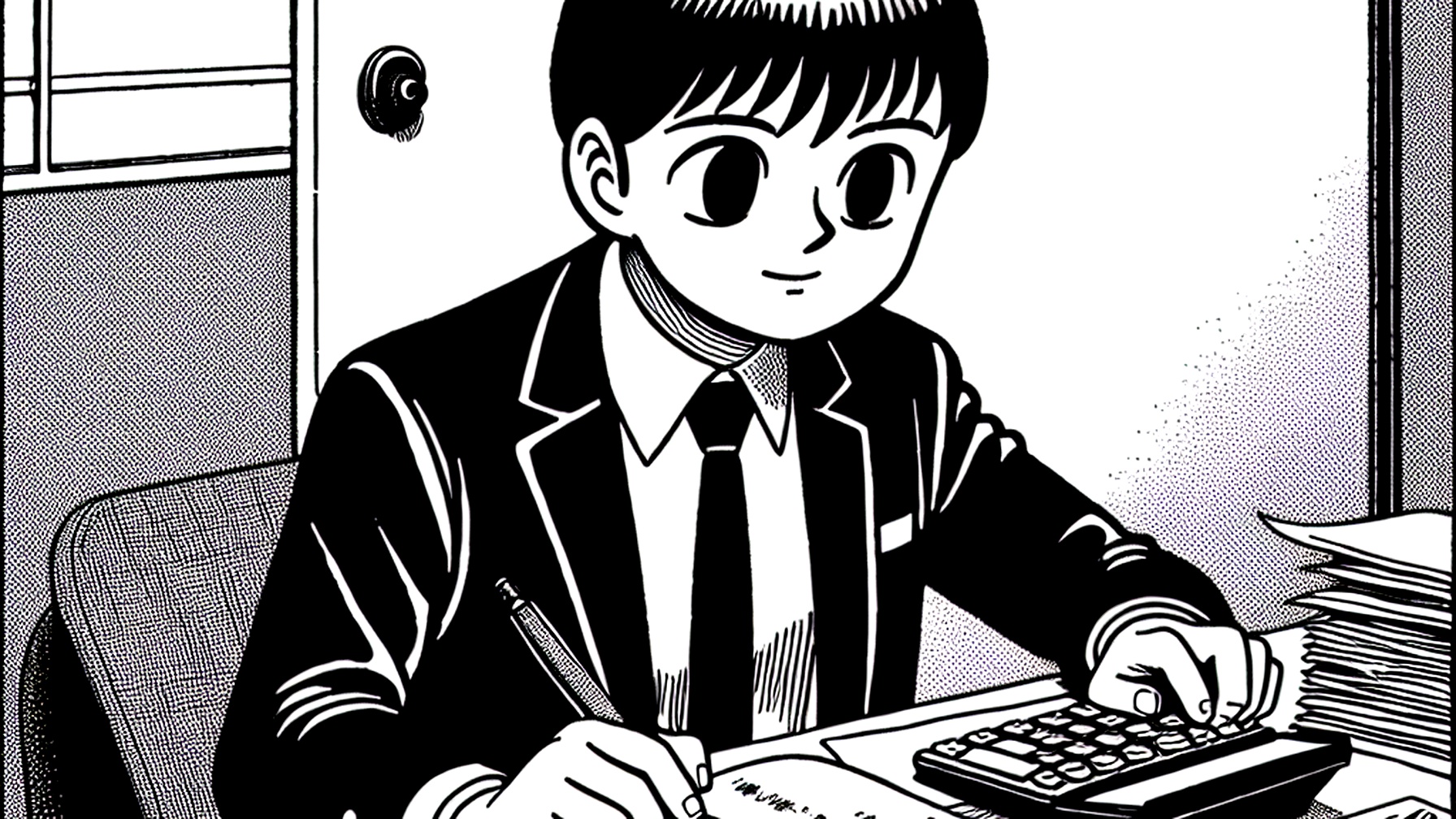
重要なのは、購入前に「年間収支表」を作り、最悪シナリオでも赤字転落しないか確認することです。
まず押さえておきたいのは、ローンの元利均等返済では元金と利息の比率が毎月変わる点です。元金は経費にならないため、手元キャッシュを圧迫します。金利1.8%、期間25年、借入額3,000万円のケースでは、初年度返済額は年間146万円で、そのうち利息は52万円しか経費計上できません。家賃年収が360万円の場合、経費・減価償却を差し引き、手残りキャッシュが100万円を切ることもあります。
一方で、減価償却費は実際の支出を伴わない経費です。木造なら法定耐用年数22年、RC造(鉄筋コンクリート)は47年ですが、中古で購入すれば簡便法により耐用年数を短縮でき、経費額が増えることがあります。これにより税負担を抑え、キャッシュフローを厚くできるため、物件選びでは築年数も大きな判断材料になります。
金融機関選びも忘れがちな要素です。2025年10月時点で地方銀行の投資用ローン金利は年1.5〜3.0%が中心帯ですが、期間を短くすると金利が下がることがあります。反対に期間を伸ばせば月々の返済は減るものの、総返済額は膨らみます。つまり、自身の資金繰り計画とリスク許容度に応じて、金利と期間のバランスを設計することが鍵となります。
成功例と失敗例から学ぶリスク管理
実は、成功と失敗を分けるのは初期のリサーチ精度にほかなりません。
成功例として、東京都23区内で築35年のRCマンション一棟を購入したAさんは、購入前に半径500メートルの賃料相場、人口動態、再開発計画を徹底的に調査しました。結果として平均家賃を2%上乗せしても満室を維持でき、購入4年目の今も空室率はゼロです。Aさんは修繕費用を家賃の5%ずつ積み立て、急な設備交換にも慌てず対応しています。
一方で失敗例となったBさんは、表面利回り15%の地方アパートをネット情報だけで契約しました。取得後すぐに空室が増え、入居者獲得のため家賃を20%下げても埋まらず、利回りは8%まで低下しました。空室が続くと建物は荒れ、さらなる空室を呼ぶ悪循環に陥ったのです。ここから学べるのは「人口減少エリア」「管理の手抜き」「家賃下落」は三位一体でリスクを引き上げるという点です。
つまり、リスク管理とは購入時点で終わる話ではなく、運用開始後も継続的にデータをチェックし、必要なら売却やリフォームを迅速に判断する姿勢にかかっています。
2025年度の税制優遇と融資環境
まず押さえておきたいのは、2025年度も不動産所得に対する青色申告特別控除65万円が継続していることです。複式簿記と電子申告を行えば適用でき、実効税率を大きく下げられます。国税庁のモデルケースでは、課税所得500万円の個人が控除をフル活用すると所得税と住民税が約15万円減少します。
一方で、租税特別措置法の「中小企業経営強化税制」は2025年3月末で一部終了しましたが、不動産賃貸業のうち法人化した場合、設備投資額の即時償却対象になる機器が限定的ながら残っています。法人化を検討する際は税理士に最新リストを確認することが欠かせません。
融資環境に目を向けると、日本銀行は2024年春にマイナス金利政策を解除しましたが、2025年10月現在でも長期金利は1%台前半で推移しています。政府系金融機関である日本政策金融公庫は、自己居住を伴わない賃貸用物件への直接融資を行わないものの、区分マンションなど小規模物件なら民間銀行が前向きなケースも増えています。これにより、物件価格が2,000万円以下でもフルローンが可能な事例が見られるようになりました。
安定運用のために今すぐできること
まず、既に物件を探し始めている人は「一次情報」に触れる習慣を持ちましょう。自治体の都市計画図や人口推計、大学の移転計画などは無料で公開されています。机上で利回りを計算する前に、地域の将来像を把握すれば空室リスクを大幅に下げられます。
さらに、管理会社選びはキャッシュフロー改善の近道です。同じ物件でも入居付けのスピードは会社により大きく変わります。家賃の5%という管理料だけに目を奪われず、募集力やトラブル対応の質を重視してください。実際、国土交通省の賃貸住宅管理業者登録簿によると、登録業者は2025年時点で約5,800社あり、サービス内容は千差万別です。
最後に、手元資金の3〜6か月分を運営予備費として確保することを推奨します。屋上防水や給排水管の交換など大規模修繕が重なると、1室あたり50万円以上の費用が発生することもあります。予備費があれば、急な出費でも借入れに頼らず迅速に対応でき、入居者満足度を落とさずに済みます。
まとめ
ここまで、収益物件が「本当に」利益を生むための条件を数字と事例で見てきました。空室率や経費を加味したキャッシュフロー計算、徹底したエリア調査、税制優遇の活用、管理体制の強化がそろって初めて安定収益が生まれます。裏を返せば、この一連のプロセスを丁寧に実行すれば、初心者でも堅実な不動産投資が可能です。まずは小さく試算し、一次情報を確認しながら行動に移してみてください。知識と準備があなたの不安を自信へと変えてくれるはずです。
参考文献・出典
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
- 国土交通省 賃貸住宅管理業者登録簿 2025年度版 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨 2025年9月 – https://www.boj.or.jp/
- 国税庁 青色申告特別控除の手引き(令和7年版) – https://www.nta.go.jp/
- 中小企業庁 税制優遇制度一覧 2025年度 – https://www.chusho.meti.go.jp/

