預金金利が上がらない一方、物価だけがじわりと上昇する状況に焦りを感じていませんか。とはいえ、マンションを丸ごと購入するような本格的な不動産投資は、資金面でも知識面でもハードルが高いものです。そこで注目されているのが、証券取引所で手軽に売買できる不動産投資信託=REIT(リート)です。本記事では「誰が REIT 始め方」に焦点を当て、向いている人の特徴から購入ステップ、2025年度に活用できる税制メリットまでを整理します。読み終えたときには、あなたが次に取るべき具体的な一歩が見えているはずです。
REITとは何か、株式との違い
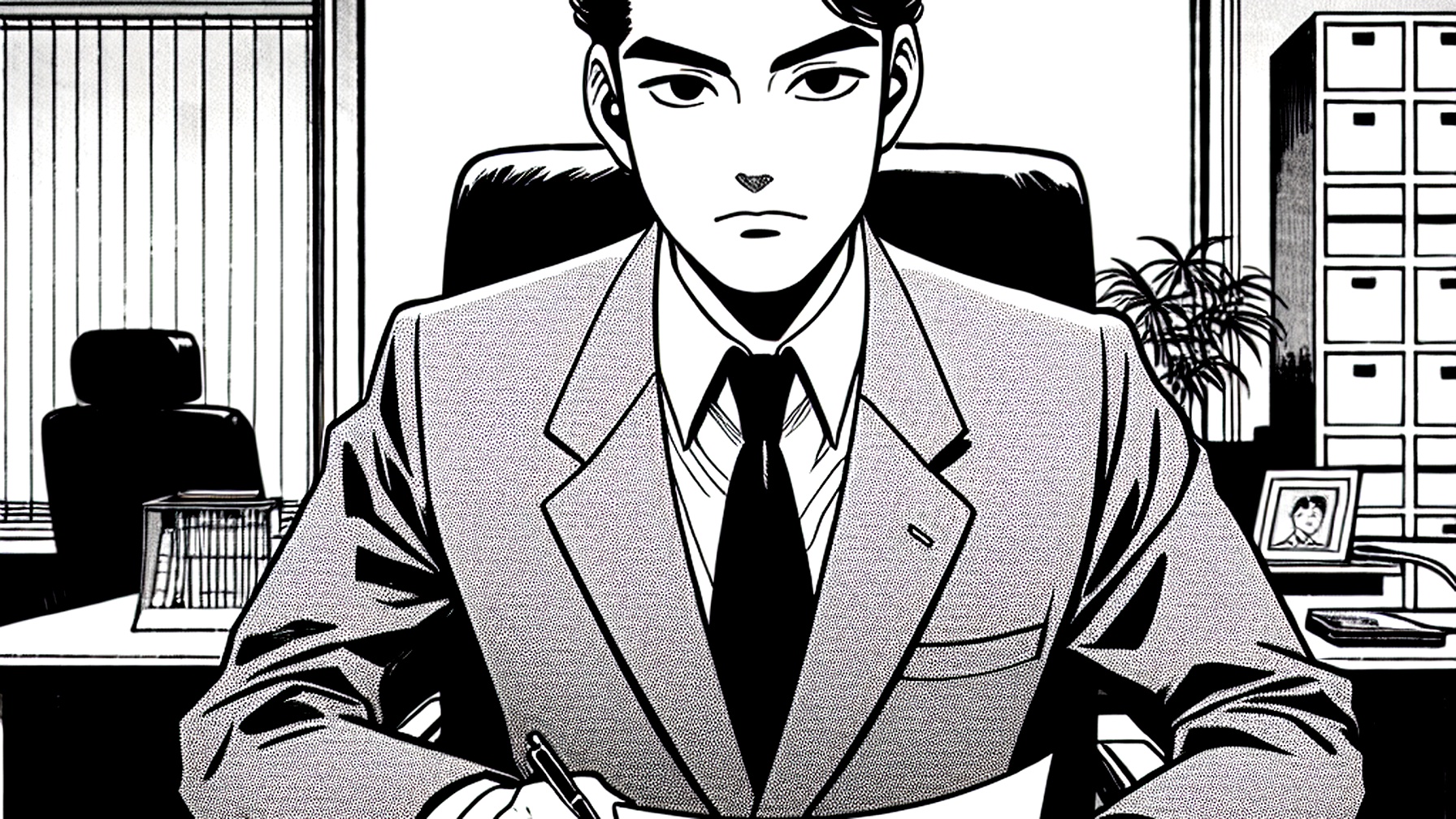
重要なのは、REITが不動産を裏付け資産とする投資信託でありながら、株式と同じように市場で売買できる点です。投資家はオフィスビルや商業施設、物流センターなど複数の物件に間接的に投資し、賃料収入や物件売却益を分配金として受け取ります。
まず株式との共通点を挙げると、価格は需給で動き、証券会社の口座さえあれば誰でも1口から売買できることです。取引時間も東証の立会時間に準じ、指値・成行など注文方法も株と同じなので、ネット証券の操作に慣れている人ならすぐ始められます。
一方で決定的に違うのは、収益源が「企業の利益」ではなく「不動産からのキャッシュフロー」だという点です。上場REITの分配金利回りは2025年10月時点で平均3.7%前後(日本取引所グループ統計)と、東証プライム全体の配当利回り約2.5%を上回ります。つまり安定収入を重視する投資家には、株式よりREITが魅力的となる局面が多いわけです。
さらに法制度上、J-REIT(日本版REIT)は利益の90%以上を分配すれば法人税が実質的に免除されます。そのため内部留保が少なく、配当性向が高い状態が維持されやすいというメリットがあります。ただし内部留保が少ない分、物件入替え時に追加増資を行うケースもあり、株式とは異なる希薄化リスクを理解する必要があります。
初心者でも買える理由と向いている人
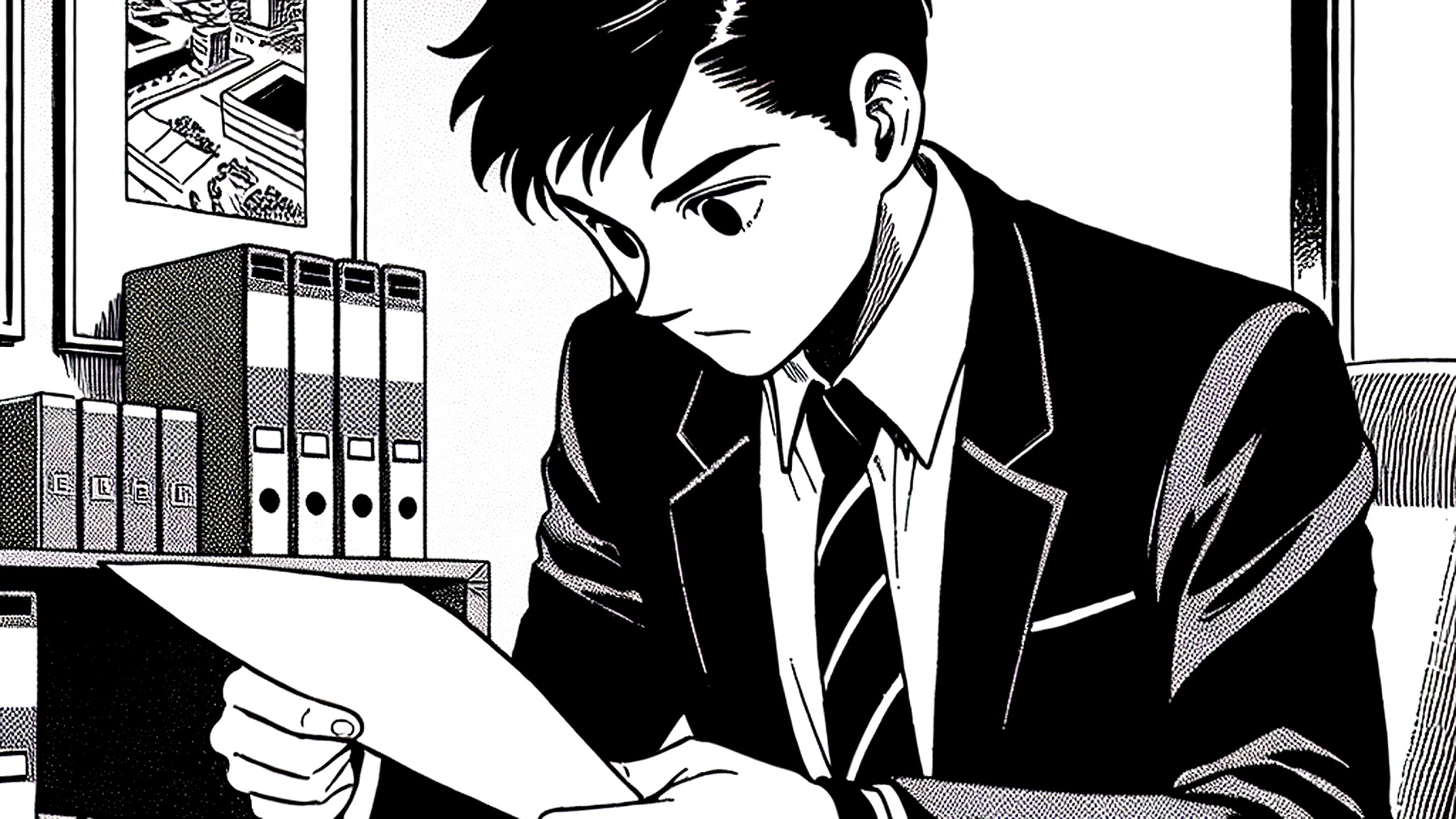
ポイントは、REITが「小口投資」であると同時に「上場商品」であることです。1口5万円前後で買える銘柄も多く、少額から分散投資を組めるため、初期費用の重さに悩む不動産投資初心者に適しています。
まず、短期的な値上がり益よりインカムゲイン(分配金)を重視する人には向いていると言えます。実は、REITの価格変動は株式よりも低い傾向があり、ボラティリティ(価格の振れ幅)は同期間のTOPIXより1〜1.5割ほど低いというデータもあります(資産運用研究所調べ)。つまり値動きで精神的に消耗しにくいのです。
また、本業が忙しく物件管理に手を割けない人にも最適です。REITの運用は専門の不動産運用会社が行い、テナント募集や修繕計画、家賃交渉まで代行します。投資家は四半期ごとに運用報告書を確認し、必要に応じて銘柄を入れ替えるだけで済みます。
一方で、レバレッジを効かせた「一発逆転」を狙いたい人や、物件を自分で選び細部にこだわりたい人には物足りなさが残るかもしれません。誰が REIT 始め方を学ぶべきかと言えば、時間・資金・知識の3つを効率的に使いたい幅広い層だとまとめられます。
口座開設から購入までのステップ
まず押さえておきたいのは、株式と同じ証券総合口座で取引できるため、特別な手続きは不要だということです。ネット証券を未開設の場合でも、本人確認書類をオンライン提出すれば最短翌営業日には取引が可能になります。
実際の流れは次のとおりです。
- 証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選択して開設
- 入金後、取引ツールで「REIT」や「コード番号(例:8951)」を検索
- 1口単位で指値または成行注文を発注
- 約定後は保有口数に応じて分配金権利日を待つだけ
ここで重要なのは、最初から複数銘柄を組み合わせることです。オフィス特化型だけに偏ると、景気後退で空室率が上がった際に打撃を受けやすくなります。物流系や住宅系、さらには海外REIT ETFも加えることで、景気サイクルが異なるセクターに分散でき、分配金の安定性が高まります。
また、スマホアプリでは「定期買付サービス」が普及し、毎月同じ金額を自動で積み立てる設定も可能です。ドルコスト平均法を活用すれば、価格変動リスクを平準化しながら口数を増やせます。
2025年度の税制と手数料を押さえる
実は、税金と手数料のコストを把握していないと、いくら高利回りでも手取りが減りかねません。2025年度時点でREITの譲渡益・分配金にかかる税率は、上場株式と同じく20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。証券会社の特定口座を利用すれば、確定申告なしで源泉徴収が完結します。
さらに活用したいのが2024年に刷新された新NISA制度です。成長投資枠では上場株式やJ-REITが非課税対象となり、年間240万円、非課税保有限度額1,800万円の範囲内で取引できます。非課税期間は無期限となったため、分配金をまるごと受け取れるメリットが大きいのです。20年の従来NISAや5年の一般NISAと比べ、長期投資と相性が良い点を押さえておきましょう。
手数料については、売買手数料が無料化されるネット証券が増えていますが、REIT ETFなど一部商品では信託報酬が別途かかります。例えば東証REIT指数連動型ETFの信託報酬は年0.155%程度と低水準ですが、長期保有ではじわじわ効いてきます。コストを抑えるには、銘柄選定時に信託報酬を比較し、同じ指数連動でも最も低コストの商品を選ぶことが大切です。
リスク管理とポートフォリオの組み方
まず押さえておきたいのは、REITも株式同様、市場価格が毎日変動するという事実です。つまり高利回りだからと集中投資をすると、金利上昇や天災で物件価値が下がった際にポートフォリオ全体が揺らぎます。
一方で、REITには現物不動産投資では取りにくい市場リスクが存在します。例えば2023年の米国金利急上昇時には、国内REITでも借入コスト上昇懸念から価格が一時的に10%以上下落しました。こうした環境変化に備えるには、物件用途の分散だけでなく、為替影響の少ない国内銘柄と外貨建て海外REIT ETFを組み合わせるのが有効です。
また、キャッシュポジションを持つことも立派なリスク管理策です。分配金が入るたびに全額再投資せず、数割を待機資金として残しておけば、相場急落時に安値で買い増しできる“弾”になります。
最後に、定期的なリバランスが欠かせません。資産配分は時間とともに歪みます。半年から1年に一度、当初の目標比率(例:REIT30%、株式50%、債券20%)に戻す作業を行うことで、リスクとリターンのバランスを維持できます。いわば“資産の健康診断”を欠かさないことが、長期投資で成果を残すコツです。
まとめ
配当利回りが物価上昇率を上回り、少額から分散投資が可能なREITは、忙しいビジネスパーソンにとって心強い資産運用ツールです。株式と同じ証券口座で取引でき、新NISAを利用すれば分配金に税金がかかりません。物件用途や地域の分散、定期的なリバランスを徹底すれば、価格変動リスクを抑えながら安定収益を積み上げられます。まずは口座開設と銘柄研究を進めて、次の分配金権利日に間に合うよう準備を始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp/
- 資産運用研究所 – https://www.soken.ne.jp/
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省 不動産市場動向 – https://www.mlit.go.jp/

