不動産を売却して「手取りで1000万円を確保したい」と考える人は少なくありません。とはいえ、売買価格がそのまま手元に残るわけではなく、仲介手数料や税金を差し引いた後の金額が思ったより少ないと感じるケースが多いです。本記事では、売却前に押さえるべき費用構造を整理し、譲渡所得税の仕組みや値付けの戦略をわかりやすく解説します。さらに、2025年度時点で利用できる控除制度やローン残債との調整方法にも触れ、結果として手取り1000万円を確実に手にするための具体的なステップを提示します。
売却額と手取りの違いを正しく理解する
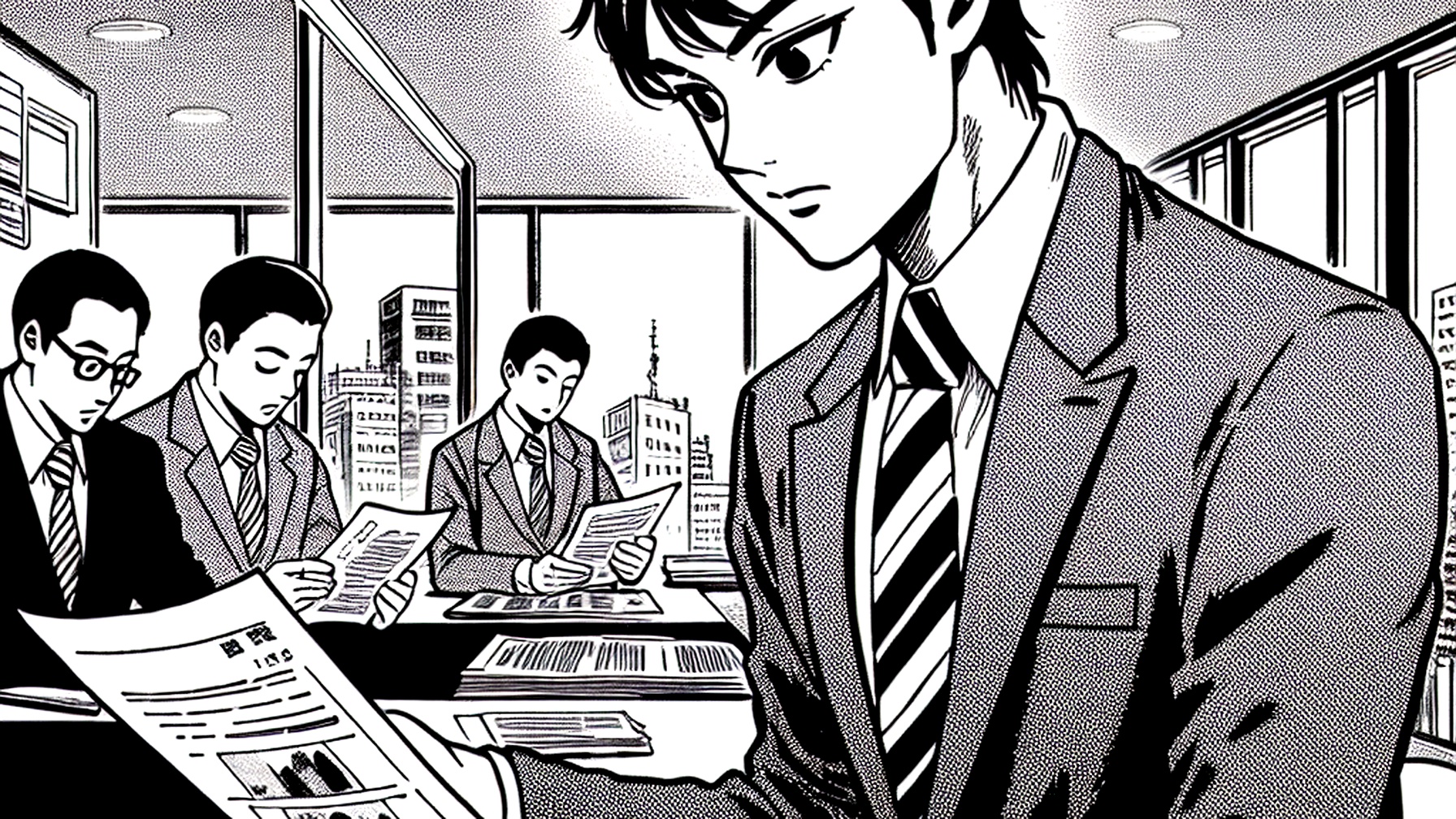
まず押さえておきたいのは、売却額と手取り額のギャップが生じる仕組みです。売買契約で合意した価格から諸費用を差し引くと、実際に受け取れる金額は大きく変わります。
仲介手数料は法律上、売却価格の3%+6万円に消費税を加えた額が上限です。たとえば5000万円で売れると約171万円が必要になり、手取りに確実に影響します。また、司法書士への登記費用や抵当権抹消費用も数万円単位で発生します。さらに、ローン残債がある場合は決済時に金融機関へ一括返済するため、残債額が手取りから差し引かれる点も見落とせません。
こうした諸費用をすべて一覧化し、売却前に収支シミュレーションを作成することが重要です。国土交通省の「不動産価格指数」によると、2025年は首都圏中古マンションの平均単価が前年より2.8%上昇しましたが、費用構造は変わらないため、上昇分をそのまま利益と考えるのは危険です。事前の試算で赤字を防ぎ、最終的に「売却 1000万円」の目標をブレずに追求しましょう。
譲渡所得税と控除制度のポイント
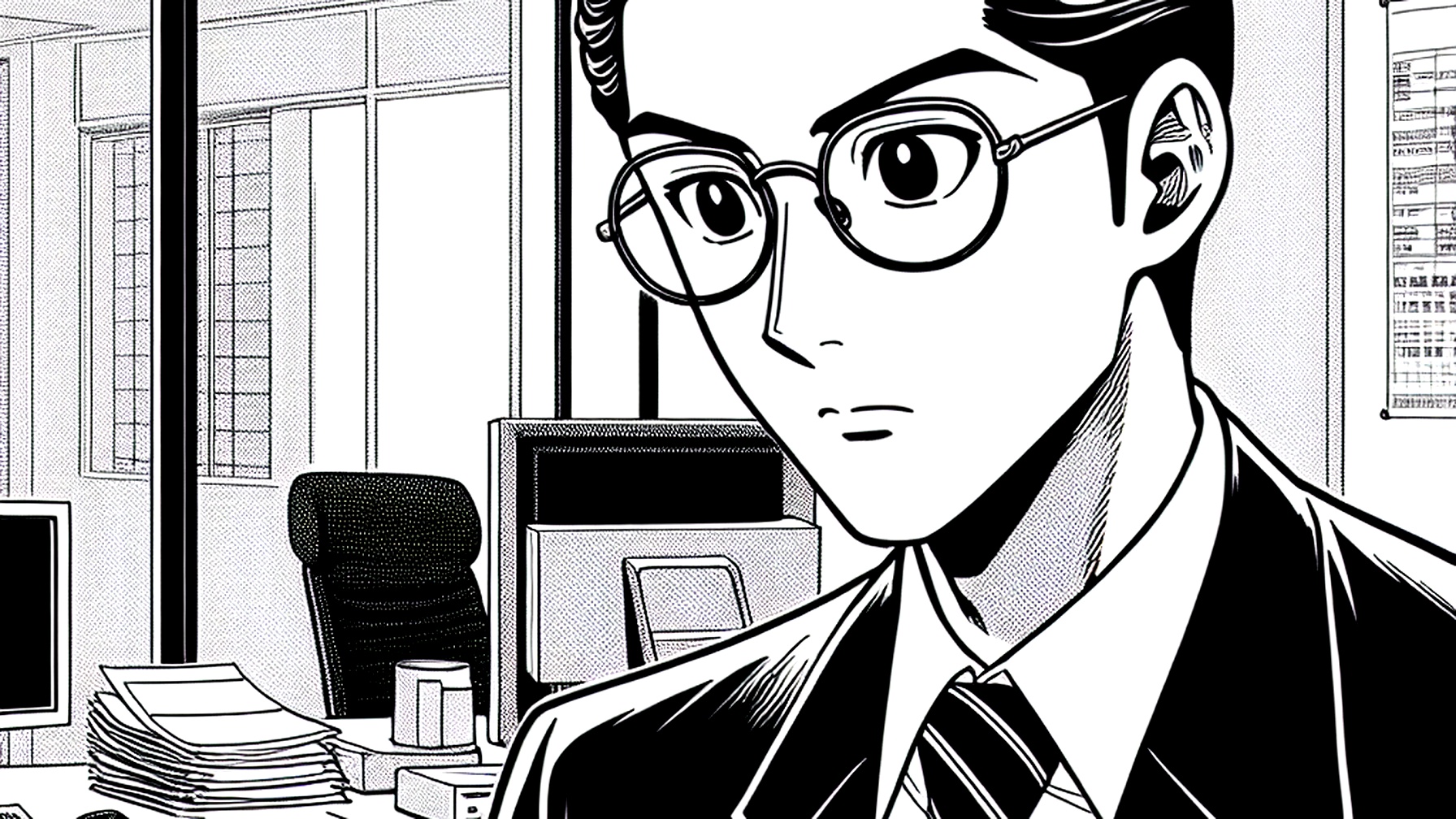
次に、譲渡所得税の計算方法を理解しておく必要があります。譲渡所得は「売却価格−取得費−譲渡費用」で算出され、保有期間に応じて税率が変わります。
保有期間が5年を超える長期譲渡の場合、所得税15%と住民税5%が基本税率です。ここに復興特別所得税が加わるため、実効税率は約20.315%となります。一方、5年以下の短期譲渡では約39%と高率になるので、売却タイミングの見極めが利益確保の鍵です。
居住用財産には「3000万円特別控除」が2025年度も適用できます。この控除を利用すれば、譲渡所得から3000万円を差し引けるため、多くのケースで税負担を大幅に軽減できます。ただし、転勤などで空き家期間が3年を超えると適用外になる可能性があるため、国税庁の最新Q&Aで適用条件を確認してください。こうした制度を活用すれば、同じ売却価格でも最終的に残る手取りは大きく変わります。
相場より高く売るための値付け戦略
実は、手取り額を増やすために最もインパクトが大きいのは値付けそのものです。相場よりも高い価格で売却できれば、費用が同じでも手元資金は増えます。
査定依頼は複数社に出し、価格と販売戦略の両面で比較することが基本です。不動産流通推進センターの調べでは、2024〜2025年にかけて一括査定サービスを活用した売主は、平均して3社以上を比較し、単独依頼よりも最終成約価格が約6%高かったと報告されています。複数査定は時間こそかかりますが、1000万円規模の利益に直結する可能性があるため労力を惜しむべきではありません。
さらに、販売開始価格を高めに設定し、問い合わせ状況を見ながら段階的に調整する「プライスリダクション戦略」も有効です。開始30日以内に十分な内覧予約が入らなければ5%下げるなど、あらかじめルールを決めておくと感情に左右されません。一方で、相場とかけ離れた高値設定は長期化リスクを招き、結果的に値崩れを起こすのでバランス感覚が求められます。
売却益を1000万円残すためのローン残債調整
ポイントは、ローン残債と売却益のバランスを適切に管理することです。特に、残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の状態では、たとえ高値で売れても手取りが出ないケースがあります。
2025年現在、多くの金融機関では一括繰上げ返済手数料が無料または3万円以下に抑えられています。しかし、繰上げ返済資金を自己資金で用意できない場合は、買主からの代金決済と同時に返済する「相殺決済」に対応してくれる仲介会社を選ぶと安心です。なお、変動金利で返済中の人は、2024年後半からの政策金利引き上げを受けて金利がじわじわ上昇しているため、売却タイミングの前倒しを検討する価値があります。
繰上げ返済後、残る手取りを1000万円に近づけるには、売却価格を上げるか、ローン残債を減らすかの二択です。月1万円ずつの繰上げ返済でも、5年間で約60万円の元金を圧縮でき、利息軽減効果もあるため、売却計画を立てた段階で早めに行動すると有利になります。
1000万円を次の資産形成に活かす方法
最後に、手取り1000万円を受け取った後の運用を考えておくことが長期的な資産形成を左右します。総務省の家計調査によれば、2025年の普通預金平均金利は0.02%と依然として低迷しており、ただ預けるだけでは資産は増えません。
一方、2025年から拡充された新NISAは年間360万円の非課税投資枠を提供しており、売却益の一部をインデックスファンドへ分散投資する選択肢があります。また、住宅ローンを完済して余剰資金が生まれた場合でも、将来的な住み替えや相続対策を視野に入れ、不動産クラウドファンディングなど流動性の高い投資商品で分散することがリスク管理につながります。
つまり、「売却 1000万円」をゴールではなくスタートと捉え、資産ポートフォリオ全体の最適化を図ることが重要です。資金の一部を緊急予備費として普通預金に確保し、残りを長期投資に回すなど、ライフプランに沿ったバランスが求められます。
まとめ
ここまで、売却額と手取り額の違い、譲渡所得税の仕組み、値付け戦略、ローン残債の調整方法、そして受け取った1000万円の活用法まで一連のプロセスを解説しました。重要なのは、各ステップを事前にシミュレーションし、税制や金利動向など最新情報を反映させることです。手取り1000万円を確保できれば、次の投資やライフイベントの選択肢が広がります。今日から情報収集と計画作りを始め、理想の資産形成に踏み出しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数(2025年9月版) – https://www.mlit.go.jp/
- 国税庁 譲渡所得の課税のしかた(令和7年度版) – https://www.nta.go.jp/
- 不動産流通推進センター 2025年版不動産業統計集 – https://www.retpc.jp/
- 日本政策金融公庫 住宅ローン金利動向レポート2025 – https://www.jfc.go.jp/
- 総務省統計局 家計調査年報2024 – https://www.stat.go.jp/

