不動産投資を始めたいけれど、「円安が進むと物件価格はどうなるのか」「海外マネーが流入すると利回りは下がらないか」「良い管理会社をどう見極めればいいのか」と迷う人は多いはずです。実際、2024年から続く円安局面で海外投資家の買いが強まり、都市部の収益物件は想定以上の値上がりを見せました。しかし、運用のコツさえ押さえれば、初心者でもこの環境をチャンスに変えられます。本記事では円安が賃貸経営に及ぼす影響を整理し、キャッシュフロー改善に直結する管理会社の選び方まで丁寧に解説します。読み終えた頃には、市場環境に左右されにくい運用戦略と具体的な行動指針を得られるでしょう。
円安が不動産収益に与える影響
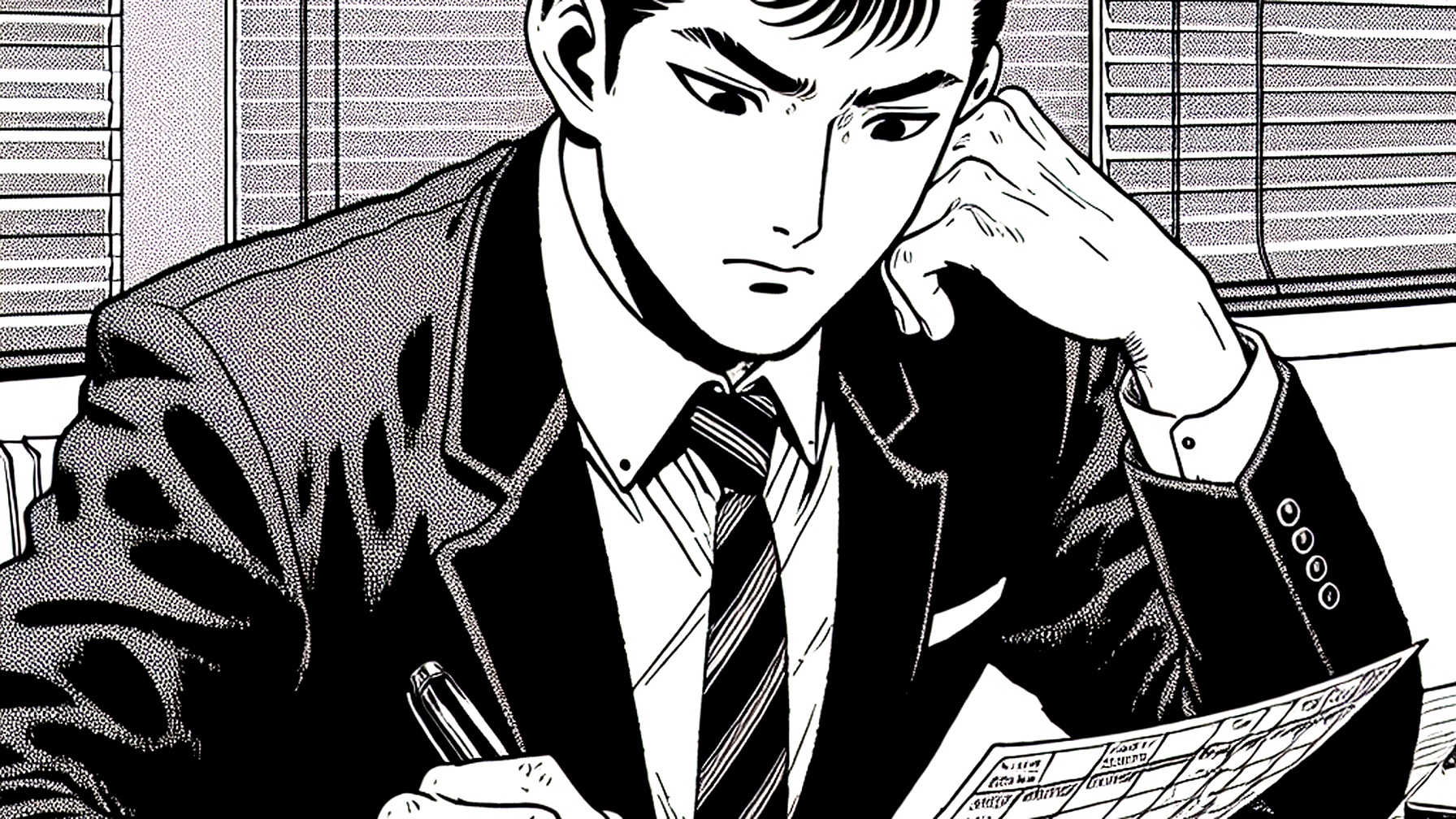
重要なのは、円安が家賃収入と物件価格に相反する動きをもたらす点を理解することです。円建て家賃は基本的に国内賃料相場で決まる一方、物件価格はドル換算で割安に見えるため上昇しやすくなります。
まず日本銀行の「資金循環統計」によると、2025年上期の海外からの不動産直接投資額は前年比18%増でした。背景には1ドル=165円前後で推移する円安があり、東京や大阪のオフィスビルだけでなく中規模のレジデンスにも海外資金が入っています。つまり物件取得コストは高くなる可能性がある反面、家賃そのものは急に上がりません。
しかし、円安は輸入資材価格の上昇を通じて新築供給を抑制する効果もあります。国土交通省の建築着工統計では、2024年度の賃貸住宅着工戸数が8.3%減となり、空室率を押し下げる要因として機能しています。つまり既存物件を保有する投資家には、家賃下落リスクが小さい追い風が吹いているといえます。
一方で円安は金利上昇圧力を伴うため、融資条件が厳しくなる点には注意が必要です。実際にメガバンクは、投資用ローンの変動金利を2023年末から0.25ポイント程度引き上げました。したがって、購入時には利回りだけでなく固定・変動の金利タイプや返済比率を精査することが欠かせません。
外国人投資家と競合する市場で勝つには

ポイントは、物件選定で「競争を避けるニッチ」を見いだすことです。海外マネーは都心タワーマンションや大型オフィスに集中しがちで、中小規模の中古レジデンスまでは手が回っていません。
例えば、不動産流通推進センターの「2024年度不動産取引価格指数」によれば、築15年以上のファミリータイプ区分マンションは都心5区でも年4%程度の上昇にとどまっています。つまり過熱感が比較的緩やかな中古ファミリー層向け物件は、円安下でも手が届きやすい価格帯で残っています。また、外国人投資家は管理の手間がかかる地方都市を敬遠しがちです。そのため、政令市クラスの駅近アパートや築浅の一棟レジデンスに目を向けると利回り7%超の案件を見つけやすくなります。
さらに、賃貸需要を測る指標として地方自治体が公表する「人口ビジョン」を確認する方法があります。たとえば札幌市は2030年までの人口微増を見込み、観光客数も北海道運輸局の統計で2025年上期に過去最高を記録しました。言い換えると、観光都市かつ人口が維持されるエリアは、外国人投資家が注目する前に仕込む絶好の機会となります。
加えて、円安で海外旅行が割高になった日本人の内需回帰も追い風です。国際線代替として地方観光地が人気化し、短期滞在型のマンスリーマンション需要が高まっています。短期賃貸に対応できる管理会社と組めば、競争の少ない市場で収益拡大を狙えます。
管理会社選びで差がつく収益力
実は、同じ物件でも管理会社によって手取りキャッシュフローが年10万円以上変わることがあります。だからこそ、管理会社は「家賃集金」と「空室対策」を総合評価して選ぶ必要があります。
まず押さえておきたいのは、管理委託契約の形態です。一般管理型は手数料が家賃の5%前後で、募集や清掃はオプション扱いの場合があります。サブリース型は空室リスクを管理会社が負う代わりに、設定家賃の80〜90%がオーナーに支払われる仕組みです。どちらが得かは物件の空室率と市場家賃の伸びで決まるため、賃貸住宅新聞社の「平均空室率レポート」を参考にすると良いでしょう。
次に、リーシング(入居付け)の能力をチェックします。具体的には、直近1年間の募集から契約までの平均日数、退去から次の入居までの平均空室期間、広告費(AD)の水準を質問します。優良会社はデータを開示し、空室期間を30日以内に抑えている場合が多いです。数字を提示できない会社は避けた方が無難です。
さらに、IT重説やオンライン内見などデジタル対応も重要です。国交省が推進する「賃貸取引のデジタル化」は2025年度も引き続き有効で、専用ウェブ内見システムを導入する管理会社は入居者募集の幅が広がります。結果として、繁忙期以外でも成約が決まりやすくなり、安定収益につながります。
最後に、修繕・清掃の品質を現場で確認します。管理会社が委託する清掃会社の作業チェックシートを見せてもらい、週1回以上の巡回記録があるか確認するだけでも長期的なリフォーム費用を抑えられます。つまり、数字と現場の両面で比較することで、管理コストを最小化しながら賃料を最大化できるのです。
具体的なキャッシュフロー改善策
まず押さえておきたいのは、キャッシュフローを「家賃収入−運営費−返済額」で測るだけでは不十分という点です。実際は、減価償却費や税控除を考慮した“税後キャッシュ”が最終的な手取りを左右します。
税務面では、「青色申告特別控除65万円」を活用すると課税所得を圧縮できます。所得税率33%のゾーンであれば、年間約21万円の節税インパクトになります。また、2024年に拡充された建物耐用年数の見直しにより、木造アパートは最短22年で償却可能です。築古物件を取得して短期で償却を取り、繰り延べた資金を次の物件頭金に回す戦略が有効になります。
運営費の削減では、共用部のLED化が依然として費用対効果が高い施策です。経済産業省「エネルギー白書2025」によると、LEDは蛍光灯に比べて電気代を約35%削減でき、交換サイクルが長いためメンテ費も減ります。加えて、インターネット無料設備を導入すると空室期間を平均12日短縮できる事例が、多くの管理会社で報告されています。初期費用は1戸あたり3〜5万円ですが、空室リスク低減の効果が高く、結果としてキャッシュフローの安定化に寄与します。
金融面では、借り換えによる金利引き下げが依然として有効です。たとえば、2025年4月にネット銀行Aが発表した投資用ローン固定1.9%(10年)の商品に乗り換えると、残高3000万円・残期間25年のケースで総支払利息を約230万円削減できます。金利交渉の際は、他行の事前審査承認書を提示すると条件が通りやすくなります。
最後に、家賃アップ戦略として人気が高いのが「家具・家電付きプラン」です。国土交通省住宅局の調査では、単身物件で家電付きにすると平均家賃を月額7%上げても入居率が維持できるとの結果が出ています。この追加収入と運営コストを比較し、実質利回りを計算したうえで導入可否を判断しましょう。
2025年度の税制と公的支援の活用ポイント
重要なのは、2025年度税制改正と各種支援策を正しく理解し、無理なく使いこなすことです。投資家が直接利用できる主な制度は以下のとおりです。
まず、登録免許税の特例措置が2025年3月31日まで延長されており、一定要件を満たす中古住宅の保存登記は税率が0.3%から0.15%へ半減します。物件取得後にリフォーム計画を立てる場合は、期限までに登記を済ませることでコストを抑えられます。
次に、マンション共用部の省エネ改修に対する「賃貸住宅省エネ改修補助金(2025年度)」が継続しています。補助率は工事費の1/3、上限100万円で、LED化や高効率給湯器の導入が対象です。採択件数には上限があるため、管理会社や施工会社に早めに相談し、申請書類を整えるのが得策です。
さらに、地方自治体独自の家賃補助や移住促進制度も見逃せません。たとえば長野県飯田市は2025年度までの時限措置として、移住者向け賃貸住宅への改修費を最大80万円補助しています。このような地域限定の支援策を利用すれば、築古物件でも付加価値を高めつつ、実質利回りを押し上げられます。
また、インボイス制度開始に伴う賃貸オーナーの消費税課税事業者選択も検討しましょう。課税売上高が1000万円未満でも、将来的に家賃以外の課税収入が増えるなら、簡易課税を選択した方が控除額を確保できる場合があります。税理士にシミュレーションを依頼し、長期的なキャッシュフローで比較することが肝要です。
最後に、所得拡大促進税制の活用も選択肢になります。従業員を雇用し、給与総額を前年度より増やした場合、増加額の15%相当を法人税から控除できます。小規模法人で物件を保有しているなら、人件費を投じて管理効率を上げつつ、税負担を減らすダブルのメリットを検討できます。
まとめ
この記事では、円安時代における収益物件の選び方から管理会社の比較ポイント、税制・補助金を活用したキャッシュフロー改善策までを解説しました。円安で物件価格が上がる局面でも、中古ファミリー物件や地方都市の築浅一棟レジを狙えば、手ごろな価格帯で安定した家賃収入を得られます。さらに、リーシング力とデジタル対応を兼ね備えた管理会社を選ぶことで、空室期間を最小化し、運営コストも削減できます。最後に紹介した税制優遇や省エネ補助金を組み合わせれば、実質利回りを一段と高められるはずです。今日紹介したステップを一つずつ確認し、数値と現場の両面で意思決定を行えば、円安相場でもブレない堅実な投資が実現できるでしょう。
参考文献・出典
- 日本銀行 資金循環統計 – https://www.boj.or.jp/statistics/
- 国土交通省 建築着工統計 – https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/
- 不動産流通推進センター 不動産取引価格指数 – https://www.retpc.jp/
- 経済産業省 エネルギー白書2025 – https://www.enecho.meti.go.jp/
- 賃貸住宅新聞社 平均空室率レポート – https://www.chintaishimbun.com/
- 国土交通省 賃貸取引のデジタル化関連資料 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/

