投資用のマンションを一棟で購入したいけれど、資金や運営の不安が先に立って踏み出せない――そんな声をよく耳にします。区分所有と違い、建物全体を持つことで得られるメリットは大きい一方、調査や管理の負担も増えます。本記事では「マンション投資 一棟買い 講座」と題し、仕組みの基本から物件選び、融資、リスク対策、そして2025年度時点で活用できる制度まで網羅的に解説します。読み終えたとき、行動に移すための具体的な道筋が見えるはずです。
一棟買いの基礎を押さえよう
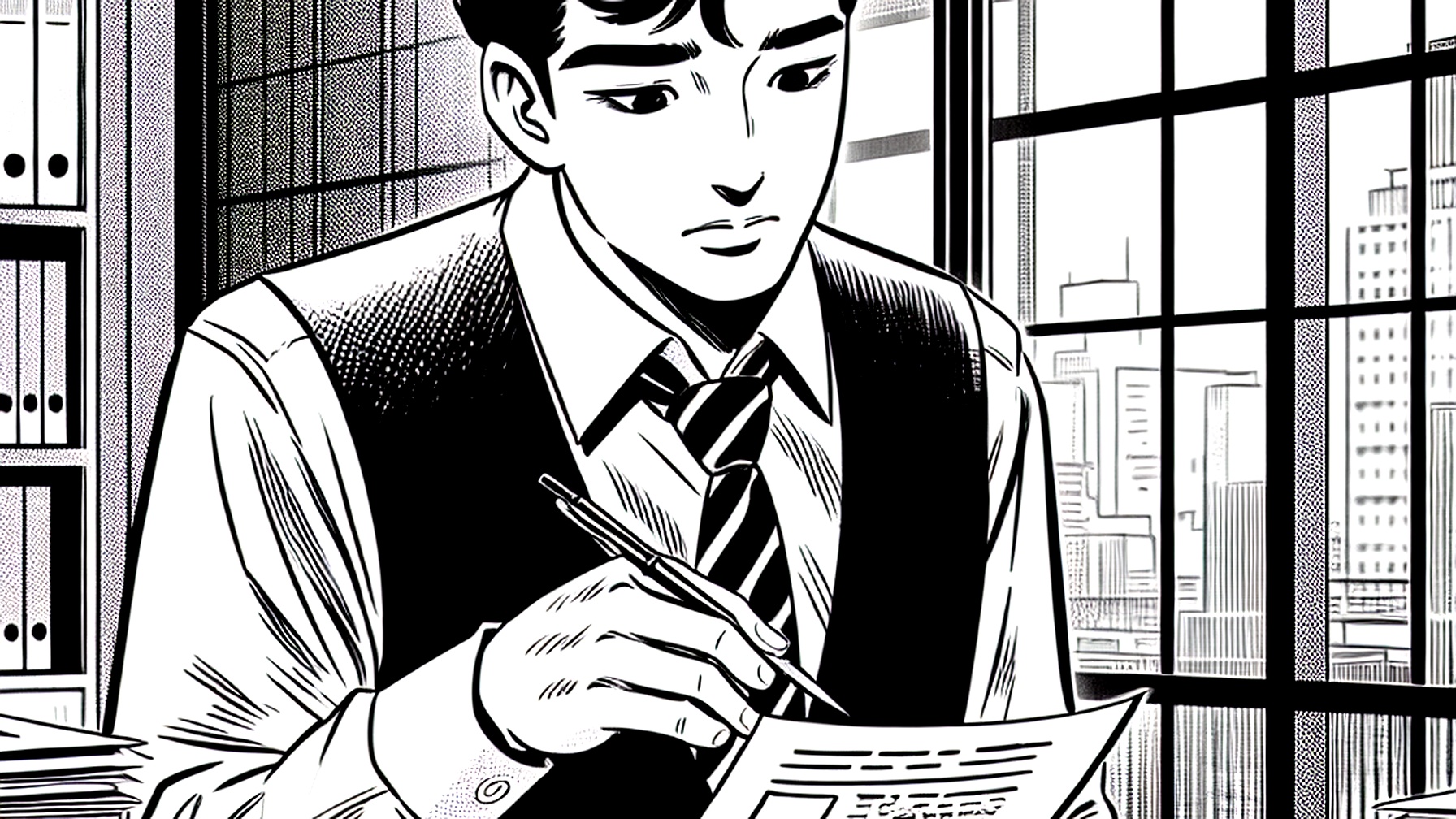
まず押さえておきたいのは、一棟買いが区分所有とは収益構造も責任範囲も大きく異なる点です。所有権が建物全体と土地に及ぶため、空室や修繕の影響を自分でコントロールしやすい一方、初期投資額は高くなります。
一棟を持つ最大の魅力はキャッシュフローが読みやすいことです。複数戸から賃料が入るため、空室の発生が収入全体に与える影響を緩和できます。言い換えると、戸数が多いほど収益が平均化され、家賃下落のリスクが分散されます。ただし土地と建物全体を購入する分、銀行評価が厳しめになるのが実情です。
さらに、一棟物件では共用部の修繕計画も自分で立てる必要があります。区分所有の理事会に相当する組織がないため、資金繰りを含めた長期修繕計画を独自に策定しなければなりません。管理会社へ委託する手もありますが、費用と責任のバランスを事前に検討しておきましょう。
収益を左右する立地と建物の見極め方
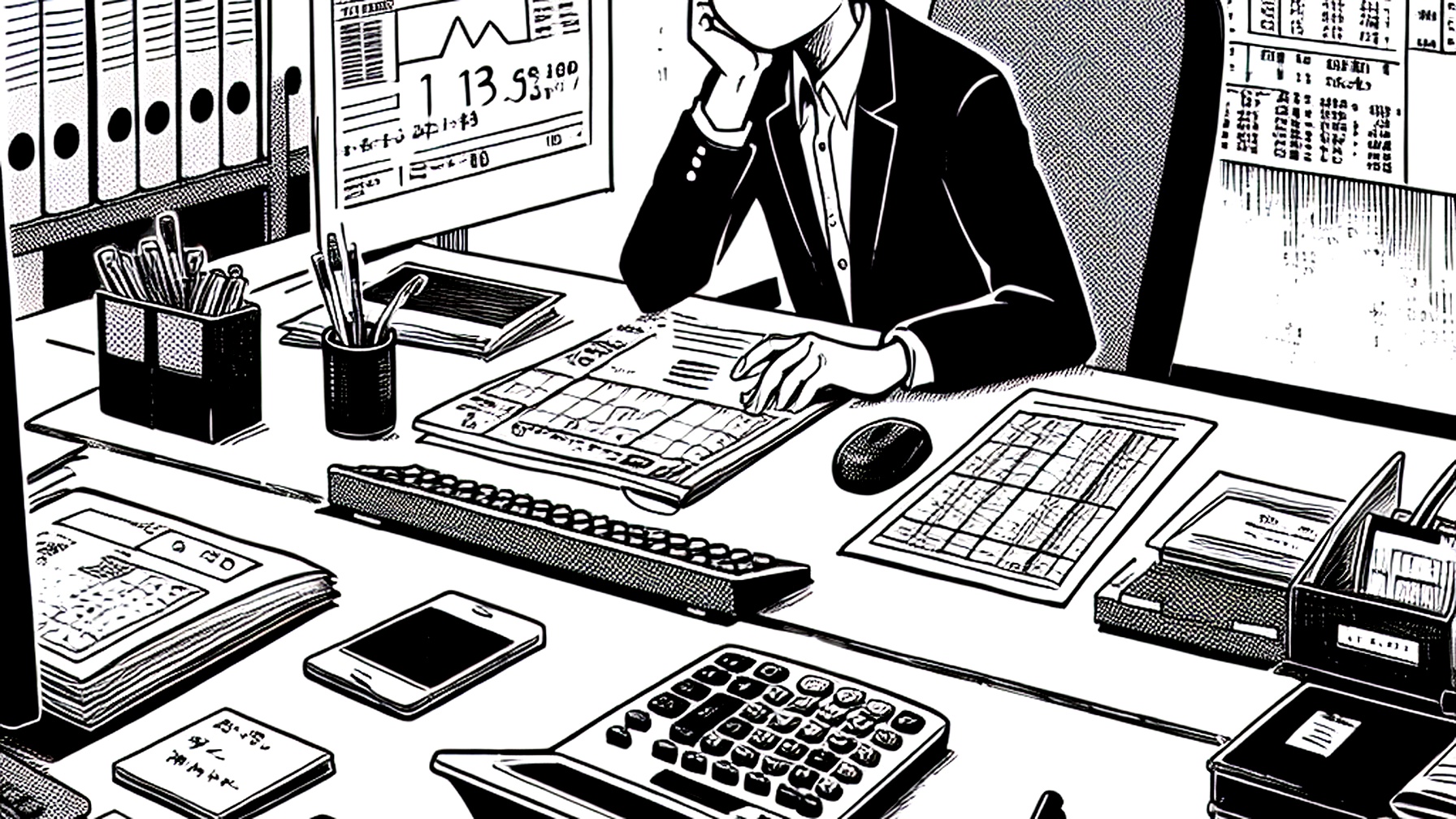
重要なのは、立地と建物の両面を総合的に評価することです。立地が良くても建物が老朽化していれば修繕費が膨らみ、逆に新築でも交通アクセスが弱いと長期的な空室リスクが高くなります。
立地評価では、最寄り駅までの徒歩分数と乗降客数、さらに将来の人口動態を確認します。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、都心5区は2024年以降も転入超過が続き、25~39歳の単身層が増えています。この層をターゲットにするなら、ワンルーム比率の高い物件が有利です。一方で郊外でも大学や病院が近いエリアは需要が底堅く、利回りが高めに設定される傾向があります。
建物チェックでは、1981年以降の新耐震基準であるか、配管更新歴があるかが分かれ目になります。国土交通省の統計では、築30年超物件の配管交換費は戸当たり平均35万円に達します。築古を狙う場合は、購入直後に大規模修繕を想定した資金計画が不可欠です。また、検査済証の有無も金融機関の評価ポイントになるため、取得前に必ず確認しましょう。
資金計画と融資戦略の最新ポイント
ポイントは、自己資金割合と金利タイプの選択を投資目的に合わせることです。自己資金は物件価格の20~30%を用意すると、融資審査が通りやすく、月々の返済比率も下がります。
2025年10月時点で主要地方銀行のアパートローン金利は変動型年1.8~2.6%が中心です。固定金利は長期プライムレート上昇の影響で年3%台に入るケースが増えました。日本銀行の金融政策決定会合では緩やかな金利正常化が示唆されており、将来的な上昇リスクを織り込むなら、変動で借りて繰上返済を柔軟に行う戦略が有効です。
融資期間は耐用年数との兼ね合いが鍵です。鉄筋コンクリート造(RC)の法定耐用年数は47年ですが、金融機関は築年数+融資期間が60年以内に収まるよう設定する場合が多くあります。築20年のRCなら最長40年融資を期待できますが、築30年を超えると融資期間が短くなり、キャッシュフローが苦しくなるため注意が必要です。印紙税や登録免許税などの初期費用も、物件価格の6~8%を目安に見込んでおきましょう。
運営とリスク管理で差をつける
実は、購入後の運営で収益の成否が決まります。満室想定利回りだけで判断せず、運営費率を現実的に計上することが必須です。
国土交通省「不動産投資市場動向調査」によれば、RC一棟マンションの平均運営費率は25~30%です。管理委託費、固定資産税、共用部電気代、長期修繕積立を合算し、この範囲に収まるか確認しましょう。特に修繕費は年ごとに変動しますから、毎年家賃収入の10%以上を積み立てると資金ショックに備えられます。
空室対策では柔軟なリノベーションが効果的です。ワークスペース付き1Kや高速インターネット無料化など、働き方の変化に合わせた設備投資は、退去抑制と賃料アップの両方に寄与します。小規模な改装でも写真映えを意識すると60%以上の入居希望者が内見予約を増やした、という大手仲介会社の社内分析もあります。
リスクとして忘れがちなのが災害です。火災保険に加え、地震保険を付帯すれば保険料は高くなりますが、資産を守る上では欠かせません。ハザードマップを確認し、浸水想定区域の物件では止水板を導入するなど物理的対策も検討しましょう。
2025年度に活用できる制度と税制
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続する住宅ローン減税の投資家向け活用法です。自宅併用型の一棟物件を取得し、50㎡超部分を自己居住用と認定されれば、年末ローン残高の0.7%を最大13年間控除できます。併用面積が50%を超えると対象外になるため、設計段階での面積配分がポイントです。
さらに、固定資産税の新築住宅軽減措置は2025年度も継続し、居住用部分が50㎡以上であれば、建物部分の税額が3年間半額になります。賃貸併用であっても、居住用割合が1/2以上なら適用可能です。これにより、一棟新築マンションを建てる場合はキャッシュフローの改善効果が大きくなります。
相続税対策としては、貸家建付地評価の活用が基本です。国税庁の財産評価基本通達では、宅地を貸家建付地とすることで路線価の約20%を減額できます。一棟マンションは区分所有より評価圧縮効果が高く、相続人の納税資金確保にも貢献します。ただし、過度な節税目的と見なされると否認リスクがあるため、税理士と二人三脚でスキームを組んでください。
まとめ
ここまで見てきたように、一棟買いは資金面でも運営面でもハードルが高い反面、自らの裁量で収益を最大化できる魅力的な手法です。立地と建物を丁寧に見極め、適切な融資と長期修繕計画を組み合わせれば、安定したキャッシュフローが期待できます。まずは自己資金と目標利回りを整理し、本記事で紹介したチェックポイントを手元のメモに落とし込んで物件情報を比較してみてください。行動を積み重ねることで、あなたの「マンション投資 一棟買い 講座」は実地経験へと昇華していくでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 不動産経済研究所 新築マンション市場動向 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 財産評価基本通達 – https://www.nta.go.jp

