不動産投資に興味はあるけれど、多額の資金や物件管理の手間が不安で一歩を踏み出せない――そんな悩みを抱える人は少なくありません。実は、上場不動産投資信託(REIT)なら少額から始められ、物件の運営はプロに任せられるため、時間や知識が限られていても不動産収益に参加できます。本記事では、REITの仕組みと始め方を解説しつつ、筆者自身の体験談を交えて注意点を整理します。読み終えた頃には、投資スタートに必要なステップとリスク管理のポイントが明確になり、明日から行動に移せるはずです。
REITとは何か、まず押さえておきたい仕組み
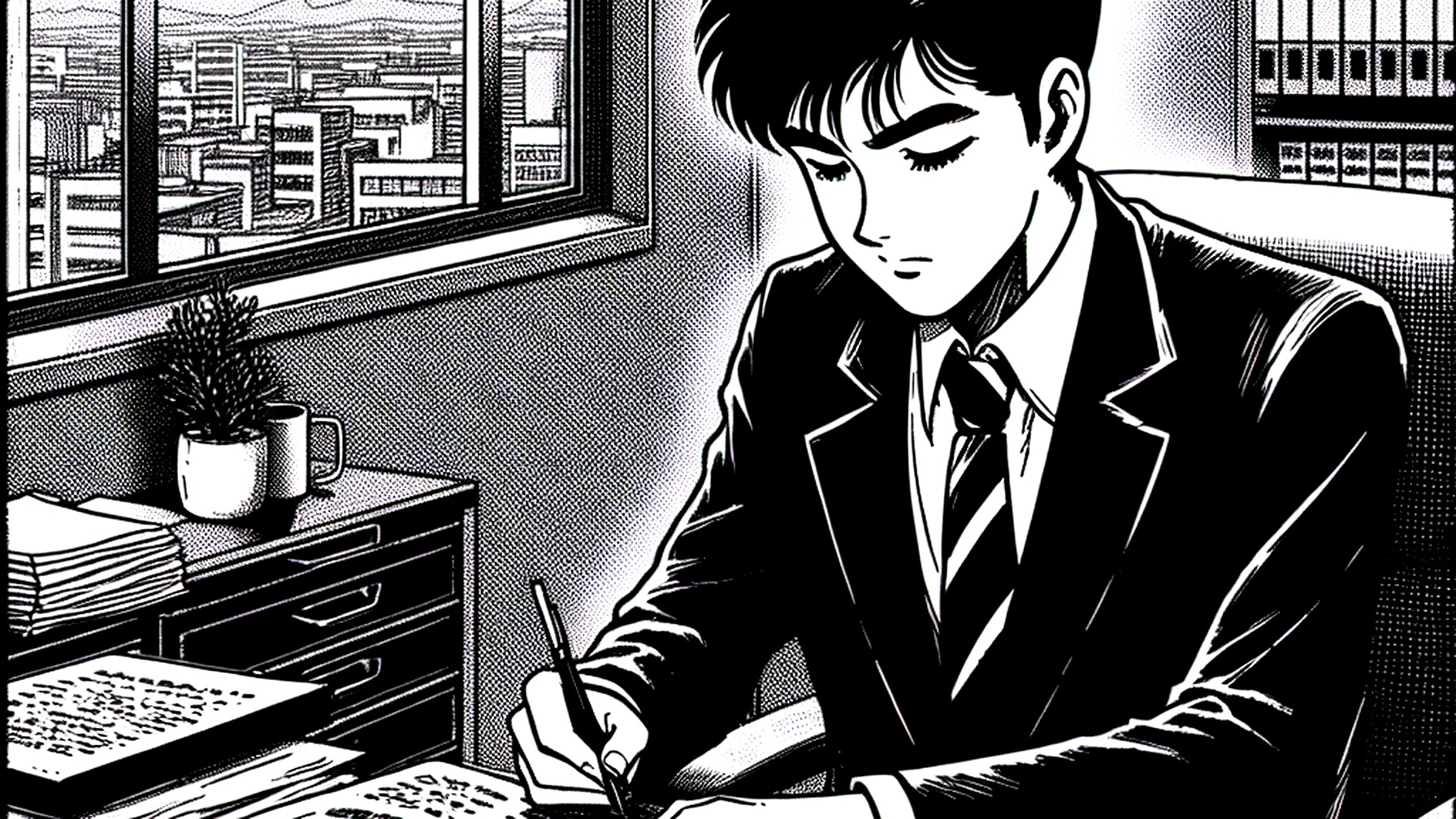
重要なのは、REITが不動産を裏付け資産とする投資信託である点です。投資家は証券取引所でREITの投資口を売買し、運用会社は集めた資金でオフィスや商業施設、物流倉庫などを取得・運営します。運用益の大半は分配金として還元されるしくみで、東京証券取引所のJ-REIT指数をみると、2025年9月時点の平均分配利回りは約3.7%と、国内株式配当利回りを上回る水準です。
一方で価格変動リスクも株式同様に存在します。新型感染症拡大時にはオフィス需要懸念から指数が20%以上下落しました。つまり、安定したインカムゲイン(分配金収入)を得られる一方、市況によって元本が動く点を理解する必要があります。また、J-REITは投資口保有率の50%以上を利益分配に充てることで法人税を実質的に免除されるため、高い利回りを維持しやすい特徴があります。税制メリットがリターンを支えることを頭に入れておきましょう。
口座開設と銘柄選びのステップ
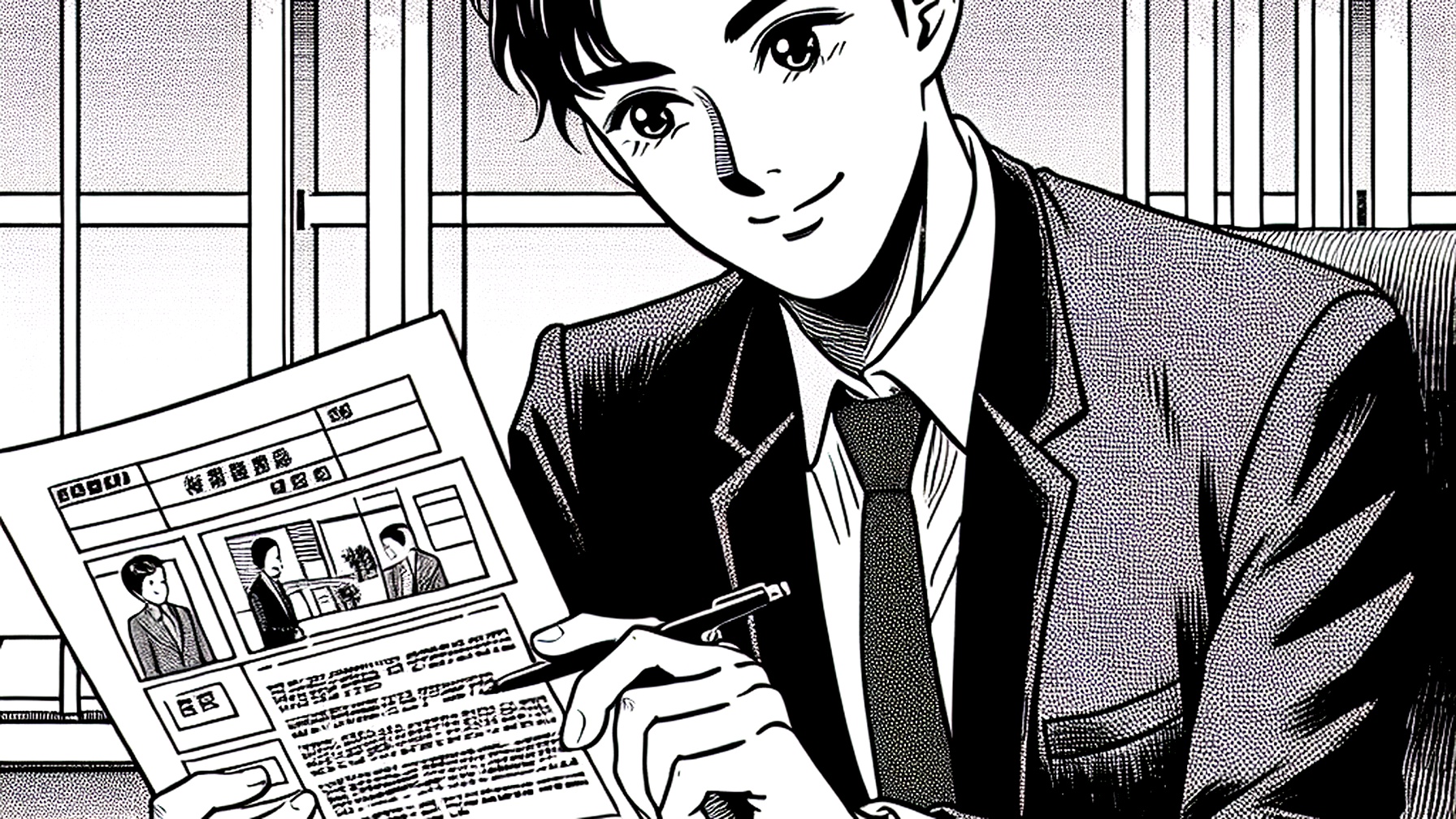
まず押さえておきたいのは、REIT投資には証券口座が必須という点です。既に株式取引用の口座を持っているなら、そのままREITも売買できます。未開設の場合は、オンライン証券であれば最短数日で手続きが完了し、スマホだけで本人確認が済むサービスが主流です。筆者は手数料とアプリの操作性を比較し、ネット専業のA社を選びました。
銘柄選定では、利回りだけでなくポートフォリオ構成と財務健全性をセットで確認します。具体的には、「オフィス型」「物流型」「総合型」のように資産タイプが分かれるため、経済環境に応じた分散が可能です。たとえば物流型はEC需要が追い風で賃料上昇が続いていますが、価格が割高な局面もあるため注意が必要です。また、格付会社が発行するレポートやLTV(総資産有利子負債比率)が50%以下かどうかをチェックすると過剰債務リスクを回避しやすくなります。
注文方法には成行と指値があり、分配金権利落ち日の値動きを考慮すると指値が安心です。2025年度からは新NISAの積立投資枠でREIT ETF(上場投資信託)も購入できるようになりました。年間360万円の投資枠を活用して、長期で分散購入すると価格変動の影響を抑えられます。
体験談:初めてのREIT購入から半年で得た学び
実は、筆者が初めてREITを買ったのは2024年末です。当時、オフィス需要の回復期待から価格が上向きで、分配利回り4.2%の総合型REITを10万円分購入しました。半年後の2025年6月に初回分配金が入金され、税引き後で1,700円強のキャッシュフローを獲得。利回りどおりの数字に思わず笑みがこぼれました。
しかし、その直後に長期金利上昇懸念が浮上し、投資口価格は瞬間的に7%下落。慌てて売却を検討しましたが、分配金再投資を続ける方針を思い出し、保有を継続しました。結果的に価格は3カ月で回復し、長期視点の大切さを痛感。言い換えると、REITはインカム狙いの長期保有に向く資産であり、短期値動きに翻弄されると本来の魅力を損ねると実感しました。
また、分配金の安定性を高めるために、追加で物流型と住宅型のREITを購入し、ポートフォリオを3銘柄に分散。分配金支払月がずれているため、ほぼ毎月何らかの入金がある体制を構築できました。このように実践を通じ、分散とキャッシュフロー管理の重要性を学んでいます。
分配金と税金のしくみを理解して手取りを最大化
ポイントは、分配金への課税が株式配当と同じく20.315%の源泉徴収で自動的に差し引かれることです。ただし、2025年度の新NISA口座を利用すれば、年間成長投資枠240万円までの分配金が非課税になります。たとえば利回り4%のREITをNISA枠で100万円保有すると、年間4万円の分配金がそのまま手取りになる計算です。課税口座で同額を保有すると、約8,000円が税金で引かれてしまいます。
さらに、特定口座で保有する場合でも、株式やETFの譲渡損とREIT譲渡益は損益通算が可能です。つまり、値下がり売却損を出しても、他の運用益と相殺できる仕組みがあるため、確定申告を活用すると税負担を抑えられます。一方で、分配金と譲渡益の損益通算はできない点に注意が必要です。
企業型DCやiDeCoではREITに投資できる商品が限られています。運用コストが高めに設定されているケースもあるため、目論見書の信託報酬を確認しましょう。コストの差は長期で見れば複利効果に直結します。実際、日本取引所グループのデータでは、年間信託報酬が1%違うと10年後の取り崩し可能額が10%以上変わるシミュレーションが示されています。
2025年度の制度とリスク管理の最新ポイント
基本的に、REITの制度は株式市場と連動しますが、2025年度には投資環境を改善する動きが進んでいます。ひとつは金融庁が推進する「上場REITディスクロージャー強化策」で、ESG情報の開示が義務化されます。これにより、運営会社の環境対策やテナント満足度が数値で比較しやすくなり、投資判断の材料が増えるでしょう。
また、国土交通省は2025年度から大規模修繕計画の情報開示基準を改定し、REITが保有する物件の修繕積立状況を詳細に公表するよう求めています。言い換えると、隠れた修繕負担を早期に把握できるため、長期保有リスクを見積もりやすくなります。物件寿命に影響を与える耐震性や省エネ性能もチェックポイントとして明示される見込みです。
リスク管理の観点では、金利上昇が最重要テーマです。日本銀行は2023年末にマイナス金利を解除し、2025年上期までに政策金利を0.5%まで段階的に引き上げました。J-REITの平均調達金利は0.8%程度ですが、今後1%台に乗ると分配金が圧迫される恐れがあります。したがって、固定金利比率が高く、長期借入が多いREITを選ぶと影響を和らげられます。運用報告書に記載された「平均残存借入期間」を確認すると、金利リスクを客観的に把握できます。
自然災害も無視できません。気象庁のデータによると、近年の台風進路は日本海側へシフトし、物流施設が集積する北陸地方で浸水リスクが上昇しています。REIT各社は保険加入や防災投資を強化しているものの、投資家自身も所在地分散や保険金額の注記をチェックする姿勢が求められます。
まとめ
ここまで、REITの仕組みから口座開設、筆者の体験談、税金対策、そして2025年度の最新制度までを一気に確認しました。ポイントは、少額から始められる手軽さと高い分配利回りの裏に、市況変動と金利上昇というリスクが潜むことです。分散投資と長期保有を基本に、制度改正やディスクロージャー情報を定期的にチェックすれば、手取りキャッシュフローを安定させながら資産形成を進められます。今日紹介したステップを参考に、自分の投資方針と許容リスクを整理し、まずは小額でも市場に参加してみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 – https://www.mlit.go.jp
- 気象庁 – https://www.jma.go.jp
- 東証REIT指数データ(東京証券取引所) – https://www.jpx.co.jp/markets/indices/j-reit-indices/

