家賃収入に興味はあっても「不動産は高いから無理」と感じる人は多いでしょう。しかし地方には、築古アパートを一棟300万円前後で取得できる市場が確かに存在します。本記事では、経験15年の立場から、超低価格の一棟買いがどう実現するのか、どこに落とし穴があるのかを丁寧に解説します。読むことで、300万円という限られた予算でも現実的にキャッシュフローを生む方法と、2025年10月時点で使える最新の制度・データを把握できるはずです。
なぜ今「一棟買い 300万円」が注目されるのか
ポイントは、地方の人口動態と投資家層の二極化です。大都市圏の利回り低下が進む一方、築古物件が値下がりし、個人でも手の届く価格帯が出てきました。
総務省の2025年国勢調査速報では、三大都市圏以外の20万人未満都市で空き家率が22%に達しています。つまり物件数が過剰で、オーナーは価格を下げてでも手放したいのが実情です。また、クラウドファンディングやREITに流れていたライト層が「現物を持ちたい」と方向転換していることも需要を押し上げています。
一方で、安さだけで飛びつくと修繕費で利回りが吹き飛ぶリスクがあります。地方自治体の長期空き家対策が強化され、倒壊の恐れがある物件には行政代執行費用が請求されることもあるため、建物の状態を見極める目が欠かせません。
実は、この価格帯でも年間家賃収入が200〜250万円取れるケースは珍しくありません。土地値がゼロに近いため、建物が償却後も地代並みの固定資産税だけで保有できる点が利益を押し上げます。
物件を見極める五つの視点
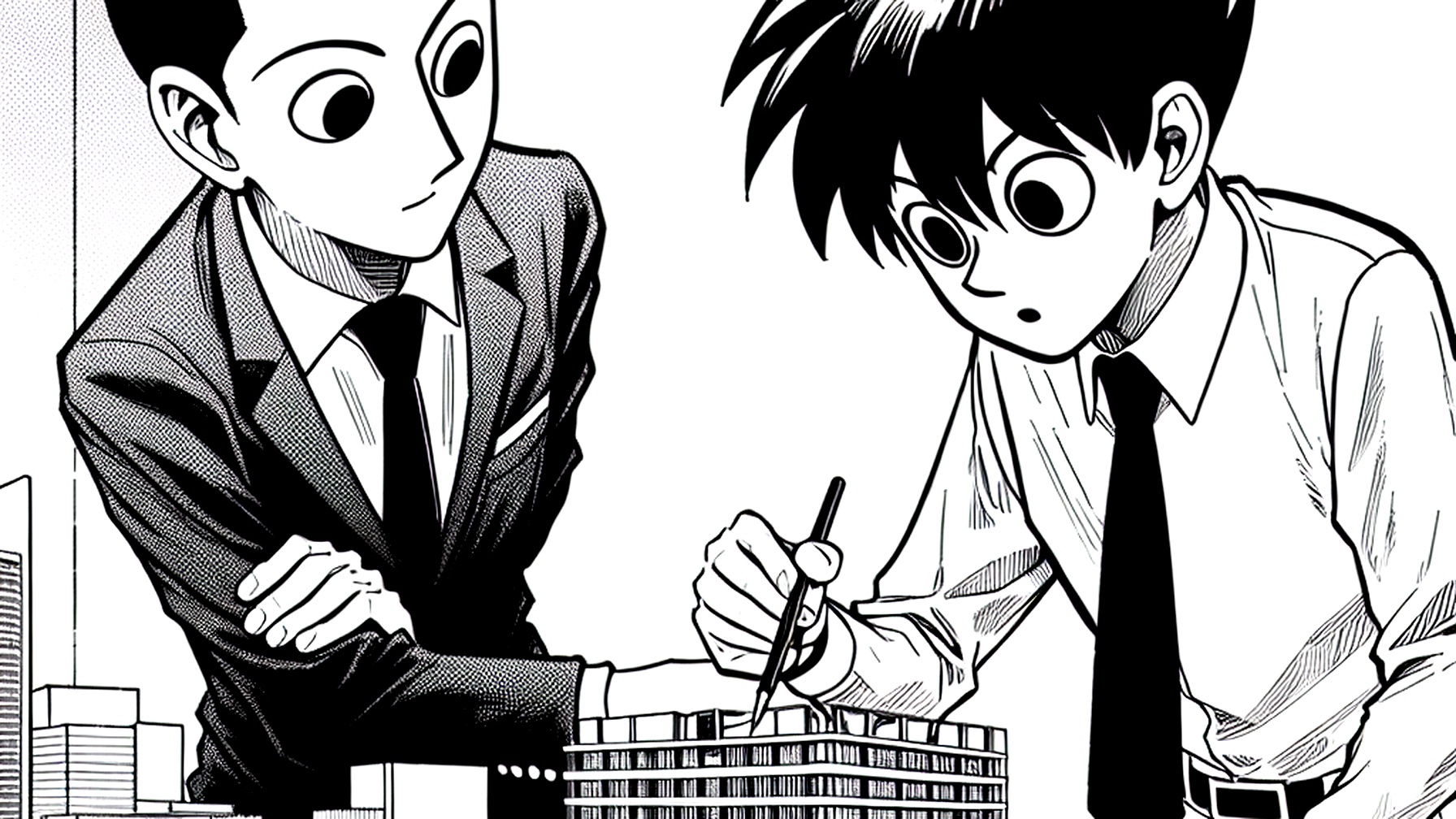
まず押さえておきたいのは、立地よりも「需給ギャップの小さいエリア」を選ぶことです。都市近郊でも、大学や工業団地、病院の近くは入居需要が底堅い傾向があります。
次に、建物構造を確認します。木造アパートは法定耐用年数22年を超えていても融資が出ることがありますが、屋根・配管・基礎の劣化が激しいと修繕が高額になります。外壁に大きな亀裂がないか、床が沈んでいないかを内見時にチェックしましょう。
三つ目は、インフラ費用です。下水道未整備地域では浄化槽の維持費が年間5〜10万円かかります。家賃が安いエリアほど微妙なコストが収益を圧迫するため、上下水の状況を必ず役所で確認してください。
最後に、競合物件の家賃設定を調べ、逆算でリフォーム費を決めます。同じ築年数でも内装を整えれば家賃が1.5倍になる地域もあります。国土交通省「賃貸住宅市場概況2025」によると、表面利回りが15%を超える物件のうち、実質利回りが10%未満に下がる主因は過大な改装費でした。
低価格でもローンを活用すべきか
重要なのは、自己資金を温存し、リスク分散を図る姿勢です。300万円の物件であっても、地銀や信用金庫がリフォーム費込みで500万円程度までのアパートローンを組めるケースがあります。
金融機関は「担保評価より収益性」を重視します。収支計画に空室率20%シナリオを織り込み、金利2.5%で返済比率を25%以内に収めると審査が通りやすいです。また、2025年度の小規模事業者向け制度融資は、個人大家でも利用可能な自治体が増えていますが、地域差が大きいため事前に商工会へ相談すると確実です。
一方で、現金購入なら手続きが簡単で短期売却もしやすいメリットがあります。築古物件は減価償却を4年で取り切れるため、所得税の圧縮効果を狙う高所得者に向いています。
つまり、ローンを使うか現金かは「キャッシュフローの厚み」と「節税メリット」のどちらを優先するかで決めると失敗が少なくなります。
300万円で購入後の改善プラン
実は、入居者が求めるのは最新設備よりも「清潔感とネット環境」です。総務省通信利用動向調査2025年版では、一人暮らし世帯の92%が「無料Wi-Fi付き住宅を選ぶ」と回答しています。光回線込みで月額5,000円の法人契約を導入すれば、家賃を2,000円上乗せできる計算です。
さらに、室内のアクセントクロスやLED照明は費用対効果が高い改装です。材料費は一室あたり3万円程度ですが、内見時の印象が大きく変わります。
外観については、破風板や雨樋の塗装だけでも修繕済みアピールになります。DIYで行えば10万円以下に抑えられるため、総投資額350万円で利回り15%超を狙うことも可能です。
入居募集では、地元の管理会社に一任せず自ら家賃保証会社と契約条件を交渉すると、滞納リスクを低減できます。オーナー参加型のリーシングは手間が増えますが、家賃の下落を防ぎ、長期的な収益につながります。
2025年度の税制優遇とリスク管理
ポイントは、投資用でも利用できる固定資産税の減額措置と、自然災害リスクへの備えです。2025年度税制では、建物の耐震改修を行うと翌年度の固定資産税が半額になる制度が継続しています。工事費が50万円未満でも対象となるため、築古アパートにも適用しやすい点が魅力です。
一方、気候変動の影響で浸水リスクが高まっています。国土交通省ハザードマップポータルの「重ねるハザードマップ」を使い、床上浸水想定0.5m以上のエリアは避けましょう。
火災保険は2025年10月の改定で最長契約期間が5年に短縮され、築25年以上の木造住宅は割増率が平均18%上昇しました。コスト増を見込んだうえで、地震保険とセット契約を行い、万一に備えることが不可欠です。
結論として、制度を知らずに支出を抑えるより、使える優遇をフル活用し、リスクを数値化して管理することが「一棟買い 300万円」を成功させる鍵になります。
まとめ
超低価格の一棟買いは、購入額の小ささゆえに「失敗しても傷が浅い」と思われがちですが、実際には現地調査と計画的な修繕が不可欠です。入居需要のある立地を見極め、収支シミュレーションを保守的に作り、2025年度の税制や融資制度を効果的に活用すれば、300万円の投資でも年間100万円以上の手残りを目指せます。まずは一物件を丁寧に運営し、経験を積むことが次のステップへの近道です。
参考文献・出典
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場概況2025 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 通信利用動向調査2025 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 ハザードマップポータル – https://disaportal.gsi.go.jp
- 住宅金融支援機構 2025年度融資データ – https://www.jhf.go.jp

