株式より手軽に不動産へ投資できるREIT(リート)が気になるものの、「REIT どこで 税金」という検索ワードで調べても情報が散らばっていて分かりにくい、と感じる人は多いはずです。本記事では、購入先の選び方から2025年度時点で有効な税制までを丁寧に整理します。読了すれば、証券口座を開く前に押さえておきたいポイントが明確になり、余計なコストを抑えながらREIT投資を始める自信が持てるでしょう。
REITの基礎知識と利益の生まれ方
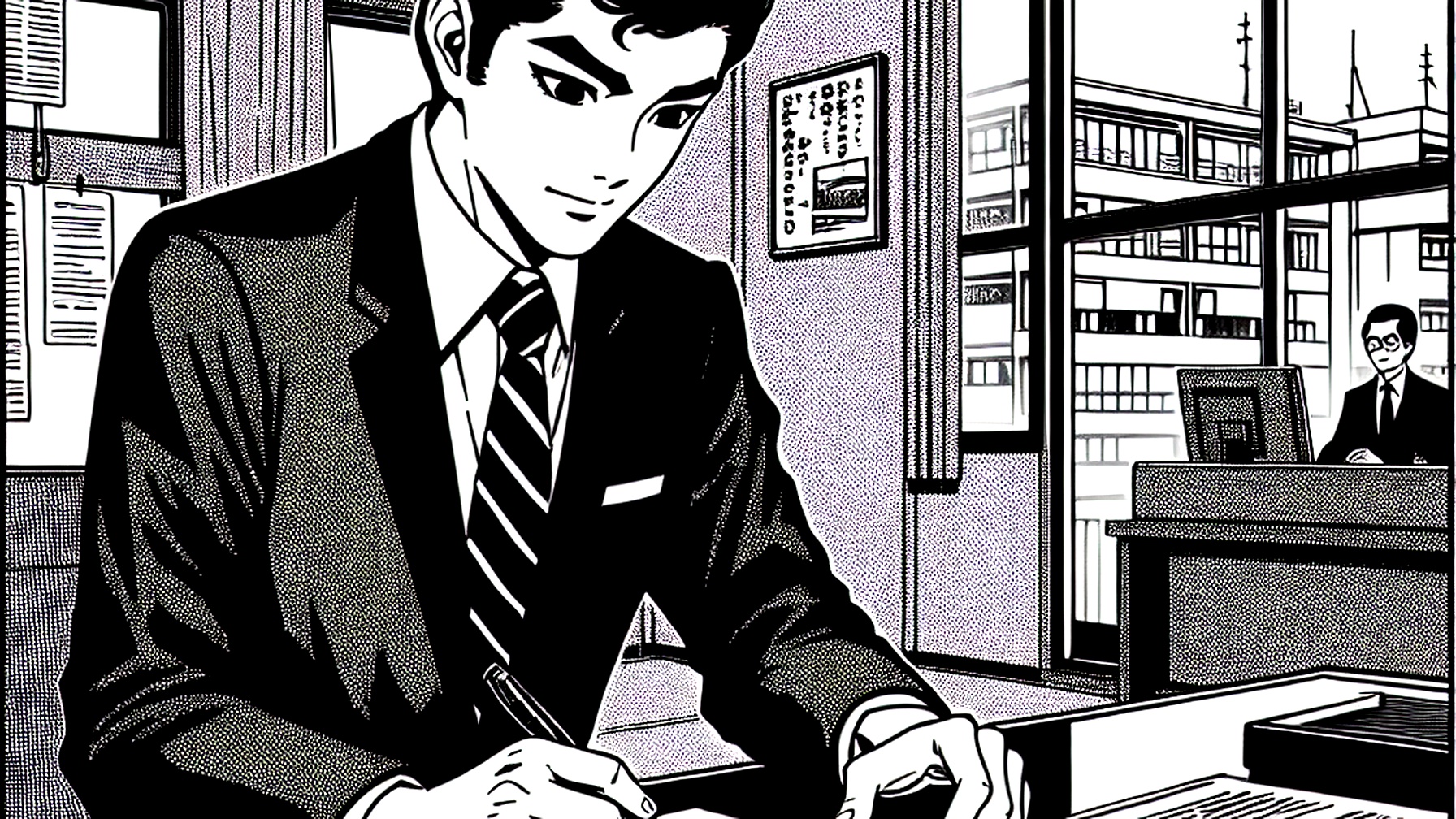
まず押さえておきたいのは、REITが「投資家から集めた資金で多数の不動産を保有し、その賃料や売却益を分配する仕組み」である点です。株式に例えると、ビルや住宅を束ねた不動産ファンドが上場し、私たちはその受益証券を売買します。
仕組みを理解すると、収益の柱が二つあることが見えてきます。ひとつは賃料収入などから生まれる「分配金」、もうひとつは市場価格の上昇による「譲渡益」です。日本取引所グループの統計によると、上場REITの平均分配利回りは2025年8月時点で3.5〜4.0%前後と、国内株式の平均配当利回りをやや上回ります。
つまり、インカムゲイン(分配金)を得ながら、タイミングによってはキャピタルゲイン(値上がり益)も狙えることがREITの魅力です。一方で価格変動は株式並みに起こるため、利益だけでなくリスクの分散も意識する必要があります。
REITはどこで買えるのか:証券会社とNISA口座
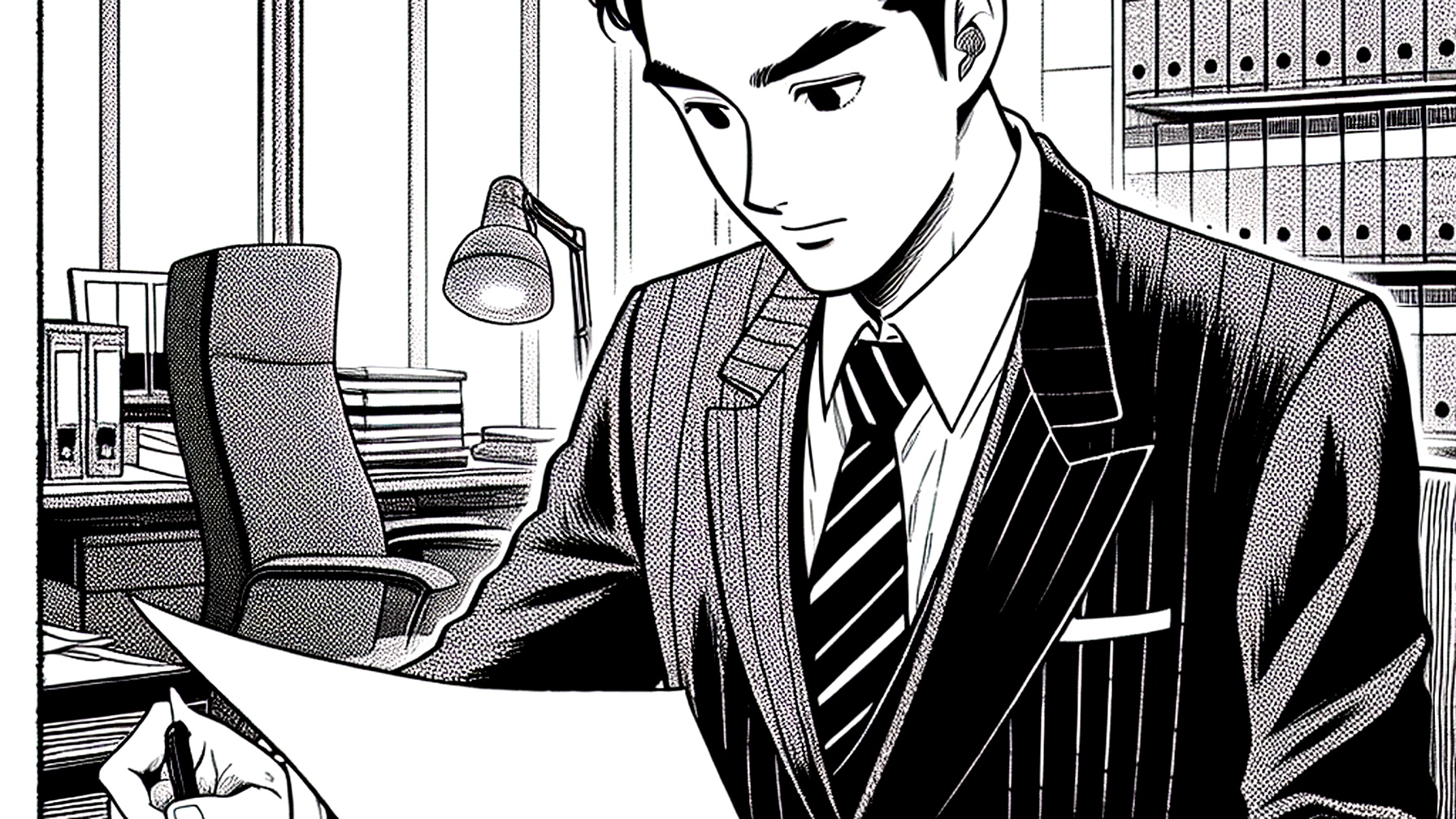
ポイントは、「一般の株式と同じく証券取引所に上場している」という事実です。したがって購入手段は証券会社の口座に集約されますが、2025年度は新NISA制度が2年目を迎えており、口座の種類によって税メリットが大きく変わります。
具体的には、①特定口座(源泉徴収あり)、②一般口座、③NISA口座の三つが代表的です。初心者がまず検討すべきは①と③で、前者は面倒な確定申告が原則不要、後者は年間360万円までの投資枠で分配金と譲渡益が非課税になります。なお、成人年齢到達後なら誰でも開設できる点は株式と同じです。
証券会社選びでは売買手数料と取扱本数が鍵になります。オンライン専業大手は売買手数料0円を打ち出す一方、老舗対面型はアドバイス料を含む手数料が発生します。自分で情報収集できるならネット証券がコスト面で有利ですが、ライフプラン相談まで含めてサポートを受けたい場合は店舗型も検討する価値があります。
どちらにせよ、REIT どこで 税金の疑問を解くには「口座区分」「手数料」「サポート体制」という三つの軸で比較することが出発点になります。
分配金と譲渡益にかかる税金の基本
重要なのは、REITの分配金が法律上「配当所得」に分類され、株式配当と同じく20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収がかかる点です。譲渡益も同率で課税され、特定口座なら売買益と損失を自動で相殺してくれます。
一方で、REITの分配金には「みなし配当」という特殊な性質があります。投資法人が利益の90%以上を分配すると法人税が課税されない仕組みのため、投資家側が負担する税率は実質的には一段と軽く感じられます。ただし税率自体は株式と同一なので、「税金ゼロ」と誤解しないよう注意が必要です。
譲渡益については購入価額と売却価額の差額が計算基礎になります。2025年度税制でも損失の3年間繰越控除が認められているため、含み損を抱えたまま年をまたぐ場合は確定申告で繰越しておくと翌年以降の節税につながります。
このように、分配金と譲渡益は同じ税率ながら計算方法が微妙に異なるため、取引履歴を整理しておくと確定申告で慌てずに済むでしょう。
節税のポイント:新NISAと確定申告の活用
実は、2025年度で最も効果が大きい節税策は新NISA口座の活用です。年間360万円、通算1,800万円の非課税投資枠をREITにも充てられ、分配金と譲渡益が最長無期限で非課税になります。新NISAでは売却しても枠が翌年復活しないため、長期保有前提で高利回りのJ-REITを選ぶ戦略が定番です。
次に検討すべきは確定申告による損益通算です。例えば上場株式で利益が出てREITで損失が出た場合、同じ申告分離課税扱いなので相殺できます。これにより源泉徴収で差し引かれた税金の一部が還付され、手取りが増える効果が得られます。
さらに、所得が一定以下の人が分配金を受け取る場合、総合課税を選択すると配当控除が使えるケースがあります。ただし住民税も含めた税負担を比較しないと逆に税額が上がることもあるため、シミュレーションソフトや税理士に相談しながら判断すると安心です。
最後に、住宅ローン控除や医療費控除など他の所得控除と重ねて申告する際は、証券会社から届く年間取引報告書を紛失しないよう注意しましょう。
国内REITと海外REITでは税金がどう変わるか
まず押さえておきたいのは、海外REIT(ETFを含む)の分配金には現地課税がかかる点です。たとえば米国REITの場合、日米租税条約により現地10%が源泉徴収され、日本での20.315%と合わせて二重課税になります。ただし確定申告で外国税額控除を使えば一部または全部が取り戻せます。
一方、国内REITについては前述の源泉徴収のみで完結します。為替リスクがない分、税金計算もシンプルですが、物件が国内に集中するため地震リスクや人口減少の影響を受けやすいという別の課題があります。
投資対象の分散という意味では、国内と海外REITの組み合わせが望ましいとされますが、税務上の手間を嫌う初心者はまず国内REITをNISA口座で始め、慣れてから海外REITへ広げると負担が少なくて済みます。
このように、投資対象の地域によって税制やリスクが大きく変わるため、「どこで買うか」を検討する際には税務コストと分散効果を同時に考えることが大切です。
まとめ
ここまで、REITをどこで買い、税金をどう抑えるかという視点で見てきました。重要なのは、①証券会社と口座区分を選ぶ段階でコストと税メリットを把握すること、②分配金と譲渡益の税率は同じでも計算方法が違うと理解すること、③新NISAと損益通算を組み合わせれば節税効果が飛躍的に高まることの三点です。まずはネット証券でNISA口座を開き、小口から国内REITを試しながら、翌年以降に海外REITや高リスク商品へ広げるステップが現実的なプランと言えるでしょう。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 財務省「令和7年度(2025年度)税制改正の概要」 – https://www.mof.go.jp
- 金融庁「NISA制度の概要」 – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の税率表」 – https://www.nta.go.jp
- 総務省統計局「家計調査報告」 – https://www.stat.go.jp

