不動産投資に興味はあるものの、「利回りって何が違うの?」「東京ではもう遅いのでは?」と悩む声をよく耳にします。確かにマンション投資は大きな資金が動くため、わずかな数字の違いが将来のキャッシュフローに大きく影響します。本記事では「利回り マンション」をテーマに、基礎の確認から最新データの読み方、さらに利回りを高める具体策まで丁寧に解説します。読了後には、自分で数字を判断し、納得して一歩を踏み出せる視点が手に入るはずです。
利回りとは何か
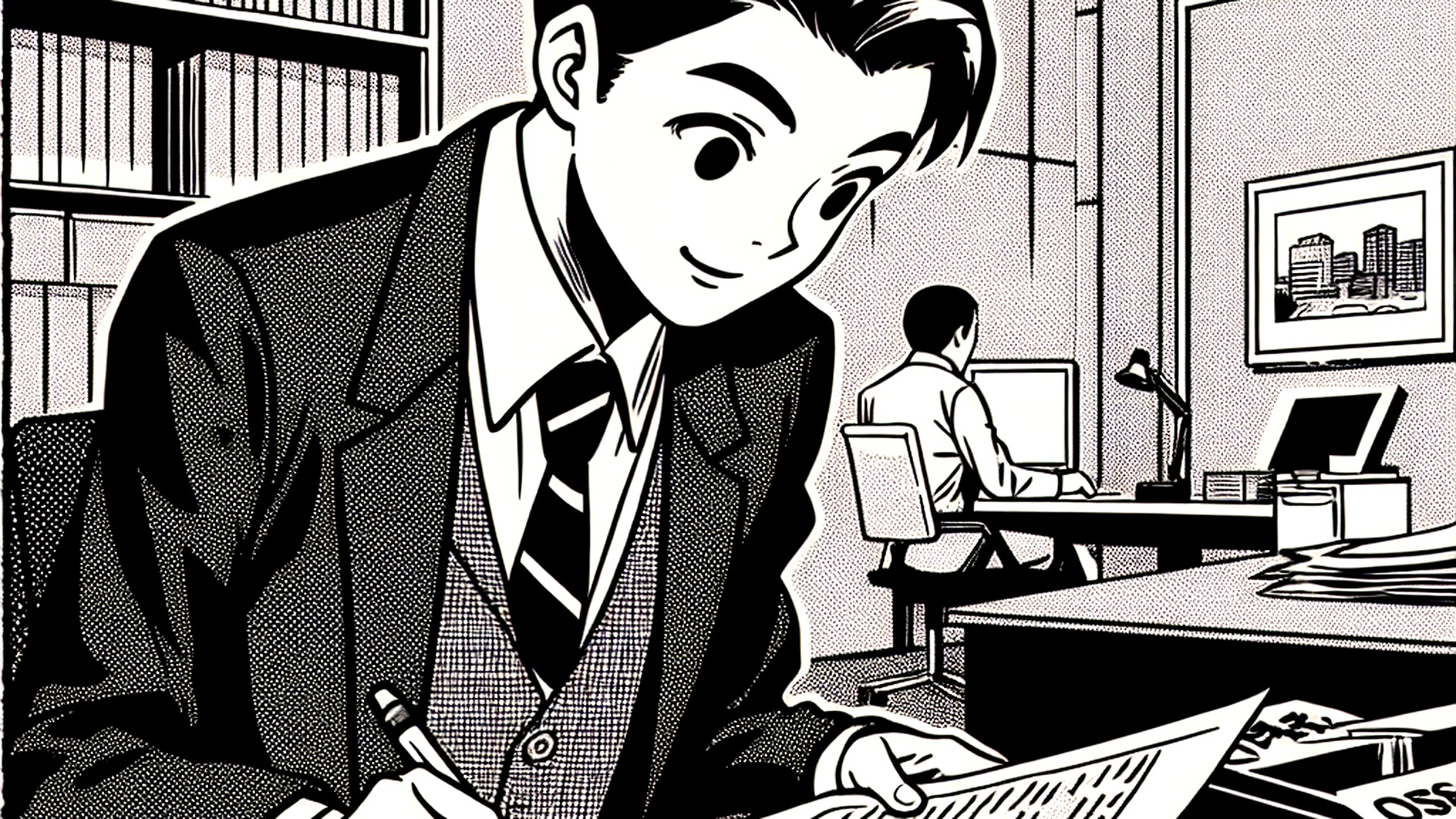
まず押さえておきたいのは、利回りが投資効率を示す指標である点です。利回りは一年間の賃料収入が物件価格に対して何%かを示し、株式でいう配当利回りに近いイメージです。数字が大きいほど収益性は高く見えますが、実際の手取りを示すものではありません。そのため利回りは「目安」であり、鵜呑みにせず背景を読み解く姿勢が欠かせません。
一般的に広告に載るのは表面利回りと呼ばれる指標です。これは年間賃料総額を購入価格で割った単純計算のため、管理費や税金などのコストが含まれていません。つまり、表面利回りだけで投資判断をすると、手取りが想定より下がるリスクがあります。一方で短時間で複数物件を比較できるメリットもあり、入り口としては有効です。
投資家が最終的に見るべきは実質利回りです。こちらは賃料から管理費、修繕積立金、固定資産税などを差し引き、さらに空室リスクも考慮した上で算出します。実質利回りが黒字なら、物件が安定的にキャッシュフローを生む可能性が高いと判断できます。したがって表面利回りを確認したら、コストを丁寧に洗い出し、実質利回りへの落とし込みを行うことが第一歩となります。
表面利回りと実質利回りの違い
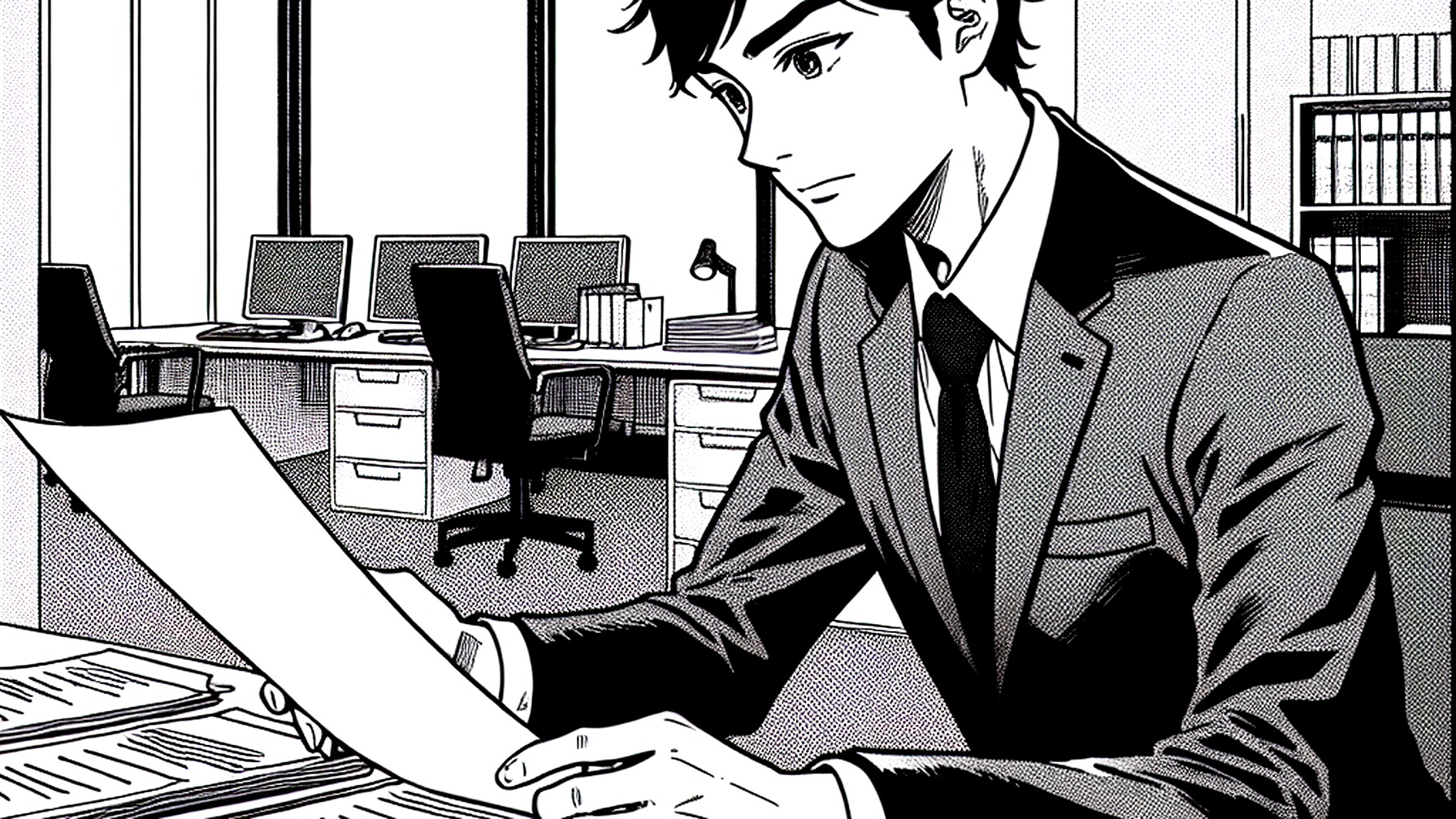
重要なのは、両者の計算方法と目的が異なる点を具体的に理解することです。表面利回りは物件価格と想定賃料だけのシンプルな指標ですから、市場全体を俯瞰する際に有用です。しかし投資プランを詰める段階では、実質利回りを用いなければ手取りを読み誤ります。
実は実質利回りの算出では、空室率の想定が肝になります。例えば東京都心のワンルームは空室率5%前後と言われる一方、郊外では10%を超えるエリアもあります。空室リスクを低く見積もれば数字は良く見えますが、収支が狂う原因にもなるため、敢えて厳しめに設定するほうが安全です。
また、融資を利用する場合は返済額も差し引き、キャッシュフローベースでシミュレーションする必要があります。金利が1%上がるだけで、30年返済では総支払額が数百万円増えるケースもあるため、金利動向を織り込んでおくと安心です。言い換えると、表面利回りが高い物件でも、金利や維持費を差し引くと実質利回りが低下することは珍しくありません。
つまり、表面利回りは第一フィルター、実質利回りは最終判断材料と位置づけると混乱しにくくなります。両者を行き来しながら数値を磨き上げ、自分のリスク許容度に合った水準を見極めましょう。
東京23区の最新利回り動向
ポイントは、市場平均を知ることで自分の投資対象の位置づけを把握できる点です。日本不動産研究所の2025年10月データによると、東京23区の平均表面利回りはワンルームマンション4.2%、ファミリーマンション3.8%、木造アパート5.1%となっています。前年と比べるとワンルームとファミリーはいずれも0.1ポイント下がり、価格上昇の影響が出ています。
背景には23区の新築マンション平均価格が7,580万円へ上昇したことが大きく関係します。不動産経済研究所の報告では前年比3.2%の値上がりで、特に湾岸エリアのタワー物件が価格を押し上げました。価格が上がれば同じ賃料でも利回りは低下しますから、表面利回りの数字だけを追うと割安感がないように映るでしょう。
一方で賃料相場は2024年以降、都心部を中心に再び緩やかな上昇傾向にあります。テレワーク定着後もオフィス回帰が進み、単身者の都心居住ニーズが戻ったためです。この賃料の底堅さは、実質利回りを支える要素となります。つまり表面利回りが横ばいでも、空室リスクの低さや将来の賃料上昇余地を加味すると、都心物件の実質収益性は意外に高い場合があります。
しかし、郊外や地方都市では賃料が伸び悩むケースもあり、利回りの平均値だけで判断するのは危険です。地域ごとの人口動態や再開発計画、交通インフラの動きをチェックし、エリア別の需給バランスを読むことが欠かせません。
利回りを高める物件選びと運営
まず押さえておきたいのは、利回りは購入時点だけでなく、運営で上げる余地があるという事実です。物件選びの段階では、築年数と修繕履歴、周辺の賃貸需要を丁寧に確認します。築浅物件は修繕コストが抑えられる反面、価格が高く利回りが低くなりがちです。一方で築古物件は取得費を抑えられますが、大規模修繕が近いかどうかで実質利回りが大きく変わります。
購入後に利回りを向上させるには、差別化戦略が有効です。たとえば、スマートロックの導入や共用部Wi-Fiの無料提供は、コストを抑えながら賃料アップを実現した成功例があります。また、短期賃貸ニーズが強いエリアで家具付きプランを用意すると、表面利回りが1ポイント高まった事例も報告されています。小さな改善の積み重ねが、長期的なキャッシュフローの安定につながります。
さらに、管理会社の選定も利回りに直結します。管理手数料が同じでも、リーシング力の差で空室期間が大きく変わり、結果として年間収入に差が生まれます。管理会社の実績や担当者の提案力を比較し、定期的な打ち合わせでデータを共有して改善策を探る姿勢が大切です。
最後に出口戦略も視野に入れましょう。築年数が進むほど修繕費は増え、利回りが低下します。適切なタイミングで売却すれば、キャピタルゲイン(値上がり益)とインカムゲイン(賃料収入)のバランスを最大化できます。市場価格が高いうちに出口を確保できれば、次の投資へスムーズに資金を回せます。
2025年度の税制・融資を味方にする
実は制度をうまく活用することで、実質利回りを底上げできます。2025年度の税制では、住宅ローン減税の投資用適用はありませんが、個人が取得した賃貸マンションの減価償却費は従来通り経費計上が可能です。耐用年数を過ぎたRC造(鉄筋コンクリート)の中古物件なら、短い償却期間を選択でき、初期数年間の課税所得を大きく圧縮できます。
また、青色申告を行い65万円の特別控除を受ければ、所得税と住民税の負担が軽減されます。さらに赤字が生じた場合は給与所得との損益通算も可能なため、手取りベースの利回り改善に役立ちます。帳簿付けは手間ですが、クラウド会計を使えば作業時間を半分以下にできるため、費用対効果は高いと言えます。
融資面では、2025年度も日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」や一部地方銀行が投資用マンション向けに最長35年・金利1.2%前後の固定プランを提供しています。自己資金を2割以上入れることで審査が通りやすく、金利引き下げ幅も大きくなる傾向があります。金利が低い局面で長期固定を確保できれば、将来の金利上昇リスクを抑え、実質利回りの安定化に直結します。
ポイントは、税制と融資のメリットを受けたうえで、空室リスクを抑える戦略を同時に講じることです。この両輪がかみ合えば、同じ表面利回りでも手取りは大きく変わり、長期保有の安心感が高まります。
まとめ
利回りはマンション投資の羅針盤であり、表面・実質の両方を理解してこそ精度の高い判断ができます。東京23区の平均値は下がり気味でも、賃料の底堅さと制度活用で実質利回りを伸ばす余地は十分あります。物件選びでは立地と修繕履歴を吟味し、購入後は差別化と適切な管理で収益を底上げすることが肝心です。最後に税制と低金利融資を組み合わせれば、数字だけでは見えない安定感が手に入ります。まずは気になるエリアの空室率と家賃相場を調べ、シミュレーションを作ってみましょう。行動を起こすことで、数字の意味が具体的に見えてくるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国税庁「所得税法令解釈通達」 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 不動産市場動向レポート2025年10月 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫「融資制度のご案内2025年度版」 – https://www.jfc.go.jp

