不動産投資に興味はあるものの、いきなり現物を買うのは資金的に不安という声をよく聞きます。そこで候補に挙がるのが少額から参加できるREIT(不動産投資信託)ですが、「株より値動きが穏やか」と聞いていたのに意外と損をした、という相談が後を絶ちません。本記事では、実際の体験談を交えつつREITのデメリットを深掘りし、2025年10月時点で押さえておきたいリスク管理法を解説します。これを読むことで、初心者でも失敗を減らし、長期で安定収益を目指す具体的な手順をつかめるはずです。
REITの基本と株式との違いを整理する
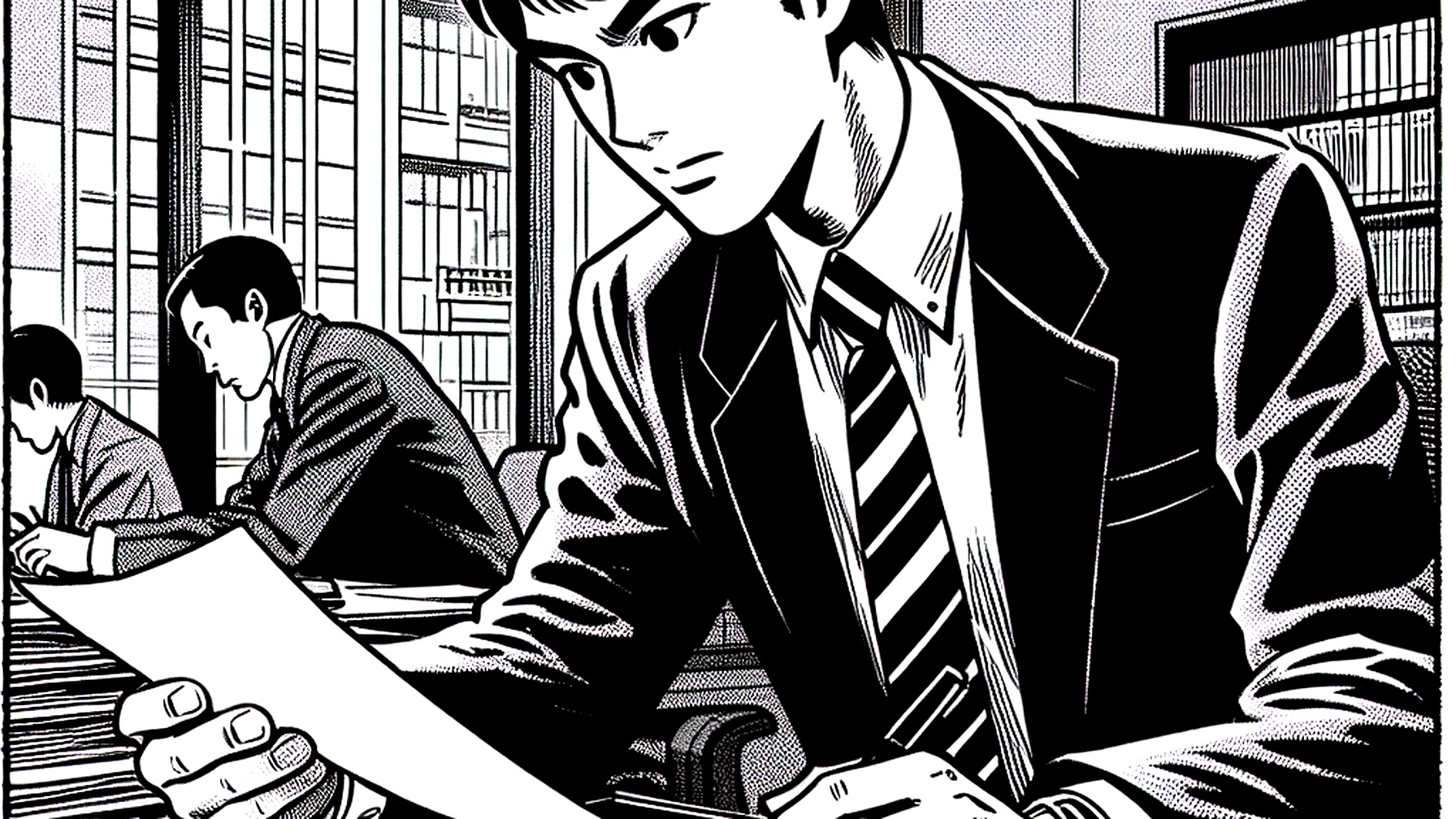
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を裏付けとしながらも、取引の仕組みは株式とほぼ同じという点です。証券取引所で売買されるため価格はリアルタイムに変動し、分配金は配当のように現金で受け取ります。一方でREITは法令により利益の九割超を分配しなければ法人税が免除されるため、内部留保が極めて少ないという構造的な特徴があります。つまり安定して見えても、景気後退時に備える余力が薄い点が株式との大きな違いです。
実際、国土交通省「不動産投資市場動向調査2025」によれば、上場J-REITの平均自己資本比率は約五〇%で、上場企業平均の六〇%より低くなっています。この数字は一見健全に思えますが、賃料収入が減った際のクッションが小さいことを示唆します。また、J-REIT指数は過去十年で年率七%程度のリターンを示したものの、コロナ禍直後の最大下落率は三五%に達しました。値動きが穏やかとされる背景には大型オフィスや住宅などの実物資産がある一方、流動性の高さがボラティリティを引き上げる側面も見逃せません。これが体験談でよく語られる「思ったより上下が激しい」という感想につながっています。
体験談に見る価格変動リスクの実態
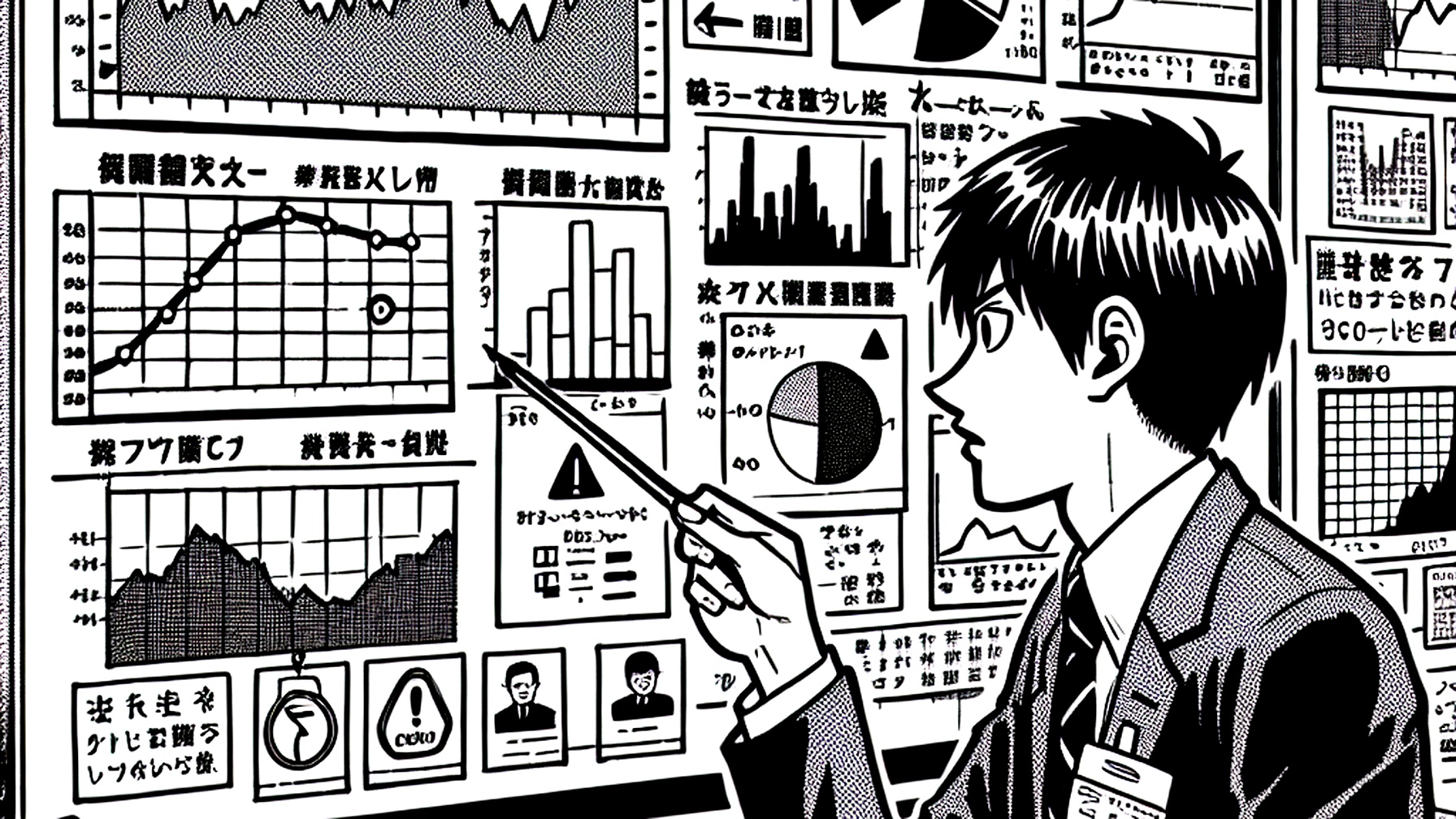
ポイントは、価格変動を甘く見ると短期で資金が拘束される恐れがあることです。筆者のコミュニティでは、二〇二三年春にJ-REIT投資を始めたAさんがいます。上昇相場に乗り一割の含み益を得たものの、二四年の金利上昇観測で基準価額が急落し、売り時を逃して一時二五%近い含み損を抱えました。Aさんは「分配金をもらいながら待てばいい」と考えましたが、心理的負担は想像以上で、最終的に損切りして退場しています。
実はこのケース、長期投資を前提にしたなら損失を回避できた可能性があります。日本取引所グループのデータでは、J-REIT指数は下落後二年以内に八割以上の確率でピーク水準を回復しています。しかし人は損失を抱えると行動が保守的になり、必要以上に早く売却しがちです。つまりREIT デメリット 体験談が示す本質は、価格変動そのものよりも投資家の感情コントロールの難しさにあります。適切な投資期間を決め、余裕資金で運用する仕組みが不可欠です。
分配金減少とキャッシュフローへの影響
重要なのは、分配金が将来も一定とは限らないという現実です。REITは賃料収入を原資とするため、空室率や賃料水準に直結します。日本不動産研究所「市況予測2025」によると、大都市オフィス空室率は二五年四月時点で五%台に落ち着いていますが、物流施設の一部では新規供給過多で一〇%超に達するエリアもあります。空室が増えると分配金は直ちに減り、利回りが低下します。
Bさんの体験では、物流特化型REITに集中投資していたところ、二四年後半に分配金が一七%カットされました。Bさんは生活費の一部を分配金で賄っていたため、家計が急に苦しくなったと語っています。このように、分配金を生活資金に組み込むと、減配がそのまま家計リスクになります。言い換えると、分配金は固定収入ではなく、景気や需給に応じて変わる変動給です。分配金依存度を下げ、再投資で複利効果を狙う方が堅実でしょう。
物件価値とREITの財務健全性を見抜く
まず押さえておきたいのは、REITが保有する物件の資産価値と負債構成をチェックする習慣です。金融庁「ディスクロージャー制度2025」により、REITは運用報告書でLTV(負債比率)や平均賃料などを公開しています。専門用語ですが、LTVとは物件価値に対しての借入金割合を示し、数値が高いほど金利上昇時の負担が重くなります。
Cさんの体験談では、住宅系REITのLTVが六〇%前後まで上がっていることに気づかず保有を続けた結果、二四年の政策金利引き上げで借入コストが急増し、分配金が三割近く減りました。資料を読めば予想できた減配を見落としたと悔やんでいます。逆に、インフレ局面で賃料改定が進みやすい物流REITやホテルREITは、適度なLTVであれば収益機会が広がる可能性があります。つまり財務指標を定期的に確認し、金利と賃料のバランスを見極める姿勢がリスク管理の核心です。
デメリットを補うための実践的ポートフォリオ戦略
実は、REITの弱点は組み合わせで緩和できます。筆者は自らのポートフォリオで、REITを最大でも総資産の三割にとどめ、残りを個別株、国内債券、米国ETFに分散しています。この結果、過去十年で最大下落率は一五%程度に抑えられ、分配金減配時も株式配当や債券利息で補填できました。
また、同一セクターへの集中を避け、オフィス、住宅、物流、商業施設、ホテルの五分類に分散する方法も有効です。日本銀行「金融システムレポート2025」によると、セクター間の相関係数は〇・六前後で完全に連動するわけではありません。さらに、分配金の再投資設定を使うことで、景気後退期に口数を自動的に増やし、回復局面のリターンを底上げできます。
結論として、REIT単体のデメリットはゼロにできなくても、資産配分と再投資を組み合わせれば長期的には十分コントロール可能です。投資開始前に余裕資金かどうかを確認し、体験談で指摘された心理的ハードルを下げる準備が成功の鍵になります。
まとめ
ここまで、REIT デメリット 体験談を通じて値動き、減配、財務リスクという三つの落とし穴を見てきました。重要なのは、これらが仕組み上の宿命であり、感情と情報不足が損失を拡大させる点です。価格変動に動じない資金計画とLTVチェック、そのうえで分散と再投資を徹底すれば、REITは手軽で効率的な資産形成ツールへと変わります。今日紹介した視点を実践し、自分自身の体験談を「成功例」に変えてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場動向調査2025 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ J-REIT市場データ – https://www.jpx.co.jp
- 日本不動産研究所 市況予測2025 – https://www.reinet.or.jp
- 金融庁 ディスクロージャー制度2025 – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025 – https://www.boj.or.jp

