独立して事業を営むと、売上は好調でも「収入が安定しない」「税負担が読みにくい」といった悩みがつきまといます。そこで注目したいのが不動産投資です。家賃収入は毎月の固定収入をつくり、減価償却などの仕組みを活用すれば課税所得を抑えることもできます。本記事では、個人事業主だからこそ活かせる資金調達術や節税策、2025年10月時点で有効な制度を整理しながら、失敗しない物件選びまでを体系的に解説します。読み終えるころには「おすすめ 個人事業主」視点で取るべき具体的なアクションがイメージできるはずです。
個人事業主と不動産所得の相性を理解する
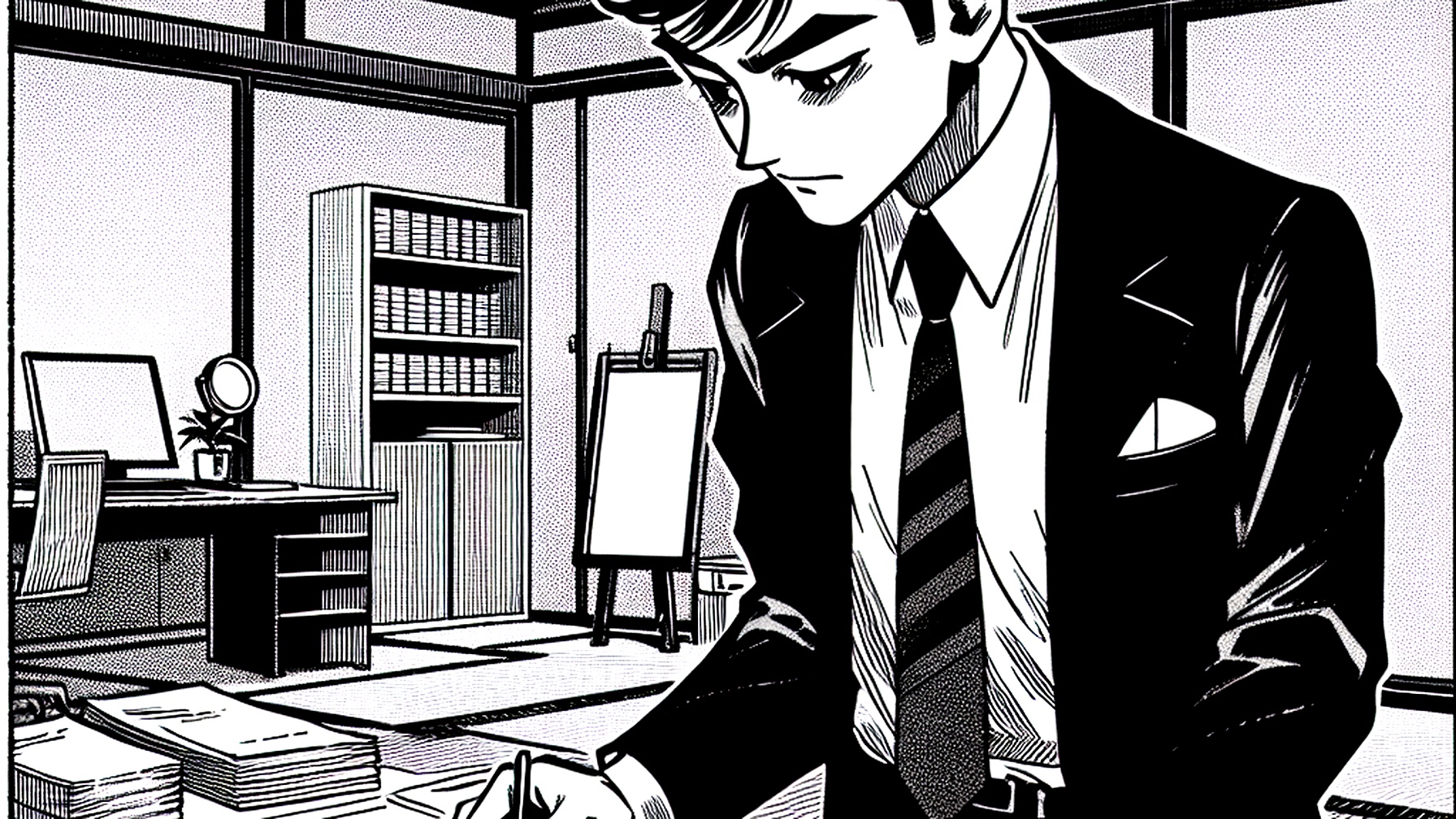
まず押さえておきたいのは、不動産投資による家賃は「不動産所得」として事業所得とは別に区分される点です。国税庁のガイドによれば、不動産所得と事業所得は損益通算が可能で、赤字が出た場合には本業の黒字と相殺できます。つまり収入が変動しやすい個人事業主にとって、不動産はキャッシュフローと税務の両面でバランスを取る役割を果たします。
一方で、空室や修繕費が想定より増えれば赤字が続くリスクもあります。この点について総務省「住宅・土地統計調査」(2023年速報値)は全国の空き家率を13.8%と示しており、エリア選びを誤れば計画は容易に崩れます。また、金融機関は事業主の与信を事業所得と合わせて審査するため、記帳や納税を疎かにすると融資条件が不利になる恐れがあります。
重要なのは、不動産事業を「副業」ではなく「もう一つの本業」と位置づけ、収支計画と帳簿管理を本業と同水準で行うことです。そうすることで、金融面でも税務面でも最大限のメリットを享受できる土台が整います。
資金調達で差がつくポイント
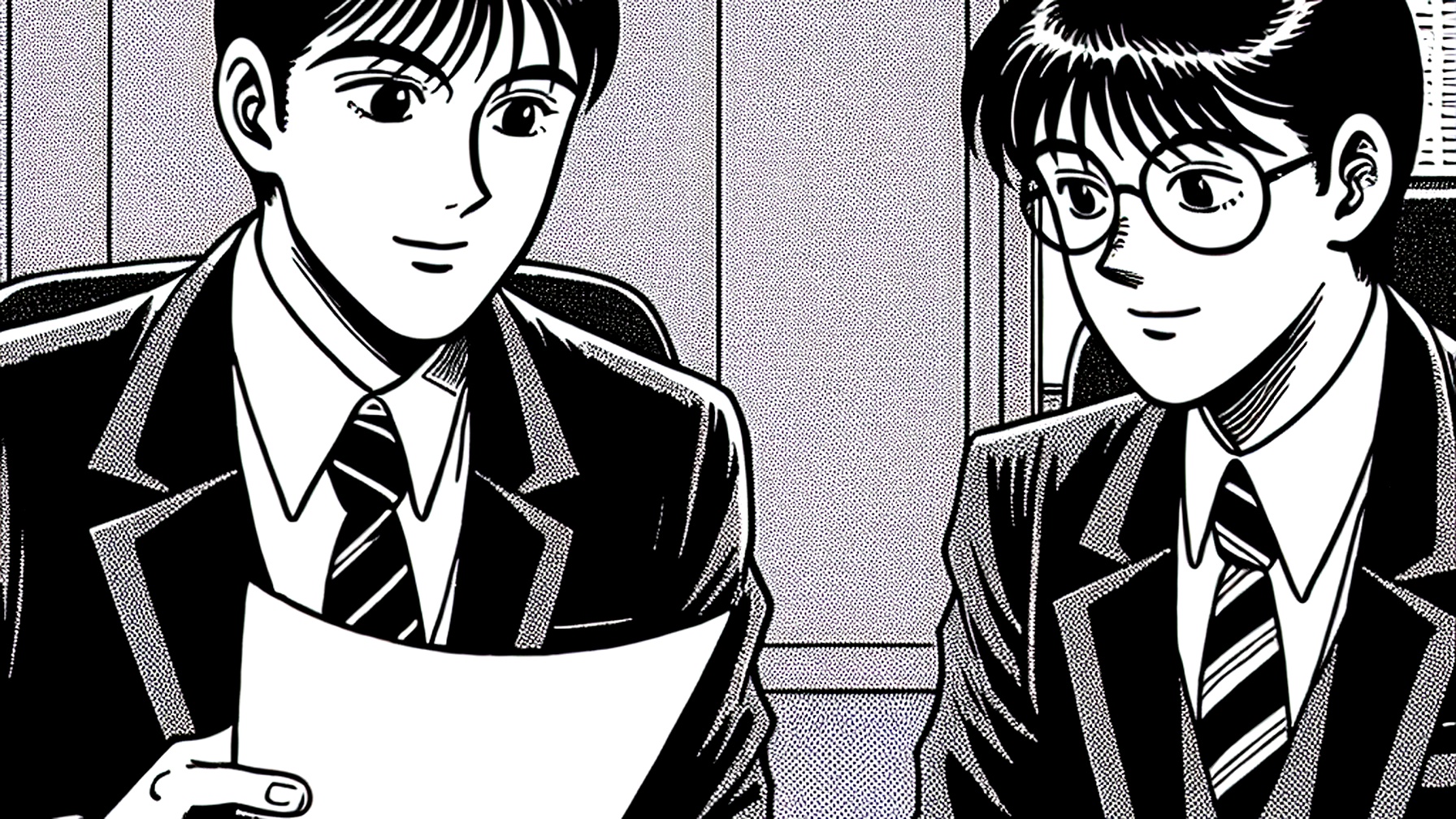
実は、個人事業主が不動産融資を受ける際に最も重視されるのは、過去3期分の確定申告書と事業実績です。銀行は「安定したキャッシュフロー」と「納税姿勢」を信用の物差しにしています。したがって、青色申告を採用し、月次で試算表をまとめておくと審査が格段にスムーズになります。
さらに、2025年10月現在は民間金融機関に加え、日本政策金融公庫が「生活衛生貸付」の枠組みで不動産賃貸業向けの融資を行っています。金利は固定で年2%台と民間よりやや高めですが、自己資金が少ない初期段階でも利用しやすい特徴があります。将来的に金利負担を軽減したい場合は、公庫で実績を積んでから都市銀行へ借り換える二段構えが効果的です。
また、自己資金は物件価格の20~30%を目安に準備したいところです。金融庁の「金融モニタリング結果」(2024年)では、自己資本比率が20%を下回る投資家は返済負担率の上昇時に延滞リスクが高まる傾向が示されています。手元資金に余裕を持たせることで、急な修繕や空室期間にも耐えられる体力が生まれます。
法人化と比較した個人事業主のメリット
ポイントは、規模が小さいうちは「おすすめ 個人事業主」の形態で始める方がシンプルでコストも低いという事実です。法人を設立すると節税余地は広がりますが、設立費用と毎年の決算・税務申告コストが発生します。家賃収入が年間1,000万円未満なら、個人事業主の青色申告特別控除65万円(2025年度)を活用する方が手取りが多くなるケースが珍しくありません。
もう一つの利点は、損益通算により本業の利益を圧縮できることです。法人の場合は不動産と本業が別会社になるため通算できず、この点で個人が有利になります。ただし、所得が900万円を超えるあたりから累進税率が一気に高まるため、物件数が増えて利益が読める段階で法人化を検討するとバランスが取れます。
言い換えると、個人事業主→合同会社→株式会社の順にステップアップする戦略が王道です。最初はシンプルな青色申告で経験と資金を蓄え、規模拡大のタイミングで法人化していく流れが、実務上も心理的にも負担が小さい方法といえます。
節税と2025年度の関連制度
まず押さえておきたいのは、減価償却費を活用した所得圧縮です。木造アパートなら耐用年数22年が基準で、築古物件を購入すれば短い期間で大きく費用計上できます。国税庁の「耐用年数表」では、築年数が経過した分だけ償却期間を短縮できるため、手取りキャッシュを残しやすくなります。
加えて、青色申告特別控除65万円と専従者給与を組み合わせることで、家族への給与支払いを経費化できます。2025年度もこの仕組みは継続しており、届出を行えば年間103万円以内の配偶者給与は配偶者側の所得税もゼロに抑えられます。また、小規模企業共済への加入は掛金全額が所得控除となり、将来の退職金準備にもつながります。
なお、エネルギー価格高騰への対策として国土交通省が2025年度も継続する「住宅省エネ改修減税」は、省エネ性能向上を目的とした改修費用の10%(上限250万円)が所得税額から控除される仕組みです。投資用物件でも入居者サービス向上と節税を両立できるため、古い物件を購入後に断熱改修を行う戦略は検討に値します。期限は2026年12月31日完了工事までと発表されていますので、スケジュール管理が欠かせません。
物件選びと運営の実践的アドバイス
重要なのは、立地と賃料設定のバランスです。国土交通省「不動産価格指数」(2025年6月公表)では、地方中核都市の中古マンション価格が前年同月比で8.1%上昇しており、一方で賃料指数は4.3%の伸びにとどまっています。価格が先行して上がったエリアでは利回りが低下しやすいので、購入前に周辺の成約賃料を徹底的に比較する必要があります。
また、管理体制によって収益は大きく変わります。入居者アプリやスマートロックを導入するクラウド管理会社を活用すれば、問い合わせ対応や鍵交換の手間が減り、オーナー業務を効率化できます。空室募集においても、仲介会社任せにせずネット広告の写真やコピーを自らチェックすることが、募集速度を上げる近道です。
最後に、運営開始後はキャッシュフロー表を毎月更新し、目標利回りとの差異を分析しましょう。家賃値下げや追加投資が必要かどうかを早期に判断でき、資金ショートのリスクを減らせます。ここでも本業で培ったPDCAサイクルをそのまま転用すれば、大きな失敗を回避できます。
まとめ
今回は「おすすめ 個人事業主」の視点から、不動産投資の基本から節税、物件運営までを網羅しました。青色申告と減価償却を活用すれば、キャッシュを残しながら税負担をコントロールできます。さらに、公庫融資や省エネ改修減税など2025年度に利用できる制度を組み合わせることで、自己資金を効率よくレバレッジできます。まずは本業の財務管理を整え、無理のない自己資金と収支計画を立てることが第一歩です。安定収入と将来の資産形成を同時にかなえるために、本記事を参考に行動を始めてみてください。
参考文献・出典
- 国税庁 https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 https://www.stat.go.jp
- 金融庁 金融モニタリング報告 https://www.fsa.go.jp
- 日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp

