突然の相続が発生したとき、評価額の高い土地や自宅だけを残すと、相続税の負担が重くなりがちです。そこで注目されるのが「アパート経営 相続対策」という選択肢ですが、空室リスクや資金繰りが不安で踏み出せない人も少なくありません。本記事では、2025年9月時点で有効な制度や最新データを踏まえつつ、アパート経営がどのように相続税を抑え、家族の暮らしを守るのかを基礎から丁寧に解説します。読み進めることで、評価減の仕組みからキャッシュフローの管理方法まで、実践に役立つポイントが体系的に理解できます。
相続税と不動産評価の基本を押さえる
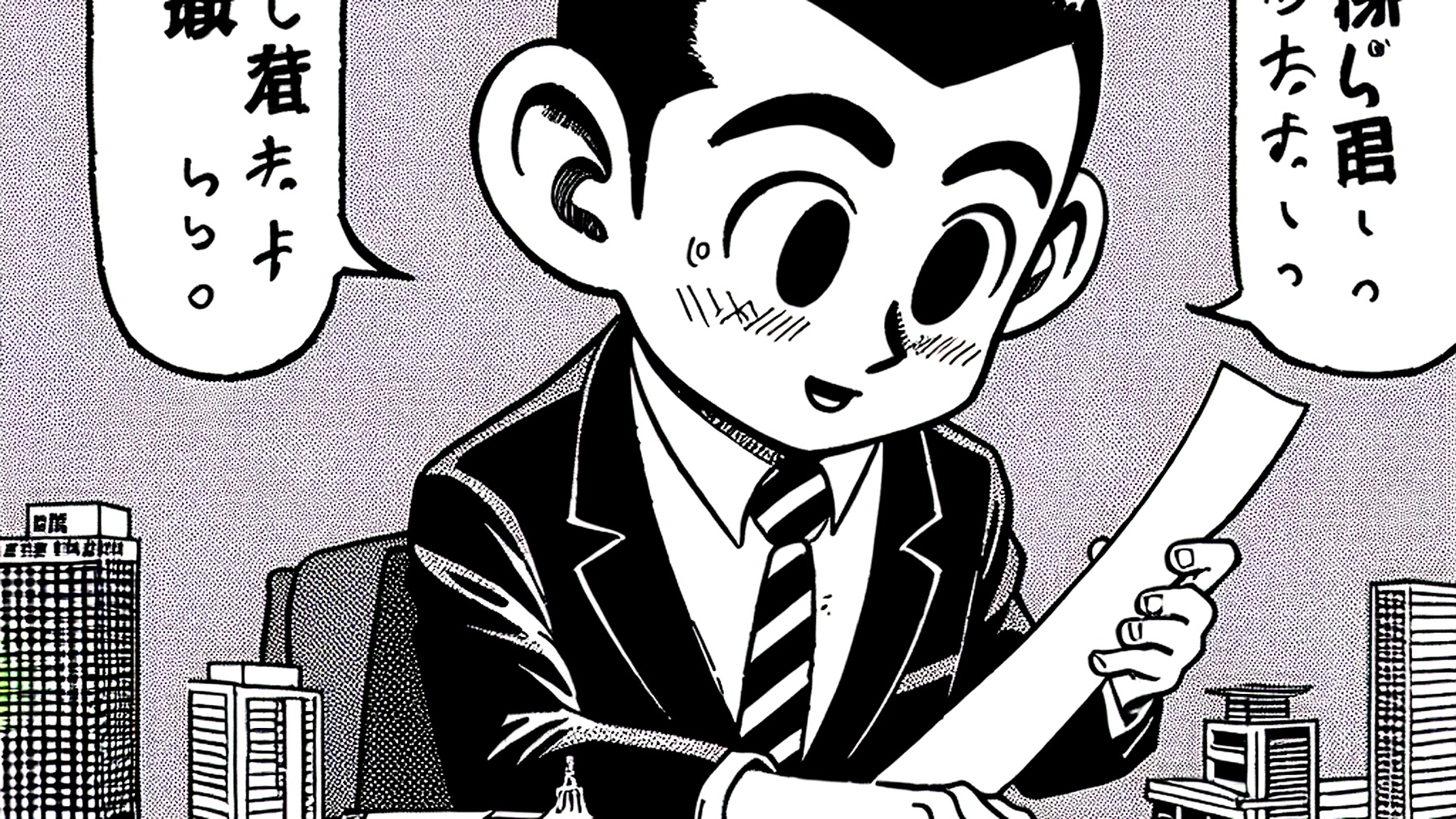
重要なのは、相続税が「時価」ではなく「相続税評価額」を基準に計算される点です。土地は路線価、建物は固定資産税評価額を用いるため、実際の市場価格より2〜3割低くなることが一般的です。ここにアパートを建築すると建物の評価額がさらに下がり、土地も貸家建付地(かしやたてつけち)として約20%評価減される仕組みが働きます。
また、家賃収入を生む建物は「貸家」として区分され、建物評価額から30%の控除が適用されるため、合計で40%以上の評価減が見込めるケースも珍しくありません。つまり、同じ土地でも更地よりアパートを建てた方が相続税の課税対象となる額を大きく圧縮できます。ただし、評価が下がる一方で借入金が増えるため、返済計画まで含めた総合設計が欠かせません。
国税庁の2024事務年度統計では、相続税の課税割合は9.6%と過去最高水準が続いています。課税対象者が増えるなか、不動産を活用した評価減の効果は年々重要度を増していると言えるでしょう。
生前に仕込む評価減のテクニック
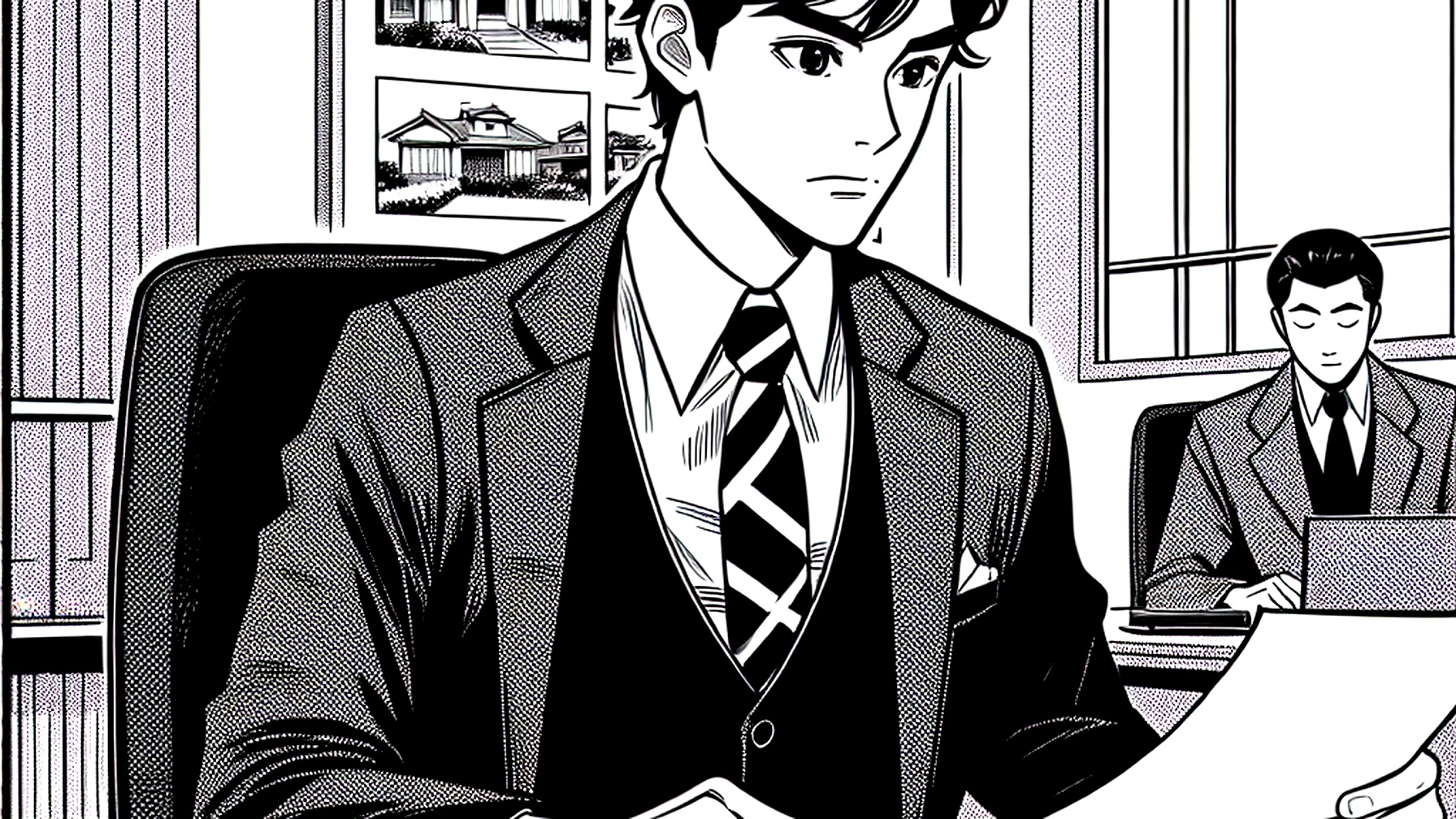
ポイントは、建物を完成させるタイミングと持ち分の分散方法を早めに決めることです。建物は「建築中」の段階でも課税上は未完成物件として評価され、完成後より約30%低い価額で固定されるケースがあります。相続が近いと感じた際には、着工時期を意識するだけで節税効果が大きく変わる可能性があります。
さらに、親世代が全額借入をして建築し、子ども世代に土地の一部持ち分を移しておくと、将来の遺産分割協議がシンプルになります。このとき贈与税の基礎控除や暦年贈与を組み合わせれば、年間110万円まで非課税で移転できるため、長期計画で少しずつ土地の共有化を進める手法が有効です。
一方で、共有名義は賃貸経営の意思決定を複雑にする側面もあります。賃料改定や大規模修繕の判断が遅れると収益性が下がるため、家族間で議決ルールや代表者を決めておくことがトラブル回避の鍵となります。
キャッシュフローが相続後の家計を守る
まず押さえておきたいのは、相続税を減らせてもアパートが赤字では本末転倒という点です。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年から0.3ポイント改善していますが、地方の小規模市場では30%を超える地域もあります。空室率が貸付事業用宅地の特例適用要件に直接影響しなくても、ローン返済に支障が出れば相続対策どころではありません。
家族信託を活用すれば、親が判断能力を失った場合でも受託者である子が修繕や入居付けの決定を行え、キャッシュフローの停滞を防げます。また、生命保険金を借入金の一部に充当する設計にしておくと、相続開始後の返済負担が急に軽くなり、家賃を生活費に回しやすくなる仕組みが作れます。
つまり、評価減と同時に安定収入を確保する二段構えが家族を守る最善策です。収支計画を作成する際は、空室率15%、金利上昇1.5%のシナリオでも毎月の手残りが黒字になるかを試算し、保守的に設計しましょう。
2025年度に使える融資・税制優遇の最新事情
実は、2025年度も住宅金融支援機構の「賃貸住宅建設融資」は金利優遇枠が継続しています。省エネ基準に適合する新築アパートであれば、固定金利を年0.3%引き下げる制度が適用でき、長期安定経営に寄与します。さらに、地方公共団体によっては空き家対策と連動した「賃貸住宅供給促進補助金」(例:埼玉県2025年度は最大200万円)が利用可能です。ただし、申請期間が年度内に限定されるため、建築スケジュールと合わせて逆算が必要です。
税制面では、小規模宅地等の特例が2025年度も存続し、貸付事業用宅地の場合は最大200㎡まで50%評価減が受けられます。併せて、登録免許税の軽減措置(新築から1年以内の保存登記が0.15%)も継続中です。こうした制度は告知なく改正されることが多いため、着手前に税理士や行政窓口で最新要件を確認する習慣をつけましょう。
専門家チームを組むメリット
ポイントは、建築会社だけに任せず、税理士、司法書士、賃貸管理会社を含むチーム体制を構築することです。税理士は土地の有効活用プランと相続税評価をリンクさせ、司法書士は生前贈与や家族信託の契約書を作成し、管理会社は市場調査と賃料設定で空室リスクを抑えます。役割を明確に分担すれば、意思決定のスピードと質が飛躍的に向上します。
さらに、複数の専門家を同席させた定期ミーティングを行うことで、法改正や金利動向に即応できる点も見逃せません。例えば、固定資産税が3年ごとに評価替えされるタイミングで賃料の改定案を同時に検討するなど、部門横断の意思決定が可能になります。家族を交えた場で議論すると、世代を超えた事業承継の意識も自然と高まります。
専門家報酬はコストではなくリスクヘッジの保険料と捉えると、長期的には家族の安心感とトラブル回避効果で十分に元が取れるはずです。
まとめ
アパート経営を組み込んだ相続対策は、評価額を下げる「防御」と家賃収入を生む「攻撃」を両立させる戦略です。土地に対する貸家建付地評価や建物の貸家評価を活用すれば、相続税を大きく圧縮できますが、安定経営には空室率や金利上昇を見込んだキャッシュフロー管理が欠かせません。2025年度も続く融資・税制優遇を賢く使い、家族信託や保険でリスクを抑えつつ、専門家チームと共に長期計画を立てることが成功の近道です。今日からできる第一歩として、現状の土地評価とローン残高を整理し、家族と将来像を話し合ってみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 国税庁「令和6事務年度 相続税の申告事績」 – https://www.nta.go.jp/
- 国土交通省 住宅統計調査「2025年7月賃貸住宅市場動向」 – https://www.mlit.go.jp/
- 住宅金融支援機構「賃貸住宅建設融資のご案内 2025年度版」 – https://www.jhf.go.jp/
- 埼玉県都市整備部「2025年度 賃貸住宅供給促進補助金」 – https://www.pref.saitama.lg.jp/
- 総務省「固定資産税評価基準のあらまし 2024改訂」 – https://www.soumu.go.jp/

