不動産価格の高騰で「現物には手が届かない」と感じる方でも、REITなら少額からプロ並みの運用に参加できます。しかし仕組みを誤解したまま買えば、価格変動や分配金の減額で後悔しかねません。本記事ではREITの基礎から2025年の最新市場動向、税制優遇までを丁寧に解説します。読み終えたとき、あなたはリスクとリターンを数値で判断し、自分に合った投資プランを描けるようになるはずです。
REITとは何か、その魅力を正しく理解する
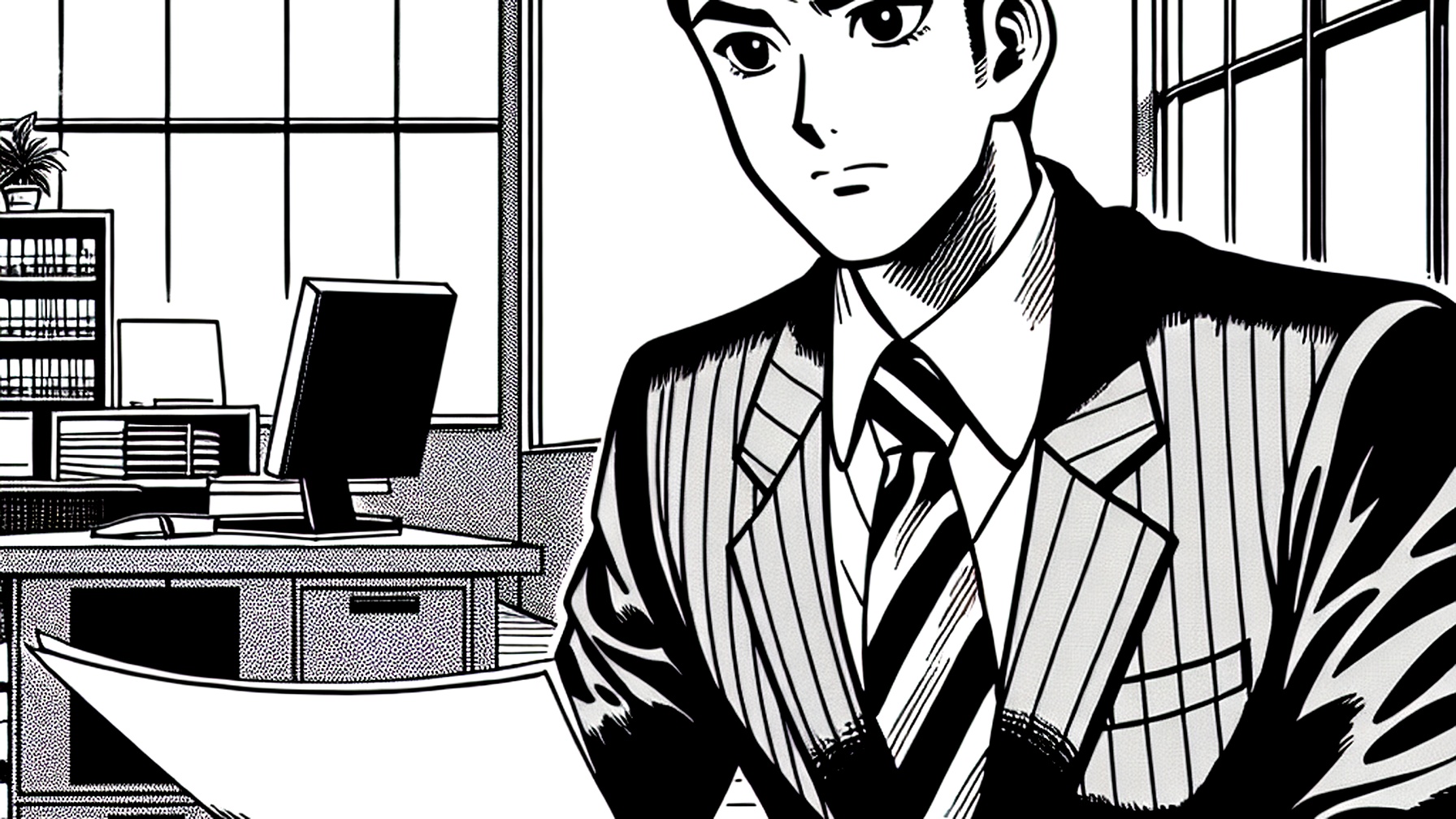
まず押さえておきたいのは、REIT(Real Estate Investment Trust)が投資家から集めた資金で複数の不動産を保有・運営し、賃料や売却益を分配する仕組みだという点です。上場REITなら株式と同じ証券取引所で取引でき、1口数万円から購入できます。これにより個人でも大型オフィスビルや物流施設のオーナー収益を享受できるのが大きな魅力です。
次に注目すべきは、税制上のメリットです。投資法人は利益の90%以上を分配すれば法人税が実質免除されるため、投資家は手取り利回りの高い分配金を受け取れます。また、国土交通省のデータによると2024年度の平均分配利回りは3.8%で、10年国債利回り(1.3%前後)を大きく上回っています。つまりインカムゲインを重視する投資家にとって、REITは安定した選択肢になりやすいわけです。
さらに、日銀のマネタリーベース拡大とGPIFの国内REIT組み入れ比率上限引き上げ(2023年実施)が流動性を押し上げ、市場規模は2025年7月末時点で約22兆円に達しました。流動性が高いということは、売買したいタイミングで約定しやすく、機動的な資金管理が可能になるということです。
2025年の市場動向と利回りのリアル
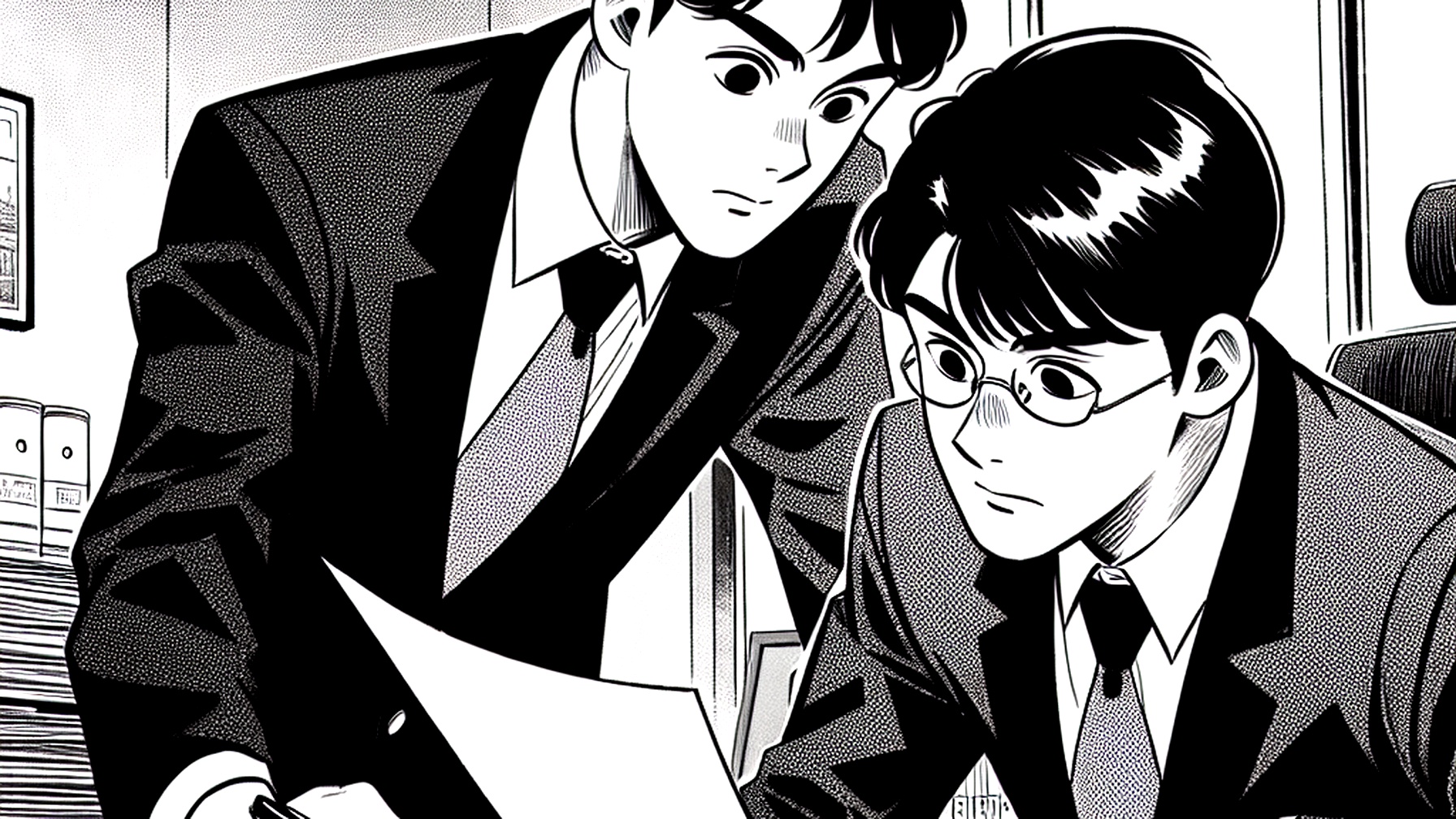
重要なのは、表面的な利回りではなく、分配原資となる賃料動向と空室率のトレンドを把握することです。日本取引所グループが公表した2025年上期データによれば、オフィス系REITの平均分配利回りは3.5%、物流系は3.9%、住宅系は3.4%でした。これだけを見ると物流系が優位に見えますが、背景にある賃料インデックスの伸びを合わせて読む必要があります。
たとえば東京23区Aクラスオフィスの空室率は2024年の6.0%から2025年6月には4.8%へ改善しています。これはコロナ禍後のオフィス需要回復が続いている証拠で、オフィス系REITの分配安定性を下支えします。一方、物流施設はEC需要が成熟し成長率が鈍化傾向にあり、新規供給増が賃料水準を抑えています。利回りが高めでも、今後のキャピタルゲインは限定的かもしれません。
住宅系は人口減少を背景に地方では弱含むものの、都心の単身向け需要が底堅く、家賃水準は前年比1.2%の上昇です。したがってエリア分散の意義が高まっており、ポートフォリオの中で住宅系を補完的に使う投資家が増えています。加えてホテル系REITはインバウンド客数が2019年比112%まで回復し、客室単価の上昇が追い風になっていますが、景気後退時のブレも大きいため比率を抑えるのが無難でしょう。
個人投資家が避けたい三つのリスク
ポイントは、値動きが株式市場のセンチメントに左右されやすい点です。REITは実物不動産よりも金利上昇に敏感で、長期金利が0.25%上がると価格が3~5%下落するケースが過去にありました。したがって日本銀行の金融政策変更や米国金利動向のニュースには常に目を配る必要があります。
また、物件の集中リスクにも注意が必要です。上場REITの中には特定エリアや用途に偏ったポートフォリオを持つ銘柄があり、災害や規制強化が直撃すると短期で分配金が減少する恐れがあります。投資信託協会の資料では、用途分散が進む銘柄ほどコロナショック時の価格回復が早かったと示されています。
三つ目は流動性の落とし穴です。市場全体の売買代金が一時的に細ると、中小型REITは板が薄くなり、数千口の成行注文でも価格が大きく動く場面があります。板状況を確認せずに大口で売買すれば意図しないスリッページを被るため、売買は分割発注が基本です。
購入と売却のタイミング戦略
まず押さえておきたいのは、分配金の権利落ちタイミングです。多くのREITは年2回決算で、権利確定の翌営業日には価格が分配金相当額だけ下落します。高配当狙いで直前に買い付けると、実質利回りが目減りするケースが少なくありません。むしろ通年での分配金成長を重視し、権利落ち後の調整を拾う形が有効です。
次に、NAV倍率(純資産価額倍率)を活用しましょう。REITの保有物件評価額と市場価格の比率が1倍を割り込む銘柄は、賃料が安定していれば割安と判断しやすいです。2025年6月時点でオフィス系平均は0.99倍、物流系は1.11倍と逆転しており、オフィス系に妙味が出ています。もっとも、NAVは半年ごとに更新されるため、直近の取引事例や公示地価の推移を補足データとして確認すると精度が上がります。
売却の判断では長期的な金利トレンドが鍵です。過去10年間で長期金利が0.5%を超えた期間は短いものの、その局面ではREIT指数が平均で9%下落しました。金利上昇局面では価格下落よりも分配金利回りが低下して割高感が強まるため、いったん利益確定して様子見する選択も検討できます。
税制優遇と2025年度に使える制度
実は、税制面をうまく使うことで手取り利回りを底上げできます。REITの分配金は「配当所得」として扱われ、株式配当と同じ20.315%が源泉徴収されます。しかし2024年にスタートした新NISAでは、年間240万円の成長投資枠でREITを含む上場株式を非課税で保有可能です。2025年9月現在も制度は継続しており、非課税保有限度額は通算1,800万円となっています。
また、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば確定申告が不要になり、損益通算や繰越控除も可能です。加えて、2025年度の「上場株式等に係る配当控除」は継続中で、総合課税を選択し課税所得が900万円以下の場合、最大10%の税額控除が受けられます。もっとも、医療費控除など他の所得控除との兼ね合いで税率が変動するため、シミュレーションソフトで比較すると良いでしょう。
さらに、REITの売却益は株式譲渡所得と同一課税なので、年間20万円以下なら確定申告が不要です。投資金額を抑えて小口で積み立てる場合、この仕組みを活用しやすいと言えます。逆に、譲渡損が出た年には損失の繰越控除を3年間適用できるため、大きな含み損があるまま放置するより売却して節税する方が有利になる場合があります。
まとめ
ここまで、REITの仕組み、2025年の市場動向、リスク管理、売買戦略、税制優遇までを体系的に整理しました。要するに、利回りの数字だけでなく物件ポートフォリオの質と金利動向を合わせて確認すれば、大きな失敗を避けやすくなります。さらに新NISAなどの非課税枠を活用すれば、同じ銘柄でも実質利回りが向上します。あなたが次に行うべきアクションは、気になるREITの運用報告書を読み込み、NAV倍率と分配金の推移をチェックしたうえで少額から買い付けを試すことです。結論として、学びながら小さく実践する姿勢こそ、長期的な資産形成への近道と言えるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向調査2025年上期 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本取引所グループ J-REIT市場データ – https://www.jpx.co.jp/
- 投資信託協会 REITガイドブック2025 – https://www.toushin.or.jp/
- 財務省 税制改正の概要2025年度版 – https://www.mof.go.jp/
- 日本銀行 金融政策レポート2025年7月 – https://www.boj.or.jp/

