不動産投資に興味はあるものの、物件を所有するのはハードルが高いと感じる人は少なくありません。そんな悩みを解消してくれる選択肢として、上場不動産投資信託―いわゆるREIT(リート)が注目を集めています。しかし「REIT 評判 デメリット」で検索すると、好意的な声と同じくらい懸念点も見つかり、何を信じてよいのかわからなくなるのが実情です。本記事では、2025年10月時点で有効な制度や最新データをもとに、REITの基本からメリット・デメリットまでを初心者向けに整理します。読み終えるころには、REITを選ぶべきかどうかを自分自身で判断できる力が身につくはずです。
REITとは何か―評判が高まる背景を整理
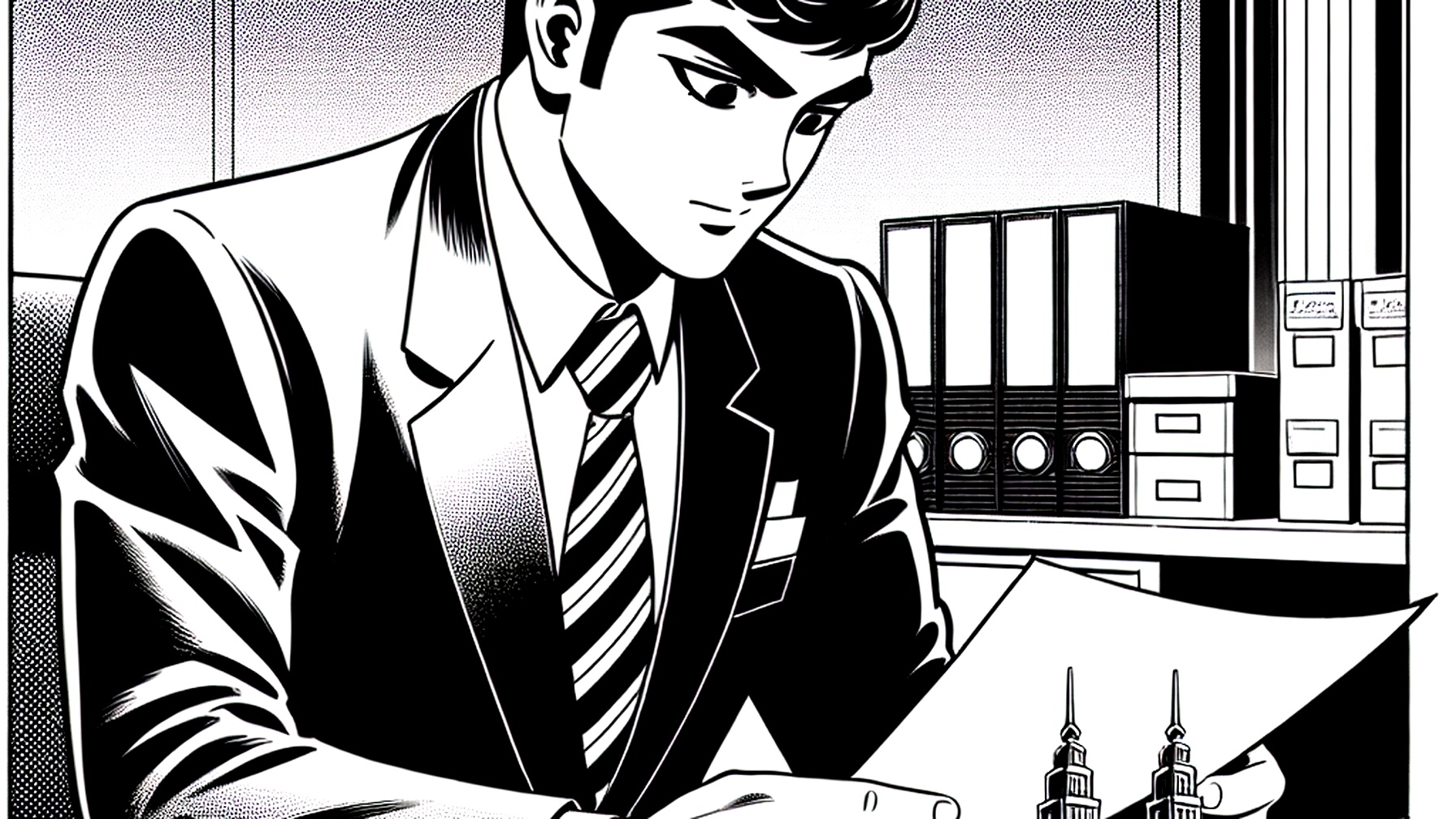
まず押さえておきたいのは、REITが「投資家から集めた資金で複数の不動産を運用し、その賃料収入や売却益を配当に回す仕組み」だという点です。東京証券取引所に上場しているため、株式と同じように売買でき、少額から分散投資が可能だという利便性が評判の源になっています。また、金融庁によると2025年8月末時点でJ-REITの時価総額は約18兆円に達し、着実な市場拡大が確認できます。
重要なのは、裏側にある法制度が投資家保護を重視していることです。不動産投資法人は資産の大部分を収益不動産に投じ、利益の90%超を分配することで法人税が実質的に免除されます。つまり、税コストを抑えた形でインカムゲイン(配当)を受け取れる点が高評価につながっているのです。一方で、価格変動がある以上リスクは避けられず、「手軽さゆえに深く調べず買ってしまう」という失敗談も耳にします。
分配金の魅力と隠れたリスク
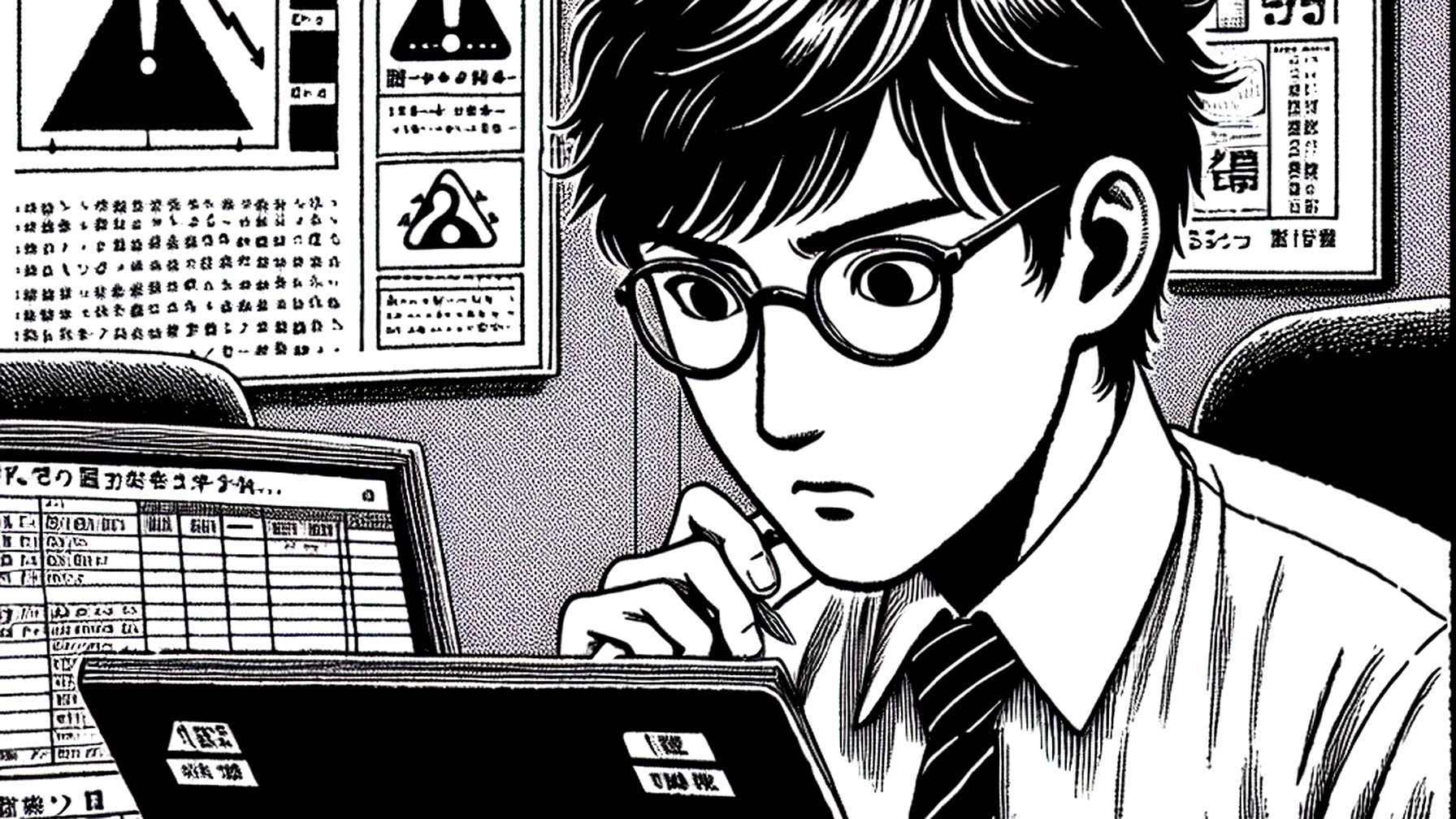
ポイントは「高い分配利回りが本当に持続するのか」という視点です。日本取引所グループの月次データによると、2025年9月の平均分配利回りは3.8%前後で、長期国債利回り(約1.3%)を大きく上回ります。そのため、年金代わりやインフレ対策として人気が高いのですが、分配金は不動産賃料に依存しているため景気が悪化すると減額される可能性がある点を見逃せません。
また、REITは借入金(LTV=負債比率)を活用して物件を増やし、分配金を底上げする仕組みが一般的です。低金利環境では利ザヤが拡大しますが、金利が上昇すれば逆に利回りが圧迫されます。さらに、空室率の増加や大規模修繕の発生は即座にキャッシュフローを悪化させる要因となります。つまり、高利回りに惹かれて投資する前に、物件ポートフォリオの質や負債依存度を確認する姿勢が欠かせません。
市場価格の変動要因と主なデメリット
実は、REITの価格は株式市場と不動産市場の両方の影響を受けるという二重構造にあります。株式市場が大きく調整すると、実体の賃料収入が安定していても投げ売りが増え、基準価額が急落するケースが過去に何度もありました。2020年3月のコロナショックでは、J-REIT指数が1か月で約40%下落した事実がその典型例です。
さらに、不動産市場そのもののリスクも無視できません。少子化が進む地方商業施設はテナント需要が急減し、空室リスクが高まっています。運用会社がこうした物件を多く保有している場合、分配金の減少だけでなく長期的な資産価値の下落につながるおそれがあります。また、投資口価格が純資産価値(NAV)を大きく上回ると「割高」と判断され、将来的に調整される可能性が高い点もデメリットのひとつです。
2025年度の税制・制度面での注意点
基本的に、REITの分配金は「配当所得」として総合課税または申告分離課税(株式と同様20.315%)を選択できます。2025年度税制ではこの仕組みが維持されており、NISA(少額投資非課税制度)成長投資枠でもJ-REITが対象となる点は大きな追い風です。ただし、NISAで保有できるのは年間360万円までという上限があるため、高額投資を予定する場合は枠外の課税コストも計算に入れる必要があります。
一方で、REIT特有の制度リスクとして覚えておくべきなのが「投資法人の倒産時の扱い」です。法的には資産と負債が分別管理されているため直接の債務超過リスクは限定的ですが、再建まで分配金が停止する可能性があります。また、2025年10月現在、国土交通省が推進する「不動産特定共同事業法」改正によりクラウドファンディング型の小口化商品が拡大しています。同じ不動産投資でも制度が異なるため、混同しないことが大切です。
上手に活用するためのチェックポイント
まず、ポートフォリオ全体の中でREITをどの程度組み入れるかを決めましょう。総務省家計調査によると、金融資産のうち株式・投信を合わせた比率が平均16%前後という実態があります。この数字を参考に、REITを含むリスク資産が家計の30%を超えないよう設定すれば、過度な価格変動に耐えやすくなります。
次に、投資口価格とNAVの乖離率、LTV、平均賃料の伸び率といった指標を定点観測する習慣が不可欠です。具体的には、四半期ごとに開示される運用報告書を確認し、分配金の原資が本業の賃料で賄われているかを見極めます。最後に、資産タイプの分散も忘れずに行いましょう。オフィス特化型、住宅特化型、物流特化型などを組み合わせることで、景気変動に対する耐性が高まります。こうしたプロセスを経てこそ、REITの評判どおりの手軽さと分配収益を享受でき、デメリットを最小限に抑えられるのです。
まとめ
本記事では、REITが少額で分散投資できる点から高い評判を得ている一方、価格変動や金利上昇、空室リスクといったデメリットが存在することを確認しました。分配金利回りの高さに目を奪われる前に、ポートフォリオの質や負債比率、NAVとの乖離などを丁寧に検証する姿勢が求められます。制度面では2025年度もNISAの活用が有効ですが、枠の上限と税コストを踏まえて計画を立てることが重要です。行動に移す際は、まず少額から始めて四半期ごとに運用報告書を読み、データに基づいて判断を更新する習慣を身につけてください。冷静なチェックと長期視点を持てば、REITは堅実な収益源としてポートフォリオに貢献してくれるでしょう。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産・建設経済局 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産証券化協会(ARES) – https://www.ares.or.jp
- 総務省統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp/data/kakei/

