円安が定着しつつある今、輸入品の高騰や光熱費の上昇に頭を抱える投資家は少なくありません。とくに海外から調達する設備や資材の価格が跳ね上がり、賃貸経営のコスト構造は大きく変化しました。本記事では「管理会社 円安時代」という視点から、為替変動が不動産収益へ与える影響と、オーナーが管理会社と連携して取るべき具体策をわかりやすく解説します。初心者でも読み終えた瞬間から行動に移せる内容にまとめましたので、ぜひ最後までお付き合いください。
円安が不動産経営に与える影響
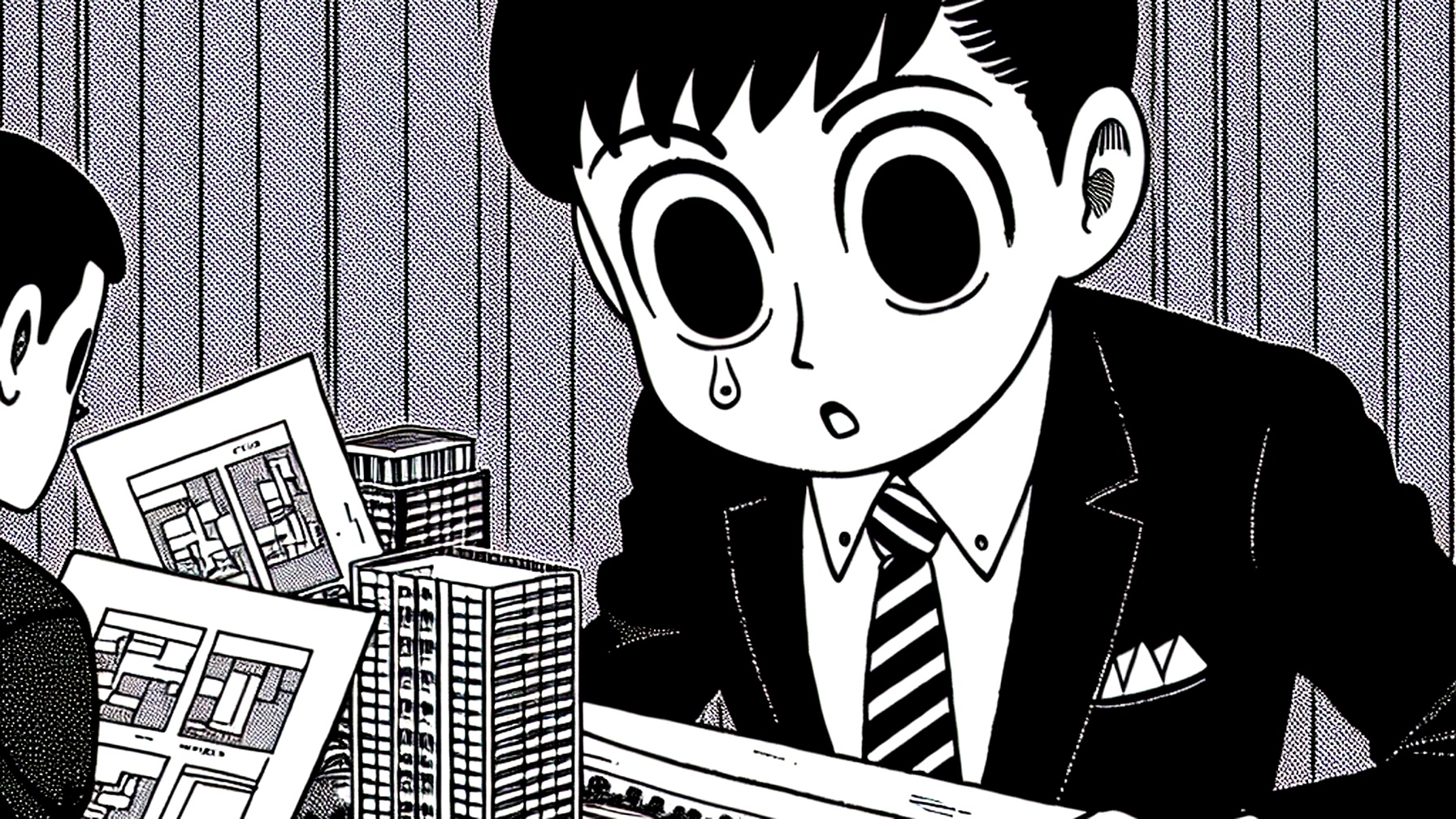
まず押さえておきたいのは、為替が動くと収支のどこが揺さぶられるのかという点です。2025年10月時点で1ドル=170円前後という水準は、2010年代平均より約40%円安となります。この変動は主に修繕費、光熱費、ローン金利の三方面でオーナーを直撃します。
一つ目の修繕費では、輸入部材の単価が上昇し、大規模改修の見積もりが前年比で15%程度高くなるケースが散見されます。国土交通省の資材価格指数でも2024年度から上昇傾向が続き、円安がそれを後押ししました。二つ目の光熱費は、都市ガスや電力の原料をドル建てで輸入するため、円安が長期化するほど公共料金の上昇が避けられません。三つ目に変動金利型ローンですが、日銀はマイナス金利を解除し政策金利を0.25%程度に据え置いているものの、海外金利との差が拡大すると上昇圧力がかかる可能性があります。
つまり円安は「支出の増加」と「金融コストの上振れ」を同時に招くリスク要因です。一方で訪日客の増加や外貨建て賃料の導入など、収入面でのプラスも期待できるため、管理会社を巻き込んでバランスよく対策を練る姿勢が重要となります。
管理会社に求められる新しい役割
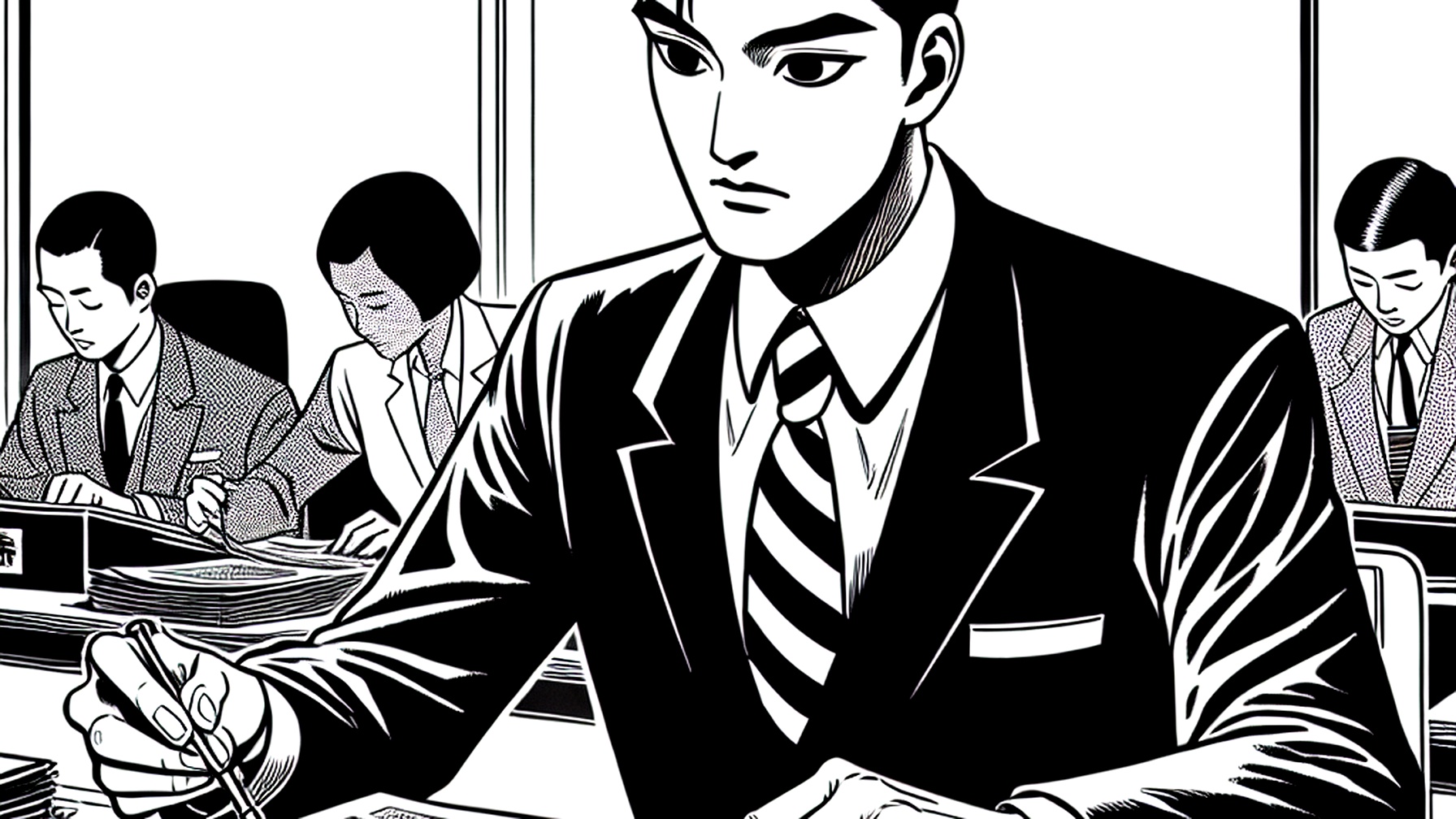
ポイントは、管理会社を単なる窓口やクレーム処理担当と見なさず、為替リスクを共有するパートナーとして位置づけることです。円安の現場では、リフォーム費用の見積もり精査や適切な修繕タイミングの提案力が差を生みます。
例えば2025年度の国交省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は上限250万円の補助金を提供し、断熱改修やバリアフリー化に対応しています。管理会社がこうした制度を熟知していれば、円安で高騰する工事費を一部相殺できるでしょう。また、エネルギー効率の高い設備を導入して光熱費を削減する際、補助申請の書類作成までサポートできる会社は心強い存在です。
さらに、為替動向を踏まえた家賃改定シミュレーションを行い、オーナーとテナント双方の負担を最適化するアドバイスも欠かせません。賃料を一律に上げるだけでは空室リスクを高めますが、定期借家契約の更新タイミングで小刻みに調整する手法など、きめ細かい提案が求められます。
実は、こうした総合的サポートを行う管理会社はまだ少数派です。選定時には「補助金の提案実績」「資材価格の情報網」「家賃改定の成功事例」を確認し、数字で示せる会社を優先するのが賢明です。
外貨建て家賃とインバウンド需要への対応
重要なのは、円安が続く局面で「収益を外貨で取り込む」発想です。とくに東京都心や京都・福岡などでは、外資系企業に勤務する駐在員向けにドルやユーロ建てで賃貸契約を結ぶ事例が増えています。家賃を実質的に指数連動させることで、円安による目減りを防ぐ効果があります。
管理会社が外貨建て契約に対応する場合、為替リスクの説明責任や、毎月のレート適用ルールを明文化する作業が不可欠です。さらに、日本円でしか家賃を受け取れないオーナー向けに為替予約(フォワード契約)を紹介するなど、金融知識も要求されます。
一方で、観光庁のデータによると2025年の訪日客数は3,600万人と過去最高を更新しました。短期民泊やマンスリーマンション市場も拡大しており、円安は宿泊単価の引き上げと稼働率向上を同時に後押ししています。管理会社が多言語対応のカスタマーサポートや、OTA(オンライン旅行代理店)の運用代行までカバーすれば、オーナーは新たな収益機会を取り込めるでしょう。
ただし、住宅宿泊事業法の届出や消防設備の基準を満たさない物件での無許可運営は行政指導の対象になります。法令遵守を徹底しつつ、需要のあるエリア・物件タイプを見極めることが、円安恩恵を最大化する近道です。
オーナーが取るべきリスクヘッジ戦略
まず自己資金の比率を高め、ローン返済負担を抑える戦略が基本です。日銀の「金融システムレポート」では金利1%上昇で不動産投資向け貸出残高の不良債権比率が0.3ポイント上振れする試算を示しており、余裕資金の確保は欠かせません。
次にキャッシュフローの見通しを、円安・金利上昇・空室率悪化の三つのストレスシナリオで検証します。管理会社に依頼し、例えば「空室率15%、金利+1%、修繕費+20%」という厳しめの条件でも手元に月5万円のキャッシュが残るかを試算すると、想定外の事態でも慌てずに済みます。
加えて、上昇した光熱費をテナントに転嫁するだけでなく、太陽光発電や蓄電池を導入し共用部電気代を削減する選択肢もあります。2025年度の「住宅・建築物省エネ投資促進事業」で最大50%の補助を受ければ、投資回収期間を大幅に短縮できます。管理会社が補助要件の確認から工事監理までサポートすれば、オーナー単独で動くよりもリスクが小さくなります。
最後に、複数エリアへのポートフォリオ分散です。円安メリットが大きいインバウンド向けエリアと、国内需要が安定するベッドタウンの両方を保有することで、為替変動の収益インパクトを平準化できます。管理会社にも対応エリアの広さやネットワーク力が求められるため、選定基準が一段と厳しくなるでしょう。
管理会社選定でチェックすべきポイント
基本的に、円安時代に強い管理会社は情報力と実行力のバランスに優れています。オーナーが確認すべき項目を整理すると、次の三点に集約できます。
1. 為替影響を加味した長期収支シミュレーションを提示できるか 2. 2025年度以降の補助金・減税制度を具体的に提案し、申請まで伴走する体制があるか 3. 外貨建て契約や民泊運営など、多様な賃貸スキームの実績を数字で示せるか
これらを面談時に質問し、言葉だけでなく過去の事例資料で回答を求めると、実力の差が浮き彫りになります。また、管理手数料の安さだけで選ぶと、為替や金利変動時に対応が後手に回り、結果的に収益を圧迫するリスクが高まります。
結論として、円安の追い風を生かすも逆風にするも、管理会社の力量次第と言っても過言ではありません。オーナー自身が最低限の為替知識を身につけ、数字で語れる担当者をパートナーに選ぶ姿勢が、長期安定経営への近道となります。
まとめ
円安は修繕費や光熱費を押し上げ、不動産経営に新たな負担をもたらします。しかし外貨建て家賃やインバウンド需要を取り込めば、収入面でのチャンスも同時に生まれます。要は「支出の増加を抑えつつ、外貨収益を伸ばす」戦略を管理会社と二人三脚で実行できるかが鍵です。補助金の活用、リスクシミュレーション、契約スキームの多様化をバランス良く進め、円安時代を味方につけましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 資材価格指数(月報) – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 貿易統計(2025年10月) – https://www.customs.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート(2025年4月) – https://www.boj.or.jp
- 観光庁 訪日外国人統計(2025年8月) – https://www.mlit.go.jp/kankocho
- 総務省統計局 家計調査(家賃・光熱費項目) – https://www.stat.go.jp

