急激な円安で海外マネーが日本の不動産市場に流入し、物件価格や賃料がじわじわ上昇しています。投資家としては値上がり益が期待できる一方、仕入れコストや金利負担が重くなる点が気掛かりです。本記事では「収益物件 円安時代 管理会社」という3つのキーワードを軸に、為替の影響、資金調達の考え方、そして管理会社の選定基準まで丁寧に解説します。読み終えるころには、円安局面でも安定収益を実現する具体策が見えてくるはずです。
円安が収益物件に与える影響
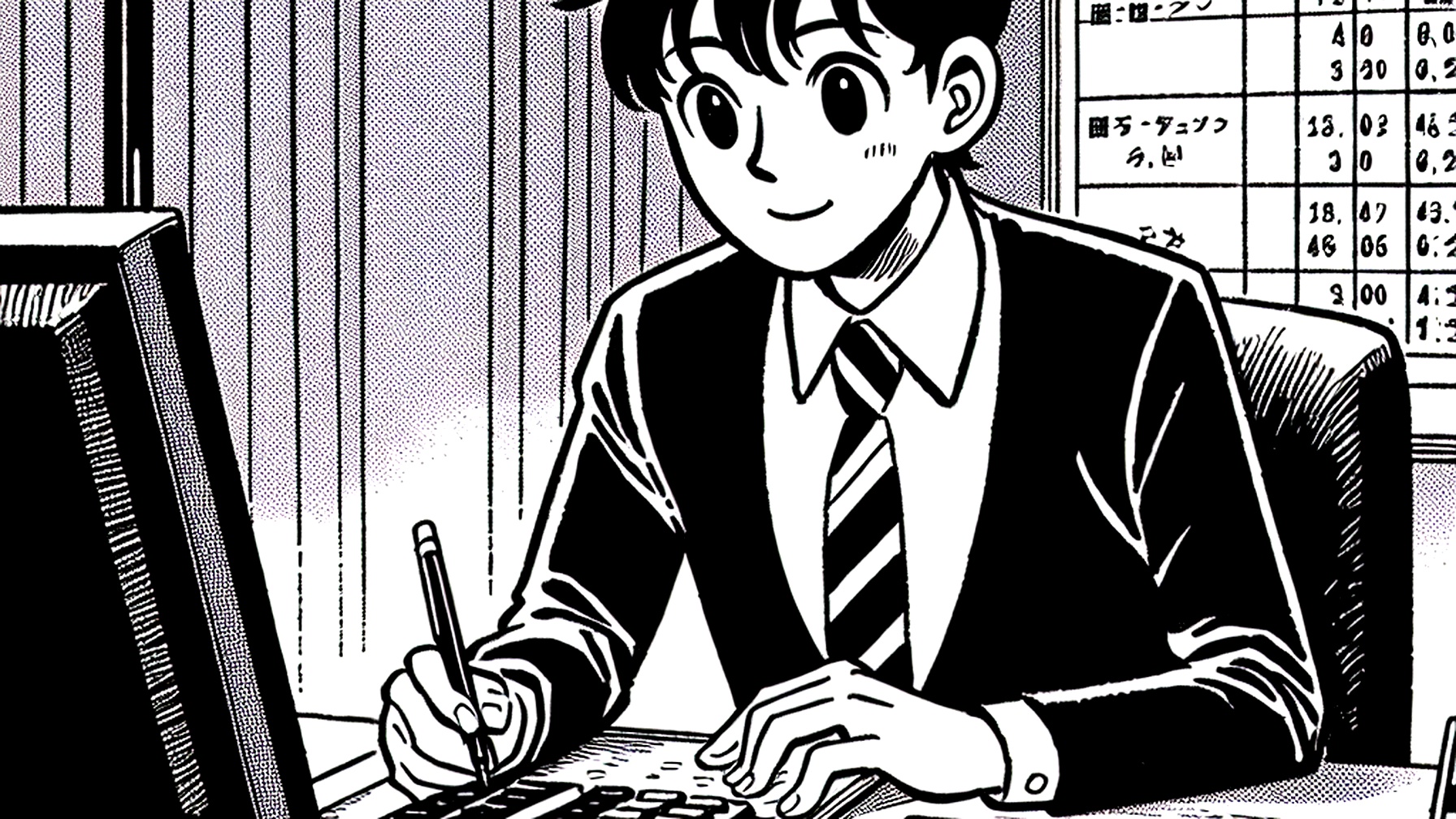
ポイントは、円安が「買い手」と「貸し手」の双方に異なるインセンティブを生むことです。日本銀行の統計によると、2025年10月の実効為替レートは過去15年で最も円安方向に振れています。
まず外国人投資家にとって、日本の不動産は相対的に割安に映ります。1ドル=160円の水準では、同じ10億円の物件を購入しても、ドル建てでは18か月前より約20%安く買える計算です。一方で国内投資家は、仕入れに必要な円資金が増え、利回り低下を招きやすくなります。
さらに円安は建材価格にも波及します。国土交通省の建設工事費指数は前年同月比で6%上昇しており、修繕コストの見積もりが甘いとキャッシュフローを圧迫します。つまり購入時だけでなく、長期保有中の運営費も為替を通じて膨らむ可能性があるのです。
外国人投資家の動きとリスクの正体
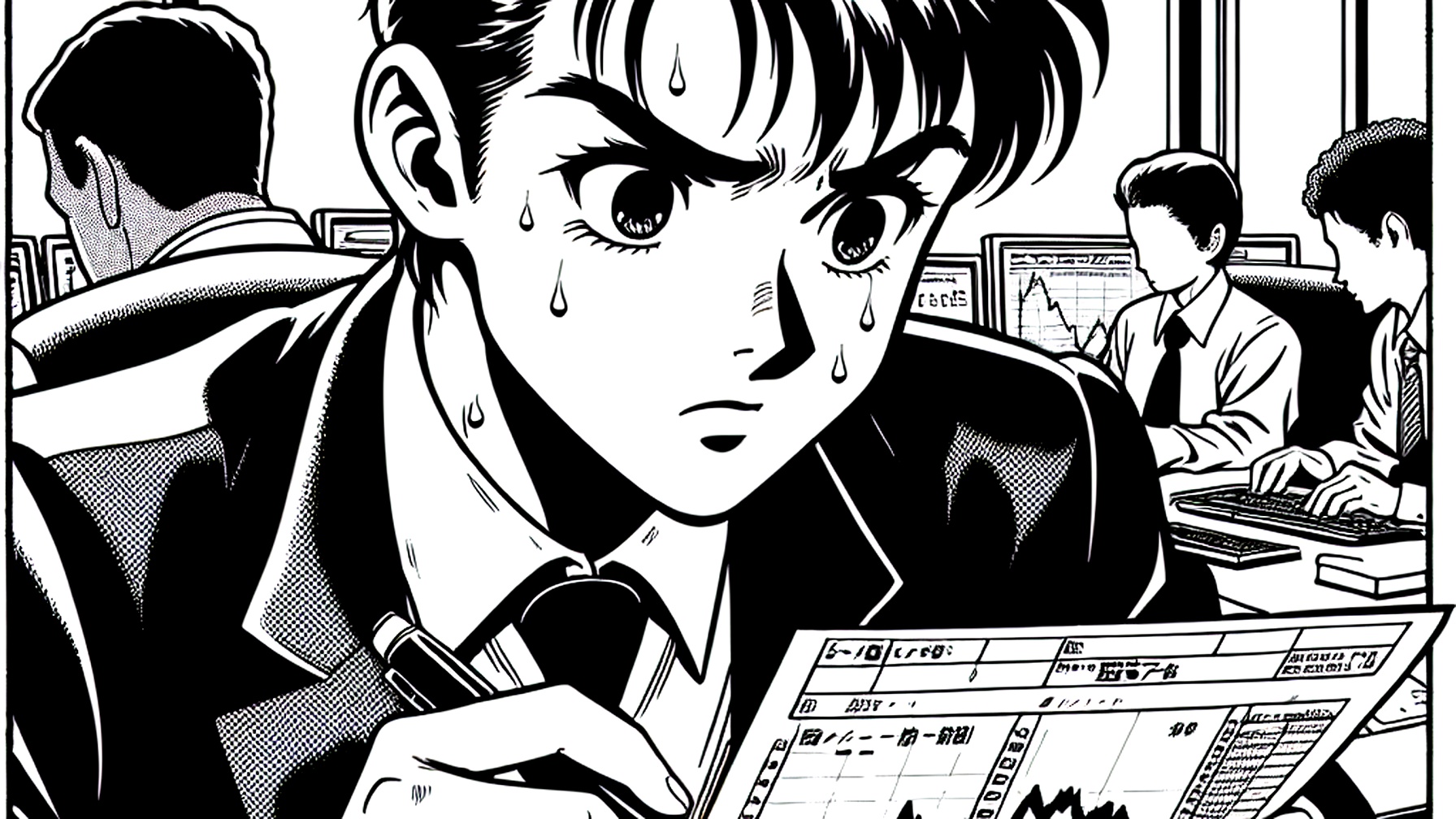
実は、円安で一気に存在感を増したのが東南アジア系ファンドです。財務省の国際収支統計によれば、2024年度の外国人による不動産直接投資額は前年比37%増でした。彼らは都心Aクラスのオフィスやホテルに加え、地方中核都市のレジデンスにも手を伸ばしています。
ところが過去の事例を見ると、為替が反転した途端に売却を急ぐケースが多いのも事実です。2012年の円高局面では、外資系ファンドが含み益を確定させるために一斉売却し、局地的に空室率が跳ね上がりました。したがって周辺に大型物件を持つ外資の動向を注視しないと、賃料単価の下落や競合物件の急増に巻き込まれる恐れがあります。
加えてクロスボーダー取引の多くはドル建てで契約します。売買契約に為替ヘッジ条項が盛り込まれていないと、最終的な受取額が変動し、キャッシュフロー予測が崩れるリスクを抱えます。国内投資家が共同出資に参加する場合は、通貨建てと解約条件を細かく確認することが重要です。
国内投資家が取れる資金調達戦略
まず押さえておきたいのは、円安でも長期固定金利が歴史的低水準にある点です。住宅金融支援機構の「フラット35」金利は2025年10月時点で年1.8%台にとどまっています。銀行融資も信用補完のある法人なら1%後半が現実的で、米ドル建て5%超と比べれば十分に優位性があります。
しかし融資枠は物件評価額と自己資金比率で決まるため、購入前に「円安で価格が上がった分」を自己資金で補う必要があります。そこでインカムゲイン(賃料収入)とキャピタルゲイン(値上がり益)のバランスを再計算し、自己資金の回収期間が10年以内に収まる中規模案件を狙うとリスクを抑えやすくなります。
また、為替ヘッジ付きのローンは金利が高めでもキャッシュフローが安定するメリットがあります。たとえば都市銀行A社の「為替リンク型不動産ローン」は、ドル/円が10%以上変動すると金利が自動調整され、実質的に返済額を円建てで一定に保つ設計です。変動コストと安定性のどちらを優先するか、シミュレーションで比較したうえで選択すると安心です。
管理会社選びで収益を守る
重要なのは、管理会社が円安リスクをどう吸収するかという視点です。具体的には、賃料改定の交渉力と修繕コストの仕入れ力が鍵を握ります。たとえば都心で5000戸以上を管理する大手は、資材を一括購入するため、円建てでも単価を抑えやすい傾向があります。
一方で中小の管理会社は、オーナーに対して柔軟なサブリース条件を提示できる点が魅力です。実際、東京23区内でサブリース率90%以上の中小5社を調べると、平均で賃料保証期間が2年と短く、為替変動に応じて早期に賃料を見直せる仕組みを採っています。固定賃料型で安定を取るか、変動型で市場追随を狙うか、物件のポジションとキャッシュフロー計画に合わせて選ぶことが大切です。
管理委託契約を結ぶ際は、資材調達先と手数料体系を確認しましょう。「海外仕入れ比率」と「円建て上限価格」が明記されていれば、材料費高騰のリスクを事前に把握できます。加えて、英語対応スタッフの有無や24時間コールセンター体制など、外国人入居者を想定したサービスがあるかどうかも、今後の競争力を左右します。
2025年度の制度と税制のチェックポイント
ポイントは、2025年度も有効な減価償却ルールとインバウンド関連の税制優遇です。国税庁の通達では、木造アパートの法定耐用年数22年は据え置かれており、築古物件を取得すれば大きな減価償却費を計上できます。これにより所得税・住民税の圧縮効果が期待できます。
また観光庁は「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の規制緩和を2025年4月に一部改正し、年間営業日数の上限を180日から210日に延長しました。円安で訪日客が増加する今、地方都市の空室対策として民泊転用を検討する価値が高まっています。ただし消防法や自治体条例の追加設備基準があるため、管理会社が届け出から運営までサポートできる体制か確認することが欠かせません。
さらに、2025年度税制改正では「不動産取得税の軽減措置」が延長され、新築住宅は課税標準から1200万円が控除されます。期限は2026年3月31日までなので、取得時期を前倒しするかどうか、金融機関と資金計画を擦り合わせると良いでしょう。
まとめ
ここまで、円安が収益物件の購入・運営に与える影響と、その対処策を見てきました。為替変動はチャンスとリスクが同居しますが、低金利を生かした固定金利ローン、管理会社の仕入れ力、2025年度の税制優遇を組み合わせれば、キャッシュフローを安定させる道は十分にあります。最後に、物件選定と管理スキームを為替シナリオ別に試算し、専門家と二重三重にチェックする習慣を持ちましょう。そうすることで、円安時代でも収益物件の可能性を最大限に引き出せるはずです。
参考文献・出典
- 日本銀行 統計データ – https://www.boj.or.jp/statistics/
- 国土交通省 建設工事費デフレーター – https://www.mlit.go.jp/
- 財務省 国際収支統計 – https://www.mof.go.jp/
- 住宅金融支援機構 金利情報 – https://www.flat35.com/
- 観光庁 住宅宿泊事業法 改正資料 – https://www.mlit.go.jp/kankocho/
- 国税庁 法人税基本通達 – https://www.nta.go.jp/

