老朽化したマンションを所有していると、「建て替えに踏み切るべきか、それとも改修で持たせるべきか」という悩みがつきまといます。さらに投資家の立場から見ると、建て替え後に期待できる表面利回りが不明確だと、資金計画に踏み出せません。本記事では「建て替え いくら マンション投資 表面利回り」というキーワードを軸に、費用の概算から利回り計算のコツ、2025年10月時点で利用可能な補助制度までを体系的に解説します。読み終えるころには、建て替え判断に必要な数字を自分で整理し、投資戦略を具体化できるようになるはずです。
建物はいつ建て替えるべきか
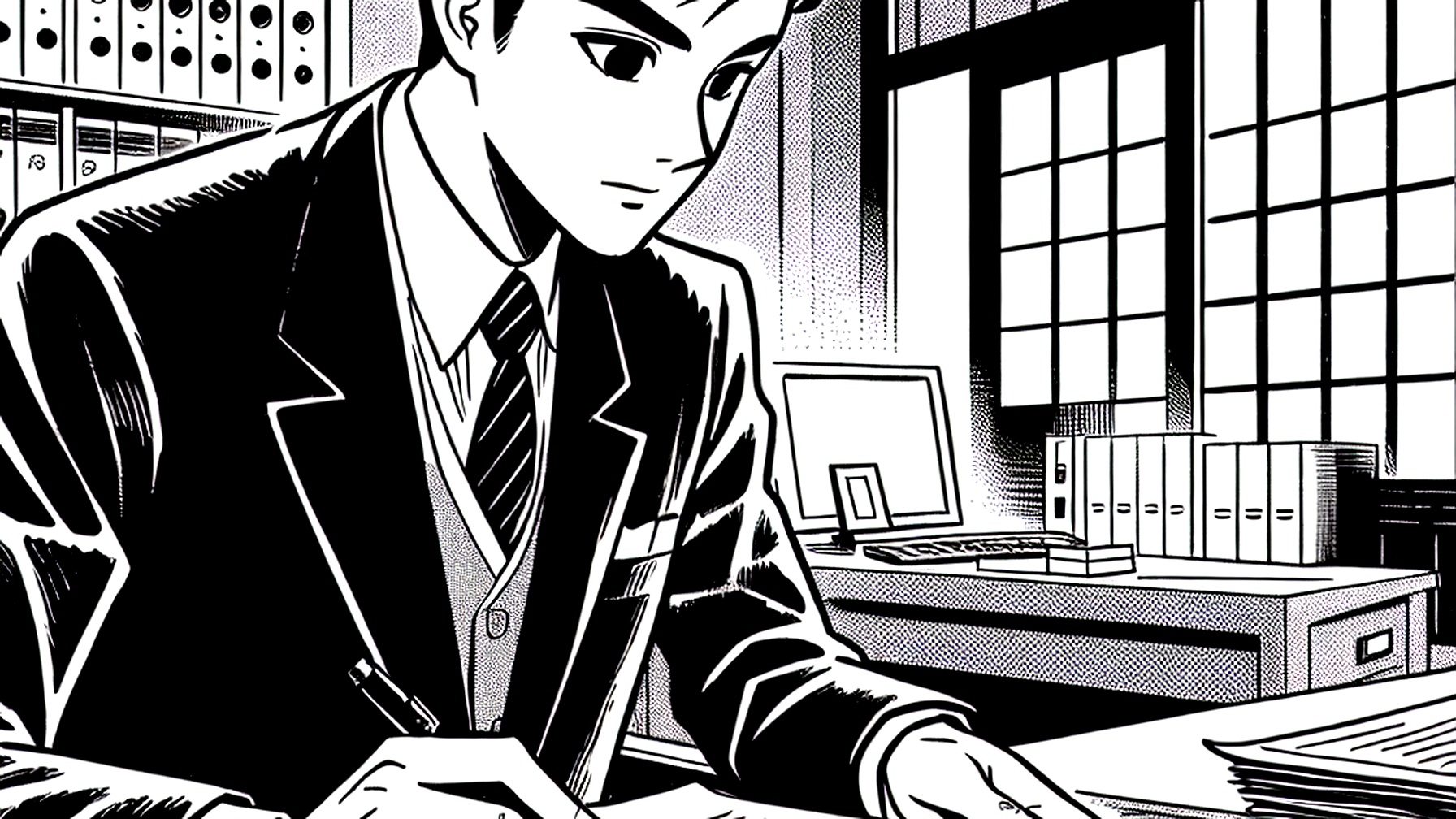
まず押さえておきたいのは、築年数だけで建て替えを決めると後悔しやすい点です。国土交通省の統計によると、分譲マンションの平均築年数は2024年末で28.5年ですが、適切な修繕を行えば50年以上使用できる事例も珍しくありません。一方で、耐震基準や省エネ性能が旧仕様のままだと、空室率が上昇してキャッシュフローを圧迫しやすいのも事実です。
重要なのは、修繕積立金の残高と改修コスト、そして将来の賃料下落リスクを比較することです。例えば、大規模修繕に1戸当たり150万円を投じても、耐震適合証明を取得できなければ、家賃を据え置かざるを得ません。つまり投資家にとっては、修繕後のキャッシュフロー改善が見込めない限り、建て替えがより合理的な選択肢となります。
さらに、2025年に予定されている「マンション管理適正化法」の改正では、管理不全認定を受けた物件への行政勧告が強化される見通しです。勧告を受けてから建て替えを検討すると、資金調達のハードルが上がる恐れがあります。先手を打ってシミュレーションを行い、築30年を超えた段階で建て替え計画を練ることがリスク管理の第一歩です。
建て替え費用はいくらかかるのか
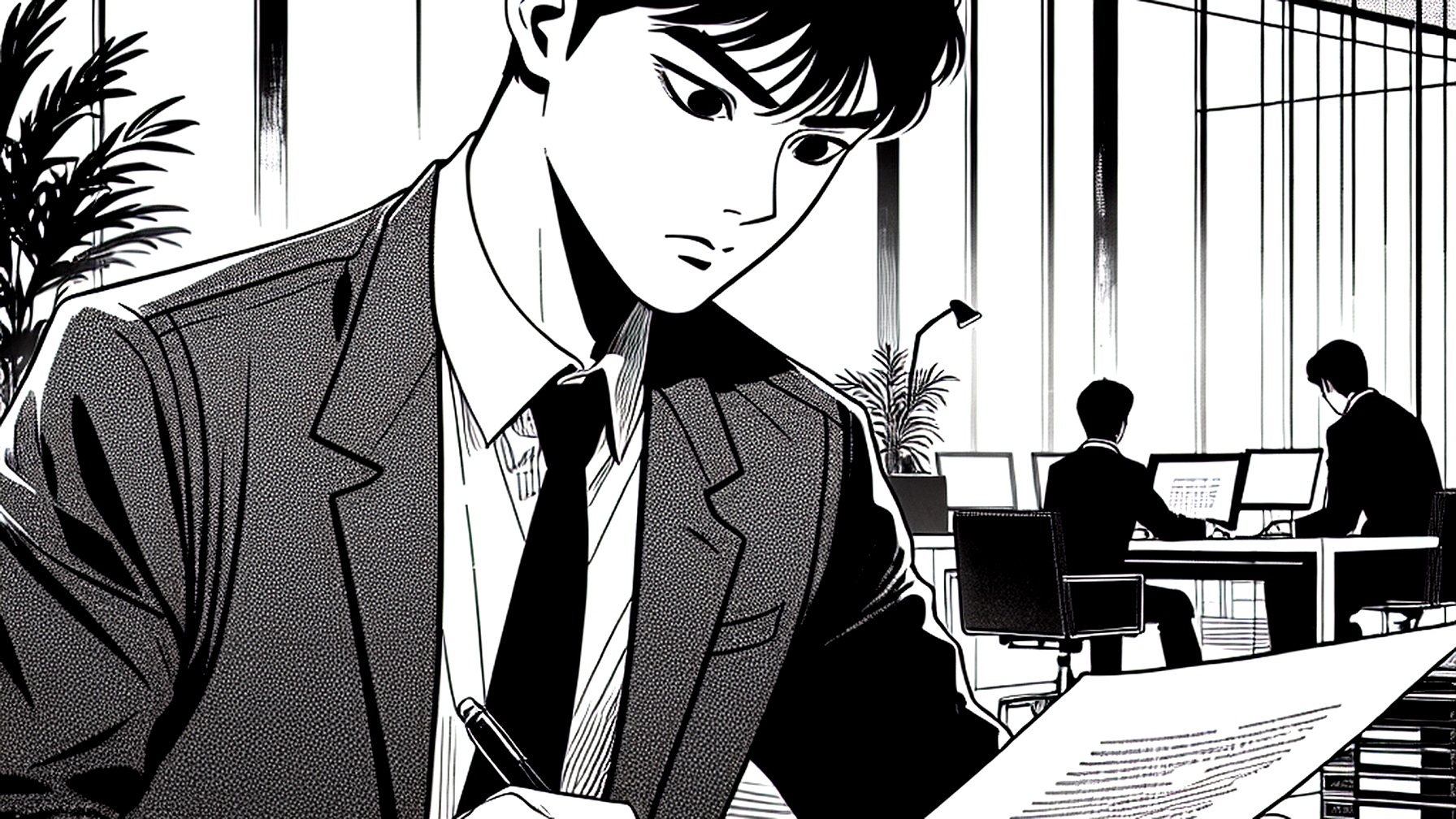
ポイントは、解体費・建設費・仮住まい費用を合算し、戸当たりの負担額を早期に把握することです。日本建築学会の2025年度調査によれば、RC造マンションの平均解体費は首都圏で1平方メートルあたり1.5万円、建設費は同12.8万円が目安です。延床2,000平方メートル(30戸規模)なら、解体3,000万円、建設2億5,600万円、合計約2億8,600万円となります。
実は、この総額を戸数で割る単純計算だけでは不十分です。建て替え期間中の賃料損失と仮住まい費を加味しないと、資金計画が狂いやすくなります。30戸が平均月10万円で賃貸していた場合、18か月の工期で5,400万円の家賃収入が消失します。入居者に家賃保証を続ける契約なら、その負担もオーナー側に跳ね返ります。
そこで有効なのが、金融機関の建替え一括融資と住宅金融支援機構の「マンション建替え融資」です。2025年度の金利は固定1.70%台で、返済期間は最長35年が選択できます。建て替え後に資産価値と賃料が同時に上がるなら、ローン返済と家賃収入のバランスが取りやすくなります。費用が「いくら」かかるかを把握したら、次に「収益がどれだけ」伸びるかを検証しましょう。
表面利回りの数字だけを信じてはいけない
マンション投資では、表面利回り=年間家賃収入÷物件価格×100で算出するのが一般的です。2025年10月時点の東京23区平均表面利回りは、ワンルームで4.2%、ファミリータイプで3.8%と日本不動産研究所が報告しています。しかし、建て替え案件では工事期間中の無収入期間を含めて初年度利回りを計算しないと、数字が大きくズレます。
例えば、総事業費3億円の建て替え後に年間家賃収入が3,000万円見込めるケースを考えます。表面利回りは10%のように見えますが、18か月の空白期間の家賃損失5,400万円を織り込むと、10年目でようやく実質利回りが5.9%に落ち着く試算になります。つまり、表面利回りは「完成後の見かけ上の数字」に過ぎず、投資判断にはキャッシュフロー表を必ず併用することが求められます。
また、固定資産税や管理費の増減も無視できません。建て替え後は建物評価額が上がるため、固定資産税が2〜3倍になることが珍しくありません。利回り計算において経費率を20%前後に設定し、想定以上のコスト増に耐えられるか検証することで、表面利回りの限界を補えます。
建て替え後の賃料設定と資産価値の伸ばし方
重要なのは、築浅プレミアムをどこまで賃料に転嫁できるかを冷静に見極めることです。東京都心の場合、SUUMOの2025年成約データでは築1年以内のワンルームは築20年超より平均12%高い賃料で契約されています。ただし、この差は築5年時点で半分に縮小する傾向があります。賃料アップを根拠にした収支計画は、5年後の下落を織り込むと安定します。
一方で、建て替えを機に間取りや共用設備をグレードアップすると、資産価値の伸びに繋がります。たとえば、宅配ボックスや高速インターネットを標準装備すると、初期費用は戸当たり20万円程度でも空室期間が短縮されます。空室損が1か月減るだけで、表面利回りは0.3〜0.4ポイント改善することが期待できます。
さらに資産価値を高める方法として、長期優良住宅認定の取得があります。2025年度も継続するこの制度では、フラット35Sの金利引き下げが10年間利用でき、販売時の付加価値としても有効です。高性能な断熱や省エネ設備を導入すると建設コストは5〜7%上がりますが、エンドユーザーへの売却出口を確保する保険になる点を覚えておきましょう。
リスクを抑える資金計画と2025年度の補助制度
まず、自己資金と融資のバランスを整えることで、金利上昇リスクを抑えられます。物件価格の20〜30%を自己資金で賄うと、金融機関の審査がスムーズになり、金利優遇幅も広がります。また、予備費として総事業費の5%を別口座に確保しておくと、想定外の追加工事にも対応しやすくなります。
2025年度に利用可能な公的支援としては、国土交通省の「住宅エコリフォーム推進事業」が挙げられます。建て替えでもZEH-M Ready相当の省エネ性能を確保すれば、戸当たり最大60万円の補助が受けられます。東京都内なら、併用できる「既存建築物省エネ改修補助」と合わせて、追加で30万円の助成が見込めます。こうした制度を活用すると、資金繰りの安全余裕率が高まり、実質利回りの底上げに直結します。
最後に、保険と信託を組み合わせた出口戦略も忘れないでください。建て替え直後に生命保険付きローンを利用すると、万一の際に債務が消え、相続人へ無借金の資産を残せます。信託活用で管理を外部化すれば、賃料管理の手間を省きつつ、キャッシュフローの見える化が進みます。リスクを多面的に抑えることで、表面利回り以上の安心感を得られるでしょう。
まとめ
ここまで、建て替えにかかる費用が「いくら」なのかを解体・建設・家賃損失まで含めて算出し、表面利回りの落とし穴や賃料設定の現実的な上限を確認しました。さらに、2025年度時点で利用できる補助制度や融資条件を活用すれば、自己資金の圧縮と実質利回りの底上げが可能です。次のステップとして、物件ごとの詳細シミュレーションを行い、数字で判断できる体制を整えてください。早めの検討と正確な試算が、長期にわたり安定したマンション投資を実現する鍵となります。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省 住宅局「マンション政策」 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
- 日本建築学会 2025年度 建設コストデータ – https://www.aij.or.jp/
- 東京都 環境局「既存建築物省エネ改修補助」 – https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/

