不動産投資に興味はあるものの、「本当に黒字になるのか」と不安を覚える方は少なくありません。特に収益物件の収支計算は数字が多く、何をどう見ればよいのか混乱しがちです。この記事では、投資歴15年の筆者が実際に経験した失敗と成功を交えながら、2025年時点で押さえるべき計算方法と注意点を解説します。読み進めることで、数字に対する苦手意識が薄れ、購入前にリスクを見抜く力が身につくはずです。最後までお付き合いいただき、ご自身の投資判断に役立ててください。
収支計算の基本を押さえる
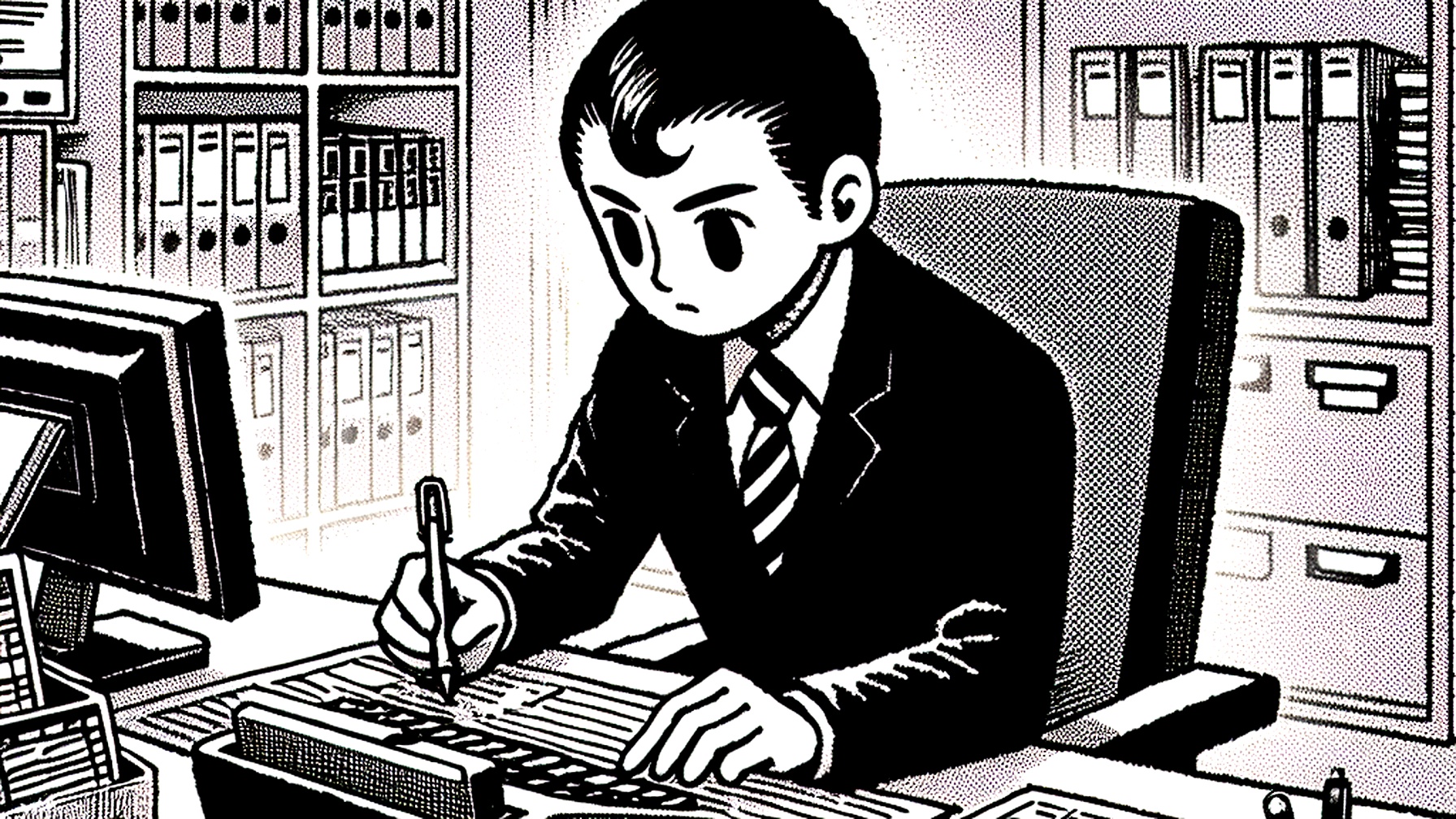
重要なのは、表面利回りではなく実質利回りを基準に判断することです。見た目の数字に惑わされず、年間キャッシュフローまで落とし込むと、物件の真の収益力が浮き彫りになります。
まず表面利回りとは、年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標です。便利ですが、管理費や修繕費を加味していないため、実際の手残りとは大きく異なります。一方、実質利回りは家賃収入から運営費用を差し引き、さらに物件取得費を含めた総投資額で計算します。筆者の体験では、表面利回り9%の木造アパートが実質5%に落ち込んだ例もありました。つまり、購入前に支出を漏れなく洗い出す姿勢が不可欠です。
収支計算では「年間家賃-年間運営費-年間返済=年間キャッシュフロー」という式を使います。運営費には固定資産税や保険料だけでなく、入退去時の原状回復費を見込むと精度が高まります。また、取得時の仲介手数料や登記費用も総投資額に含めることを忘れてはいけません。国土交通省の住宅市場動向調査(2025年版)によると、平均的な諸費用は物件価格の6〜8%とされています。この数値を目安に、過小評価を避けましょう。
最後に、空室率の設定がポイントです。筆者は首都圏築浅物件で5%、地方築20年超で15%をシミュレーションに反映させています。低く見積もると過大評価につながるため、周辺の賃貸市場データを参照し、保守的な数字を採用しましょう。
キャッシュフローを左右する主要コスト
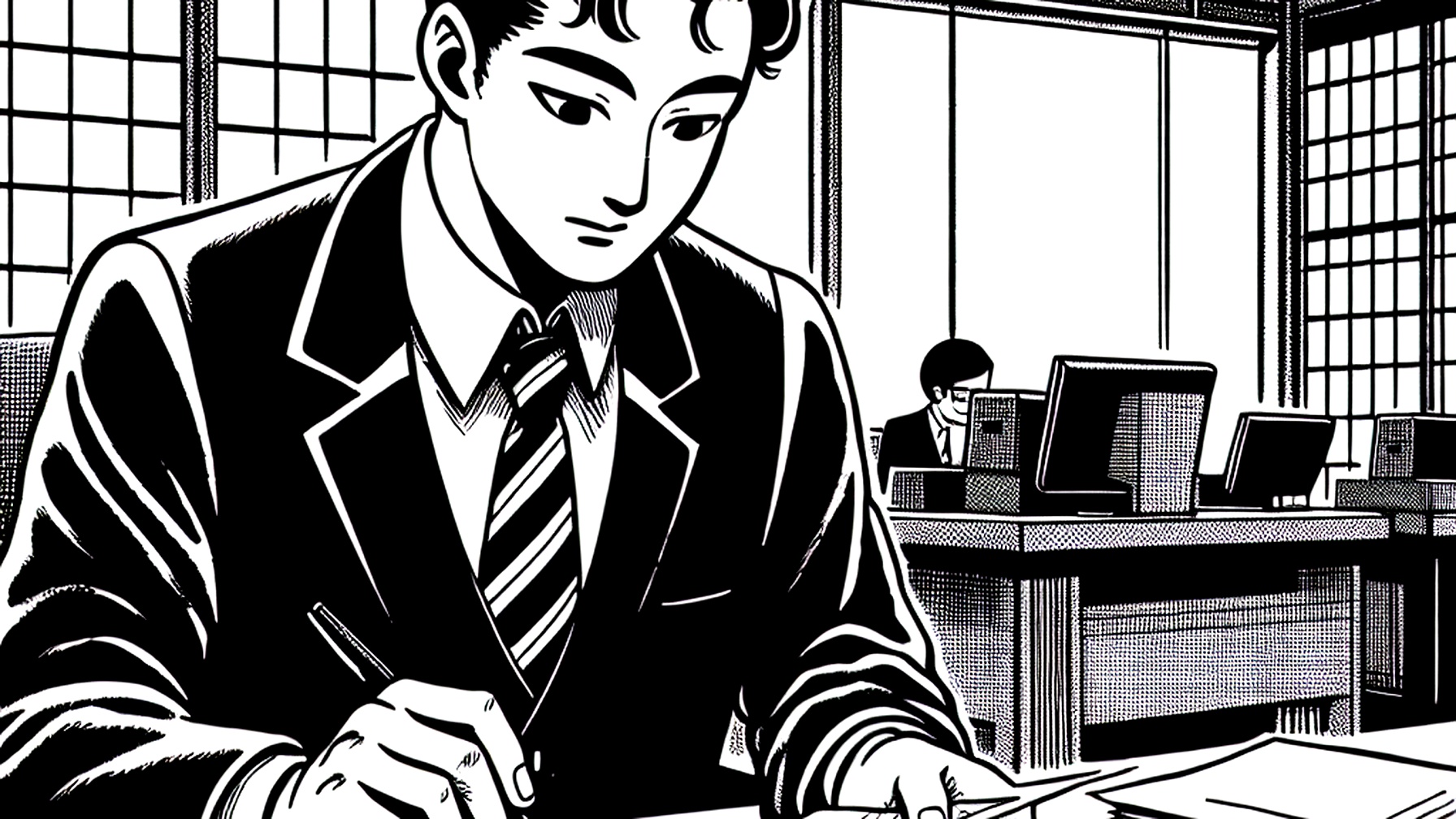
まず押さえておきたいのは、ランニングコストの把握こそが安定経営のカギになる点です。固定費が読めれば、家賃下落や金利上昇への備えが立てやすくなります。
ランニングコストで最も大きいのが金融機関への返済額です。2025年10月時点、大手銀行の投資用ローン金利は固定2.3〜3.5%が目安とされています。変動型はさらに低いものの、将来の上昇リスクを考慮する必要があります。日本銀行の金融システムレポートでは、長期金利1%上昇で平均返済額が約12%増えると試算されています。返済比率を家賃収入の50%以内に抑えると、金利変動にも耐えやすくなります。
次に注目すべきは修繕費です。築年と構造によって差が大きく、木造アパートは10年ごとの外壁塗装、鉄骨造はエレベーター保守などが重荷になります。国交省の「長期修繕計画ガイドライン」では、年間家賃収入の10〜15%を修繕積立に充当するよう推奨しています。筆者の物件では、築30年RCマンションの大規模修繕に一度で800万円を投じましたが、事前に積み立てていたためキャッシュフローを壊さずに済みました。
さらに見落としやすいのが入居促進費用です。広告料や鍵交換費、インターネット導入費などは空室が出るたびに発生します。特に地方都市では広告料が家賃の2カ月分になるケースも珍しくありません。これらを年間平均で試算し、シミュレーションに含めておくと、後で慌てずに済みます。
体験談で学ぶシミュレーションの落とし穴
実は、数字だけで安心してしまうと予想外の出費に振り回されることがあります。ここでは筆者自身の失敗談を共有し、回避策を探ります。
2017年に購入した郊外の築25年木造アパートでは、当初空室率8%で収支計算をしました。しかし人口減少が加速し、2021年から実質20%に悪化、家賃も月1,000円下落しました。年間キャッシュフローは130万円の黒字から一気に30万円の赤字に転落しました。教訓は、自治体の人口統計や開発計画を確認し、最悪シナリオも組み込むことです。
一方、2023年に購入した築浅区分マンションでは、家賃保証会社の破綻で家賃振込が2カ月遅延しました。このときも家賃滞納率を0%と置いた楽観的なシミュレーションが原因で、短期的に資金繰りが厳しくなりました。保証会社の格付けを調べ、滞納リスクを1〜2%上乗せすることで、より実態に近い予測ができます。
2025年現在、筆者が重視しているのは「CFカバー率」という指標です。これは年間家賃収入を年間返済額+運営費で割るもので、1.2倍以上あれば余裕があるとされます。過去の体験から、1.0を切るとわずかな変動で赤字に転落するため、購入前には必ずチェックしてください。
2025年の金利・税制動向と対策
ポイントは、制度変更が収支に与える影響を先に計算しておくことです。特に金利と税制は毎年のように改正があり、油断は禁物です。
まず金利ですが、2024年3月の日銀マイナス金利解除後も、政策金利は0.25%前後で推移しています。ただし、国際金利の上昇を背景に、2025年7月には長期固定型の一部で0.3ポイント引き上げがありました。今後も緩やかな上昇が見込まれるため、変動型を選ぶ場合は金利上昇2%まで耐えられるか試算することが重要です。
税制面では、2025年度の所得税改正により、青色申告特別控除が最大65万円から60万円に縮小されました。年間所得が高い投資家ほど影響が大きくなるため、経費計上の精度を高める必要があります。筆者はクラウド会計ソフトを活用し、領収書を即日入力して控除漏れを防いでいます。
また、2025年度固定資産税評価替えでは、築古木造の評価額が平均8%下落しました。税負担は軽くなる一方、減価償却費も減少するため、所得税の節税効果が小さくなる点に注意が必要です。シミュレーション時には、減価償却費の減少を織り込んで、手取り後キャッシュフローを算出しましょう。
数字を味方にする管理運営のコツ
まず押さえておきたいのは、購入後の運営こそが収益を決定づけるという事実です。運営効率を高めれば、想定より低い利回りでも十分な利益が期待できます。
入居者募集では、家賃設定を機械的に相場に合わせるのではなく、設備やサービスで差別化して値崩れを防ぎます。筆者はオートロック後付けや高速Wi-Fi導入で、相場より5%高い家賃を維持しています。初期費用はかかりますが、空室期間の短縮と原状回復費の削減で回収できます。
コストカットでは、共用部電気をLEDに交換するだけで年間電気代が30%減るケースもあります。また、火災保険は3年契約より5年契約の方が割引率が高いため、長期契約で支出を抑えると効果的です。これらの小さな積み重ねが年間キャッシュフローを底上げします。
最後に情報管理です。エクセルやシートで物件ごとの収支を月次で可視化すると、赤字兆候を早期に発見できます。筆者は毎月1日に入金状況を確認し、7日までに対策を決定するルールを設けています。数字を「後追い」ではなく「先読む」姿勢が、安定経営を実現します。
まとめ
本記事では「収益物件 収支計算 2025年 体験談」というテーマで、実質利回りの重要性、主要コスト、失敗事例、最新の金利・税制動向、運営改善策を解説しました。数字を細かく分解し、悲観シナリオまで想定することで、想定外を最小限にできます。まずはご自身の投資候補物件で、空室率と金利上昇を厳しめに設定したシミュレーションを作成してみてください。そのうえで、改善できるコストや設備投資を検討し、確かなキャッシュフロー計画を立てることが成功への近道です。行動を先延ばしにせず、今日から数字に向き合いましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 長期修繕計画ガイドライン(2025年改訂) – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025年上期 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 国勢調査2020・住民基本台帳概況(2025年更新) – https://www.stat.go.jp
- 財務省 2025年度税制改正大綱 – https://www.mof.go.jp

