家賃収入は安定していると聞くけれど、具体的に「利回り」がどれほど重要なのか、さらにREITはどう評価すれば良いのか──そんな疑問を抱く方は多いでしょう。実は利回りは表面だけを見ても本質はつかめず、REITでも異なる指標を組み合わせて分析する必要があります。本記事では初心者でも理解できるよう、利回りの基本からREIT評価の実践的な手順まで順を追って解説します。読み終えたときには、自分の投資目的に合った利回り水準を判断し、REITを比較検討できる力が身につくはずです。
利回りとは何を示すのか
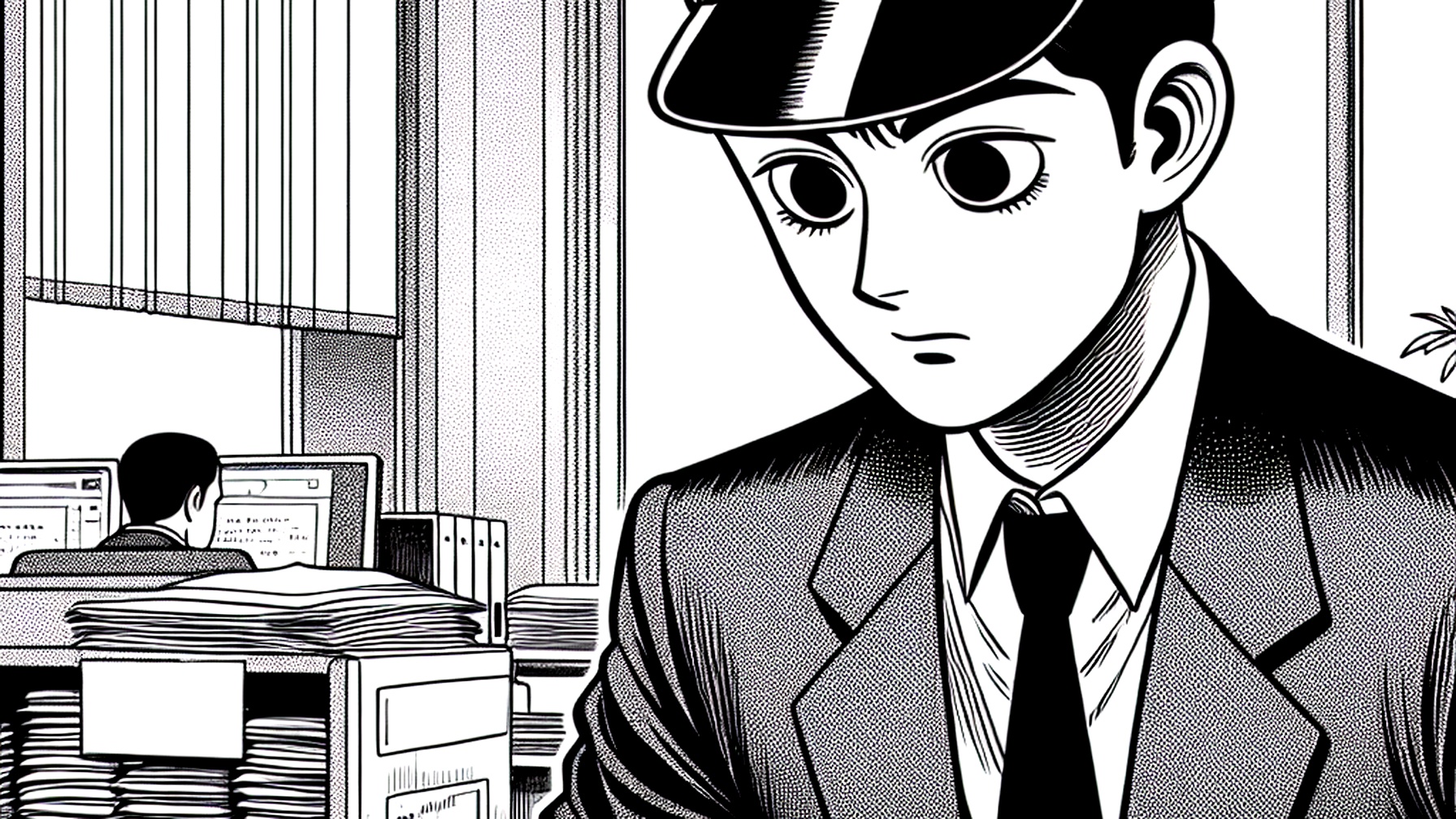
まず押さえておきたいのは、利回りが「投資額に対して得られる年間収益の割合」を示すという点です。多くのサイトで見かける「表面利回り」は年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標ですが、管理費や修繕費を含まないため、実態より高めに見える傾向があります。一方で「実質利回り」は諸費用を差し引き、手元に残るキャッシュフローを基準にするので、より現実的な判断に役立ちます。
しかし、利回りは高ければ必ずしも優れているわけではありません。日本不動産研究所の2025年10月調査によると、東京23区のワンルーム平均表面利回りは4.2%、アパートは5.1%です。これを大きく上回る数字が提示されている場合、立地や築年数にリスクが潜んでいる可能性を疑うべきでしょう。また、空室率や賃料下落のリスクを考慮すると、長期保有で安定収益を目指すなら実質利回り3%台後半〜4%台が一つの目安となります。
つまり利回りを評価するときは、収益と費用の内訳を丁寧に把握し、地域平均と比較する姿勢が欠かせません。数字の裏側に潜むリスクを読み解く力こそが、安定した投資成果への第一歩となります。
REITの仕組みと魅力
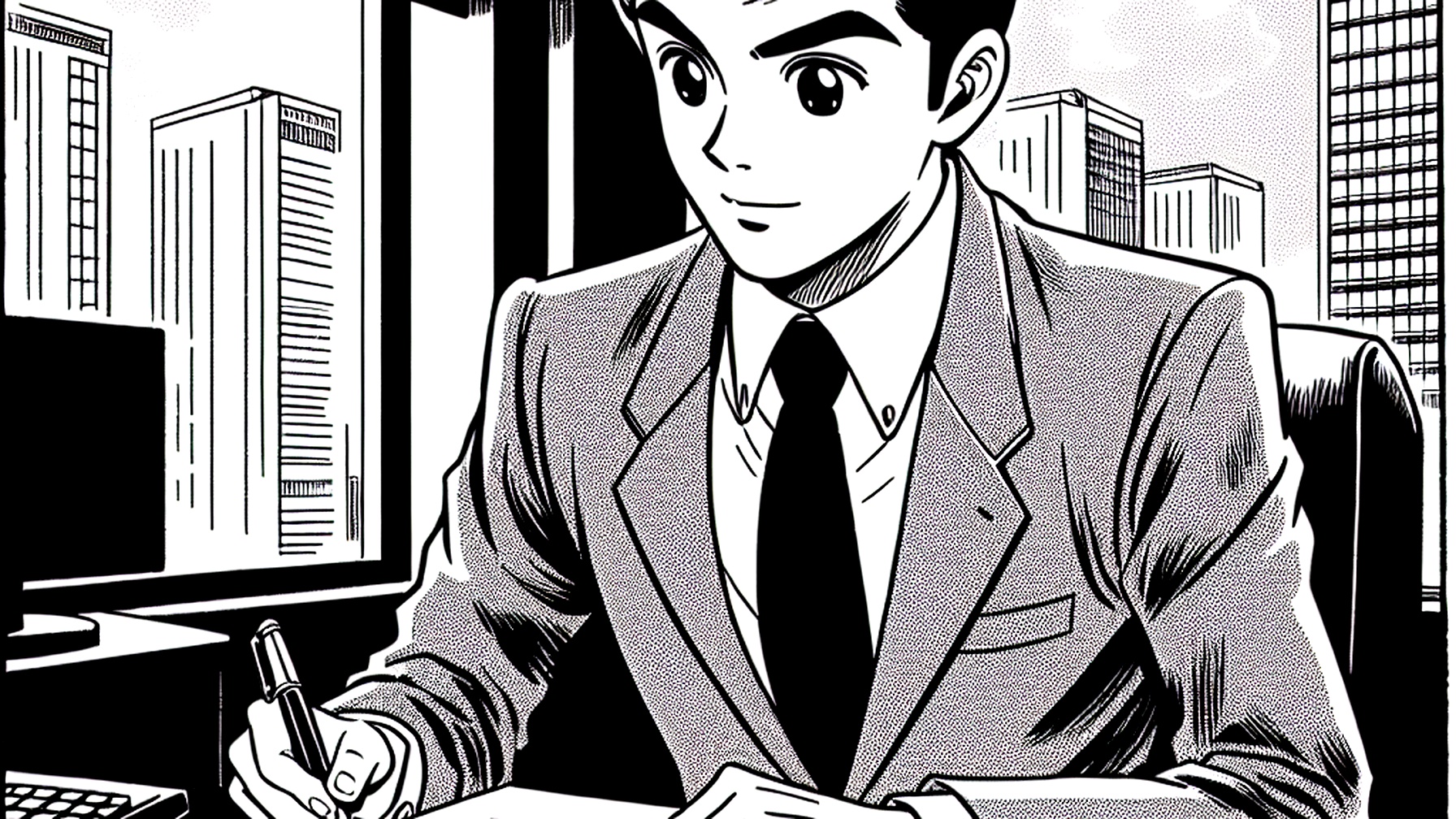
ポイントは、REITが複数の不動産をパッケージ化し、投資家に小口で販売する金融商品だという点です。不動産特定共同事業法に基づき運用され、投資家は証券取引所で株式のように売買できます。そのため、個別物件より少額から分散投資が可能で、流動性も高いのが大きな魅力です。
また、REITは税制メリットにも注目されます。投資法人が90%以上の利益を配当に回すことで、法人税が実質的に免除される仕組みがあり、その分が投資家への分配金に反映されやすい構造です。2025年10月時点で東証に上場するJ-REITは65銘柄、平均分配金利回りは3.7%前後で推移しています。
しかし、REITにも価格変動リスクがあります。景気動向や金利の影響を受けやすく、短期的には基準価額が上下しやすい点には注意しましょう。個別物件投資と比較すると、管理の手間は大幅に省けますが、物件の細部を自らコントロールできないため、運用会社の実力が結果に直結します。
評価で押さえる三つの視点
重要なのは、利回り以外にも「純資産価値(NAV)」「分配金成長率」「LTV(負債比率)」の三点を総合してREITを評価することです。NAVは保有不動産の時価総額から負債を差し引いた純資産を示し、株価がNAVより大きく割安なら潜在的な値上がり余地があります。一方、分配金成長率は物件の賃料アップや新規物件の取得による収益拡大が続いているかを測る指標となります。
さらに、LTVは総資産に対する有利子負債の割合を示し、数値が高すぎると資金繰りの余裕が乏しいと判断されがちです。一般に50%台前半までが健全とされ、60%を超えると金利上昇局面での負担増が懸念されます。よって、利回りが高くてもLTVが過大なら慎重に検討すべきです。
また、運用会社のスポンサー力も忘れてはなりません。大手デベロッパー系は物件取得ルートが豊富で資金調達コストも低く抑えやすい傾向があります。言い換えると、分配金の安定性はバックボーンの強さとも密接に関係しており、財務データと併せてチェックすることで投資判断の精度が高まります。
個別物件とREITの利回り比較
まず押さえておきたいのは、個別物件とREITでは利回りの算出方法が微妙に異なる点です。個別物件は実質利回りを重視し、現金収支の安定度が鍵となります。一方でREITは分配金利回りに加え、株価値上がり益も含んだトータルリターンが焦点となります。
例えば、東京23区のワンルームを3,000万円で購入し、年間家賃収入126万円、諸費用を差し引いた実質収入90万円なら実質利回りは3.0%です。同時期に平均分配金利回り3.7%のREITを1,000万円分購入すると、年間分配金は37万円です。ここで株価が5%上昇すればトータルリターンは8.7%相当となり、物件投資を上回る結果になります。
しかし、株価が5%下落すれば利回りは同じでもトータルリターンはマイナスに転じます。逆に個別物件は価格変動が緩やかでレバレッジを活用しやすい利点があります。つまり、短期的な値動きを許容できるか、長期の安定キャッシュフローを優先するかで選択が分かれるわけです。
2025年度の市場動向と投資戦略
実は、2025年度は日銀の緩やかな利上げ継続が想定されており、不動産全体の利回り格差が再評価される局面に入っています。金利上昇はREITの分配金に影響する一方、過度な借入を抑えている銘柄にはかえって割安感が出る可能性があります。また、インフレ率が2%台で推移すると仮定すれば、実質利回りを確保できる不動産セクターは依然として魅力的といえます。
ポイントは、金利感応度と物件タイプの組み合わせでリスクを分散することです。オフィス主体のREITはテナントの更新タイミングが利回りに直結しやすく、景気変動の影響を受けやすい一方、住宅や物流施設は需要が底堅く、分配金の安定に寄与します。個別物件でもファミリーマンションは回転率が低く、長期保有に向くなど、物件タイプごとの特性を見極める視点が欠かせません。
さらに、2025年度の住宅省エネルギー改修補助(上限50万円、12月申請締切)が継続中で、個別物件の修繕計画に活用できます。利回り改善につながる施策を取り入れることで、長期的な収益性を底上げできるでしょう。一方、REITはESG(環境・社会・ガバナンス)要素を評価する投資家が増えており、脱炭素方針を明示する銘柄がプレミアム評価を受けています。この流れを踏まえ、投資対象を選ぶ際には環境対応力も確認しておくと安心です。
まとめ
本記事では、利回りの基本概念からREITの評価指標、さらに2025年度の市場動向まで幅広く解説しました。数字を読む際は表面ではなく実質利回りを基準にし、NAVやLTVなど複数の指標を組み合わせることでリスクを可視化できます。また、個別物件とREITはリターンの構造が異なるため、自分の投資目的とリスク許容度を明確にすることが最重要です。最後に、金利や政策の変化を定期的にチェックし、データに基づいたリバランスを行うことで、長期的に安定した資産形成を目指しましょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo
- 投資信託協会 J-REITデータ – https://www.toushin.or.jp/
- 東京証券取引所 J-REIT Monthly Report – https://www.jpx.co.jp/
- 総務省統計局 消費者物価指数 – https://www.stat.go.jp/

