マンション投資を始めようと考えたとき、多くの人が「結局どの物件が一番得なのか」と悩みます。広告では高い表面利回りが強調されますが、実際の手取りを示す実質利回りを把握しないと資金計画は大きく狂います。本記事では最新の市場データを交えつつ、初心者でも分かるように表面利回りとの違いと物件タイプ別の特徴を解説します。読み終えるころには、自分の投資目的に最も合ったマンションを比較できる判断軸が手に入り、将来のキャッシュフロー計画が具体化するでしょう。
実質利回りとは何か
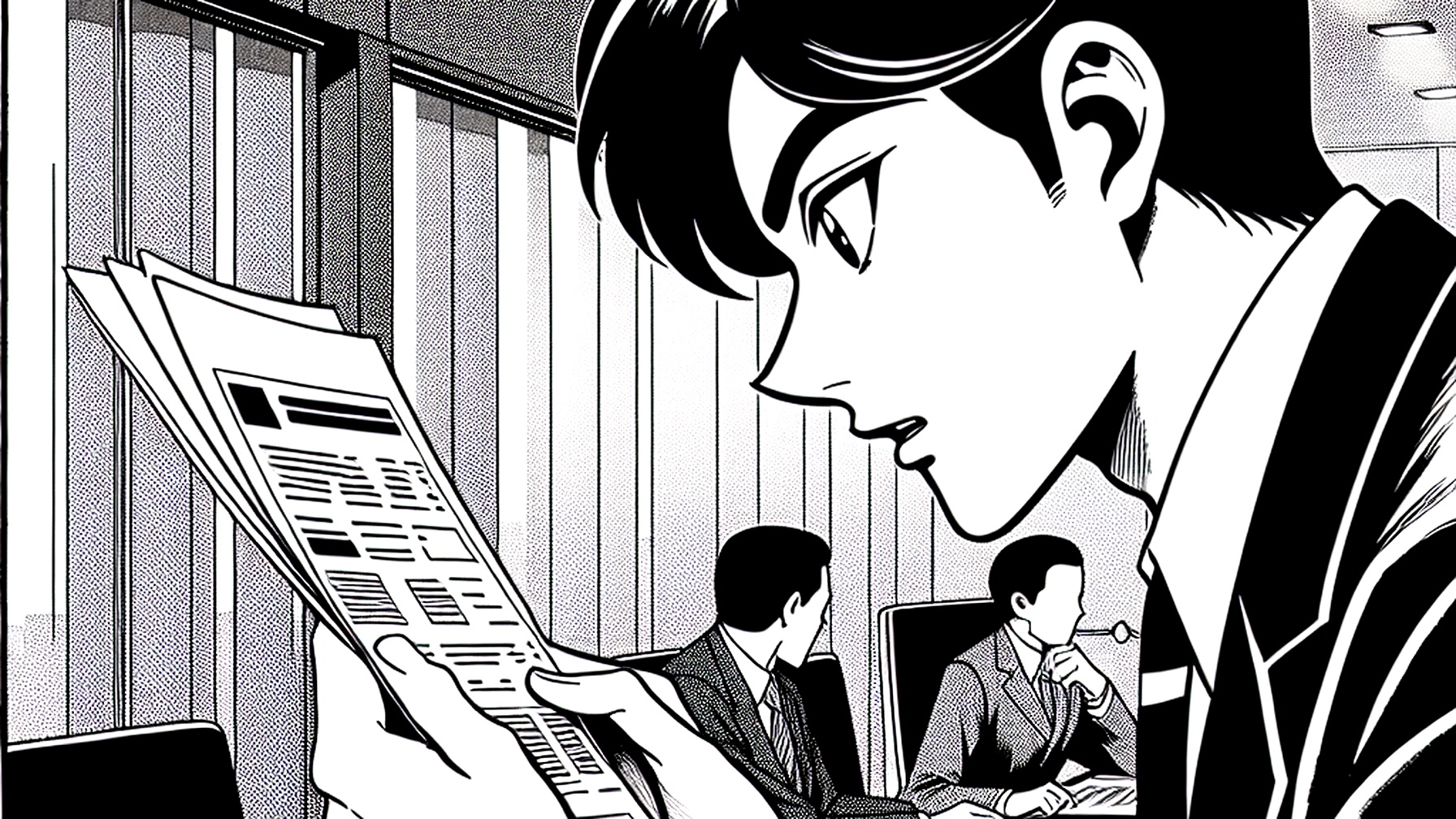
ポイントは、実質利回りが「年間の手取り運用益」を「総投資額」で割って算出される指標であることです。表面利回りと違い、購入時の諸費用や維持費を差し引くため、リアルな収益性を示します。
まず購入時には仲介手数料、登記費用、不動産取得税などが発生し、総額は物件価格の6〜8%に達します。維持段階でも管理費、修繕積立金、固定資産税が毎年必要となり、表面利回りを1〜1.5ポイント押し下げるのが一般的です。つまり実質利回りを無視すると、想定より月の手残りが数万円減るリスクが高まります。
一方、実質利回りは空室期間や家賃下落を加味して初めて信頼できる数字になります。国土交通省の「賃貸住宅市場景況調査」によれば、東京23区の平均空室期間は1.0か月前後ですが、築20年を超えると1.6か月に伸びる傾向です。この差を家賃に換算すると、年間収入が3〜5%目減りする計算になり、実質利回りに大きな影響を与えます。
表面利回りとの差を数字で確認
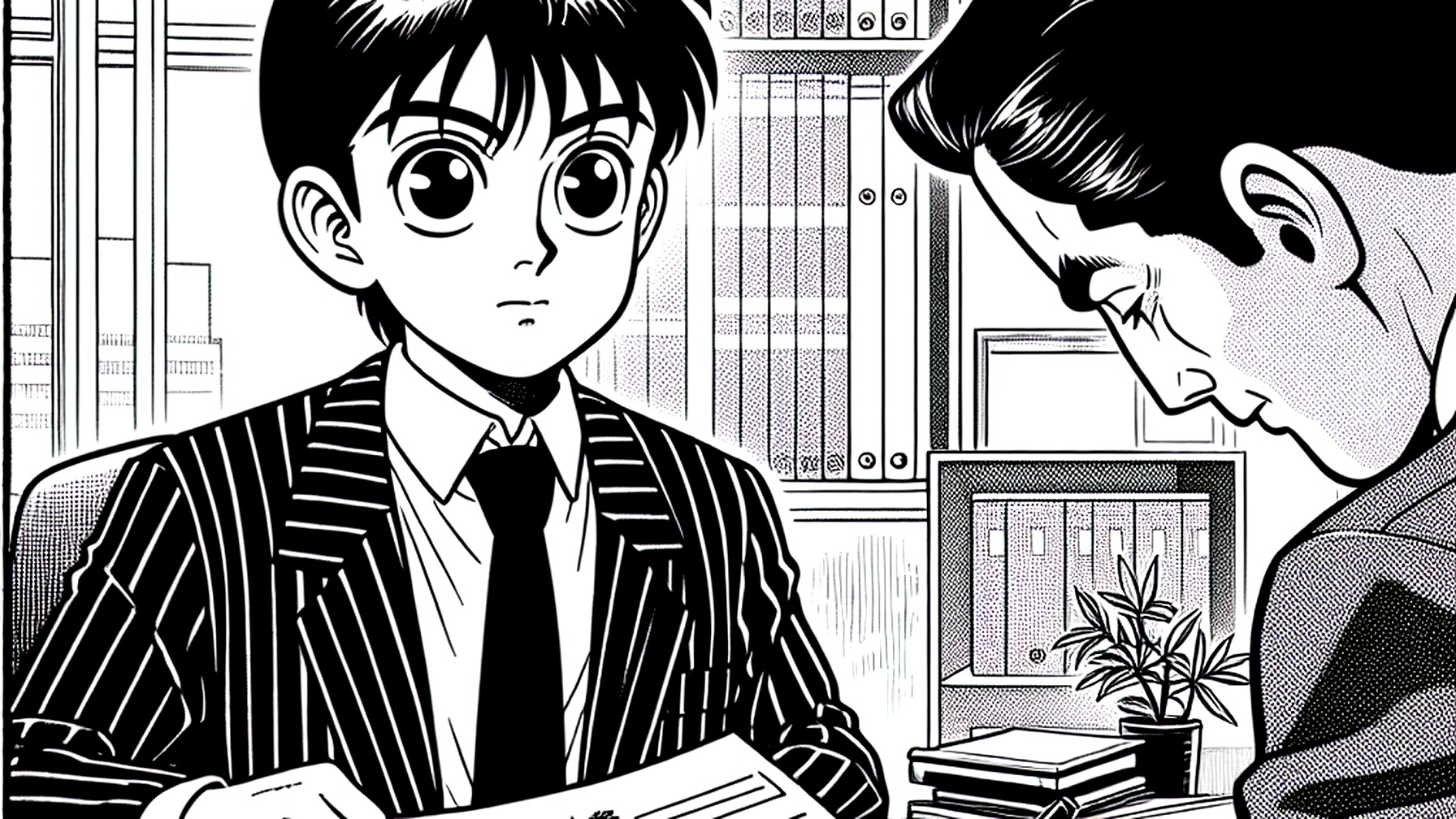
重要なのは、表面利回りから諸費用を丁寧に差し引いて初めて「実像」が見えることです。日本不動産研究所の2025年10月データによると、東京23区ワンルームの平均表面利回りは4.2%です。しかし購入費用7,000万円、諸費用7%と仮定すると、総投資額は7,490万円に増えます。
さらに年間家賃収入294万円(家賃月24.5万円)から、管理費と修繕積立金計36万円、固定資産税19万円、空室損失15万円を差し引くと、手取りは224万円に減少します。この時点で実質利回りは約3.0%となり、表面利回りとの差が1.2ポイント生じる計算です。言い換えると、表面利回りだけで判断するとキャッシュフローを約30%過大評価してしまうわけです。
ファミリータイプでは表面利回り3.8%に対し、管理費などが高めのため実質利回りは約2.5%へ下がりやすい傾向があります。逆にアパート投資の平均表面利回り5.1%でも、木造特有の修繕費が重くのしかかり、実質利回りは4%前後に落ち着くケースが多いです。数字で比較すると、物件タイプごとの差異が判然とします。
東京23区最新データで見る物件タイプ別比較
まず押さえておきたいのは、都心ワンルームが依然として安定需要を維持していることです。不動産経済研究所によれば、2025年10月の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しました。価格上昇分を家賃へ転嫁しきれないため、表面利回りは伸び悩んでいますが、単身世帯の流入が支えるため空室リスクが低い点は魅力です。
一方、ファミリーマンションは在宅勤務定着による郊外志向で、23区内でもエリア格差が拡大しています。家賃は堅調ながら購入価格の上昇率が大きく、実質利回りが圧迫されがちです。購入後にリノベーションを前提にすると、追加投資額が膨らみ、手取り率がさらに下がる点に注意が必要です。
アパートは土地付きで減価償却メリットを享受でき、実質利回りを高めやすいと語られます。しかし実は、木造の場合は大規模修繕が築15年目以降に集中するため、キャッシュフローが凸凹になりやすいです。金融機関も耐用年数を厳しく見るため、融資期間が短く毎月返済が重くなるケースが増えています。
こうした数字を踏まえると、都心ワンルームは利回り水準では見劣りしても、安定した入居需要と長期保有での資産価値維持で総合得点が高いと言えます。郊外の築浅アパートは高利回りを狙えますが、修繕計画と出口戦略を明確にしないと実質利回りが想定を下回るリスクが大きいと理解しておきましょう。
実質利回りを向上させる管理と資金計画
ポイントは、収入を増やすよりも「費用を抑える」ほうが実質利回り改善効果が大きいことです。まず管理会社の選定で手数料を家賃の5%から3%に抑えれば、年間手取りは直ちに2ポイント近く向上します。サブリース契約を検討する際は、一時的な安定収入と引き換えに、家賃の10〜15%が差し引かれる点を冷静に計算に入れる必要があります。
修繕費用の平準化も実質利回りを左右します。長期修繕計画をオーナー自ら把握し、毎月3,000円程度を別口座で積み立てれば、大規模修繕時に慌てて追加融資を探すリスクを減らせます。国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」でも、計画的な積み立てが資産価値維持に直結すると強調されています。
資金調達では、2025年度も継続中の住宅金融支援機構の「賃貸住宅融資」が固定1.9%前後と民間より低めです。期間を35年に設定できるため、月々の返済を抑えてキャッシュフローを安定させられます。また金利上昇リスクに備え、変動金利を選ぶ場合でも返済比率を家賃収入の50%以下に留めると、実質利回りの下振れを防ぎやすくなります。
このように、管理費の削減、修繕積立、適切な融資条件という三本柱を整えることで、表面利回りが同水準の物件でも最終的な実質利回りに1〜1.5ポイントの差が生まれます。つまり、運営手法こそが投資成果を分ける最大の要因になるのです。
まとめ
本記事では「マンション投資 比較 実質利回り」を軸に、表面利回りとの違い、物件タイプ別の最新データ、そして運営による改善策を解説しました。実質利回りは手取りベースの指標であり、諸費用や空室損失を含めてこそ真価が分かります。東京23区の平均表面利回りは4%前後ですが、実質では3%程度に落ち着く点を念頭に置きましょう。管理費の見直しと長期修繕計画、低金利融資の活用を組み合わせれば、同じ物件でも手取り収益を着実に伸ばせます。まずは気になる物件の収支シートを自分で作り、実質利回りを算出する習慣を身に付けることからスタートしてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場景況調査 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 長期修繕計画ガイドライン – https://www.mlit.go.jp
- 住宅金融支援機構 融資商品一覧 – https://www.jhf.go.jp

