家賃収入で暮らしたい、老後資金を増やしたい――そう考えて「アパート経営 儲かるのか」と検索した人は多いでしょう。しかしネット上には成功談と失敗談が入り混じり、何を信じればよいのか迷いがちです。本記事では、収益の仕組みから2025年度の最新制度、リスク対策までを網羅し、初めての方でも具体的な判断材料を得られるよう解説します。読み終える頃には、自分に合った投資戦略の輪郭が見えるはずです。
アパート経営で利益が生まれる仕組み
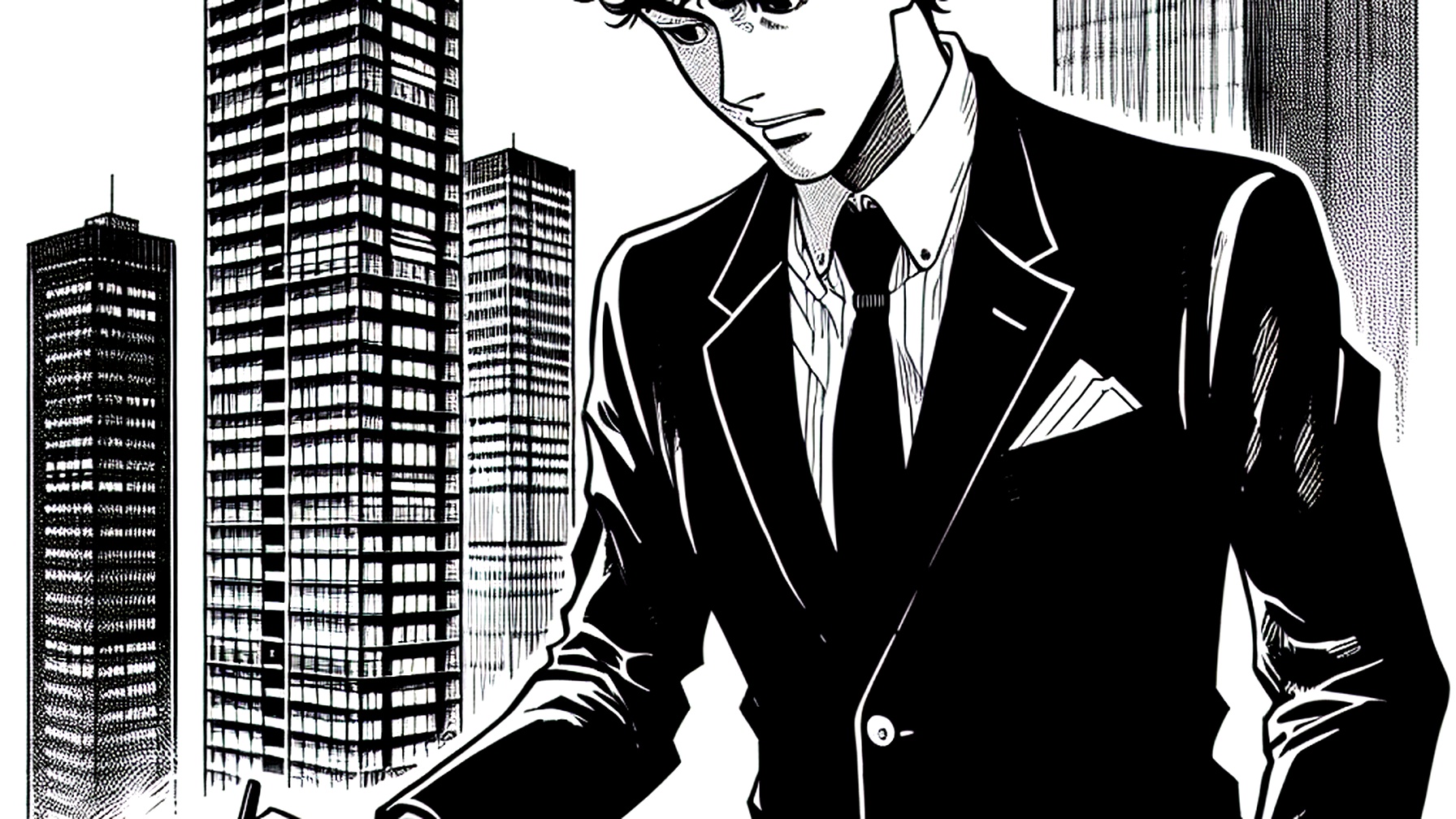
まず押さえておきたいのは、アパート経営の利益がキャッシュフローと資産価値の二つで構成される点です。キャッシュフローとは家賃収入からローン返済や運営費を差し引いた手残り金を指し、毎月の生活費を賄えるかどうかの鍵になります。一方で資産価値は物件売却時の価格に影響し、将来の出口戦略を左右します。
国土交通省の2025年8月住宅統計によると、全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しました。つまり需要は底堅いものの、依然として五戸に一戸は空いている計算です。空室リスクを減らし安定収益を確保するには、立地や入居者ニーズを細かく調べる姿勢が欠かせません。また、家賃設定を周辺相場より5%下回るだけでも平均入居期間が約1.4年延びるという調査結果もあり、長期の視点で収益を伸ばす工夫が求められます。
実は、キャッシュフローを最大化するには家賃を上げるより支出を抑える方が効果的な場合が多いです。管理費の交渉、修繕計画の長期化、保険の見直しなど、小さな改善を積み上げると家賃一室分に匹敵する利益が生まれることもあります。つまり、オーナーの経営努力が数字に直結するビジネスだと言えます。
初期費用とランニングコストの現実
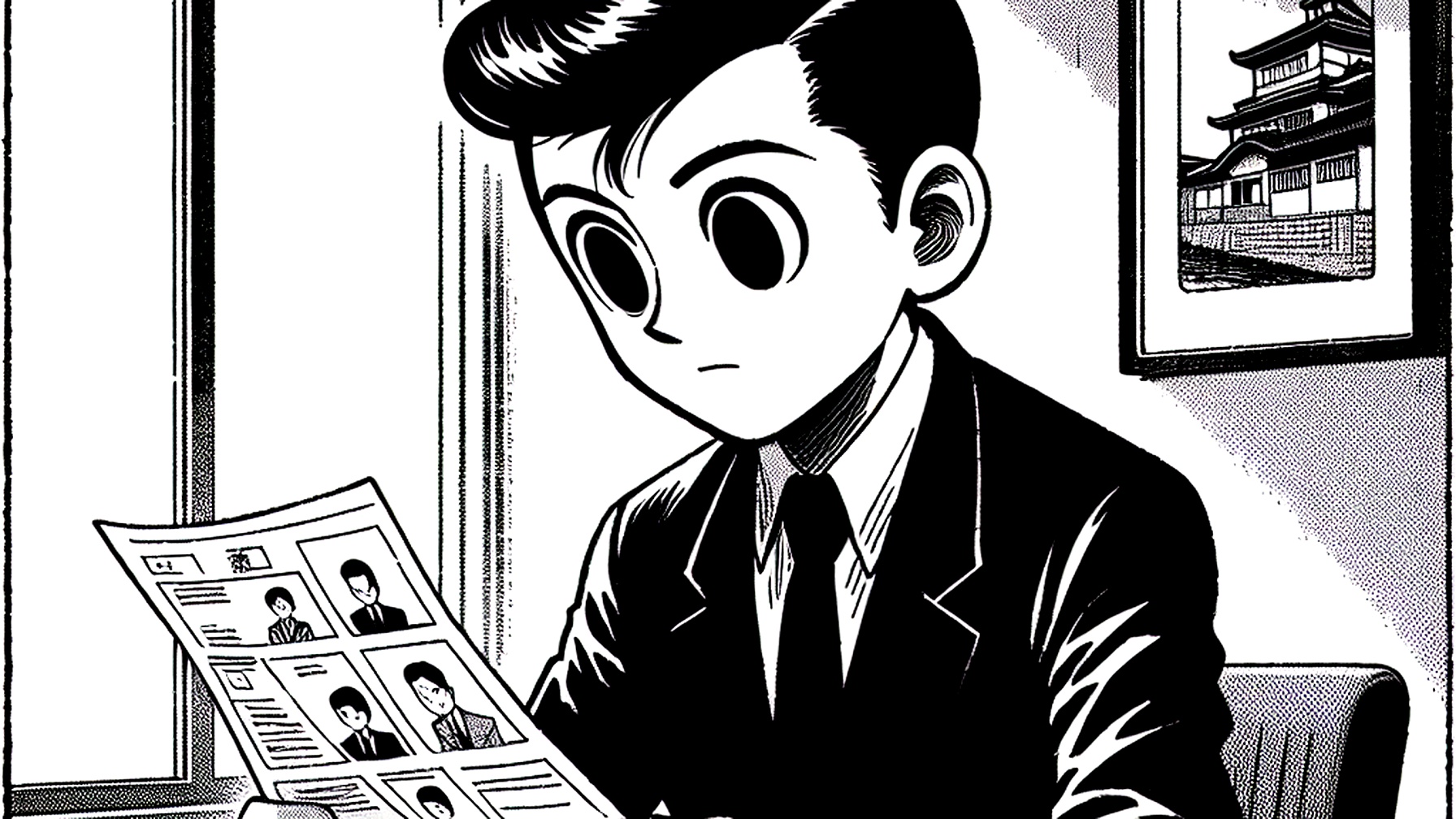
重要なのは、物件価格以外の支出を正確に把握することです。仲介手数料や登記費用、火災保険、そして取得税などを合算すると、購入価格の7〜10%が初期費用として必要になります。例えば8,000万円の一棟アパートなら、600万円前後を現金で用意する計算です。
さらに、毎年かかるランニングコストも見落とせません。固定資産税、管理委託料、共用部の電気代、将来の大規模修繕積立などを合計すると、年間家賃収入の15〜20%が消えるケースが一般的です。空室が生じた月にはローン返済が重荷になるため、最低でも半年分の返済額を自己資金としてプールしておくと安心でしょう。
ポイントは、これらのコストを金融機関に提出する収支計画書に正しく反映させることです。日本銀行の調査では、計画書が詳細な投資家ほど融資条件が年0.2%程度優遇される傾向が確認されています。金利差0.2%は30年で約300万円の差を生むため、見積もりの精度が将来の利益に直結するのです。
キャッシュフロー改善の具体策
まず押さえておきたいのは、家賃収入を「増やす方法」と支出を「減らす方法」を同時に考えることです。家賃収入を増やす手段としては、Wi-Fi無償提供やペット可など設備・ルールの付加価値化が即効性を発揮します。これにより月額2,000円の家賃アップでも、満室稼働なら年間で24万円の増収となり、利回りを0.3ポイント改善できる場合があります。
一方で支出削減の代表例が、修繕積立の平準化です。実際に10年目に予定される外壁塗装を12年目に後ろ倒ししただけで、年間キャッシュフローが50万円改善した事例もあります。また、管理会社の変更で管理料を家賃の5%から3%に下げ、年間36万円の経費削減に成功したオーナーもいます。このように、家賃一室分に相当する額をコスト面で生み出すことも現実的なのです。
つまり、収入増と支出減を組み合わせれば、購入時に利回り6%だった物件を実質7%超まで引き上げることも可能です。数字で把握し、改善策を一覧化する「アクションプラン表」を作ると漏れなく実行できます。
2025年度の制度を活用する方法
実は、2025年度もアパート経営を後押しする制度がいくつか継続しています。代表的なのが「住宅ローン減税の賃貸併用拡充」で、オーナー自身が一部に居住する場合、年間最大40万円の所得控除が10年間受けられます。ただし、控除対象は床面積が40㎡以上かつ全体の半分以上を自己居住部分とすることが条件です。
また、環境性能の高い賃貸住宅に対しては「ZEH-M支援事業」が2025年度も存続し、戸当たり最大70万円の補助金が出ます。期限は契約ベースで2026年2月までなので、設計段階から断熱等級5以上を確保しておくと良いでしょう。さらに、地方自治体独自の家賃補助制度を活用すると入居促進にもつながります。東京都は2025年度も一部地域で若年単身者向けに月額3万円を最長2年間補助しており、オーナーは空室リスクを抑えながら安定収入を得られます。
ポイントは、国と自治体の制度を組み合わせ、初期投資を圧縮しつつ入居需要を高めることです。制度の受付期間や予算枠は変更されるため、着工前に公的サイトで最新情報を確認し、書類を早めに準備しましょう。
リスクと向き合うポイント
まず忘れてはならないのが、アパート経営が事業であるという認識です。空室リスク、修繕リスク、金利上昇リスクの三つは避けられませんが、適切な対策でコントロールは可能です。例えば空室リスクには、賃貸需要の強い駅徒歩10分圏か、大学・工業団地など雇用拠点の近くを選ぶことで備えられます。
修繕リスクについては、築年数と設備グレードによって将来費用が大きく変わります。築浅を高値で買うより、築15年前後で大規模修繕を一度終えた物件を安く取得する方が、長期的には利益が残るケースも多いです。さらに金利上昇リスクに対しては、10年以上の長期固定金利を選ぶか、変動金利でも元金均等返済にしておくと、総返済額を予測しやすくなります。
結論として、リスクを完全にゼロにすることは不可能ですが、数値化し、手を打てる範囲を広げることで「儲かるかどうか」の確率は大きく変わります。継続的なデータ確認と改善が、長期的な成功を決めるのです。
まとめ
ここまで「アパート経営 儲かるのか」という疑問に対し、収益構造、費用の現実、キャッシュフロー改善策、2025年度の制度、リスク管理の五つの視点で解説しました。利益の源は家賃収入と資産価値であり、支出を丁寧に抑えることで手残りを増やせることが分かります。さらに国や自治体の補助金を活用し、立地と設備を最適化すれば空室リスクも下げられます。まずは自身のライフプランに合わせた収支シミュレーションを作成し、小さな改善から始めてみてはいかがでしょうか。継続的な学びと行動が、安定した不動産投資への近道となります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年8月速報値 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局 家計調査 2025年版 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/
- 住宅金融支援機構 2025年度フラット35調査 – https://www.jhf.go.jp/
- 全国賃貸管理ビジネス協会 賃貸住宅市場レポート2025 – https://www.zenchin.biz/

