初心者が不動産投資を考えるとき、「立地重視か利回り重視か、どっちを選べば失敗しないのか」と迷うものです。ネットには成功談があふれていますが、失敗談こそ学びの宝庫です。本記事では「不動産投資 失敗例 どっち」という視点から、選択を誤った原因と具体的な回避策を丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合った判断軸を持ち、危険な道を回避する力が身につくはずです。
失敗例に潜む共通の心理パターン
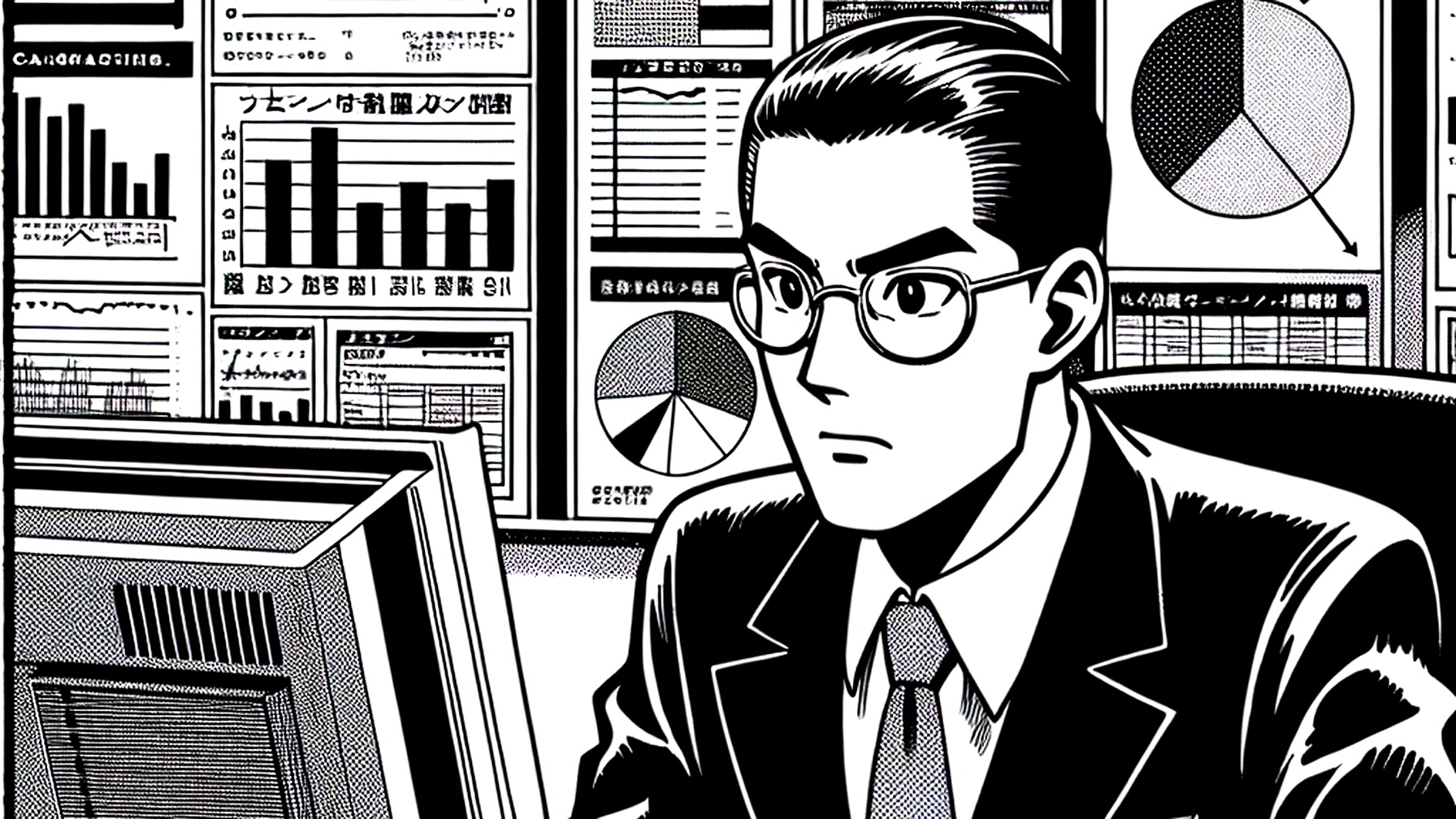
まず押さえておきたいのは、失敗した投資家が似たような心理状態に陥っている点です。日本不動産研究所の調査では、初心者の約6割が「買わない後悔」を恐れて早期契約に踏み切ったと回答しています。この「置いていかれる不安」が、情報収集不足や物件比較の省略を招きやすいのです。
次の段落では、楽観バイアスが働くケースを見てみましょう。販売資料のシミュレーションは満室・低金利前提で作られやすく、投資家は数字の裏に潜むリスクを深掘りしないまま判断しがちです。その結果、空室率が想定より5ポイント高まっただけでキャッシュフローが赤字に転落する事例が後を絶ちません。
もう一つ見逃せないのが、情報源の偏りです。販売会社やセミナー講師の話だけを信じ、第三者評価を取らないまま契約するパターンが典型的です。つまり、心理的な焦りと情報の片寄りが重なると、失敗の確率が大きく跳ね上がるのです。
資金計画でつまずくケースと回避策
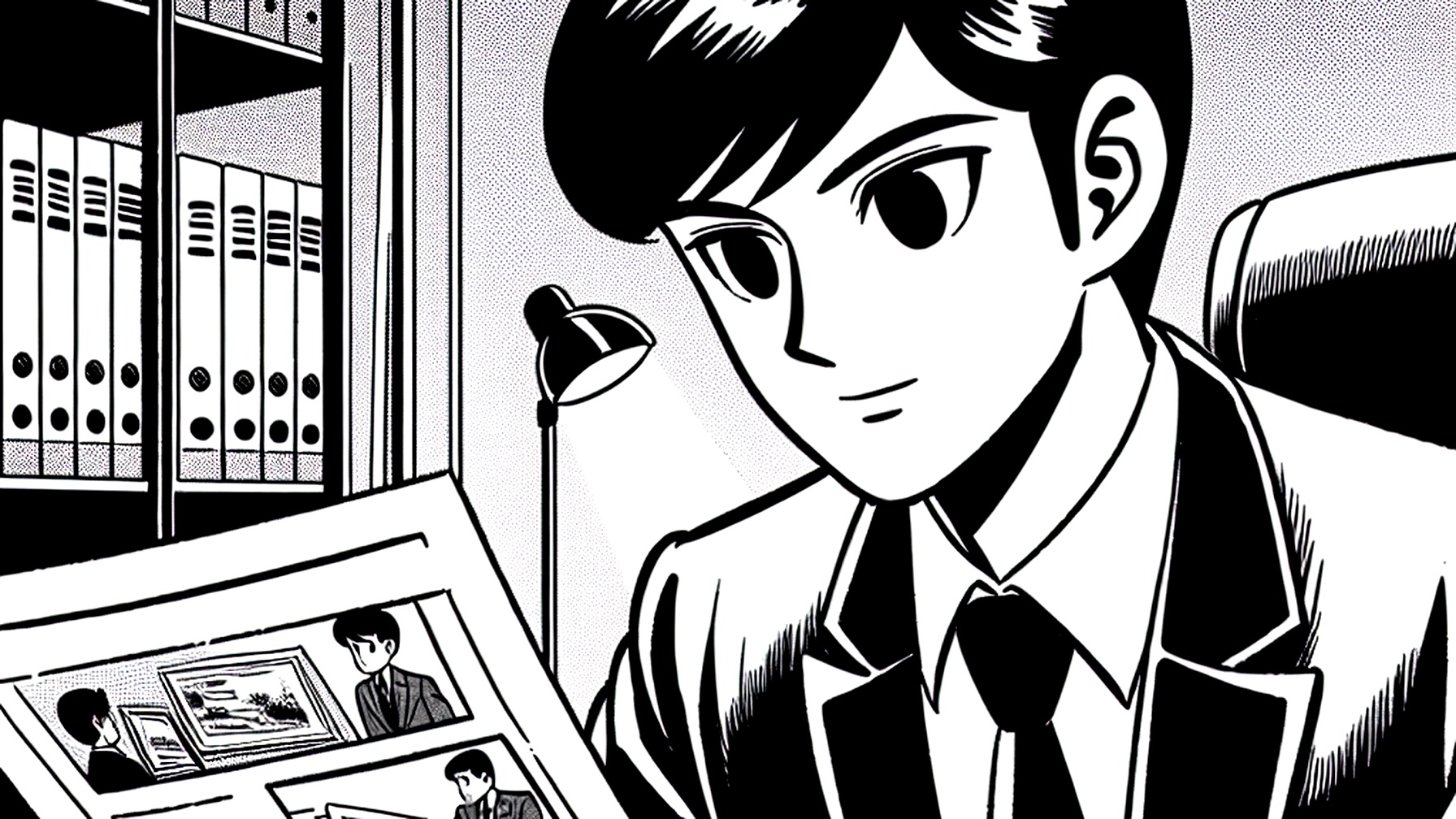
重要なのは、物件価格だけでなく長期の資金計画を組むことです。金融庁の2024年度調査によると、返済比率が家賃収入の50%を超えるとデフォルト率が急上昇します。それでも「頭金ゼロで高利回り物件を狙えば大丈夫」と考え、フルローンを組む例が後を絶ちません。
次に、金利上昇リスクを軽視した事例を見てみます。2023年からの段階的な金利正常化により、変動金利は1.2%台まで上昇しました。返済期間25年の場合、金利が0.5ポイント上がるだけで総返済額は約300万円増えます。シミュレーションに金利上昇2%を織り込まなかった投資家は、返済負担に耐えきれず早期売却を余儀なくされています。
一方で、修繕積立を怠った失敗例も顕著です。築20年を過ぎると、外壁塗装や給排水管更新で平均150万〜200万円かかります。毎月1万円ずつ積み立てるだけで備えられたはずの費用を後回しにした結果、急な修繕でキャッシュアウトし、資金繰りが破綻するのです。ここでも「どっちを選ぶか」という判断より、「いくら備えるか」という視点が欠かせません。
立地か利回りか、どっちで迷うと危ない?
ポイントは、立地と利回りを二者択一で考えないことです。国土交通省の住宅市場動向調査(2025年版)では、駅徒歩5分以内と15分以上の区分マンションを比較した場合、空室期間は平均で約1.8倍の差が出ています。それでも表面利回りが高い郊外物件に吸い寄せられ、長期的な安定性を犠牲にする失敗が続きます。
具体例で解説しましょう。都心区分マンション(利回り4%)と郊外一棟アパート(利回り8%)をシミュレーションすると、10年後の累積キャッシュフローは税引前でほぼ同水準になることがあります。郊外物件は修繕費と空室損が重く、実質利回りが想定より下がるからです。つまり、表面利回りだけで「どっちが得か」を決めると、結果としてどちらも期待以下になるリスクが高まります。
一方で、人ロ減少が緩やかな地方中核都市では、利回り6%台でも駅近の区分マンションが見つかるケースがあります。この「中庸ゾーン」を探す発想が、立地と利回りのトレードオフを和らげます。物件検索サイトで掲載期間が長い案件は、交渉次第で価格を5%程度下げられることもあるため、冷静な比較が功を奏します。
管理と出口戦略を甘く見ると起きる落とし穴
実は、購入後の運営フェーズで失敗が顕在化することが多いのです。管理会社まかせにして賃料改定を怠ると、市場家賃との差が年間数十万円に広がります。さらに、クレーム対応の遅れが評判を落とし、募集サイトの閲覧数が減る悪循環に陥ります。
出口戦略を描かないまま購入した例も要注意です。築20年を超えた木造アパートは、金融機関の融資期間が短くなり、買い手が限られます。その結果、想定していた売却価格より10%以上下がることが珍しくありません。購入前に「何年後に、どの市場で、誰に売るか」を決めるだけで、戦略の精度は大きく高まります。
また、2025年度の税制では、保有期間5年超で譲渡益税率が20.315%に軽減される現行制度が継続しています。この区切りを意識して売却タイミングを調整するだけで、手残りを数百万円単位で守れる場合があります。制度を知るかどうかが、最後の収益を左右するのです。
2025年度に活用できるリスク低減の制度と実務
まず押さえておきたいのは、減価償却費を活用した節税効果です。鉄筋コンクリート造なら法定耐用年数は47年で、築30年の中古物件でも残存期間は17年あります。毎年の経費計上で課税所得を圧縮することで、キャッシュフローの改善につながります。
次に、国土交通省が2025年度も継続する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」があります。賃貸住宅でも認定を受ければ、工事費の三分の一(上限250万円)の補助を受けられます。省エネ性能を上げて競争力を高めつつ、自己負担を抑えられるため、空室リスクと修繕費リスクを同時に下げられます。
金融面では、日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」に類似した賃貸住宅オーナー向け融資が2025年度も利用可能です。金利は1%台半ばで固定期間が長く、地銀よりも安定した条件を得やすいのが特徴です。複数行を比較し、長期固定を一部組み込むことで金利変動リスクを平準化できます。
最後に、区分所有法の改正(2024年施行)により、修繕積立金の不足があるマンションは売却時に追加負担が発生するケースが明確化しました。購入前に管理組合の長期修繕計画を精査し、将来の一時金徴収リスクを数字で見える化することが、2025年以降の必須スキルになります。
まとめ
本記事では「不動産投資 失敗例 どっち」というテーマで、心理面から資金計画、立地選択、管理・出口戦略、そして2025年度の制度活用まで幅広く解説しました。立地か利回りかを単純に比べるのではなく、長期シミュレーションと客観データで裏付ける姿勢が成功の土台になります。次に物件を検討するときは、想定外の出費と売却までの道筋を同時に描き、制度を確実に活用してください。その一歩が、安定収益への最短ルートとなるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本不動産研究所 不動産投資家アンケート2024 – https://www.reinet.or.jp
- 金融庁 フィナンシャルレビュー第147号 – https://www.fsa.go.jp
- 日本政策金融公庫 2025年度融資資料 – https://www.jfc.go.jp
- 国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業概要2025 – https://www.mlit.go.jp/project

