アパート経営に興味はあるものの、「空室ばかりで赤字になりそう」「相続対策になると聞いたけれど本当?」と迷っていませんか。ネット上には「やめとけ」という強い否定的な声も散見され、初めての方ほど一歩を踏み出しづらいのが現実です。本記事では、15年以上の実務経験をもとに、アパート経営を基礎から解説しつつ、相続対策として取り入れる際の注意点まで丁寧にお伝えします。読了後には、なぜ「やめとけ」と言われるのかを冷静に判断し、実際に行動するためのポイントがつかめるはずです。
アパート経営を巡る三つの誤解と現実
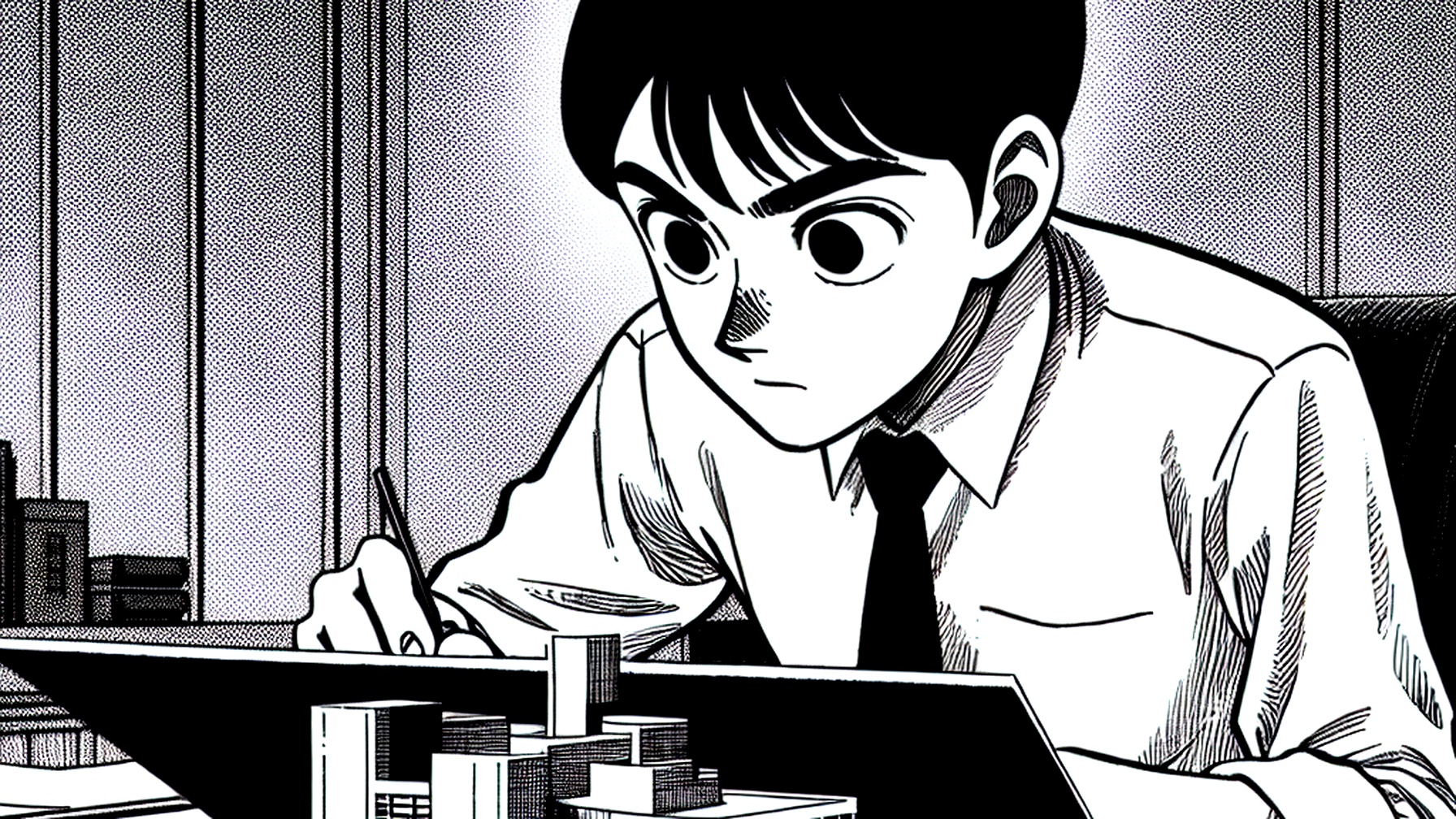
まず押さえておきたいのは、巷で語られるリスクの多くが誤解や情報不足から生じている点です。重要なのは数字と事実で判断する姿勢になります。
最初の誤解は「空室だらけで収益が出ない」というものです。国土交通省住宅統計によれば、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で、前年から0.3ポイント改善しました。確かに空室はありますが、立地や賃料設定を工夫すれば稼働率80%超を維持するオーナーも多く、平均値だけで判断するのは危険です。
二つ目は「修繕費が読めずに破綻する」という恐れです。実は、築年と構造ごとに修繕サイクルはほぼ定型化しており、長期修繕計画を立てれば年間家賃収入の10〜15%を目安に積み立てるだけで大半のリスクを吸収できます。計画性こそが鍵だと覚えてください。
三つ目に「相続税対策になるから節税できる」という過度な期待があります。建物は相続評価額が時価より下がるため効果は確かにありますが、借入金の利息や運営コストを無視すれば本末転倒です。つまり、節税だけを目的に走らず収益性とのバランスを測ることが現実的な戦略になります。
基礎から押さえる収支計算とキャッシュフロー
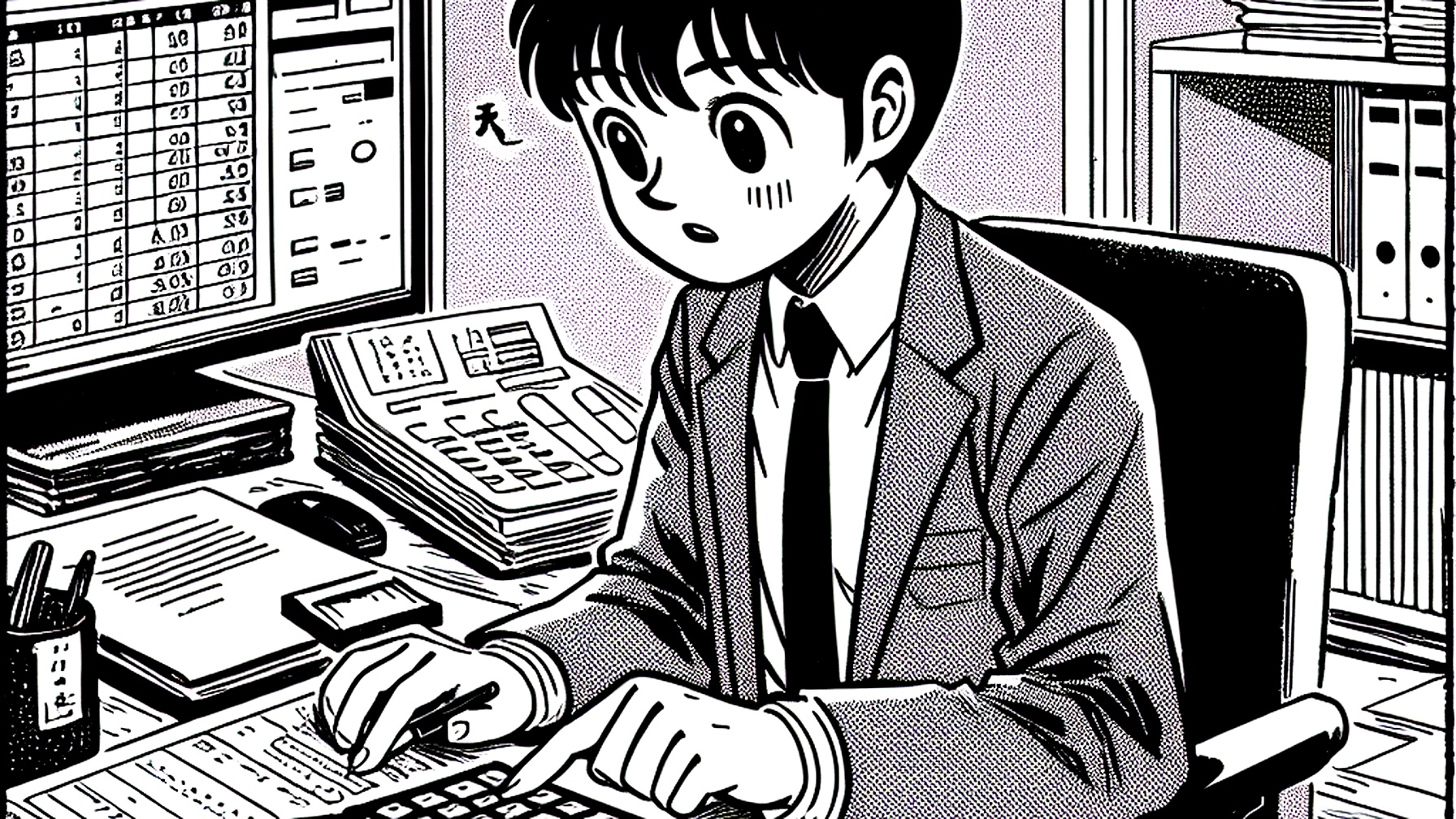
ポイントは、家賃収入から経費と返済を差し引いた手残りを正確に把握することです。この手残りをキャッシュフローと呼び、黒字か赤字かを判断する最重要指標になります。
まず家賃収入は満室想定額の90%で計算するのが実務的です。空室率10%を織り込むことで、短期的な退去や賃料交渉に動じないモデルが作れます。一方、経費は管理委託料・固定資産税・火災保険・修繕費などを合算し、年間家賃の30%前後を見込んでおくと安全です。
さらに借入金返済を組み込む際は金利上昇リスクもシミュレーションに入れます。たとえば年1%で借りていても、金融緩和が正常化すれば1.5%程度までは上がる可能性があります。返済比率が家賃収入の50%を超えないように調整すれば、金利が動いても致命傷にはなりません。
最後に手残りがプラス5万円/月を下回る場合、突発修繕一回でキャッシュが枯渇するおそれがあります。家賃10万円の部屋が6戸ある程度の規模でも、年間60万円は純利益を目指す姿勢を忘れないでください。数字が読めれば「やめとけ」という声に振り回されずに済みます。
相続対策としてのアパート経営はなぜ「やめとけ」と言われるか
実は、「相続税を減らせる」と勧められたものの、家族が引き継ぐ頃には赤字物件になっているケースが後を絶ちません。ここが「やめとけ」と警告される最大の理由です。
まず、相続開始後に物件価値が大幅に下がれば、評価減による節税効果よりキャピタルロスが上回ります。築年数が進み過ぎた木造アパートは特に下落が急で、結果的に子どもが売却しても借入金が残る事態が起こり得ます。
次に、相続人が不動産運営の知識を持たず、管理会社との連携が取れない場合、空室や家賃滞納が一気に増えるリスクがあります。経営者が変わるタイミングは入居者も敏感に察知し、退去を決めることがあるからです。
結論として、相続対策を目的にアパートを建てるなら、建築前に30年後の需要予測と残債シミュレーションを行い、相続人が引き継ぎやすい仕組みを整えておく必要があります。対策を怠れば「やめとけ」は的中してしまいます。
「やめとけ」を避けるための物件選びと運営のコツ
重要なのは、家賃需要が底堅いエリアを選び、賃貸商品としての競争力を常に高める姿勢です。これが最終的なリスクヘッジになります。
立地選びでは、最寄り駅から徒歩10分以内かつ人口が純増している市区町村を優先しましょう。総務省の住民基本台帳人口移動報告では、東京23区や主要政令市の一部は2025年も転入超過が続いており、空室リスクを抑えやすい環境が整っています。
加えて、間取りと設備のアップデートが欠かせません。単身者向けワンルームであっても、IoT対応のスマートキーや高速インターネット無料を採り入れれば月5000円程度の賃料アップが期待できます。設備投資は5年で回収できるラインを意識するとキャッシュフローを圧迫しません。
運営面では、管理会社との定例ミーティングを最低でも四半期ごとに設け、入居者属性の変化や周辺相場の動向を共有します。この習慣だけで募集家賃をタイムリーに改定でき、空室期間の短縮につながります。言い換えると、日常的な微調整こそが長期的な安全運転の秘訣です。
2025年度の税制と金融環境を踏まえた長期戦略
まず、2025年度の相続税基礎控除は「3000万円+法定相続人×600万円」で変更はありません。土地評価も路線価方式が維持され、貸家建付地の評価減ルールも継続しています。したがって、節税メリットは引き続き有効ですが、金融環境とのセットで考える必要があります。
日本銀行は2024年末にマイナス金利を解除し、2025年10月時点の短期金利は0.5%前後で安定しています。変動金利の住宅ローンは上昇しましたが、アパートローンの固定金利は1.8〜2.2%程度で推移しており、長期固定を選ぶことで金利上昇リスクを抑えられます。
一方で、建設コストは資材高騰の影響で2019年比約18%上昇しました。新築を選ぶ際は、土地購入費より建物コストが重くなる可能性を頭に入れ、収支シミュレーションをより保守的に設定することが欠かせません。中古物件をリノベーションして利回りを高める戦略も有効です。
まとめると、税制メリットを享受しつつ安定経営を目指すには、固定金利で借り入れ、修繕積立を厚めに確保し、物件の競争力を継続的に高める三本柱が欠かせません。これらを実践できれば、「アパート経営 基礎から 相続対策 やめとけ」という言葉は単なる警告ではなく、成功へのチェックリストへと変わります。
まとめ
本記事では、アパート経営の誤解を解き、収支計算の基礎から相続対策の落とし穴まで解説しました。ポイントは、需要のある立地選び、保守的なキャッシュフロー管理、そして家族が引き継ぎやすい運営体制を事前に整えることです。不安を乗り越える最短ルートは、数字と事実に基づき、小さく始めて改善を重ねる姿勢に尽きます。今日から物件情報を集め、試算表を自分で作成してみましょう。行動を起こした先に、安定した資産形成への道が開けます。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp/
- 国税庁 相続税のあらまし(2025年度版) – https://www.nta.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp/
- 日本政策金融公庫 中小企業事業融資情報 – https://www.jfc.go.jp/

