多くの投資家が保有期間の後半で「マンション投資 売却できない」と感じます。購入時は高い入居率と安定収益を見込んでいたのに、いざ売ろうとすると希望価格に届かない、そもそも買い手が現れない――そんな行き詰まりは珍しくありません。本稿では、その原因を市場データと実務経験の両面から整理し、価値を高める改善策や売却以外の選択肢まで掘り下げます。読後には、次の一手を選び取る具体的な視点が得られるはずです。
売却できないと感じる主な理由
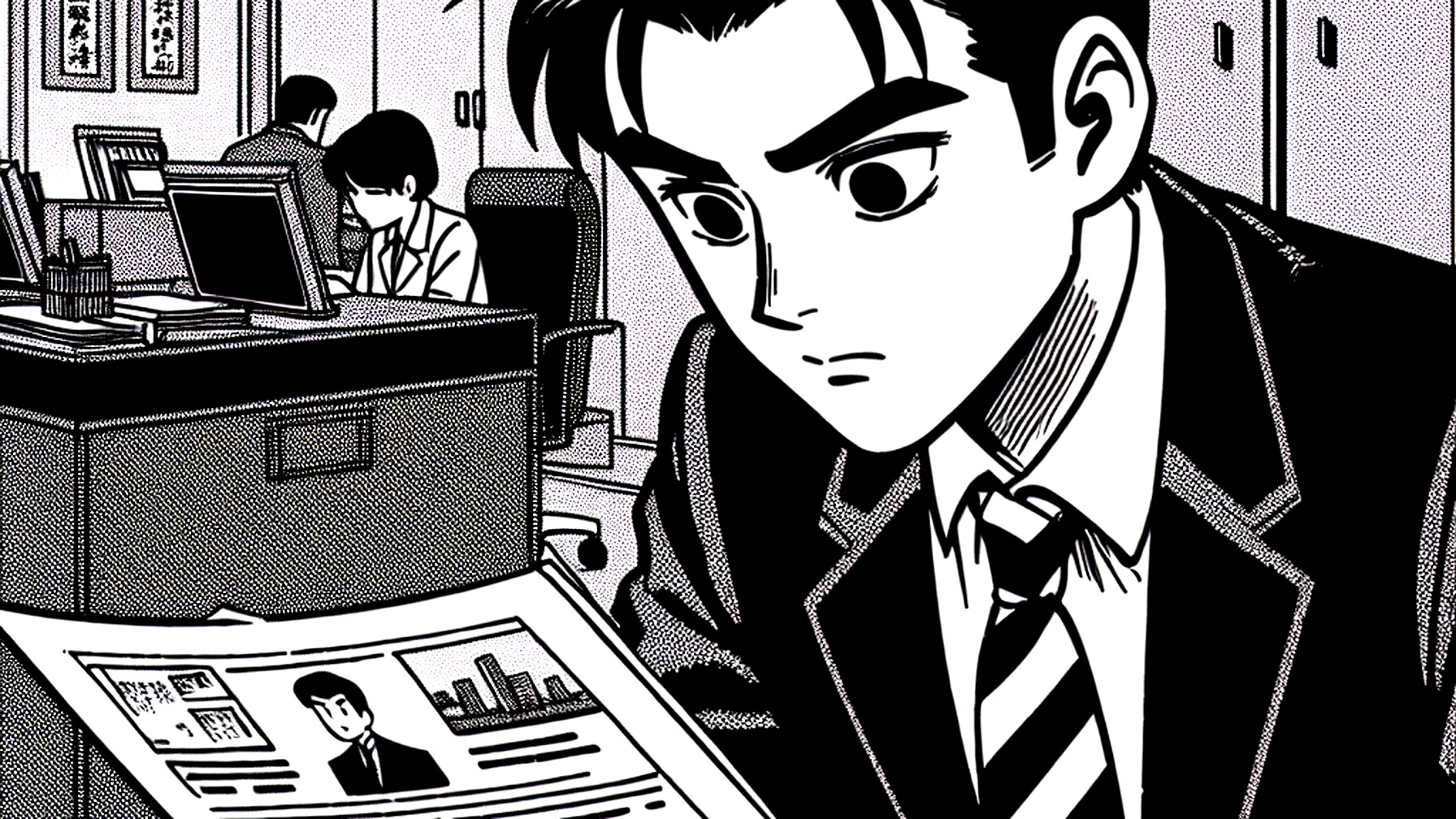
まず押さえておきたいのは、売れ残りには物件固有の事情と市場環境の二つの層がある点です。物件固有では築年数の経過、修繕履歴の不足、管理組合の運営不全などが代表例です。市場環境では人口動態や金利動向、周辺での新築供給ラッシュが影響します。
実は築二十年以上の区分マンションでも、管理状態が良好なら成約価格の下落率は緩やかです。不動産経済研究所の2025年10月レポートでは、東京23区の築二十五年物件でも平均利回り6.2%を維持しています。一方で大規模修繕積立金が枯渇している物件は、買い手が金融機関からフルローンを得にくく、買付が付きにくいという現実があります。
さらに、売却タイミングを誤ると広告費のかけ方が後手に回ります。繁忙期といわれる1〜3月は競合物件が溢れがちで、価格調整が不十分なまま埋もれてしまうパターンが多発します。つまり理由を特定せずに価格だけ下げても、根本的な問題は解決しません。
市場動向と価格形成のメカニズム
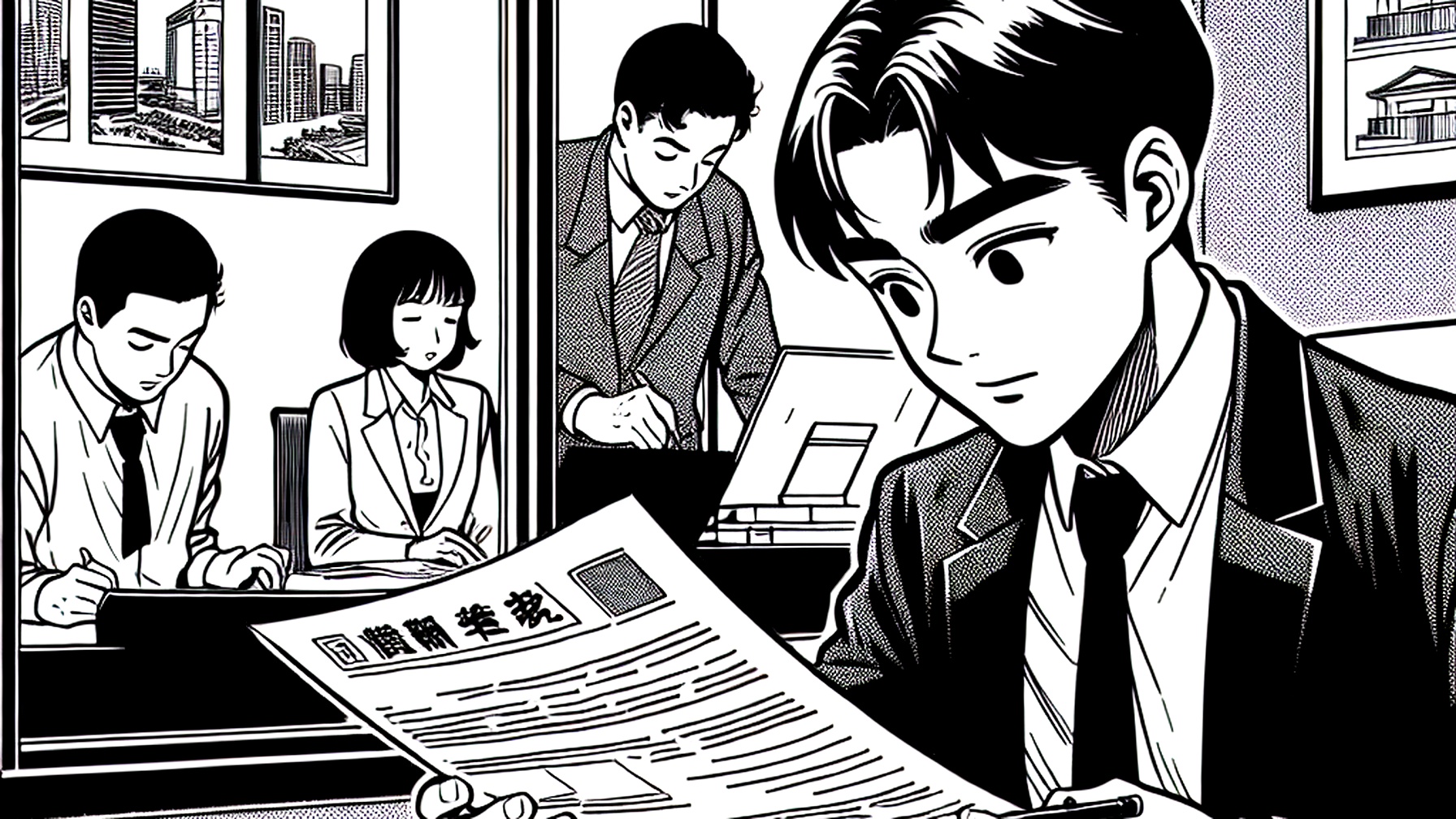
ポイントは、価格が「過去の取引事例」と「将来の期待収益」の掛け合わせで決まることです。過去の事例はレインズ(不動産流通標準情報システム)に登録された成約価格が指標となり、金融機関はここを重視して融資上限を決めます。
一方、将来の期待収益は賃料下落率と空室率で左右されます。国土交通省の賃貸住宅市場調査(2025年版)によると、東京都心三区の平均空室率は3.6%ですが、郊外では7.8%に上昇しています。買い手はこのギャップをリスクとして織り込み、利回りを二〜三ポイント要求するケースも珍しくありません。
金利も重要です。2025年10月現在の主要地銀投資用ローン固定金利は2.3〜2.7%で、前年より0.4ポイント上昇しました。わずかな金利上昇でも評価額は圧縮され、ローン審査に響きます。こうしたデータを裏付けに、自身の売却計画が楽観的すぎないかを客観視する必要があります。
資産価値を高めるための改善策
重要なのは、物件の魅力を「数字」と「見た目」の両面で底上げすることです。まず家賃を下げずに入居率を高める施策として、宅配ボックスや高速インターネットの導入は費用対効果が高いです。国土交通省の調査では、共用部に宅配ボックスを設置した築二十年以上の物件で、平均賃料が3%上昇する例が報告されています。
次に管理組合への働きかけです。大規模修繕の積立不足はディスカウント要因になるため、長期修繕計画書の更新や積立金の見直しを提案します。これにより金融機関が融資審査でプラス評価を付ける可能性が高まります。
さらに、専門家による「インスペクション(建物状況調査)」の実施も効果的です。報告書を買主へ提示すれば見えない瑕疵リスクを軽減でき、価格交渉を有利に進められます。つまり小規模な費用で透明性を高めることが、売却できない状況を打破する鍵になります。
売却以外の出口戦略を考える
一方で、焦って手放すより運用を続けた方が合理的なケースもあります。サブリース契約を見直して自主管理に切り替えれば、手取りを月2万円上乗せできる事例もあります。また、2025年度の税制では個人が保有する賃貸不動産を法人へ現物出資する際、課税の繰り延べが可能な特例が存続しています。将来的に法人売却を想定するなら、このスキームで譲渡所得税を抑えつつキャッシュフローを最適化できます。
さらに、リースバック型ファンドとの共同保有も検討の余地があります。ファンドが優先出資し、オーナーが劣後出資する形を取れば、売却益よりインカムゲインを重視する戦略へ転換できます。将来の市場上昇時に再売却するオプションを残しつつ、当面の流動性を確保できる点が魅力です。
2025年度の制度や税制が与える影響
まず、2025年度の固定資産税軽減措置は築後三年以内の新築に限定されており、既存物件の評価額には直接影響しません。ただし、売却時にかかる登録免許税の軽減(保存登記0.15%→0.1%)は2026年3月まで延長されています。買主側の諸費用が下がるため、価格交渉がまとまりやすくなる側面があります。
住宅省エネ性能向上補助金(賃貸住宅改修型)は2025年度も継続中で、外壁断熱や高効率給湯器の導入費用の三分の一(上限120万円)が助成対象です。断熱性能が向上すると賃料アップ要因になるだけでなく、売却時にエネルギー性能をPRできます。加えて、長期優良住宅化リフォーム減税も同年度いっぱい適用され、所得税控除(最大50万円)が利用可能です。
このように制度面での後押しを活用すれば、改修コストを抑えながら資産価値を底上げできます。売却できない原因が設備の陳腐化にある場合、補助金と減税を組み合わせて改善し、再度市場に出す戦略が現実的です。
まとめ
結論として、マンション投資で「売却できない」と感じたときには、物件と市場の両面をデータで検証し、改善策と別の出口戦略を同時に検討することが欠かせません。築年数が進んでも管理と改修で価値は守れますし、2025年度の補助金や税制を活用すれば費用負担を軽減できます。まずはインスペクションや家賃の見直しなど小さな手から着手し、並行して売却時期と価格のシミュレーションを更新しましょう。主体的に動くことで、次の一手は必ず見えてきます。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省 賃貸住宅市場調査2025 – https://www.mlit.go.jp/
- レインズ(不動産流通機構)取引価格情報 – https://www.reins.or.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp/
- 財務省 2025年度税制改正のポイント – https://www.mof.go.jp/
- 環境省 住宅省エネ性能向上補助金2025 – https://www.env.go.jp/

