心理的瑕疵(しんりてきかし)を抱えた「事故物件」が、実はREIT(リート)の運用資産に含まれる可能性があると聞いて戸惑う人は多いはずです。自分で物件を選ぶわけではないからこそ、知らずにリスクを負うのではという不安はもっともです。本記事では、事故物件とREITの基礎をおさらいしつつ、デメリットがどこに潜むのかを丁寧に解説します。読み終えたころには、商品選びやリスク管理のコツがつかめるはずです。
事故物件とは何か、投資家が知るべき背景
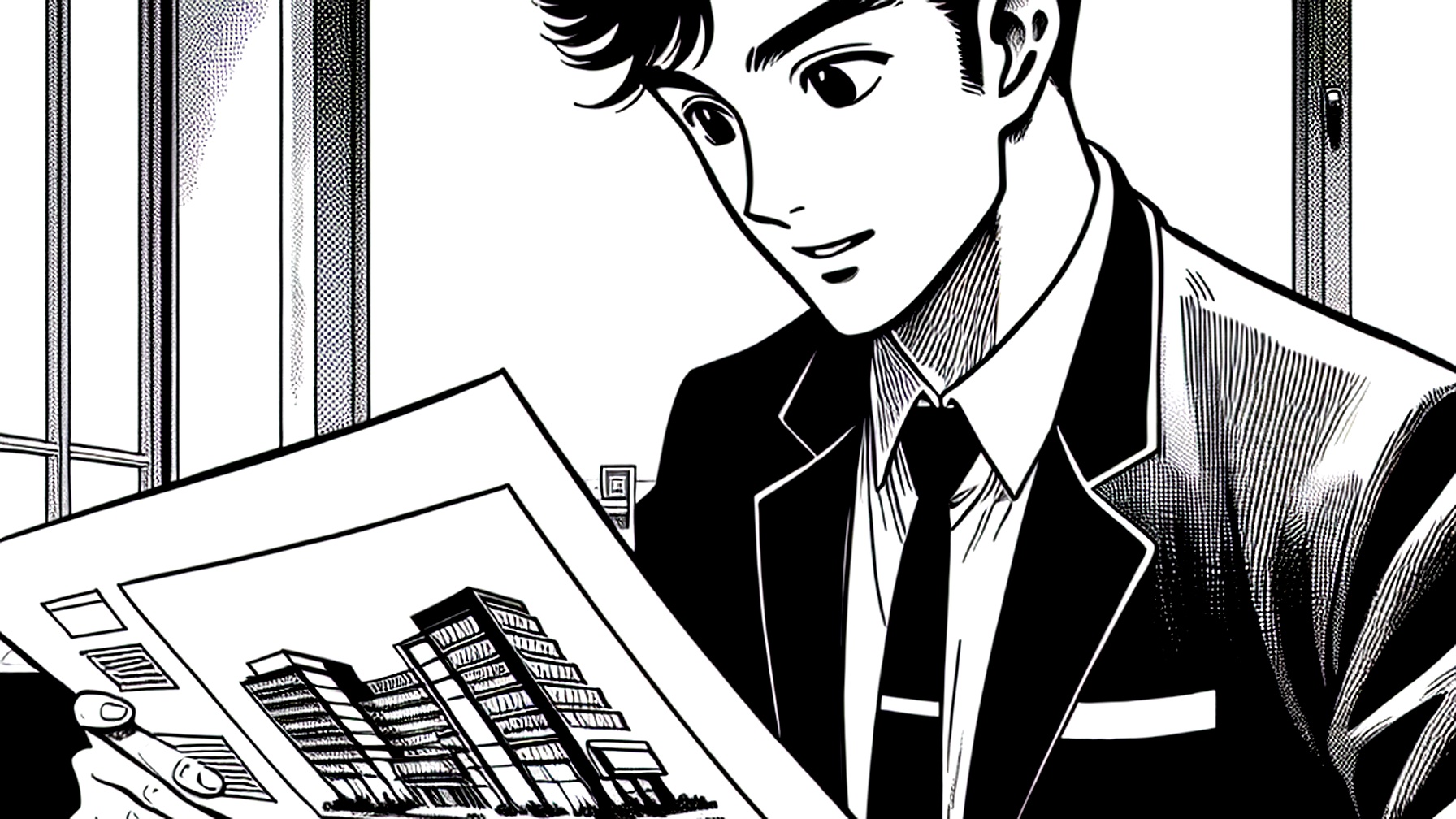
まず押さえておきたいのは「事故物件」という言葉の定義です。国土交通省のガイドライン(2021年策定)では、物件内での死亡事故や自殺、犯罪などにより、借主が心理的抵抗を感じる可能性が高い住宅を指します。告知義務の期間や範囲は細かく規定されていますが、時間の経過やその他の事情で告知が不要になる場合もあるため、表面からは判別しづらい点が悩ましいところです。
さらに、事故物件だからといって必ずしも法的な瑕疵があるわけではありません。建物の耐震性や配管の劣化といった「物理的瑕疵」と異なり、心理的瑕疵はあくまで感情面の問題です。そのため、価格や賃料を下げることで市場に流通し続けるケースは珍しくありません。日本不動産研究所の2024年調査によると、事故物件の成約価格は周辺相場の7〜30%下落にとどまる例もあり、利回りだけを見ると魅力的に映ることさえあります。
しかし、入居者が短期間で退去しやすい、長期空室が続きやすいなど、収益の不安定さが潜在的に存在します。個人投資家が直接買う場合は現地確認や近隣調査である程度見抜けますが、REITのように多数の物件がパッケージ化されると実態を把握しにくくなる点が問題になるのです。
REITの仕組みと事故物件が組み入れられる可能性
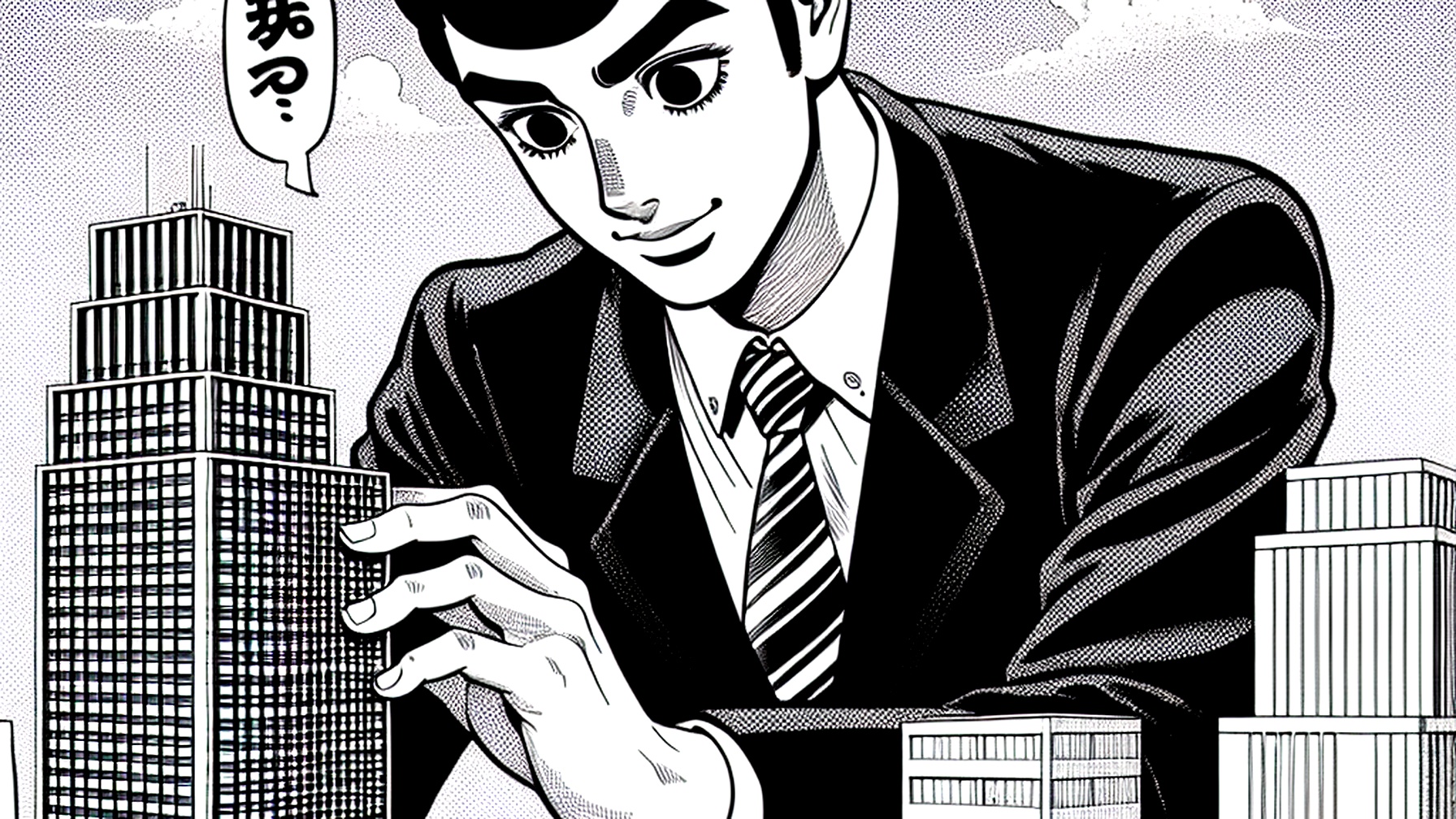
ポイントは、REITが複数の物件で構成される「不動産の投資信託」であるという性質です。投資家は証券取引所で一口数万円から売買でき、運用はプロが担います。しくみ自体は株式型投信と似ていますが、裏側で実物不動産が賃料を生み、それを分配金として受け取る点に特徴があります。
REITの運用報告書には、保有物件の所在地や用途、取得価格が一覧で載ります。ただし、過去の入居履歴や心理的瑕疵の有無を細かく開示する義務はありません。金融庁の「投資信託及び投資法人に関する規則」でも、事故物件の告知について明示的な条文は定められていないのが現状です。つまり、運用会社が取得時に十分なデューデリジェンス(調査)を実施していても、軽微な事故や時間が経過した案件までは投資家に届かない可能性が残ります。
実は、外部委託先のプロパティマネジャーが事故物件を割安で仕入れ、高い利回りを狙う戦略を取ることもあります。2023年の公募REIT市場では、取得物件のうち約1%が過去に心理的瑕疵履歴を持つと専門誌で報じられました。数字としては小規模ですが、個別銘柄を選ぶ際には頭に入れておきたい事実です。
デメリットはどこにあるのか:価格・収益・リスク
重要なのは、事故物件リスクがREIT全体の三つの側面に影響することです。第一に価格変動です。投資口価格は保有資産の評価額に連動しやすく、仮に大型物件で事故が起きた場合、その評価損がREITのNAV(純資産価値)を押し下げます。投資口数が多いほど希釈化されるものの、売りが売りを呼ぶ局面では市場価格が一時的に大きく下落しやすい傾向があります。
第二に配当利回りへの影響です。事故物件は入居率が下がり、賃料減額交渉も起こります。J-REIT全体の平均稼働率は2025年4月時点で97%前後ですが、個別物件ベースでは事故発生後に10〜20ポイント低下する例も報告されています。結果として分配金が減少し、投資家のインカムゲインが細る恐れがあります。
第三に透明性リスクです。先述したように、運用会社に情報開示の義務が限定的なため、投資家は事故の発生を決算資料やニュースで初めて知るケースが少なくありません。サプライズは市場のボラティリティを高め、短期的な価格乱高下を引き起こす要因になります。言い換えると、事故物件リスクは「見えにくいリスク」であり、事前に完全排除することが難しい点がデメリットの核心だといえるでしょう。
事故物件を含む可能性を減らすREIT選定の視点
まず押さえておきたいのは、REIT銘柄によってガバナンスや情報開示姿勢が大きく異なるという事実です。総合型よりも特化型、特にオフィスや物流などBtoB用途に絞る銘柄は、そもそもレジデンス系より事故物件が組み込まれる確率が低いと考えられます。また、スポンサー企業の信用度が高いほどデューデリジェンスも厳格になりやすく、心理的瑕疵のある物件は取得対象から外されがちです。
投資家ができる現実的な対策は二つあります。ひとつは運用報告書や有価証券報告書を読み込み、物件取得方針に「社会的レピュテーションを損なう可能性のある資産は取得しない」と明記されているか確認すること。もうひとつは物件一覧の取得日と価格をチェックし、相場より極端に安い案件がないかを探すことです。極端なディスカウントは事故や瑕疵のシグナルである場合があります。
さらに、IR説明会やウェブセミナーで運用会社に直接質問するのも有効です。2025年度から東京証券取引所は「投資家との建設的対話ガイドライン」を改訂し、運用会社に対しESG(環境・社会・ガバナンス)リスクの説明責任を強調しています。心理的瑕疵は社会リスクに含まれますから、真摯な回答姿勢が見られない銘柄は選定から外す判断材料になります。
個人投資家がとるべきリスク管理と分散の考え方
実は、事故物件リスクは完全回避よりも「分散で薄める」発想が合理的です。J-REIT市場全体に投資するETFを活用すれば、個別物件の事故による影響は平均化され、ショックが軽減されます。また、REITと現物不動産を組み合わせることで、片方のリスクをもう一方でヘッジする戦略も取れます。たとえば都心区分マンションを自主管理しつつ、物流施設特化型REITに資金を振り向ければ、事故物件リスクと用途特有の景気変動リスクを同時に抑える効果が期待できます。
加えて、キャッシュポジションを一定比率で持つことが精神的な安全弁として働きます。金融庁の家計調査(2025年版)によれば、金融資産全体に占める現金比率が20〜30%の世帯は、市場急落時でも保有資産を売却せずに乗り切る傾向が強いと分析されています。REITの事故物件問題も急落要因の一つである以上、流動性確保は無視できません。
そして、情報収集の習慣を持つことが最終的な防御策になります。国土交通省の「事故物件ガイドライン」や各種業界紙の事故・瑕疵事例データベースは無料で閲覧可能です。定期的にチェックし、保有銘柄の物件名が掲載されていないかを確かめるだけでも安心感が違います。
まとめ
事故物件は安く買えるぶん高利回りが狙えるという魅力がある一方、空室や価格下落など収益の不安定さを抱えます。REITの場合、そのリスクは投資家から見えにくく、情報開示やガバナンスの差によって影響度が変わります。投資口価格の変動、分配金の減少、サプライズによるボラティリティ上昇が主なデメリットです。したがって、開示資料の精読、スポンサーの信用調査、用途分散、ETFの活用など多角的な対策が不可欠です。読者の皆さんも、今日紹介した視点でポートフォリオを点検し、より納得感のあるREIT投資を実践してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産業課 事故物件ガイドラインhttps://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 投資信託及び投資法人に関する規則https://www.fsa.go.jp/
- 日本不動産研究所 事故物件価格影響調査(2024年)https://www.reinet.or.jp/
- 東京証券取引所 J-REIT市場概況(2025年4月)https://www.jpx.co.jp/
- 金融庁 家計調査報告(2025年版)https://www.fsa.go.jp/

