突然の金利上昇や不動産価格の変動に振り回され、「REITと現物どちらが安全なのだろう」と迷っていませんか。特にREITを短期売買、いわゆる転売で利益を得ようと考えると、価格の振れ幅や税金面の負担が気になります。本記事では、REITの仕組みを基礎から整理しながら、転売に潜むリスクと対策を分かりやすく解説します。読み終える頃には、自分に合った投資スタイルを選ぶ判断軸が手に入るはずです。
REITとは何かを改めて確認しよう
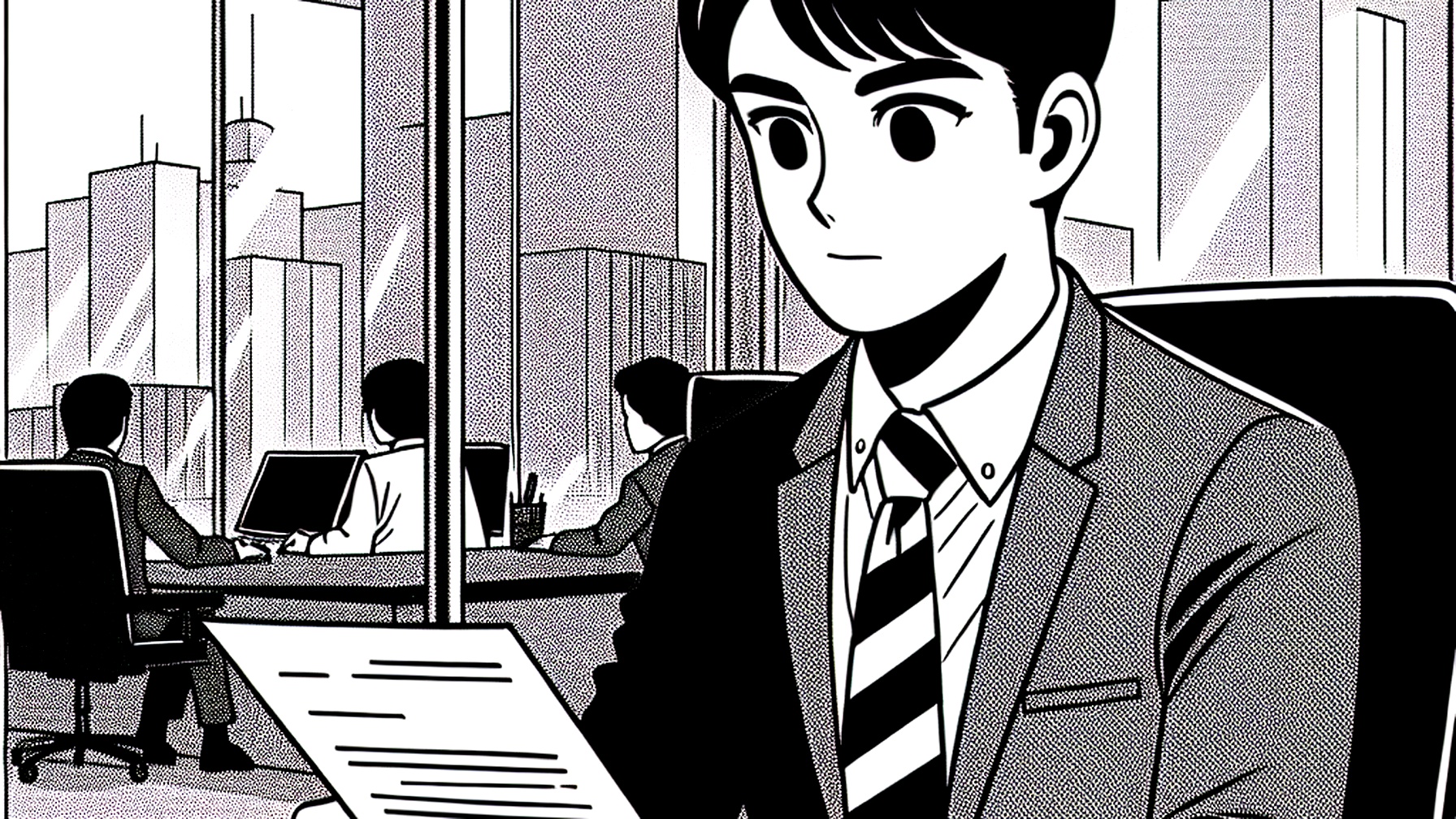
まず押さえておきたいのは、REIT(不動産投資信託)の基本構造です。REITは投資家から集めた資金で複数の不動産を取得し、賃料収入や売却益を分配金として還元します。株式と同じ証券取引所に上場されており、少額から購入できる点が魅力です。
この仕組みは高度に分散化されているため、個別物件の空室リスクを抑えやすい一方、価格は株式市場のセンチメントに左右されやすくなります。つまり、不動産市場が堅調でも株式市場が不安定ならREIT価格も下がる可能性があります。2025年10月時点の東証REIT指数は、年初来で約3%の変動幅にとどまっていますが、2022年のコロナ禍では一時30%以上下落した事例があり、ボラティリティは思った以上に大きいと認識してください。
さらに、金融庁の資料によるとREITの平均分配金利回りは3.5〜4%前後です。地方のワンルームマンション投資と比較すると見た目の利回りは低いものの、修繕費や空室広告費を直接負担しなくて済む点で手間は大幅に軽減されます。
REITを転売するときに直面する3つのデメリット
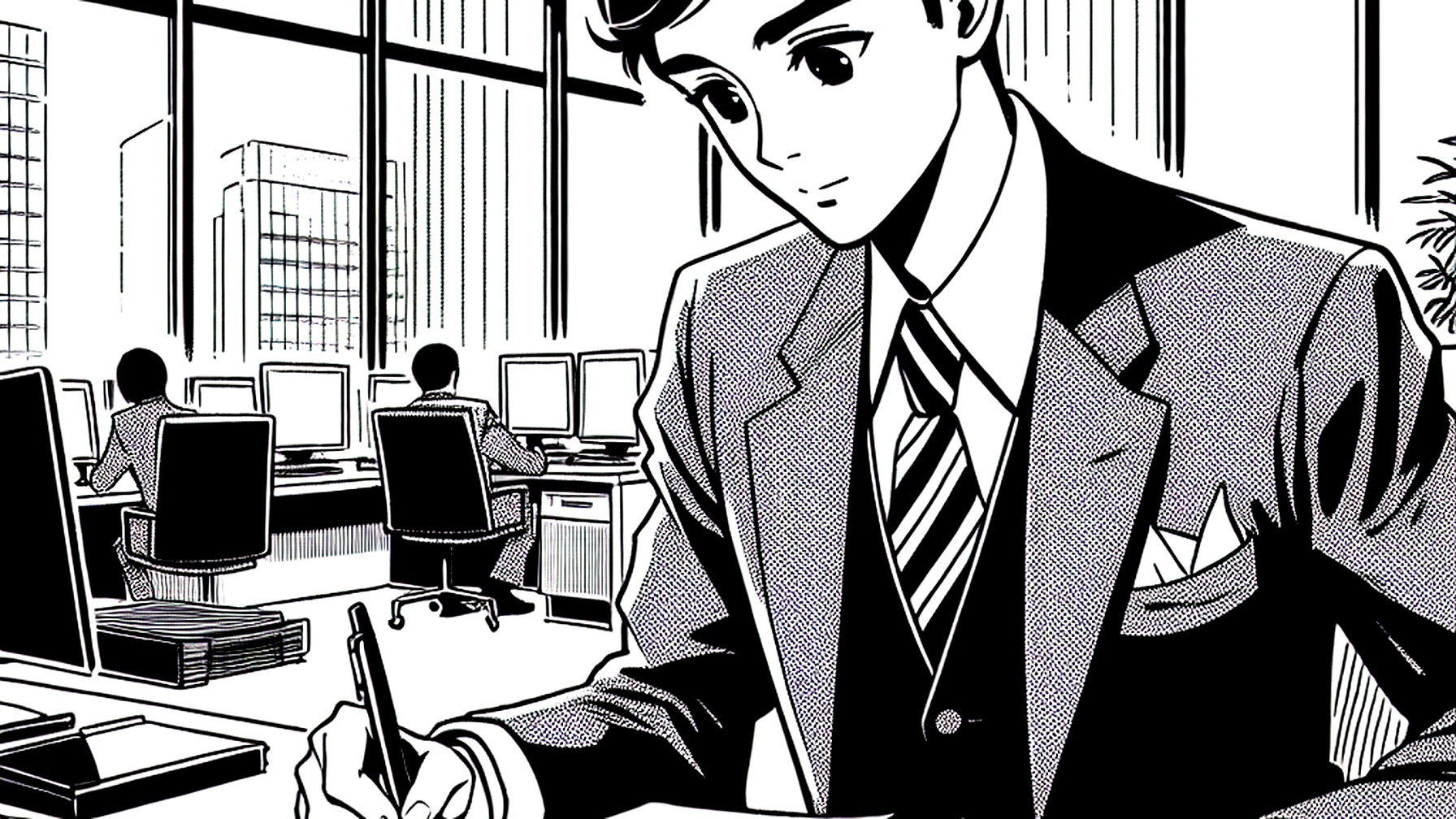
重要なのは、REITを短期で売買するときに発生する具体的なコストとリスクを理解することです。
第一に、売買手数料と税金の負担が想像以上に重い点です。証券会社の取引手数料はネット証券なら片道0.1%前後まで下がっていますが、売買を繰り返すほど利益を削ります。さらに、短期で得た譲渡益には株式と同じく20.315%の譲渡所得税がかかり、年間損益通算も行えますが、頻繁な転売で利益が安定しないと課税タイミングが読めません。
第二に、価格変動リスクです。REITは流通量が多いとはいえ、平日しか売買できず、急激な地政学リスクや金利上昇が起きた場合は一日で5%近い下落も珍しくありません。実は分配金を受け取る権利落ち日の前後で価格が調整されるため、短期転売では権利落ちによる値下がりを被る可能性があります。
第三に、心理的ストレスが重いことも見逃せません。不動産現物投資なら賃料収入が継続するため一時的な価格下落を受け流せますが、REITの転売は株式トレードと同様に画面と向き合う時間が増えます。東証REIT指数のボラティリティはTOPIXより低いとはいえ、値動きを日々確認し続ける負担は無視できません。
転売益狙いと長期保有はどちらが得か
ポイントは、投資目的とリスク許容度によって最適戦略が変わることです。仮に100万円をREITに投じ、年4回の決算期ごとに3%の値幅を狙って転売するとします。1年間で概算12%のキャピタルゲインを期待できますが、4回の売買で生じる手数料と税金で実質利回りは約8%に低下します。
一方で同じ100万円を分配金目的で長期保有すると、平均4%のインカムゲインが見込めます。過去10年の東証REIT指数は年率2%程度の値上がり傾向があり、これを加えれば合計6%前後のトータルリターンに落ち着く計算です。税金も分配金と売却益の課税タイミングを分散できるため、転売より手取り額が安定します。
つまり、高いリターンを求めて頻繁に転売するほどコストとブレ幅が広がり、時間も取られます。逆に、分配金を再投資し続ける長期保有は複利効果が働きやすく、比較的ストレスの少ない運用が可能です。
2025年度制度で知っておくべき税制・優遇枠
実は、2025年度でもNISA(少額投資非課税制度)の新枠がREIT投資に活用できます。年間最大360万円の投資枠に対し、配当・売却益が非課税になるため、長期保有なら大きなメリットがあります。投資上限は生涯で1,800万円と定められており、非課税期間の無期限化によって分配金再投資に向いた制度へと進化しています。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)では上場REIT指数連動型の投資信託に拠出でき、掛金が全額所得控除になる点が魅力です。ただし、60歳まで資金拘束されるため、転売目的の資金には向きません。
これらの制度は国税庁のガイドラインに基づき2025年度も継続しており、非課税メリットを活かすなら売買より長期保有のほうが有利です。短期転売で課税コストを負った後にNISA枠へ移すことはできないため、口座開設時に方針を決めておくと効率的です。
転売を選ぶなら守りたい2つのリスク管理手法
まず、価格変動への備えとして逆指値注文を活用しましょう。具体的には、購入価格から5%下落したら自動的に売却する設定を行い、予想外の損失拡大を防ぎます。SBI証券の取引データによれば、逆指値を入れた投資家の平均損失率は入れない投資家より2ポイント低い傾向が確認されています。
次に、分散投資を意識することが大切です。物流系、オフィス系、住宅系など用途の異なるREITを組み合わせると、個別セクターの急落を相殺できます。国土交通省のレポートでは、用途分散したポートフォリオの値動きは単一用途に比べ年率で1.2ポイントボラティリティが低下するという結果が示されています。
これらの手法を併用すれば、転売戦略でも損失を限定しつつリターンを狙いやすくなります。しかし、どちらも100%の安全を保証するものではないため、余裕資金で行う姿勢が欠かせません。
まとめ
ここまで、REIT デメリット 転売というテーマで、仕組みの基礎からリスク、制度活用まで整理しました。頻繁な売買は手数料と税金が利益を削り、価格変動のストレスも増大します。一方、長期保有なら分配金と値上がり益の複利効果に加え、2025年度NISAの非課税メリットを享受できます。転売を選ぶ場合でも逆指値と用途分散で損失限定を図り、無理のない範囲で挑戦しましょう。自分のリスク許容度と時間的余裕を見極めたうえで、最適なREIT投資スタイルを見つけてください。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 東日本不動産流通機構(東日本REINS) – https://www.reins.or.jp
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産市場動向レポート – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 NISA制度解説 – https://www.nta.go.jp

