子育てには教育費や住宅費など多くの支出が伴います。その一方で、将来への備えとして不動産投資に関心を持つご家庭も増えています。しかし「家計が苦しいのに投資なんて無謀では」と不安を抱く方も少なくありません。本記事ではリスク 子育て世代が直面しやすい課題を整理し、2025年10月時点で活用できる制度や具体的な対策を解説します。読み終えるころには、家計を圧迫せずに資産形成を進めるヒントが得られるはずです。
家計と教育費が重なる時期の資金繰りをどう組み立てるか
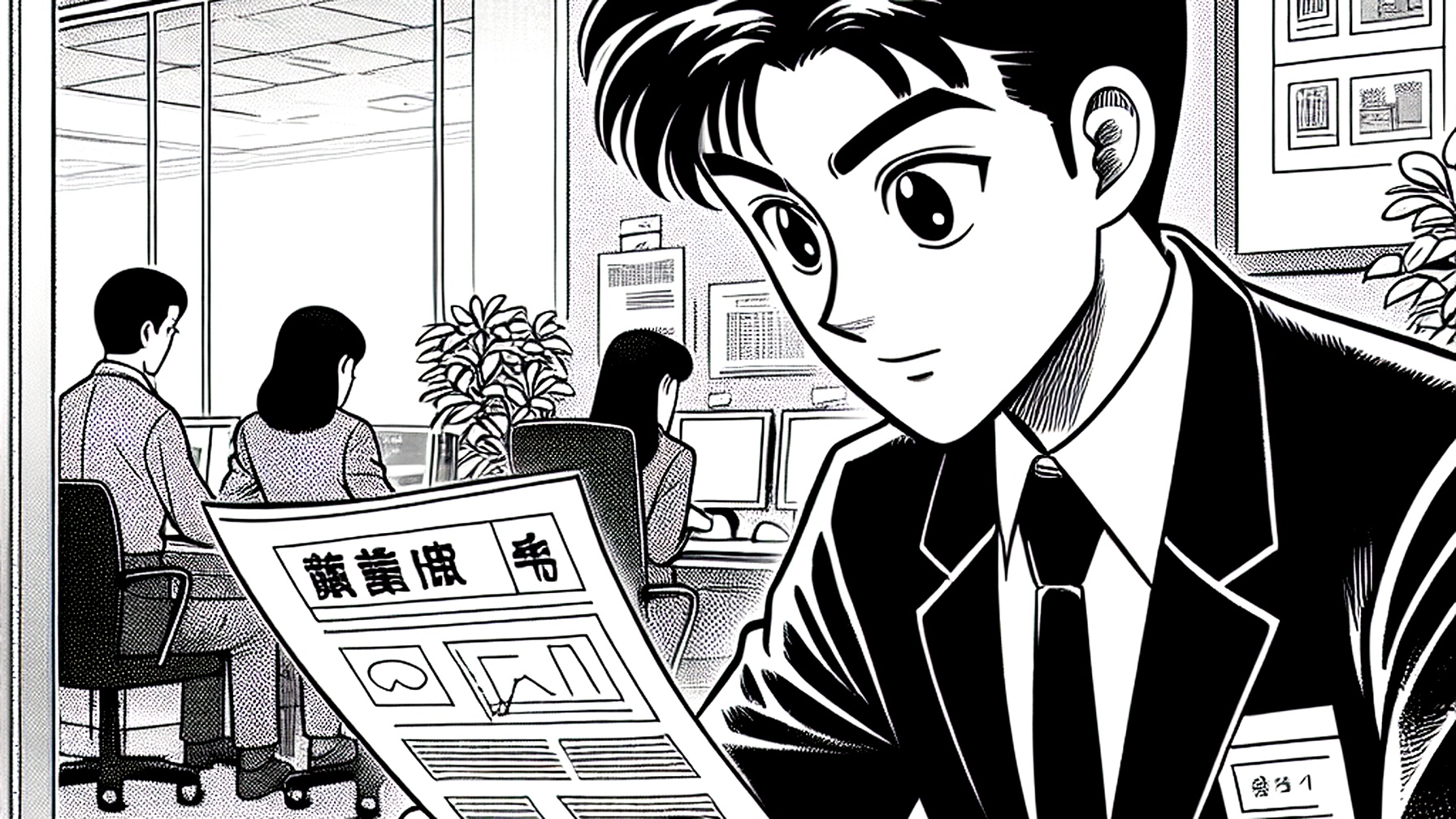
重要なのは、教育費ピークとローン返済ピークが重ならない資金計画を描くことです。総務省「家計調査」によれば、18歳以降の子ども1人当たりの教育関連費用は年間約150万円に達します。これに住宅ローン返済が加わると、可処分所得を圧迫し、投資どころではなくなる危険があります。
まず家計全体のキャッシュフロー表を作り、10年先までの収支を見える化しましょう。教育費は私立進学や留学など選択肢によって大きく変動します。最悪のシナリオでも赤字にならないよう、毎月のローン返済額を手取り収入の25%以内に抑えると精神的なゆとりが生まれます。
また、急な支出に備える生活防衛資金として、普段の生活費6か月分を預貯金で確保しておくと安心です。これにより、突発的な修繕費や空室損が発生しても家計を守れます。子育て世代は医療費控除などで一時的に所得税が減る場合がありますが、あくまで一過性の効果であり、長期の返済計画には含めない方が賢明です。
変動金利と固定金利の選択――キャッシュフローを安定させる鍵
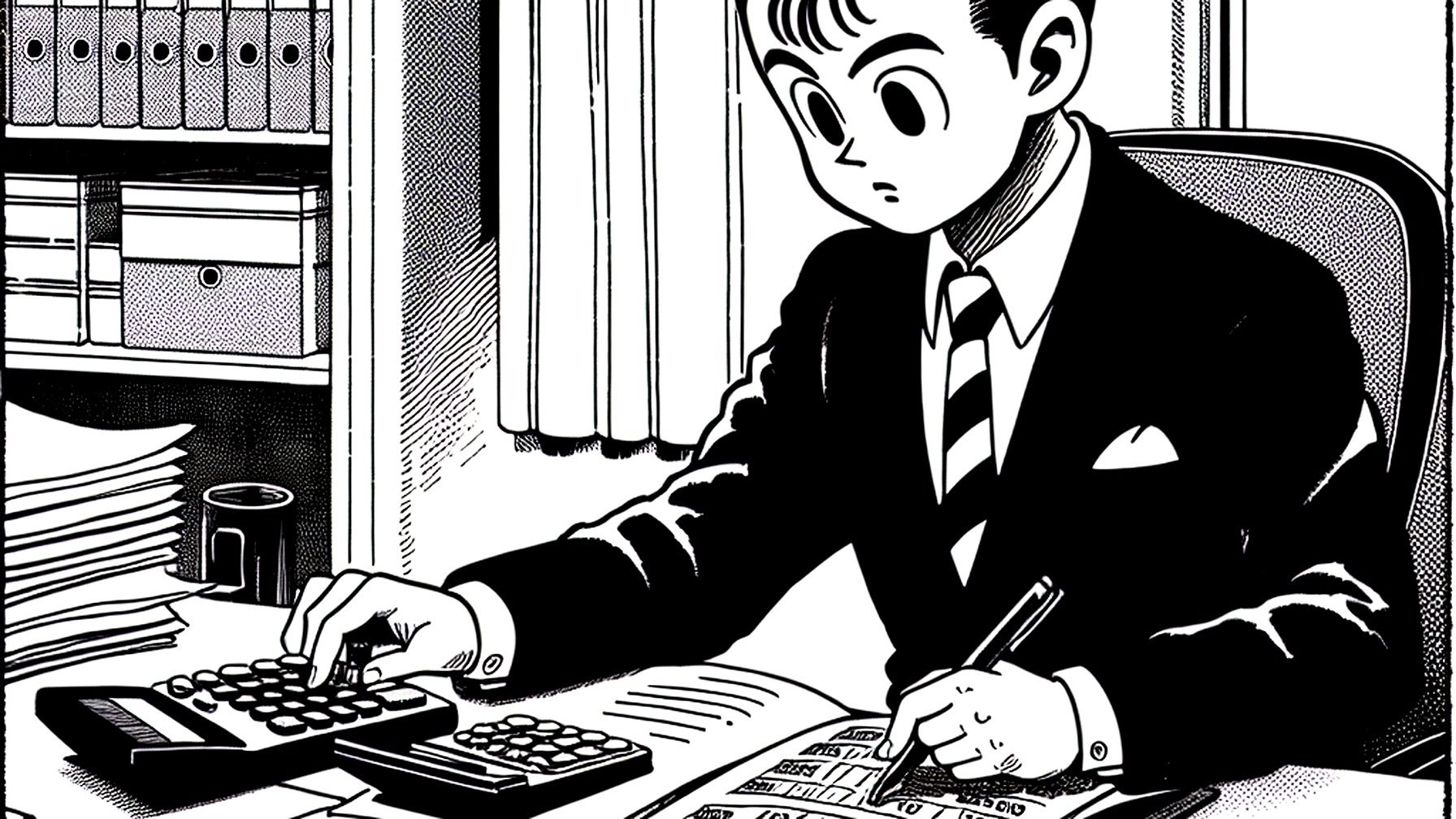
ポイントは、「返済額の予見性」と「将来金利の読みづらさ」をどう折り合いをつけるかです。日本銀行が公表する長期金利は2025年10月時点で1%台に留まっていますが、インフレ目標達成に向けた金融政策次第で変動リスクは残ります。
固定金利型ローンは金利上昇局面でも返済額が変わらないため、教育費と重なる時期に家計を守る効果があります。一方、変動金利型は当初の金利が低く、繰上返済を積極的に行う世帯には魅力的です。子育て世代が選ぶなら、教育費が高騰しやすい中学・高校期間は固定、大学進学後に繰上返済を加速できる見通しがあれば残債を変動へ借り換える、といった段階的戦略が現実的です。
日本政策金融公庫の2025年度「子育て支援融資」では、住宅ローン利用者の子ども人数に応じて金利を0.2%引き下げる優遇が続いています。この制度を使う場合でも固定と変動の選択肢があり、金利差以上に長期の家計安定を重視する姿勢が欠かせません。
空室リスクと学区ニーズ――地域選びが成果を左右する
まず押さえておきたいのは、子育て世代の居住ニーズと投資家の空室リスクが表裏一体である点です。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、2025年の転入超過上位市区は東京23区の一部と政令指定都市近郊に集中しています。ファミリー層は学区や保育園の空き状況で住まいを選ぶため、これらのエリアは空室リスクが低めです。
一方で、同じ政令市でも郊外のバス便エリアは人気が二極化しています。学区の評判が芳しくない地域では、家賃を下げても入居が決まりにくく、結果的に想定利回りを下回る可能性があります。内見時には学校までの徒歩時間や保育園の入園難易度を確認し、賃貸募集広告で訴求できる材料があるかを必ずチェックしましょう。
さらに、自治体独自の子育て支援策が豊富なエリアはファミリー滞在期間が長くなる傾向にあります。例えば、2025年度時点で中学校卒業まで医療費を無償化している千葉県流山市では、ファミリー世帯の平均居住年数が10年を超え、空室期間が短いという不動産管理会社の調査結果もあります。ただし人口増加が続く地域は土地価格上昇で利回りが低くなりがちです。利回りと空室リスクのバランスを客観的データで見極める姿勢が欠かせません。
2025年度の税制・補助制度を活用したリスクヘッジ
実は、子育て世代が不動産投資を行う際に使える制度は限定的です。そのため、ある制度が使えるときは最大限に活用することでリスク軽減につながります。2025年度住宅ローン控除は最大控除額が年30万円、控除期間が13年間です。控除率は0.7%ですが、長期優良住宅など環境性能が高い物件なら40万円まで拡大します。
加えて、親や祖父母からの教育資金贈与を活用する場合、住宅取得等資金の非課税枠(最大1000万円)は2025年12月31日契約分まで利用可能です。この枠を使って自己資金を厚くすることで、月々の返済負担を抑えられます。
2025年度に新設された「子育てエコホーム支援事業」では、一定の省エネ性能を満たす賃貸物件の新築に対し、1戸あたり最大60万円の補助が出ます。募集は年度予算に達し次第終了するため、スケジュール管理と工事計画を金融機関審査前に整えておくことが欠かせません。
出口戦略を描きながら長期的な資産形成を目指す
ポイントは、保有期間中のキャッシュフローだけでなく、売却や相続まで含めた全体設計を早い段階で決めることです。国土交通省「不動産市場動向調査」によると、築30年を超える木造アパートの成約価格は新築時の3割程度に下落します。つまり、減価償却後に売却益を見込むのは難しく、家賃収入で着実に回収する必要があります。
子どもが独立した後に自宅を賃貸化し、投資物件を売却してローンを完済する「住み替え+売却」モデルも有効です。この方法なら教育費ピークを過ぎた50代でキャッシュフローを改善し、老後資金を確保するシナリオが描けます。
また、相続を視野に入れる場合は、小規模宅地等の特例(330㎡までの評価減)を利用する余地があります。2025年度時点で制度の継続が決定しており、賃貸経営を行う土地は評価額が50%減となります。将来の相続税負担を抑えることで、家族全体のリスクを軽減できます。
まとめ
子育て世代が不動産投資に踏み出す際は、教育費とローン返済が衝突しない資金計画、金利上昇への備え、学区ニーズを捉えた物件選びが大切です。さらに、2025年度に有効な住宅ローン控除や補助金を活用すれば、初期投資と運営コストの両面でリスクを抑えられます。家計を守りながら資産を大きく育てるために、まずは10年後の家計シミュレーションを作成し、制度や地域情報を冷静に比較することから始めてみてください。
参考文献・出典
- 総務省 家計調査年報2024 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 子育て支援融資 2025年度概要 – https://www.jfc.go.jp
- 国土交通省 不動産市場動向調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- こども家庭庁 2025年度 子育てエコホーム支援事業 – https://www.cfa.go.jp
- 日本銀行 長期金利推移データベース – https://www.boj.or.jp

