不動産投資に興味はあるけれど、物件を自分で購入するのはハードルが高い――そんな悩みを抱える人にとって、REIT(不動産投資信託)は手軽な選択肢です。しかし便利さの裏には思わぬ落とし穴もあります。本記事では「REIT 投資家 デメリット」という視点から、仕組みの基本、リスクの正体、そして2025年時点での市場動向まで丁寧に解説します。読み終えた頃には、自分に合った投資スタイルを選ぶヒントが得られるでしょう。
まず押さえておきたいREITの仕組みと魅力
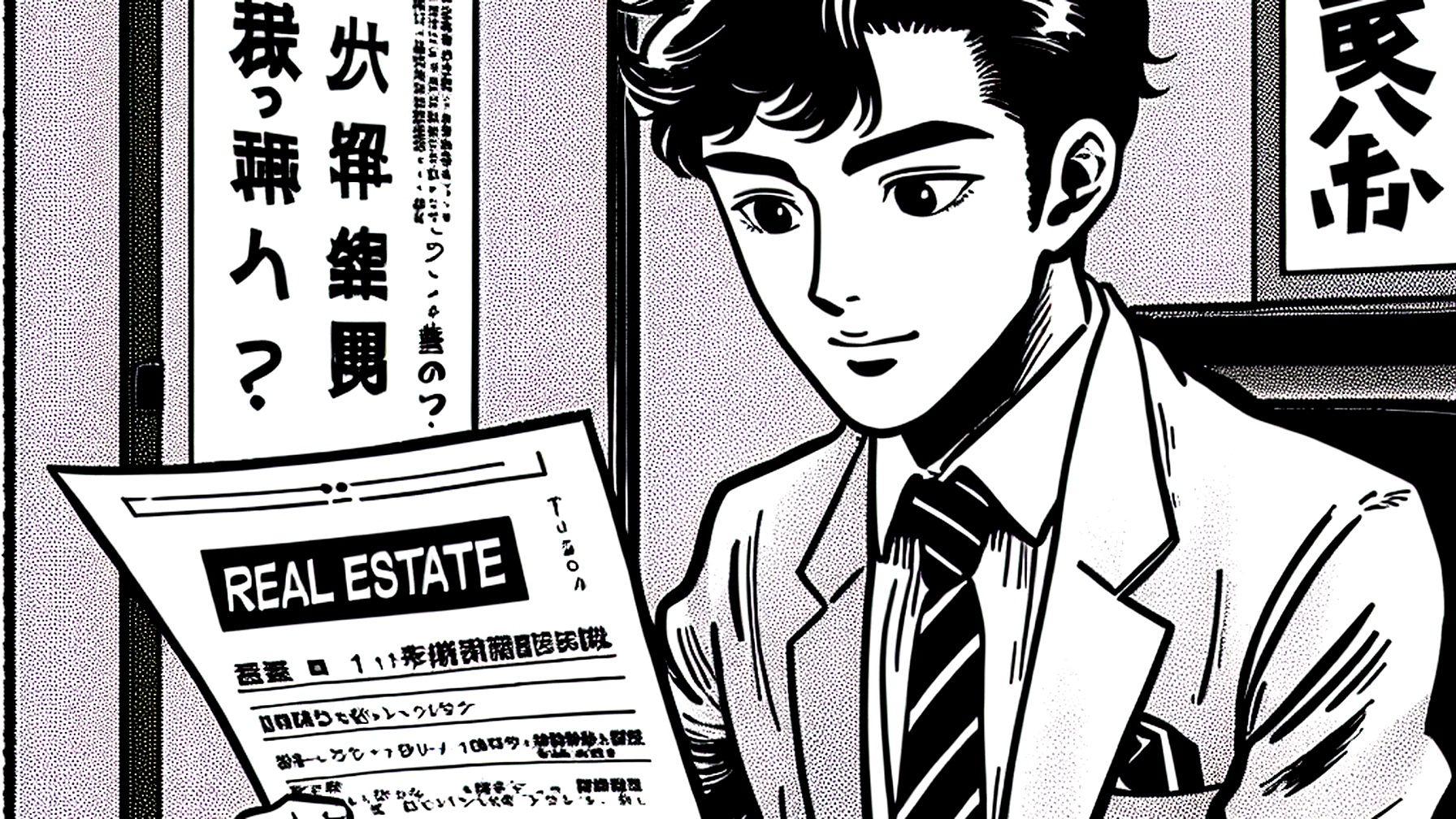
重要なのは、REITが多数の投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設を購入し、賃料収入を分配する仕組みだという点です。個人では手が届きにくい大型物件に間接的に参画でき、東京証券取引所に上場しているため売買も株式と同じ感覚で行えます。
加えて、税制面の優遇もポイントです。法律で毎期利益の90%以上を配当すれば法人税が実質免除されるため、高い分配利回りが期待できます。金融庁の2025年3月データでは、東証REIT指数の平均分配利回りは3.8%前後で推移し、長期国債利回りを約2ポイント上回っています。
さらに、少額から投資できる点も初心者には魅力です。1口十数万円で購入できる銘柄もあり、資金を分散しやすい仕組みが整っています。一方で、こうしたメリットがあるからこそ、デメリットを正しく理解しないと期待外れの結果になりかねません。
個人投資家が直面しやすい5つのデメリット
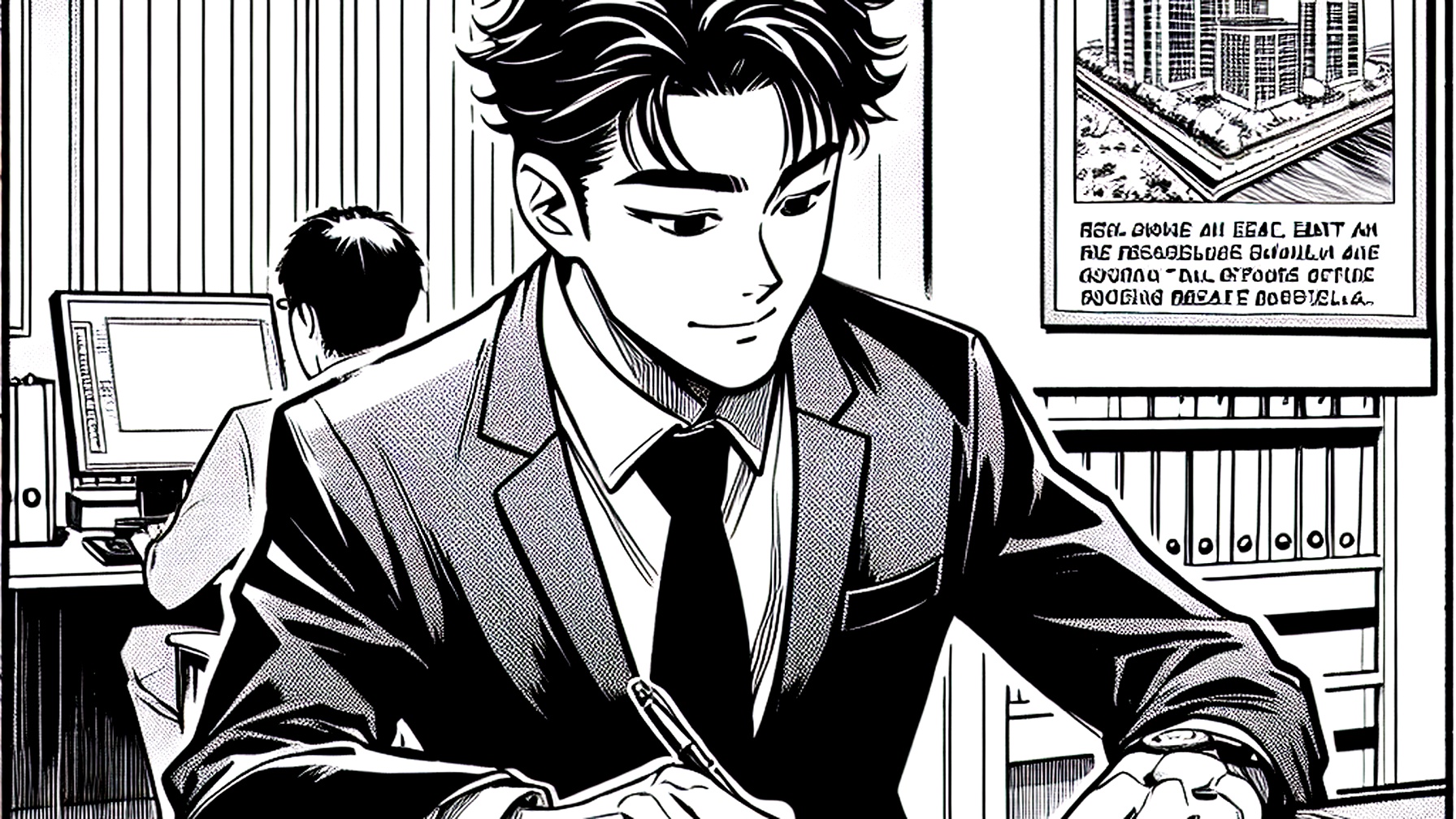
実は、REITにも株式や現物不動産とは異なる弱点が潜んでいます。ここでは代表的なデメリットを具体的に整理します。
第一に価格変動リスクです。上場商品である以上、株式市場の影響を受けやすく、景気後退局面では保有物件の収益力に問題がなくても価格が下がります。日本取引所グループの統計では、2020年のコロナショック時に東証REIT指数が一時40%近く急落しましたが、ファンダメンタルズの悪化はそこまで大きくありませんでした。
第二に金利上昇リスクが挙げられます。REITは物件購入資金の多くを借入金で賄うため、金利が上がると分配金が目減りする可能性があります。2025年7月の日銀政策修正で長期金利が1.5%台に乗せた際、借入比率の高い銘柄ほど分配予想を下方修正しました。
第三は物件集中リスクです。特定エリアや用途に偏ったポートフォリオの場合、地震や規制変更が直撃します。特に物流施設に特化した銘柄は、2024年以降のEC成長鈍化で空室率が上昇した例もあります。
第四に流動性の罠があります。東証REIT全体の出来高は株式に比べて小さく、大口で売買すると価格が大きく動くことがあります。個人でも売りたいときに出来高が薄いと成行注文で想定外の値段になるリスクがあります。
最後に情報格差も無視できません。アナリストカバレッジが株式より少なく、英語開示しかないデータもあるため、適時開示を読み込まないと細かな修繕計画やテナント動向を見逃します。つまり「手軽さ」の裏で自己責任の範囲が広い点を理解しておく必要があります。
デメリットへの対処法とポートフォリオ構築のコツ
ポイントは、リスクを完全に消すのではなく、許容範囲に収める工夫をすることです。まず価格変動リスクに対しては、ドルコスト平均法を活用し、毎月一定額で買い付けることで取得単価を平準化できます。特定月にまとめて購入するより心理的負担も軽くなります。
金利上昇への備えとしては、借入比率(LTV)が低めの銘柄を組み入れるのが有効です。投資信託協会の2025年6月データによると、LTVが40%未満のREITは平均分配利回りこそ若干低いものの、予想分配金の変動幅が約半分に抑えられています。また、固定金利比率の高い銘柄をチェックする方法もあります。
物件集中リスクを避けるには、用途・地域が異なる複数のREITを組み合わせます。オフィス、住宅、物流、ホテルといったセクターをバランスよく配置し、国内REITに加えて米国やアジアの海外上場REITを少量混ぜると景気サイクルのずれがクッションになります。
流動性の面では、出来高が20万口以上ある大型銘柄を中心に選ぶと、売却時のスリッページを抑えやすいでしょう。加えて成行ではなく指値注文を徹底するだけでも、急な値動きによる損失を防げます。
情報格差を縮めるためには、運用報告書や決算説明資料を読む習慣をつけることが大切です。不動産学会や不動産証券化協会の無料セミナーを活用すると、専門家の視点も得られます。こうした積み重ねが長期のリスク管理に直結します。
2025年のREIT市場動向と今後の見通し
2025年10月時点で、REIT市場は金利上昇とインフレの影響を受けつつも、底堅い賃料収入に支えられ緩やかな回復基調にあります。国土交通省の最新調査では、首都圏Aグレードオフィスの平均空室率が2023年の6.5%から5.2%へ改善し、賃料も前年同月比2%上昇しました。
一方で、物流セクターは新規供給が多く、空室率がやや高止まりしています。住宅REITは働き方多様化を追い風に堅調で、特に単身向け物件の賃料上昇が顕著です。このようにセクターごとの温度差が大きいため、投資家は分配利回りだけでなく今後の成長余地を見極める必要があります。
海外勢の資金流入も注目点です。財務省の資金循環統計によると、2024年度に海外投資家が純流入したREIT資金は前年比30%増となり、円安が続けばこのトレンドはしばらく継続しそうです。資金流入は価格を押し上げる一方で、利回りを低下させる可能性があるため、割安感の判断には慎重さが求められます。
最後に、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みも価値を左右します。2025年度の環境省ガイドラインでは省エネ基準を満たす物件への税制支援が強化され、ESG評価の高いREITの資金調達コストが下がる見込みです。長期で保有するなら、ESGスコアの開示状況も確認しておきましょう。
まとめ
ここまでREITの仕組みと魅力を確認しつつ、投資家が直面しやすい5つのデメリットとその対処法を紹介しました。価格変動、金利上昇、物件集中、流動性、情報格差というリスクは、組み合わせと情報収集で大きく軽減できます。まずは少額で経験を積み、四半期ごとにポートフォリオを点検する習慣を身につけましょう。行動を起こすことで得られる学びは大きく、長期的な資産形成への第一歩となります。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp/
- 投資信託協会 – https://www.toushin.or.jp/
- 国土交通省 不動産市場統計 – https://www.mlit.go.jp/
- 財務省 資金循環統計 – https://www.mof.go.jp/

