初めてアパート経営に挑戦するとき、多くの方が「利回りは何パーセントあれば安心なのだろう」と悩みます。利回りは物件選びから資金計画まで、すべての判断基準になる指標です。本記事では利回りの基本から、2025年時点の実勢データ、具体的な計算方法、さらに利回りを高める実践策までを順序立てて解説します。読み終える頃には、自分が目指すべき利回り水準と、その達成に向けたステップが明確になるはずです。
利回りの基礎と種類を正しく理解する
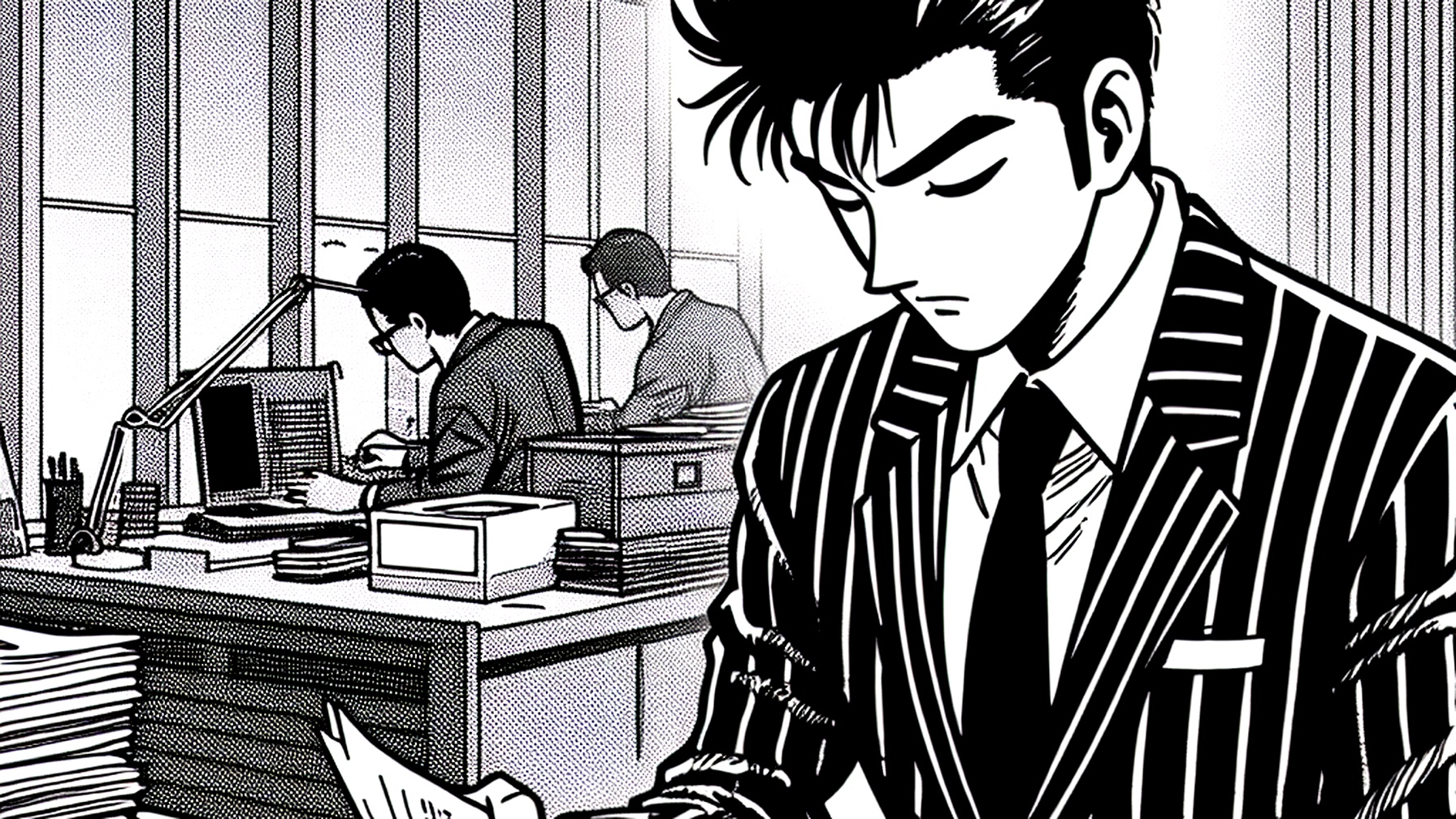
まず押さえておきたいのは、利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の二つがある点です。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標で、広告に載ることが多いため目にする機会が多いでしょう。しかし、管理費や修繕費、税金などのコストを含まないため、実際の収益力を過大評価しやすい側面があります。
一方で実質利回りは、年間家賃収入から必要なコストを差し引いたうえで物件価格で割るため、手元に残るキャッシュフローを把握しやすくなります。つまり、投資判断で重視すべきは実質利回りですが、予算や融資審査を検討する段階では表面利回りも参考にする、といった使い分けが肝心です。
この二つを混同すると、期待通りのキャッシュフローが得られず、「思ったほど手残りがない」という事態に直面します。実は初心者の失敗談の多くがこの点に集約されるため、用語の違いをしっかり理解したうえで次のステップに進みましょう。
2025年の実勢データから見る利回りの目安
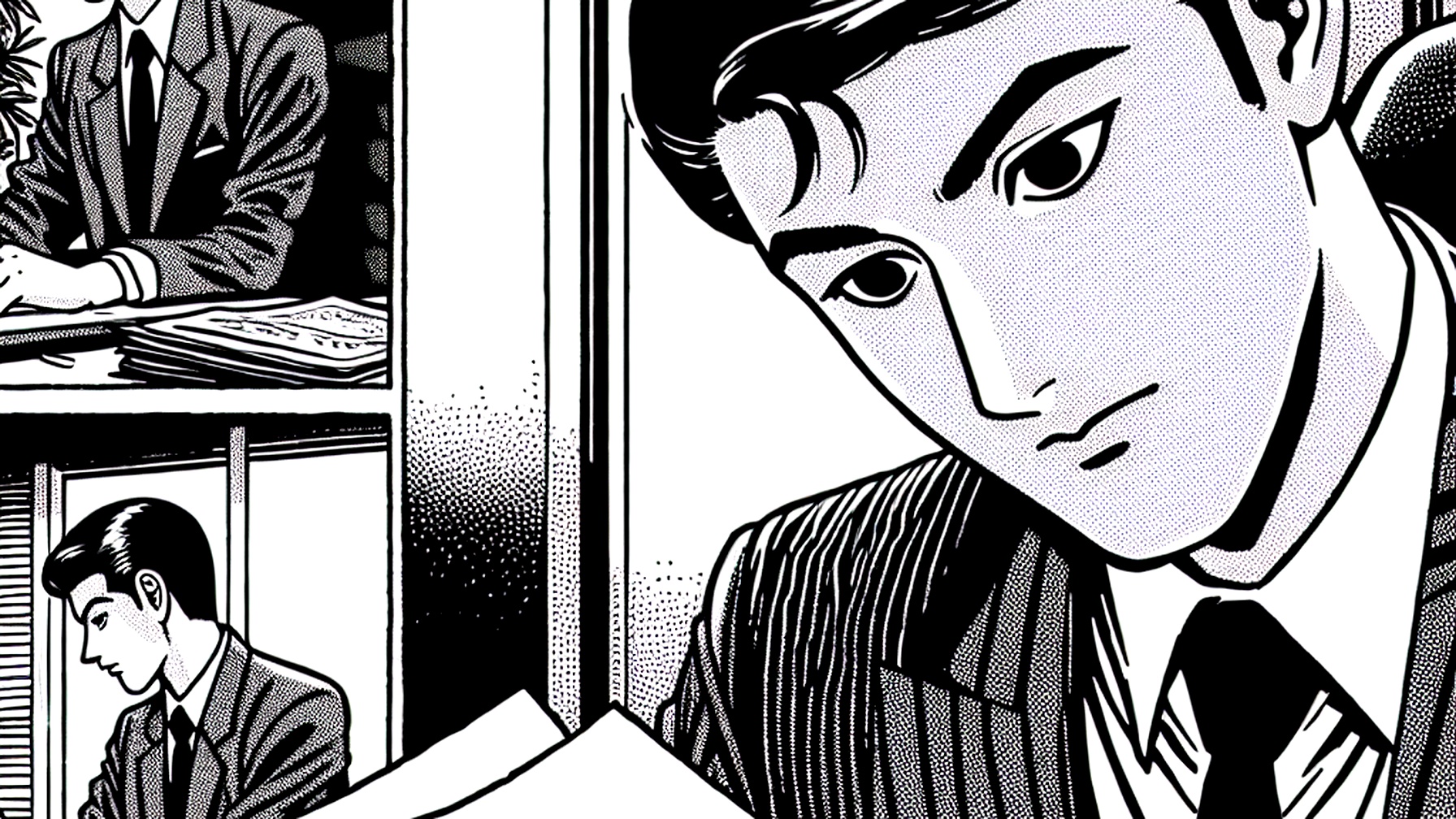
ポイントは、現在の市場利回りを知り、そのうえで自分の目標を設定することです。日本不動産研究所の調査によると、2025年10月時点で東京23区の平均表面利回りはワンルームマンションで4.2%、ファミリータイプで3.8%、木造アパートで5.1%となっています。利回りが高いほど収益性は上がりますが、同時に築年数が古い、立地が郊外などリスクが高まる傾向も見逃せません。
全国平均を見てみると、都市部より1〜1.5ポイント高いケースが多く、木造アパートの表面利回りで6〜7%が一般的です。ただし国土交通省住宅統計では、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%と依然として高水準です。空室リスクを織り込むと、実質利回りは表面利回りより1.5〜2ポイントほど低下するのが現実です。
つまり、安定経営を目指すなら、都市部で実質4%前後、地方都市で実質6%前後を目標にするのが妥当なラインといえます。これを下回る場合は、家賃下落や修繕費の増加で赤字転落の危険が高まるため、購入前に詳細なシミュレーションを行うことが不可欠です。
実質利回りを計算するステップ
重要なのは、数字を具体的に積み上げて利回りを算出するプロセスです。まず年間家賃収入を見積もる際、平均空室率を加味して稼働率を80〜90%に設定します。次に管理会社への手数料が家賃の5%、修繕積立として年間家賃の10%を見込むのが一般的です。固定資産税や火災保険料も合計で物件価格の0.2〜0.3%程度を目安にします。
このようにして年間支出を差し引いた後の手取り額を出し、物件取得時の諸費用(仲介手数料、登記費用、ローン事務手数料など)を含めた総投資額で割れば、実質利回りが算出できます。言い換えると、購入価格だけでなく初期費用まで含めることで、より現実に近い指標を得られます。
また、ローンを利用する場合は返済額をキャッシュフロー計算に組み込みますが、利回り算出の分母には総投資額を用いる形が一般的です。返済比率が高すぎると、利回りが十分でも手元資金が不足する「黒字倒産」のリスクが生じるため、月間キャッシュフローも必ずチェックしましょう。
利回りを高めるための実践的アプローチ
実は利回りを上げる方法は、購入時の値引き交渉だけではありません。物件取得後にできる施策として、第一に家賃収入を向上させるリフォームが挙げられます。たとえば単身向けワンルームでも浴室乾燥機や高速インターネットを導入することで月額5,000円程度の家賃アップが実現するケースがあります。
さらに、入居者ターゲットを明確にする運営戦略も効果的です。学生が多いエリアでは家具家電付きプランを導入し、法人需要が強い地域ではマンスリー契約を取り入れるなど、ニーズに合わせたプラン変更で稼働率を高めることができます。経費面では、複数物件をまとめて管理会社に委託し、管理料を1ポイント削減するだけでも年間数十万円のコスト削減につながる場合があります。
こうした小さな改善を積み重ねると、実質利回りが1ポイント上がるだけで投資回収期間が数年短縮されることも珍しくありません。つまり、購入後の運営こそが利回りを押し上げる最大のレバレッジポイントなのです。
ファイナンス戦略が利回りを左右する理由
まず押さえておきたいのは、借入条件によって実質利回りは大きく変動するという事実です。たとえば金利1.5%の20年ローンと2.5%の30年ローンでは、月々の返済と総支払額が大きく異なり、結果として手残りキャッシュが変わります。金融機関によっては、耐用年数を超える融資期間を設定できる場合があり、月々の返済負担を抑えられるため実質利回りが向上することもあります。
2025年度の住宅ローン減税は自宅用に限定されるため、アパート経営には適用されませんが、法人設立による節税策など間接的に手残りを増やす余地は残ります。また、公庫や地方銀行はアパートローンで金利1%台前半の商品を提供しており、自己資金20%を投入できれば審査が通りやすい傾向があります。
しかし、金利だけでなく、団体信用生命保険の有無や手数料体系も比較することが重要です。手数料が2%から1%に下がるだけで、初期費用が数十万円単位で変わることがあり、その分をリフォーム予算に回すと利回り改善効果が期待できます。つまり、金融機関選びと交渉力が、利回り向上のカギを握るのです。
まとめ
ここまで「アパート経営 利回り 何パーセント」という疑問に焦点を当て、基礎知識から2025年の市場データ、具体的な計算方法、利回り改善策、ファイナンス戦略までを解説してきました。市場平均を基準としつつ、実質利回りで都市部は4%、地方都市は6%を目指すことが現実的な目安です。そのうえで、空室リスクを抑える運営、金利や諸費用を抑える融資交渉、付加価値向上による家賃アップを組み合わせれば、安定したキャッシュフローが実現します。ぜひ本記事で得た視点を生かし、自分が納得できる利回りを見極めて、次の一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp
- 不動産流通推進センター 不動産市況月報 – https://www.retpc.jp

