賃貸住宅の利回りが伸び悩むいま、安定したテナント収入を得られる「店舗特化型REIT」に注目が集まっています。しかし、銘柄の選び方や景気変動への備えが分からず、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。本記事では、15年以上の運用経験を持つ筆者が、初心者でも実践できる店舗REITの見極め方と2025年度の最新税制を踏まえた投資戦略を解説します。読み終えるころには、自分に合った銘柄を自信を持って選べるようになるはずです。
店舗特化型REITの基礎知識
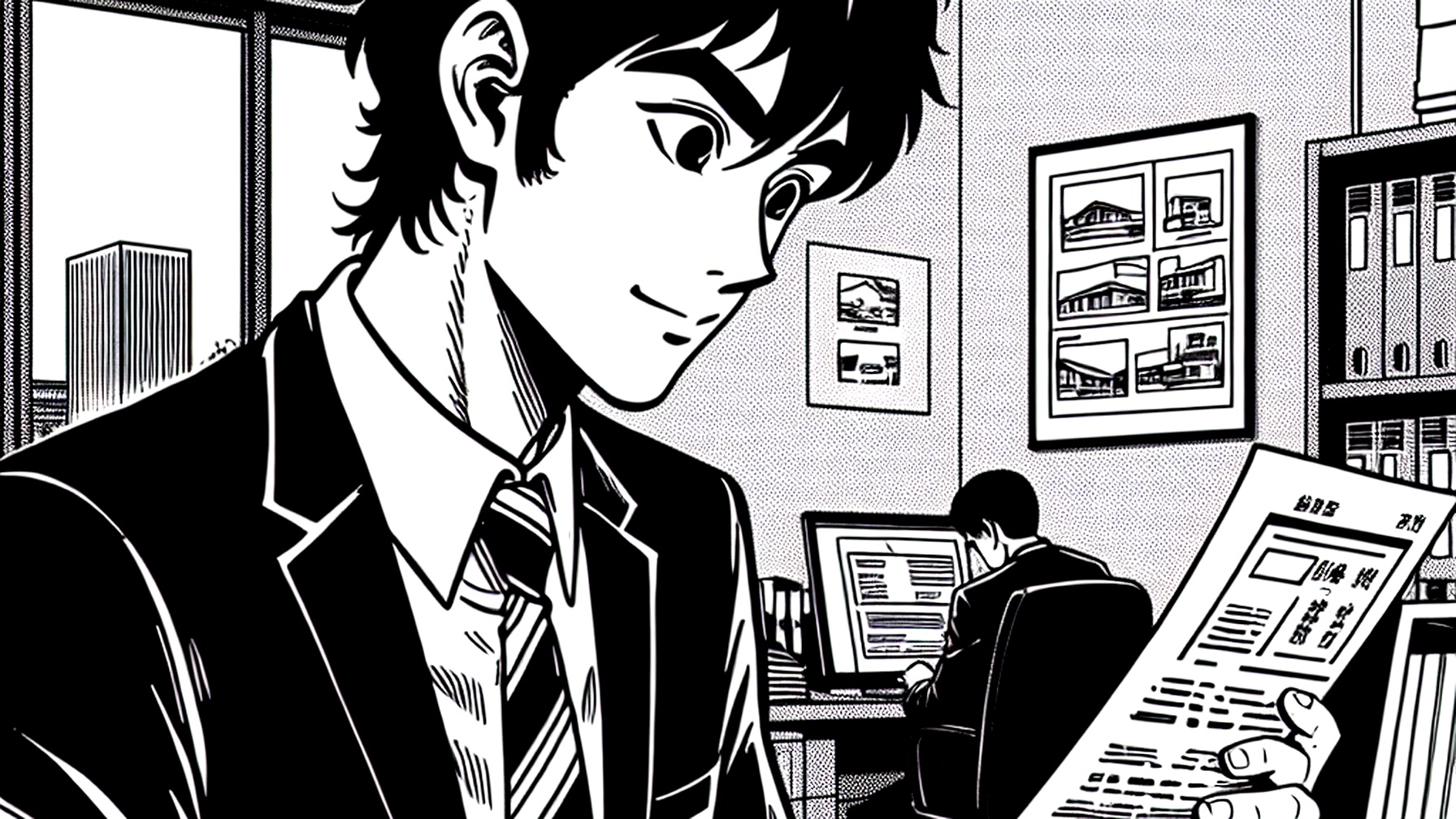
まず押さえておきたいのは、店舗特化型REITの仕組みです。REIT(不動産投資信託)は投資家から集めた資金で不動産を購入し、賃料収入を分配金として戻す仕組みを持ちます。中でも商業施設やロードサイド店舗に投資する銘柄は、消費動向に直結するため景気敏感株としての性格が強い点が特徴です。総務省「商業動態統計」によると、2025年上期の小売販売額は前年同期比3.1%増で推移しており、底堅い個人消費が店舗REITの収益を支えています。
一方で、オフィスや住宅型と比べて賃料契約が短期になりがちです。テナントが2〜5年で入れ替わることは珍しくなく、空室が続けば分配金は減少します。そのため、立地や賃料水準だけでなく、運営会社のリーシング力(空室募集力)も重要な評価軸となります。実は、管理会社がグループ内に小売運営企業を持つREITは、相互送客が可能で空室リスクを抑えやすいというメリットがあります。
さらに、店舗REITは家賃に売上連動型の部分を組み込むケースが多く、好況期には賃料が増加する仕組みになっています。つまり、インフレ局面で実質利回りが目減りしにくい投資対象といえます。日銀「物価見通しレポート」では、2025年度消費者物価指数(生鮮食品除く)は2.1%上昇と予測されており、インフレ耐性を備えた資産としての魅力が高まっています。
魅力とリスクを見極める視点
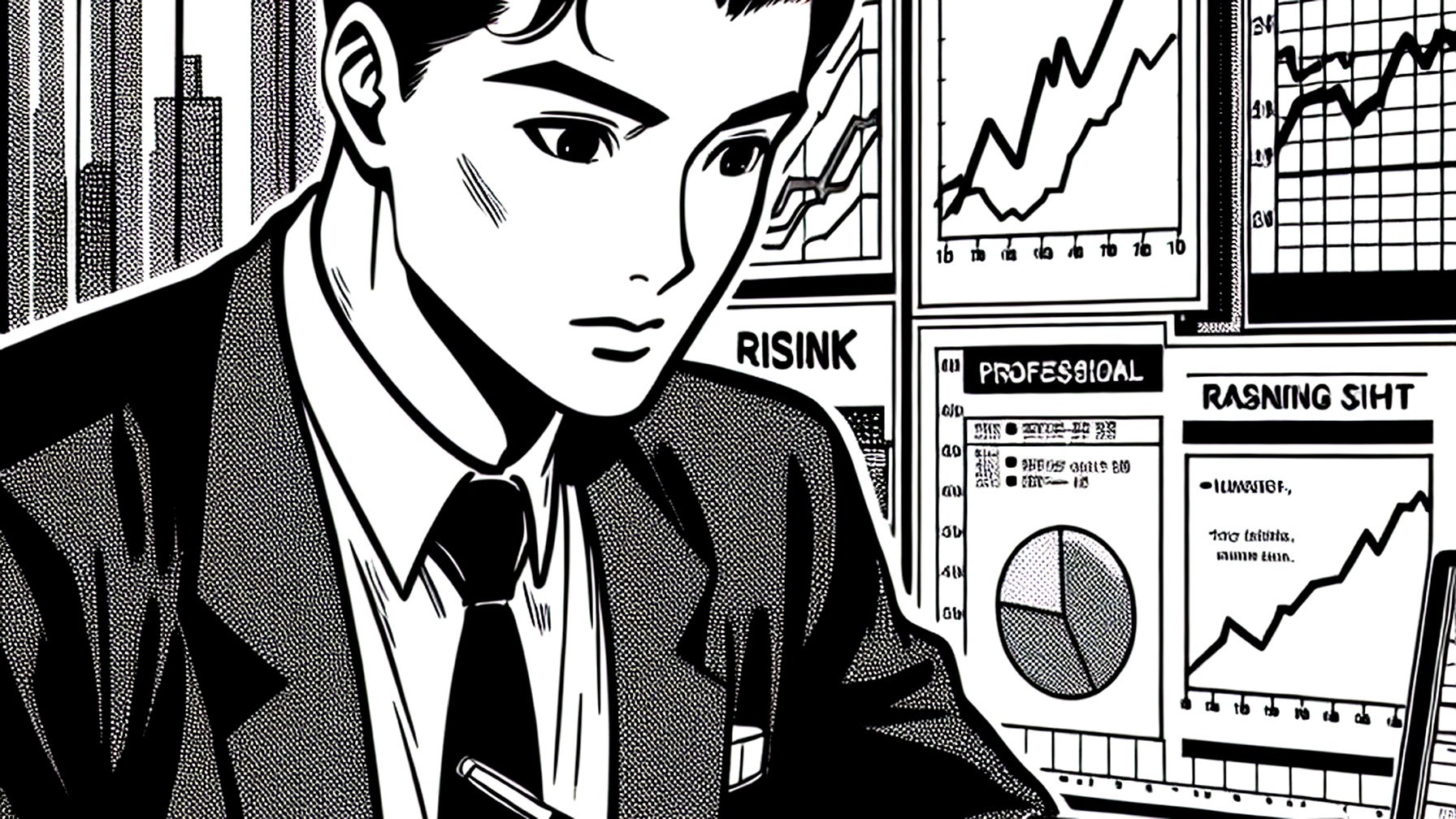
ポイントは、分配金利回りだけに目を奪われないことです。日本取引所グループのデータでは、2025年10月時点の店舗REIT平均利回りは4.2%ですが、個別銘柄間の格差は1%超に及びます。利回りが高い銘柄は、地方中心のポートフォリオや築年数の古い物件を抱える場合が多く、メンテナンス費用が将来の重荷となる可能性があります。
まず、物件の立地をエリア単位ではなく、駅乗降客数や周辺商圏人口などのミクロデータで確認しましょう。国土交通省「都市構造可視化データ」では、500メートル四方の昼間人口を閲覧できます。たとえば、昼間人口が1万人未満のエリアでは、退店後のリーシングに半年以上を要するケースが目立ちます。また、同一銘柄でも地方物件の比率が増えるほどキャップレート(期待利回り)が高くなるため、空室リスクと表裏一体である点を忘れてはいけません。
次に、テナント分散効果を確認します。20店舗以上に投資する銘柄であっても、上位5テナントの賃料依存度が30%を超える場合は、実質的に集中リスクが高い状態です。財務省「法人企業統計」によると、2025年の小売業倒産件数は前年比6.5%増加しており、特定チェーンに頼り切るポートフォリオは回避したいところです。つまり、分配金の安定度は物件数よりもテナント構成で決まると考えてください。
個別銘柄を選ぶ三つの実践ステップ
重要なのは、数値指標と現場感覚を組み合わせることです。ここでは実際に私が行っている手順を紹介します。
第一に、ネット証券のスクリーニング機能で直近12か月の分配金利回りとNAV倍率(純資産価値比率)を確認します。NAV倍率が1倍を下回り、なおかつ利回りが4%以上の銘柄は、市場が過度にリスクを織り込んでいる可能性があります。そこで投資家説明資料を読み、物件取得予定やリファイナンスの状況をチェックしましょう。
第二に、実際に主要物件があるエリアを訪れ、平日昼と週末の来客数を目視で把握します。オンライン資料では分からない、フロア占有率やテナントの業態バランスが確認できます。実は、閑散としているモールでも食品スーパーの集客が堅調なら、賃料収入の7割を支えるアンカー店舗が機能していることも多いのです。この現場確認は、リート投資家が取れる数少ない情報優位性と言えます。
第三に、運用会社のIR方針を比較します。2025年度から義務化された「サステナビリティ開示基準」に沿い、エネルギー使用量や従業員の定着率を報告するREITが増えました。開示姿勢が丁寧な運用会社は、金融機関との協議もスムーズで、将来的な資金調達コストを抑えられる傾向があります。つまり、IRの質は中長期の資本コストに直結するため、軽視できません。
失敗しないポートフォリオ設計
まず、既存の資産配分を俯瞰し、店舗REITが全体の何%を占めるべきか考えます。大和総研の試算では、株式50%、債券30%、REIT20%のバランス型ポートフォリオが、過去10年間のリスク調整後リターンを最適化しました。しかし、店舗REITに絞る場合はセクター集中リスクが高まるため、REIT全体の半分、資産全体の10%程度から始めるのが無難です。
また、分配金は半年ごとに支払われるケースが主流です。生活費の補填を目的にするなら、支払月が異なる複数銘柄を組み合わせ、毎月キャッシュが入るように設計すると良いでしょう。一方で、受取後すぐに再投資する「合成DRIP(自動再投資)」を使えば複利効果が期待できます。SBI証券では、2025年4月からJ-REITの分配金自動再投資サービスがスタートしました。手数料無料で小口買い増しが可能なため、長期投資家にはメリットが大きいです。
さらに、金利上昇局面への備えも忘れないでください。店舗REITの約7割は変動金利で借入を行っています。日本銀行は2025年7月会合で長期金利誘導目標を1.5%へ引き上げましたが、平均借入コストはまだ0.53%にとどまります。とはいえ、2028年までに1%程度の上昇余地があるとの見方もあり、LTV(総資産に対する負債比率)50%以下の銘柄を中心に組むと安心です。
2025年度の税制と購入タイミング
実は、税制を味方につけるだけで最終利回りが大きく変わります。2025年度の新NISAは非課税投資枠が年間360万円、累計1800万円に拡大され、上場REITも成長投資枠で購入可能です。非課税口座で得た分配金は再投資に回しても課税されないため、特に利回り重視の店舗REITと相性が良い制度と言えます。
購入タイミングについては、四半期決算発表後の株価調整局面が狙い目です。決算発表直後は、空室率やテナント退店が報じられ、短期筋の売りが出やすくなります。例えば、2025年8月に決算を公表したAリートは、空室率2%の悪化が嫌気され、一時5%下落しました。しかし、3日後にはエリア平均を上回るテナント入れ替え計画が示され、株価はすぐに回復しました。つまり、ネガティブサプライズ直後に精査し、内容が許容範囲なら段階的に買い増す戦略が有効です。
加えて、法定耐用年数が切れた物件の売却益には特例税率が適用されることがあります。2025年度の「特定土地等の長期譲渡所得の軽減税率」は、保有期間5年以上で15%に抑えられており、含み益を持つREITが売却を加速する要因となります。投資家は物件入替えによる一時益が分配金に上乗せされる可能性を考慮し、IR資料の「物件売却方針」を定期的にチェックすると良いでしょう。
まとめ
店舗特化型REITは、インフレ耐性と消費拡大の恩恵を受けやすい一方、景気後退時の空室リスクを抱えます。立地、テナント分散、財務健全性の三要素を客観データと現地視察で検証し、NAV倍率やIR開示姿勢も重ねて比較することが成功への近道です。さらに、新NISAを活用した非課税投資や自動再投資サービスを併用すれば、分配金利回りを最大化できます。まずは資産全体の10%から試し、景況感と金利動向を注視しながら段階的に比率を高めるアプローチで、安定したキャッシュフローを実現してください。
参考文献・出典
- 総務省 商業動態統計 – https://www.stat.go.jp/data/ssi/
- 国土交通省 都市構造可視化データ – https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/
- 日本取引所グループ J-REIT情報 – https://www.jpx.co.jp/
- 日本銀行 物価見通しレポート – https://www.boj.or.jp/
- 財務省 法人企業統計調査 – https://www.mof.go.jp/pri/
- 大和総研 資産運用レポート – https://www.dir.co.jp/
- SBI証券 J-REIT自動再投資案内 – https://www.sbisec.co.jp/

